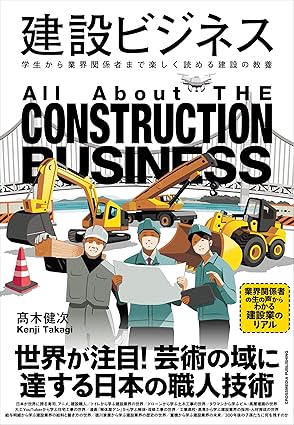学生1人に求人20社、大学生の11倍「就職に強い工業高校の学生」
2025年02月18日 公開

近年は大学進学率が上昇し、平成の30年間で私立大学の文系学部が次々と新設されてきた。しかし、その一方で、高い専門性と実用的なスキルを持つ工業高校生・高専生を求める企業の人材争奪戦が激化しているという。クラフトバンク総研所長の髙木健次氏による書籍『建設ビジネス』より解説する。
※本稿は、髙木健次著『建設ビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)を一部抜粋・編集したものです。
工業高校と高専の進路指導室の今
「今、工業高校の学生を採用するのは大学卒の10倍以上難しい。高専生はさらに困難」
Yahoo!ニュースにも転載された私の寄稿記事(※ビジネスインサイダー・ジャパン2024年6月掲載)は大きな反響がありました。
「求人倍率=1人の学生に何社が求人を出しているか」を指標に考えます。
・大学卒 1.7倍(2024年リクルートワークス研究所)
・高校卒 3.5倍(2024年厚労省)
・工業高校卒業生 20.6倍(2023年全国工業高等学校校長協会、以下、全工)
・高専生 20~50倍(全国高等専門学校連合会)
今、工業高校や高専の学生は大手企業から引く手あまたです。工業高校から中小企業が採用をするのは困難になってきています。
私は首都圏の工業高校建設科の進路指導の先生に直接お話を伺う機会を得ました。その内容をまとめると以下の通りです。
・求人社数は15年前の5倍、1割以上の学生が上場企業もしくはそのグループに就職
・「高校卒で大手に入社したら、大学院卒の同僚と働くことになった」卒業生もいる
工業高校の学生が人気になる背景としては、二級土木・建築施工管理技士補など実用性の高い資格を取得していることに加え、現場で必要な溶接やCADなどを授業で経験しているなどがあります。
自衛隊、国交省などの公的機関も積極的に工業高校の学生を採用しています。工業高校の学生は「全国規模の人材争奪戦」になっており、就職する学生の25%が学校のある県とは別の県で就職する「県外就職」をし、県外就職率は九州、東北で突出して高い傾向にあります(全工調べ)。
コロナ禍などの景気変動があっても工業高校の学生の求人倍率は上がり続けており、不景気に強いとも言えます。
就職に強いのに減る工業高校
しかし「就職に強い」工業高校は減少を続けています。1970年代に全国736校あった工業高校は2023年517校まで減少(文部科学省)。定員割れの学校もあります。企業の評価が高い高専の数も増えていません。
また、リクナビなどの就職活動サイトを通じ、何社もエントリーできる大学生と違い、高校生には「1人1社制」と呼ばれる独自ルールがあります。「学校あっせん」の就職活動をする場合、生徒が学校から「推薦」を受けて応募できるのは原則1社だけです。
このルールは法律によるものではなく、都道府県ごとに学校と経済団体が決めており、「学業に支障をきたさないスケジュールで就職機会を創出する」ためにあるそうです。
しかし「いくつかの会社を実際に訪問してみて、進路を決める」ことができず、学生と企業のミスマッチにつながるとして、秋田、和歌山、沖縄は複数応募を認めているなど、県によって対応は分かれています。
企業側にも課題はあります。転職時の応募条件に大学卒以上を求める、部長などの幹部職は大学卒以外認めないなど、硬直的な人事制度の会社も存在します。高校卒で社会人経験を積んでから大学院でMBA(経営学修士)を取得して経営幹部になる人もこれから増えていいでしょう。
私が勤務するクラフトバンク株式会社の執行役員は、高専出身のITエンジニア(20代)です。課題はあるものの、工業高校、高専などの専門系学校が就職に有利なのは間違いありません。
また、工業大学、医療大学、体育大学などの学生も企業から人気です。工業高校の中には「受験偏差値」が決して高くない学校もありますが、就職率は非常に高いです。「受験偏差値」だけでは就職率や就職後の年収はわかりません。
他方で「受験偏差値」が高く、MARCHと呼ばれる都内の有名私立大学でも文系学科は学校に集まる企業求人は少ないです。求人倍率1以下、つまり学生の数より求人数が少ない学校もあります。
国家資格を保有する高専卒の正社員の現場監督を補助するのが、慶応大学法学部卒の無資格・派遣社員というゼネコンの現場も実際にはあります。
日本はトヨタ自動車をはじめとする製造業や建設業、IT、医療などの「ものづくり」「理系」の産業で大きなお金が動きます。それにもかかわらず、工業高校の数は減り、大学の博士課程に進んでも約3割が非正規雇用です。
他方、私立大学は直近15年間、新設され続けました。多く新設されたのは社会学部などの「文系」学部です。結果「無資格・文系大卒」が増え、「理系」が不足する状況になりました。日本の大学は先進国の中で最も「文系学部」が多いというデータもあります。
「工業高校の学生が企業から人気なのは安い給料で雇えるからだ」というコメントもありますが、厚労省統計を見ると「高校卒・建設業」の年収が「大学卒・飲食業」をすでに上回っています。地方の場合、大卒で市役所職員になるより、高専・工業高校から東京の大手建設会社に入社した方が年収は高いです。
住宅大手の積水ハウスのグループ会社は2023年に高校卒新入社員の初任給を月収ベースで11%引き上げました。高専に関しては三菱電機のグループ会社など大企業各社が4割増の採用計画を打ち出しています。
歴史や法律を学ぶ文系学科は社会に不可欠です。「文系理系」「年収」で物事を単純化することはできませんし、個人の向き不向きもあります。非常に難しい問題ですが、工業高校の学生の採用が過熱する一方、私立大学の約2割は経営難という現実を私たち大人は受け止める必要があります。
【髙木健次(たかぎ・けんじ)】
クラフトバンク総研所長/認定事業再生士(CTP)。1985年生まれ。京都大学在学中に塗装業の家業の倒産を経験。その後、事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。その後、内装工事会社に端を発するスタートアップであるクラフトバンク株式会社に入社。2019年、建設会社の経営者向けに経営に役立つデータ、事例などを発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、業界団体等での講演、建設会社のコンサルティングなどに従事。
【クラフトバンク総研】https://corp.craft-bank.com/cb-souken
【X】https://x.com/TKG_CraftBank