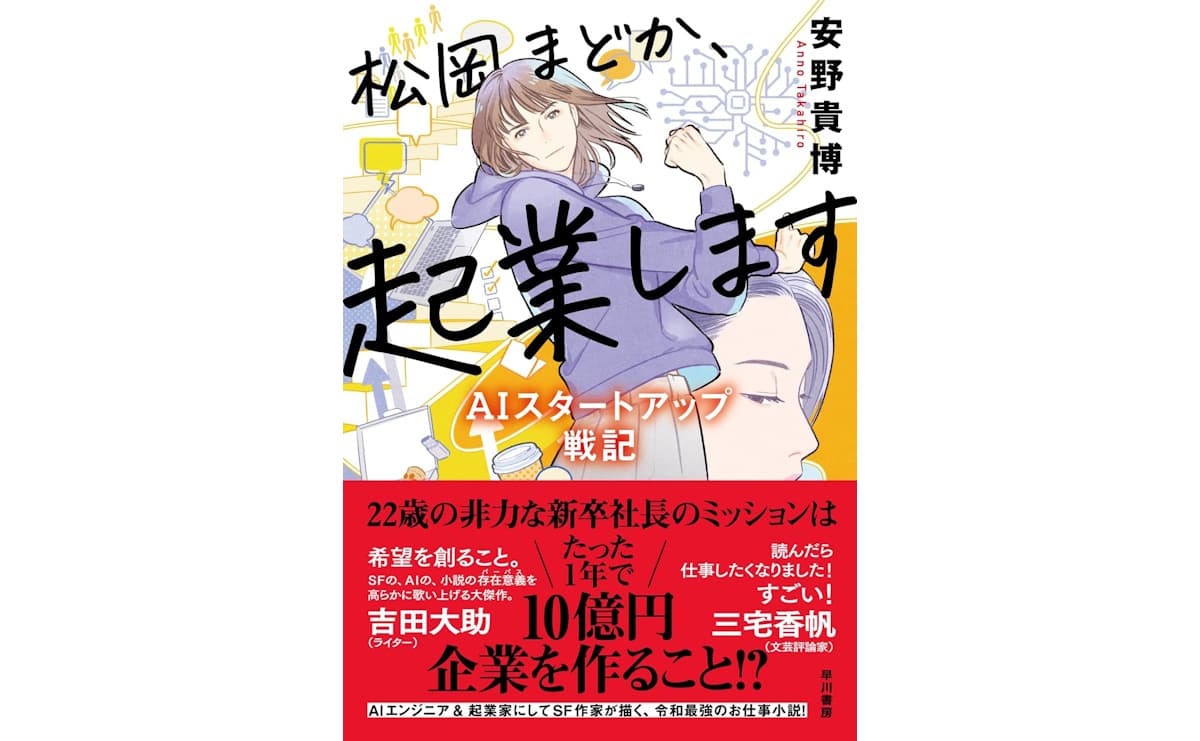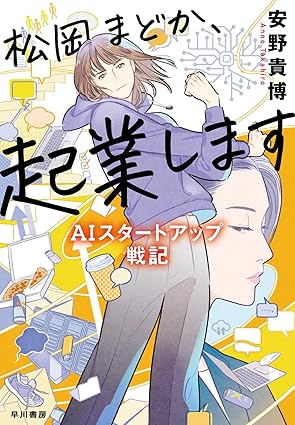強烈なプレッシャー下で鞭を打ち...『松岡まどか、起業します』が描くリアルな起業家の姿
2025年04月10日 公開

ビジネス書を中心に1冊10分で読める本の要約をお届けしているサービス「flier(フライヤー)」(https://www.flierinc.com/)。こちらで紹介している本の中から、特にワンランク上のビジネスパーソンを目指す方に読んでほしい一冊を、CEOの大賀康史がチョイスします。
今回、紹介するのは『松岡まどか、起業します AIスタートアップ戦記』(安野貴博著、早川書房)。この本がビジネスパーソンにとってどう重要なのか。何を学ぶべきなのか。詳細に解説する。
起業の世界がよく表れている作品
起業とはどんなものなのか、本書を通じてイメージができるはずです。起業家の経験が語られる本や研究者が理論を伝える本もいいものですが、事実に基づくため、様々な関係者に配慮して具体的な問題を描けない面もあります。
一方で、経済・金融小説でよく見られるように、フィクションだからこそ込められるリアルさと生々しさがこの本にはあります。
本書の著者は安野貴博さんです。都知事選挙に出馬した方というと思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。選挙の際には奥様の熱い応援演説が話題になったこともありました。そして政治家よりも、起業家、AIエンジニア、作家としての活動が主でもある幅広い才能を持つ若き天才です。
この作品は松岡まどかという架空の女性起業家が、内定先企業の社内抗争に巻き込まれ内定取消になり、起業していくところから物語が始まります。
投資契約の怖さ
主人公が起業をする後押しになった出資に関わる投資契約には、おそろしい条項が含まれていました。その条項があったため、通常以上のスピード感ですべてのことを進める必要が生じて、精神的にも追い詰められていくことになります。
起業をしようとするとほぼ確実に資金が必要になります。経営者が個人として貯めてきた預金が十分にあるケースはまれで、多くは投資家や金融機関から資金を調達していきます。
ITやAIなどのような不確実性の高い領域では、金融機関から借りられる金額は数百万円程度にとどまるため、会社を大きく成長させたい経営者であれば株式による資金調達を検討します。その際に、起業するまで目にしたことがないものを見ることに。それが資金調達時の投資契約です。
本書のストーリーでも出てくるように、日本における資金調達の現場で、投資契約が出てくるのは会社の評価額や投資金額がまとまった後、つまり資金調達交渉の最後の最後です。しかも資金的なひっ迫がある状況で焦っているのは起業家の方なので、投資契約の条項を調整できる交渉力が起業家側にはほとんどありません。
今回の投資契約では、1年間に会社の評価額を10億円にまで上げなければ、創業者がわずかな出資金を1億円で買い戻さなければならないという買取条項がついています。この例は詐欺的でここまで悪質なものは珍しいでしょうが、実質的にそれに近い契約になっているケースは実際にあり、資金に困った起業家側が不利な契約を飲まざるをえないことが多くなります。
もちろん投資家は慈善事業ではなく利益を追求する仕事なので、どちらかが悪いわけではありません。ただ本書では、投資契約によって主人公の穏やかな日常は全くなくなり、強烈な時間的なプレッシャー下で自分に鞭を打つ状況に突入していきます。起業家は構造上、時間的にも精神的にも強烈なプレッシャーがかかるものだと言えます。
ピッチコンテストと思い通りにならない事業
ITやAIの業界の起業家は、ピッチコンテストという投資家やメディア等に向けたプレゼンテーションの場に登壇していきます。大体3分から7分程度でサービスや事業プランについてのプレゼンテーションを行うもので、選抜された登壇企業10社前後の中で順位が定められ、上位に入賞できれば賞金や賞品が獲得できる他に、知名度の向上や投資を受ける機会が得られることもあります。
主人公はUVSというスタートアップイベントでの登壇を目指して準備をしていきます。実際の世界でもIVSやICCというスタートアップシーンを代表するイベントがありますので、そのイメージで語られているのでしょう。
このピッチコンテストは会社の運命を変えるような影響力があるので、起業家はプレゼンを100回程度練習して本番に臨みます。本書ではカラオケボックスで練習する様子が描かれています。起業家の全てがプレゼンの天才ではないので、苦労して本番のピッチを迎えた人が多いのではないかとも思います。
ピッチコンテストで好成績を収めて、無事資金が調達できたとしても、起業家は事業を軌道に乗せるという難題に立ち向かうことになります。
もしかするとフェイスブックやメルカリのような理想的なサービス成長を示す起業のあり様を想像するかもしれません。現実にはそのようなケースは1%もありません。ほぼすべての起業家は、当初描いた計画通りにサービスが伸びずに試行錯誤を重ねます。
本書ではAIヘッドハンターからAI面接官にピボットと言われる事業転換をした様子が描かれています。何らかの方針転換や数えきれない試行錯誤を経て、本格的なサービス成長の道が見えてくるのです。
想定外のトラブル
起業家には人・資金・事業に関わる難題が次々に降りかかります。本書では事業が順調に成長し始めたとたんにランサムウェアによる攻撃に直面します。それから主人公が立ち向かう問題は、システム復旧に関わるものだけではなく、人の裏切りやメンバーの健康の問題などの重大なトラブルの連続です。
私自身が創業前に勤めていた会社の代表に言われた言葉で印象的だったのは、「課題は困ったときにまとめてやってくる」というものでした。単独の課題であれば対処できるものでも、複数の課題がまとめて顕在化することで、解決の難易度が掛け算で上がっていくものなのです。
例えば、人員不足の課題だけであれば、メンバーを補強することは可能です。ただ、その上にサービスが停滞して資金もない状態になると採用の難易度が上がりますし、資金調達をするにもサービス成長が鈍化したタイミングで行うことになり、やはり難易度が上がります。複数の課題が同時にあると解決が格段に難しいことが想像できるでしょう。
本書の主人公は人間離れした行動力で問題を1つずつ解決していきます。まさに起業家が経験する修羅場です。読者の方も起業家の修羅場がどんなものなのかを追体験できるはずです。
一握りの成功のために何をかけるのか
本書の最終章は、半沢直樹のような復讐劇が展開されます。数々の伏線を張り巡らした本作品の集大成です。その内容は本書を読んでみてのお楽しみです。
爽快なストーリーに込められたエピソードから、起業家以外がなかなか知りえないだろうリアルな起業家の姿を感じられることは本書の魅力です。また、起業にはいわゆる起業家だけでなく、会社を支える多様な人が関わります。創業期のメンバーや、株主などの支援者、初期の顧客などが作り出すはじめの時期特有の空気があります。その空気を感じられるのも、本書を読む価値でしょう。
AIやITなどの領域で起業しようと考えている人はもちろん、スタートアップに参画している人、創業期の会社をサポートしている人や、起業家の物語が好きな方など、多くの人が楽しめる作品になっています。一般的なビジネス書ともテイストの違いを感じるはずです。起業家の世界に対する好奇心を満たし、爽快な気分にもなる本書を手に取ってみてはいかがでしょうか。