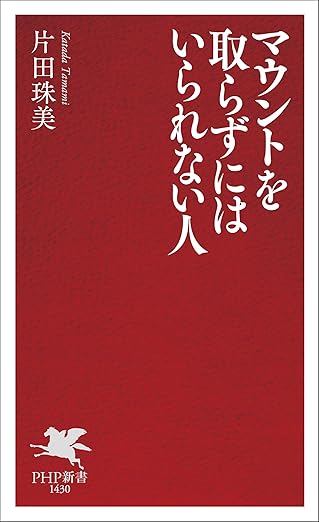われわれは他人に対して自分がどの位置にいるのかを無意識のうちに測定しており、折に触れて自身の優位性を誇示する。その根底には、他人を自分より下位に置きたいという欲望が潜んでおり、この欲望は程度の差はあれ誰の胸中にも潜んでいて、それが強い人ほどマウントを取りたがるという。
世に蔓延するマウントを取りたがる人、ここでは被害者を装う人を実例に挙げながら、その対処法について精神科医の片田珠美先生に解説して頂く。
※本稿は、片田珠美著『マウントを取らずにはいられない人』(PHP新書)を一部抜粋・編集したものです。
遅刻を注意すると「パワハラです!」と反撃する新入社員
保険会社に、遅刻を繰り返す女性の新入社員がいた。他の社員から苦情が出ており、正当な理由のない遅刻は社会人として失格だと思った40代の上司は、やんわりと注意した。
しかし、この女性は一切謝らず、「自宅が駅から遠くて、バスがいつも遅れるんです」と言い訳した。
その後も改善の兆しは一向に見られず、他の社員に示しがつかないので、上司が今度は強めに叱責した。すると、彼女はその場でワッと泣き出し、「ひどい。そんな言い方をするなんてパワハラです!」と反撃に出た。
上司としては指導するつもりだったのに、逆に非をなじられたので、しどろもどろになり、それ以上何も言えなくなってしまった。それだけではない。この女性は人事部にパワハラ被害を訴えたようで、上司は人事部に呼び出されて、事情を説明する羽目になった。
幸い、彼女が遅刻の常習犯であることは人事部も把握していた。また、周囲の証言によって、この女性の遅刻癖に他の社員も日頃から不満を抱いていたし、上司の叱責の仕方は穏当で、パワハラ的なものではなかったことも判明した。
そのため、上司に対してとくにおとがめはなかった。ただ、新入社員をうまく育てられなかったことは事実であり、今後の人事評価に影響が出る可能性も否定できない。
それ以降も、この女性には悪びれた様子がまったくなかった。以前よりは頻度が多少減ったとはいえ、相変わらず遅刻を繰り返しており、反省したわけでもなさそうだ。
しかし、上司は、少しでもきつい言い方をするとパワハラで告発されるのではないかと危惧したのか、その後は彼女に対してあまり注意しなくなった。だから、この女性はある意味では得をしたという見方もできる。
このように、自分の落ち度を注意されると、「パワハラ」と騒ぎ立て、「自分は悪くない。むしろ被害者だ」と主張する人はどこにでもいる。
被害者を装う部下、上司
某金融機関でも、30代の男性社員が「ミスが多い。もっと注意深く書類を作成しろ」と上司から叱責されて書類をいちいちチェックされるようになり、それに不満を募らせたのか、「監視されている。パワハラだ」と訴え、大騒動になった。
この男性のミスでは、同僚の多くが迷惑していたので、上司の叱責もチェックも当然だという声が圧倒的に多かった。だが、当の本人には悪びれた様子も反省の姿勢もまったく見られなかった。
しかも、上司のほうもパワハラを告発されたことで警戒するようになったのか、この男性が作成した書類をチェックすることも、厳しく注意することもなくなった。
だからといって、彼のミスが減ったわけではなく、次の工程の担当者がミスを発見するたびに修正しており、そのための作業を余計に抱え込んでいる。
このように、自分に非があっても謝らず、それどころか、自分こそ被害者と言い立て、逆に相手を攻撃する人は上司にもいる。
たとえば、PR会社で営業課長を務める40代の男性は、「お前がノルマを達成できないから売り上げが落ちた。そのせいで部長に怒られる俺の身にもなってみろ」「お前が出した企画は全然ダメ。その尻拭いをさせられるこっちの立場を考えろ」などと部下を罵倒する。だいたい、部下のせいで自分が被害をこうむって大変だという理屈をこねる。
部下の一人である20代の男性は、繰り返し罵声を浴びせられて自信を失い、自分が能力不足なのではないかと思い悩むようになった。
だが、やがて課長が怒鳴り散らすのは、課長自身が打ち出した方針に沿ったプロジェクトが成果を出せなかったときや、課長の発案で部下が練り上げた企画が失敗したときに多いことに気がついた。
それ以降、課長が部下の非をあげつらい、自分こそ被害者だと強調するのは、自身の方針や発案に問題があったことをごまかし、部下に責任を転嫁するためではないかと疑わずにはいられなかった。
この疑惑は、ある出来事を契機に確信に変わった。20代の男性が会社の入っているビルから出たところ、地下駐車場から出てきた車に危うく轢かれそうになった。
車を運転していたのは例の課長だ。どう考えても非があるのは歩行者に十分な注意を払わなかった課長のはずなのに、課長は「バカ野郎、どこ見て歩いているんだ。危ないじゃないか」と怒鳴りつけた。これを機に、20代の男性は「課長は自分が被害者であるかのようにふるまって責任逃れをしようとしている」と確信したという。
責任逃れのためという思惑を疑いたくなるのは、遅刻やミスを叱責されて「パワハラ」と騒ぎ立てた部下も同様である。部下の立場であれ、上司の立場であれ、被害者ぶるのは、それによって自身の非をうやむやにできるという利得があるからだろう。
自分が被害者であるかのように装うことによって相手を悪人に仕立て上げれば、非があるのは相手のほうということになり、相対的に自分の落ち度はかすんでいく。だから、被害者を演じることは、自己保身という目的からすれば理に適っているといえる。
この目的をどこまで意識しているかは、ケースバイケースだ。必ずしも綿密に計算しているわけではなく、直感的あるいは本能的に被害者の仮面をかぶる人もいるに違いない。むしろ、そういう人のほうが多いかもしれない。
その一因として、現在の日本社会では被害者=善人、加害者=悪人とみなす風潮が強いことが挙げられる。周囲から被害者として認知されれば、同情してもらえるだけでなく、その他もろもろ得することがあるのは否定し難い。
こうした風潮を肌身で感じているからこそ、自分こそ被害者だと強調しながら、その原因を作った加害者として相手を糾弾することによって、優位に立とうとするのではないだろうか。
対処法...リミットセッティング
被害者ぶることによってマウントを取ろうとする人は、それによってもたらされる利得を自覚しているにせよ、自覚していないにせよ、非常に厄介だ。自分自身の非をうやむやにしようとするだけでなく、相手を加害者=悪人に仕立て上げて優位に立とうとするのだから、生半可な覚悟では立ち向かえない。
まず、原則として自分の非をうやむやにしようとする思惑を許してはいけない。
そのために何よりも必要なのは、事実をきっちり記録し、すべてデータとして残しておくことだ。たとえば、遅刻やミスを繰り返す部下がいたら、何月何日にどれくらい遅れたか、何月何日にどんなミスがあり、そのせいで周囲がどれくらい迷惑をこうむったかをきっちり記録する。
そのデータを上司が一人で抱え込むのも、一人で注意したり叱責したりするのも禁物だ。
データを上層部と共有し、どう対処するか協議する。そのうえで、きちんと対処するということになれば、複数の上司が同席する場に本人を呼び出して、これこれこういう事実がありますと冷静に伝えるべきだろう。そのうえで、「この事実をどう受け止めますか」と尋ね、本人の反応を見るのが賢明だ。
事実を否認するかもしれないし、言い訳をくどくどと並べ立てるかもしれない。それに対して感情的になってはいけない。あくまでも冷静に「実際にこういうことがあり、職場全体に影響が出ている」実態をなるべく具体的に伝え、「今後もこういう事態が続くと、許容できなくなるかもしれません」と告げることが望ましい。
ここで重要になるのが、「リミットセッティング(limit setting)」の概念である。
日本語では「限界設定」と訳され、「ここまでは許容できるが、それ以上は許容できない」という「リミット(限界)」を明確に伝えることを意味する。要は、許容範囲を明確に線引きして、はっきりと伝えることだ。
なぜ「リミットセッティング」が必要なのかといえば、この線引きをあいまいなままにしておくと、遅刻やミスなどを繰り返している本人が「許されるんだ」と勘違いしてエスカレートしやすいからである。それに歯止めをかけるためにも、「リミットセッティング」を職場で共有し、きちんと伝えることが求められる。
共有しておくことが必要なのは、一人だけ優しく寛大な○○さんがいたら、本人が「○○さんは許してくれた」「○○さんは大目に見てくれた」などと周囲に訴え、揺さぶりをかけようとする恐れがあるからである。
これは、上司が被害者ぶるマウントを取る場合も同様だ。上司が怒鳴り散らすのは自身の方針や発案に問題があったことをごまかすためではないかと気づいたら、どんな問題があったのか、そしてどのように怒鳴り散らしたのかを記録しておくべきだ。場合によっては、録音しておくことも必要だろう。
そのうえで、これ以上許容できないと判断したら、データを上司の上司、別の部署の上司などと共有し、対応を協議すべきだ。相手が部下であれ、上司であれ、記録に残すこと、そしてデータを一人で抱え込まず共有して相談することが重要だ。
もっとも、せっかく相談しても、組織として何もしてくれない職場もあるかもしれない。「自分で何とかしろ」「悪いのはお前のほうだ」などと突き放される場合だってあるかもしれない。
こういう職場には早めに見切りをつけるのが賢明だと個人的には思う。