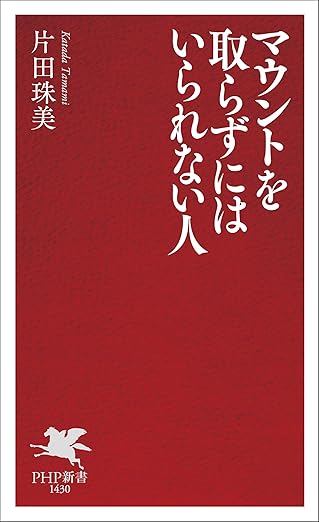われわれは他人に対して自分がどの位置にいるのかを無意識のうちに測定しており、折に触れて自身の優位性を誇示する。その根底には、他人を自分より下位に置きたいという欲望が潜んでおり、この欲望は程度の差はあれ誰の胸中にも潜んでいて、それが強い人ほどマウントを取りたがるという。
世に蔓延するマウントを取りたがる人、ここでは不機嫌を武器にする人を実例に挙げながら、その対処法について精神科医の片田珠美先生に解説して頂く。
※本稿は、片田珠美著『マウントを取らずにはいられない人』(PHP新書)を一部抜粋・編集したものです。
理由もなく不機嫌になる妻
40代の男性会社員は、しょっちゅう不機嫌になる30代の妻に手を焼いているという。妻が不機嫌になると、ときには口を利いてくれなくなる。そのため、妻の都合を尋ねたり、何かを頼んだりするのに中学生の息子か小学生の娘を介さなければならない。
メッセンジャー役を担う子どもが不憫なので、結局夫が妻の機嫌を取り、場合によっては謝ることもあるそうだが、「なぜ自分が謝らなければならないのか」と腹が立つとか。
厄介なのは、不機嫌になった妻に「何か気に入らないことがあるのか」と尋ねても、「別に」と答えるだけで、不機嫌の原因がよくわからないことだ。だからといって、放っておいたら、妻の不機嫌が続き、家庭全体に重苦しい空気が漂う。
そこで、夫としては気を遣って妻の機嫌を損ねそうな要因を一つ一つ取り除きつつ、妻が喜びそうなことをできるだけ増やすしかない。
これまでの経験から、妻が不機嫌になるのは、だいたい夫の実家がらみであることに夫は気づいている。具体的には法事、夫の両親との食事会、盆や年末年始の帰省などで、実家に連絡する必要もあって妻に相談すると、その後妻は決まって不機嫌になる。
口も利いてくれなくなるので、当然相談もできない。だから、結局法事には夫が一人で出席し、夫の両親との食事会は断ることになる。夫の実家に盆や年末年始に帰省することはここ何年かできておらず、夫一人が何か用事があるたびに実家に帰り、泊まってくる。
夫が気を遣うことによって、結局妻の思い通りになっているように見える。おそらく、この妻は夫の両親とは極力接触したくないのだろう。しかし、それを口に出して夫に伝えると、「わがまま」「自分勝手」などと非難されかねない。そこで、不機嫌になり、ときには口も利かないことによって、夫が折れてくれるのを待つわけである。
これは「パッシブ・アグレッション(passive aggression)」と考えられる。
日本語では「受動的攻撃」と訳され、怒りや不満があっても、それを明確に言葉で伝えたり、激しく怒鳴ったりするのではなく、わかりにくい形でこそこそと表明することを指す。いわば陰湿な攻撃であり、不機嫌になって口も利かないのは、典型的な「パッシブ・アグレッション」といえる。
もっとも、不機嫌になっている本人はわかりにくい形でこそこそと表明しているつもりかもしれないが、周囲はすぐに気づくだろう。とくに、ここで取り上げた夫のように家庭内に波風を立てたくなくて、常に妻の顔色をうかがうようなタイプは、「また機嫌が悪くなったな」と思わずため息をつき、「何とかしなければ」と焦るに違いない。
その結果、夫が気を遣い、先回りして妻の機嫌を損ねそうなことは極力取り除いてくれれば、妻にとってこれ以上喜ばしいことはない。不機嫌になることによって妻は夫よりも優位に立てる。そのうえ嫌なことを回避できるのだから、願ったり叶ったりだろう。
妻は、自分が不機嫌になることによって生じる利得を享受しているようにも見える。この利得は、怒りをわかりやすい形で表に出す「アクティブ・アグレッション(active aggression)」によって得られるものよりも大きい場合がある。
第一、「パッシブ・アグレッション」では原因がわかりにくいので、相手は困惑していろいろ考え、機嫌を取ったり譲歩したりするうちに疲弊していく。そうなれば、より優位に立てる。本人がどこまで意識してやっているかは不明だが、ある意味では非常に狡猾な戦略といえよう。
不機嫌マウントを容認し、助長する「イネーブラー」
もっとも、そこまで緻密に計算して不機嫌になっている人はきわめてまれかもしれない。むしろ元々感情が不安定な気分屋で、些細なきっかけによって不機嫌になりやすい人が大半を占めるのではないだろうか。
気分屋という言葉はネガティブな意味で用いられることが多い。自分の感情をコントロールできないから突然機嫌が悪くなるわけで、最近では「不機嫌ハラスメント」、いわゆる「フキハラ」という言葉も登場した。
理由も告げず、突然不機嫌になって周囲に気を遣わせ、その場の空気を悪くすることが一種のハラスメントとしてとらえられるようになったのである。
職場の「フキハラ」は問題視されるかもしれないが、家庭内で同様のふるまいがあっても必ずしもとがめられるわけではないだろう。
些細なきっかけで不機嫌になる妻に、そのことを指摘したり注意したりして、さらに不機嫌になられたら困るというのが夫の本音ではないか。だから、腫物に触るように接するしかなく、機嫌を取ったり譲歩したりするのだろうが、結果的に不機嫌マウントに拍車をかける面もあることは否定し難い。
うがった見方をすれば、妻が少々不機嫌になっても動じない、いやそれどころか「何をふくれているんだ。俺の実家に行くのは嫁の義務だろうが」と怒鳴るような夫だったら、妻は不機嫌な顔をしていられないだろう。
心の底では怒りを覚えていても、それを表に出すと夫に怒鳴られるので、表面的にはにこやかにしているしかない。このように自分の感情を抑圧することがいいとは決して思わないが、昭和の頃まではよくいた亭主関白型の夫が相手では、妻が不機嫌な顔を見せることはなかなか許されなかったはずだ。
時代とともに男女のパワーバランスが変わった影響か、昨今は妻の不機嫌マウントに悩む夫が多い印象を受ける。そういう夫から相談を受ける機会も少なくないのだが、たいてい波風を立てたくないという願望が強い。
この夫のもう一つの特徴として、何か不具合が生じると、自分に原因があるのではないかと考えがちな傾向も挙げておきたい。このような思考回路の人は自分で何とかしようとする。だから、妻がちょっとでも不機嫌になると、機嫌を取ったり先回りして謝ったりする。
一見すると優しくて寛大な夫なのだが、辛らつな見方をすれば妻の不機嫌マウントを容認し、助長するという点で「イネーブラー(enabler)」になっているともいえる。
「イネーブラー」とは、薬物やアルコールの依存症患者の周囲にいて、本人が依存している物質の購入代金を渡したり不始末の尻拭いをしたりする人物を指す。妻を増長させている張本人は夫ではないだろうか。
対処法...不機嫌マウントの「イネーブラー」になっていると気づく
何よりも大切なのは、夫が妻の不機嫌マウントの「イネーブラー」になっていると気づくことである。その自覚を持てなければ、夫は妻の不機嫌マウントに振り回され、譲歩と謝罪を繰り返す羽目になりかねない。
そもそも、家庭内に波風を全然立てないようにするのは土台無理な相談だ。複数の人間が一緒に生活する以上、感じ方や受け止め方に差異が生じることは避け難い。たとえ親子であっても、ある出来事を同じように感じ、似たような受け止め方をするとは限らない。
にもかかわらず、親のほうが「わが子なんだから、自分と同じ感覚と思考のはず」と思い込み、親の価値観や考え方を押しつけようとするとさまざまな問題が出てくる。
まして夫婦は元々他人であり、異なる環境で育ったのだから、感じ方も受け止め方も違うのは当然だろう。だから、多少の波風が立つことは仕方ない。
波風がまったく立たない家庭というのは、誰かが自分の感情や願望を過度に押さえ込んで我慢している、あるいは無理に迎合しているような抑圧的な家族関係なのではないかと疑いたくなる。
このことを肝に銘じ、妻が不機嫌になっても、それはそれで仕方ないと割り切って対処すべきだろう。
妻の機嫌を取らなかったら、不機嫌が続くので厄介だと思う方もいるかもしれないが、妻が不機嫌になるたびに機嫌を取っていたら、妻は「私が不機嫌になったら、夫が気を遣ってくれる」ことを経験的に学習する恐れもある。そうなれば、妻が不機嫌になる頻度が一層増す可能性も十分考えられる。
それを防ぐためには、妻が不機嫌になってもスルーして、伝えるべきことは伝えるというスタンスを貫くほうがいい。
あくまでも言葉でコミュニケーションを取るようにすべきであり、不機嫌という「非言語的コミュニケーション(non-verbal communication)」によって夫を自分の思い通りに操作しようとする妻を許容するのは望ましくない。
もちろん、夫婦関係においてスキンシップをはじめとする「非言語的コミュニケーション」は必要だ。ただ、その比重が増すにつれて、不機嫌やDVによって相手を支配しようとする傾向が強まることは否定し難い。
そうならないようにするには、やはり言葉によるコミュニケーション、つまり「言語的コミュニケーション(verbal communication)」によって自分の感情や願望を伝えるほうが効率的ということを双方が認識する必要がある。そのためにも、日頃から話し合える関係を築いておくべきだろう。