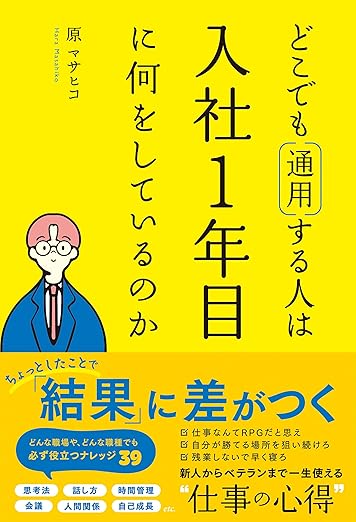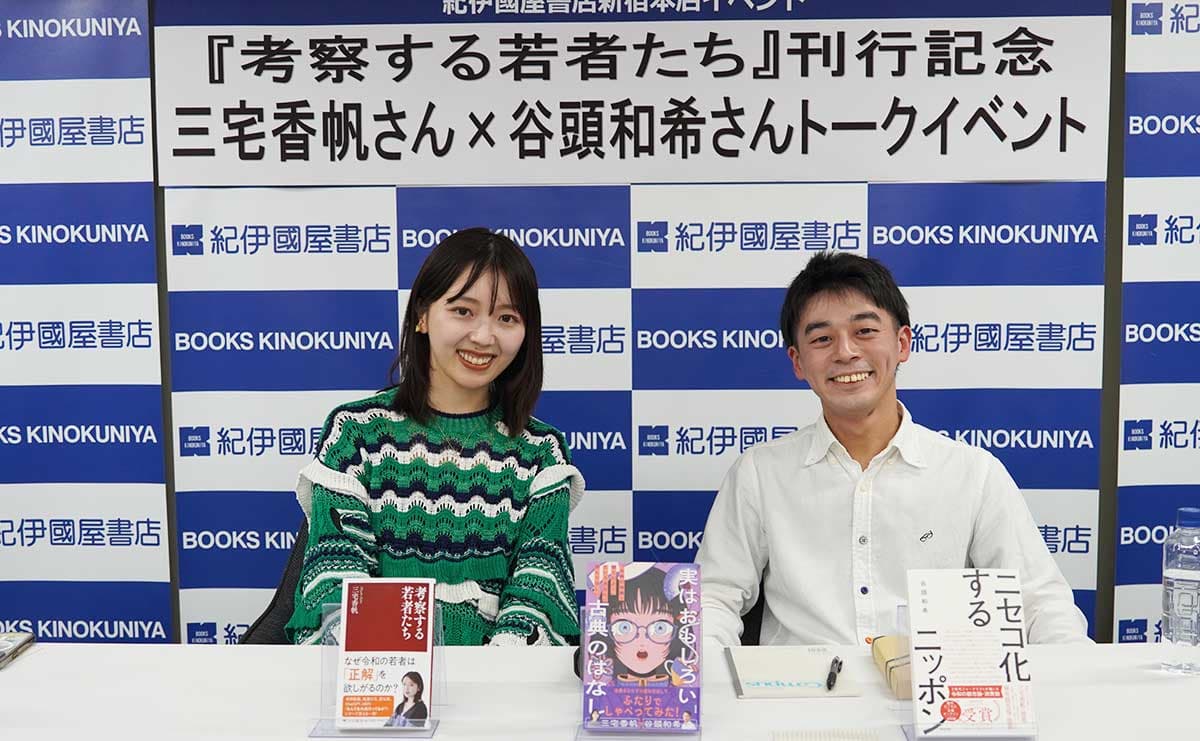就職してから時間がたってくると、さまざまな悩みを抱える人が多くなります。
入社前に抱いていた理想や希望がなかなか実現できなかったり、仕事の忙しさや人間関係に悩むあまり転職を考え始めたり...。そうすると「今とは違う場所でもうまくやっていけるだろうか」と気になってくるものです。
そのような時は、会社のようなビジネスの場ではどのような人材が求められているかをよく考えてみましょう。会社が社員に期待していることは、「成果を出すこと」です。
本稿では、書籍『どこでも通用する人は入社1年目に何をしているのか』より、どんな場所でも成果が出せる人材になるための思考について解説します。
※本稿は、原マサヒコ著『どこでも通用する人は入社1年目に何をしているのか』(総合法令出版)の一部を再編集したものです
"師匠"がいると成長は早い
昔は多くの職業で師匠の下に弟子入りをする"徒弟制度"があったそうです。今では落語などの古典芸能くらいでしょうか。漫才の世界では、吉本興業がNSC(吉本総合芸能学院)という養成所をつくったのと同時に徒弟制度がなくなっていったのは有名な話です。
徒弟制度は、時代の流れとしてはもうほとんどがなくなりつつありますが、入社1年目の皆さんには「自分で職場の師匠を決めよう」とお伝えしたいです。
仮にあなたがとんでもない天才で、人の力を借りることなく、自分の力だけでなんでも目標を達成できるというのであれば問題ありません。しかし、誰しも自分ひとりでできることには限りがあります。
私自身も会社に入って、師匠と呼べる人がいました(実際に呼んだことはないですが)。その人のやり方などを見よう見まねでやると、速く、確実に仕事を進めることができて驚いたことを、今でもよく覚えています。
考えてみれば、入社1年目の私より師匠のほうが、仕事も速く確実なのは当然です。このように、師匠から基本的なことを学んでしまえばスキルの習得が早くできるのです。
自分ひとりだけで悪戦苦闘していても、壁にぶつかってしまうと、乗り越えるまで時間がかかります。時にはどこに向かって苦労しているのかもわからなくなりますし、やる気を失ってしまうこともあるでしょう。
しかし、師匠とコミュニケーションを取ることで、その存在自体が1つの目標になり、時に励ましてもらうことでモチベーションの向上が期待できます。
ですから、自分のなかで師匠を決めてしまいましょう。
とはいえ、「誰が師匠としてふさわしいのかわかりません」という人もいるでしょう。
確かに、入社したばかりで先輩や上司のことをよくわからないのに、師匠を決めることには抵抗を感じるかもしれません。しかし、ここでの大切なポイントは勝手に設定するということなのです。
実際の徒弟制度では、師匠の下に弟子入りしたら覚悟を決めてずっと一緒に行動を共にしなければならないでしょうが、そういうわけではありません。
先輩の仕事ぶりを見ていて、部分的にでもすごいと思ったら、その部分だけでも心のなかで「この人を師匠とする」と設定してしまえば良いのです。
欠点よりも優れた点に注目しよう
多くの人は入社してすぐに先輩の嫌なところを目にしてしまい、同期と集まった飲み会などで先輩の嫌なところを言い合ってしまいます。「うちの部の先輩、こういうところが嫌いなんだよなあ」「わたしの上司は、こんなことを言ってきて嫌だ」と、愚痴のオンパレードです。
でも、よく考えていただきたいのですが、皆さんの先輩や上司が経験豊富とはいえ、人間的に完璧な人はいません。欠けている部分に目を向けていてもなんの意味もなく、時間の無駄です。
それよりも、その先輩の優れているところに目を向けて、その部分において「●●の師匠」と設定してしまうほうが自分のためなのです。
ほかの人格面はともかく、クレーム対応がとても上手で、丸く収めることに長けている先輩がいたら「クレーム対応の師匠」と勝手に設定したり、性格に嫌な部分があったとしても、会議でほかの人から意見を引き出し、スムーズに進行すること(ファシリテーション)に長けている上司がいたら「ファシリテーションの師匠」として勝手に設定し、それに関して徹底的に学んでいけば良いでしょう。そういうことなのです。
せっかく入った会社ですし、せっかく出会った上司や先輩ですから、「何か1つでも学んでやるぞ」「何か1つでも吸収してやるぞ」という気概で、勝手に師匠に設定してみてください。きっと、あなたの成長も加速していくはずです。
“こうなりたくない人”に自分がなっている可能性
「欠点より優れた点に注目しよう」と書きましたが、そうは言っても相手の悪い部分がなくなるわけではありませんよね。
でも、あなたがその相手の欠点に対して我慢してストレスをためたり、腹を立てたり、戦ったりする必要はありません。その時間がもったいないですし、何より疲れてしまいます。
私がおすすめしたいのは、反面教師にするということです。相手の嫌な部分に関して、なぜそう感じたのかを冷静に考え、「自分は同じことをしないぞ」と心がけていくのです。
こう書くとかんたんなように聞こえますが、これが実は難しいもので、どれほど心に誓っていても、数年経つと、その人と同じことを自分がやっていたりします。
たとえば、新入社員の時に上司から「俺が新人の時にはさあ...」などと武勇伝を語られることがあり、苦笑いで話を聞いていたとします。
そこで「自分は上司になったらそんなことは言わないようにしよう」と思っていても、何年かあとに新人に対して、「僕が新人の頃はさ...」などと同じようなことを語っていたりするのです。
結局これは、脳のなかに「この場面ではこういうことをする」という記憶が残ってしまっているので、なんの気なしにやってしまうことが多いのだと思います。
「反面教師」を可視化する
「なら、『反面教師にする』という考え方は何も役に立たないじゃないか」と思われるかもしれませんが、工夫をすれば良いのです。
私が実際にやっていたのは、"反面教師メモ"をつけることでした。たとえば上司が、些細なことですぐにカッとなって怒り散らすような人だったとしましょう。
その時に「あんな風にすぐカッとなって怒るような人にはなりたくない」と感じたとしても、脳のなかでは「些細なことでカッとなって怒る」という動きがインプットされ、自分でもいずれやってしまいかねません。
そこで反面教師メモに「どんな時でも穏やかな気持ちで対応できる人になろう」とポジティブに変換して記入しておくのです。メモに書いたポジティブな言葉でネガティブな事実を上書きするイメージです。
そうやって、ポジティブなイメージの理想像をしっかりと記しておき、定期的に読み返してインプットしておけば、いくら反面教師の人が身近にいたとしても、間違った方向には向かいません。
“反面教師メモ”から得られること
この反面教師メモには2つのメリットがあります。
まず1つは、自分の理想像が描きやすくなるということです。
最近では「自分の将来像を思い描けない」という人が増えているようです。なぜ思い描けないかというと、理由の1つに、目指したいと思えるような人が身近にいないことがあるようです。
何かお手本がないとイメージしにくいということなのでしょうが、気持ちはよくわかります。ただ、そういう人は立派な人が目の前に現れたとしても「あんな風にはなれないよ...」と思ってしまい、いずれにしても、未来の自分のイメージを思い描けなかったりするものです。
しかし、「ああはなりたくない」と思えるような人については、身近にいたりするわけです。であれば、その人を反面教師として、それを足がかりに自分の理想像を少しずつ描くようにすれば良いのです。
「ああはなりたくない」と思うことがあったら、ポジティブに変換してそのイメージをどんどん書いていきましょう。それが増えていくたびに、自分が理想とするイメージが固まっていくはずです。
もう1つのメリットは、目の前の嫌なことを嫌だと思わなくなるということです。
反面教師メモを書き始めると、不思議なことにメモ帳の余白を埋めたくなっていきます。
ネタが増えていけばいくほど自分の理想のイメージが固まりますから、早くネタを書きたくなるわけです。そうすると、目の前で上司が嫌なことを言ったり、同僚に嫌な態度を取られたりしても、「よし、これはメモに書こう」とか「また1つネタが増えた」とポジティブにとらえることができるようになるのです。
私も実際にメモをつけていると、なんとも不思議な感覚に陥りました。ネタを提供してくれる苦手な上司に、だんだんと「今日もネタを提供してくださり、ありがとうございます」と思うようになったのです。
私の場合は、最終的に反面教師だった上司が異動することになり、目の前からいなくなってしまいましたが、手元には素晴らしくポジティブなメモだけが残りました。私は何度もそれを読み返しながら、のちにどんな会社に行っても理想の環境をつくり上げていくことができるようになったのです。