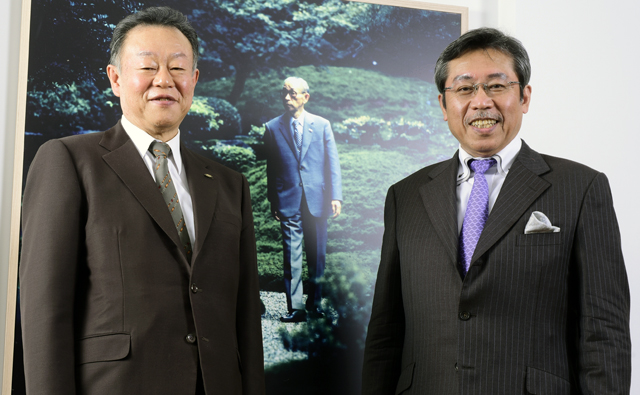みずから書く
 また、幸之助は話すことだけではなく、多くの社内媒体を通じて文書を公開することで理念の浸透に努めた。ことに終戦直後の昭和23(1948)年ごろから高度成長期に入る、松下電器においては経営が安定するまでの時期に執筆数が多いのは注目される。経営状況が厳しいときこそ、従業員に対して努めて思いを伝えようとしたのであろう。
また、幸之助は話すことだけではなく、多くの社内媒体を通じて文書を公開することで理念の浸透に努めた。ことに終戦直後の昭和23(1948)年ごろから高度成長期に入る、松下電器においては経営が安定するまでの時期に執筆数が多いのは注目される。経営状況が厳しいときこそ、従業員に対して努めて思いを伝えようとしたのであろう。
社内媒体の中でユニークなものに給料袋に毎月入れていたリーフレットがある。そこには幸之助からのメッセージが綴られていた。昭和28(1953)年1月から始めたこのメッセージについて幸之助は、「会社が小さくて、従業員の人びとの数がすくないころには、私もひとりひとりの人にお会いできたし、お話もできたのですが、今日のように会社が大きくなってしまうと、私も全部の事業場はとてもまわり切れないし、従って、私に話しかけて頂くどころか、顔も見たことがないという従業員の方がたが非常にたくさんになってきました。それでは従業員の方がたに申しわけないし、私もまたいささか淋しいので、せめて月に1回くらいは、親しくお話するつもりで、私の写真とともに、四季のあいさつを送りたいと考えて始めたのが、このリーフレットでした」(『月日とともに』収録の「まえがき」)と述べている。
ハガキ大のものを2つ折りにしたもので、2色刷り、幸之助の写真入りで、該当月のカレンダーも掲載している。毎回の文章量は700字程度、社員への手紙という体裁である。雑感を中心にしながら、日ごろの勤務への感謝の気持ちや、仕事に対する考え方をさりげなく披露している。このメッセージがスタートした当時の松下電器の従業員数は7552名であり、たしかにすべての従業員に日々直接問いかけをすることはできない。大企業へと変貌を遂げる現実に対して、従来の家族主義的な社風を維持しようという工夫でもあったかもしれない。またこの他、社内メディアとして重要な位置づけであったと思われる『社内新聞』、『PHP』誌の中で、幸之助はさまざまな連載企画を持つようになる。
幸之助の“語ろう”とするモチベーションの高さはどこからくるのであろうか。経営理念を徹底しようという意気込みによるのは当然のことであろう。
しかし、社内限定の媒体においても個々のメッセージは、必ずしも経営に直結するテーマに限られていない。たとえば、昭和28(1953)年3月の給料袋には「心に青空を」と題して次のような文章が配された。
「みなさん、春がやってきました。厳しかった寒さも、日と共にやわらいで、暖かい日射しに万物の萌え出る春が、をなでるそよ風と共にやってきたのです。
こんな季節のよく晴れた日に、胸一ぱいに大気を吸って青空を仰げば、まことに春風駘蕩、伸び伸びとした喜びに溢れます。春は人生に希望を与え、青空は人間に豊かな心を与えます。
もっとも、人の心もそして環境も、十人十色でさまざまです。だから人生を楽しむ人もあれば、これを悲しむ人もあります。しかしどんなときにも、お互いに心に青空を持ちたいものです。春の青空のように、小さいことに捉われず、つまらぬことにくよくよせず、伸び伸びとした心で仕事をやっていきたいものだと思います。
春です。春がやってきました。みなさん一しょに、この良き季節を楽しみましょう。
しかし、春を楽しんでも、これにおぼれてはいけないと思います。酒を飲んでも、微醺の時はまことに楽しく春風駘蕩ですが、酒におぼれ、これに負けると、人と口論したり迷惑をかけたりして、秋霜烈日のような目に会います。これと同じことで、春におぼれてはいけないのです。これを楽しむのです。春の青空のように伸び伸びと心を伸ばすのです。そこからきっとよい知恵が湧いてきます。希望が生まれてきます。そして、百花撩乱の心の花がひらいてきます。
心に青空を。そして青空の如き人生を。
せっかくの良き季節です。今月は一つ春の青空を仰いで、伸び伸びとした心で働いていきましょう」
エッセイのようなこの一文にも、自然と人間の関わりから、人心の妙、組織人としての規律、個性の発揮、人生の味わいを盛り込み、含蓄に富む。幸之助は経営理念をただ訴えたのではない。理念の背景にあるみずからの社会観・人生観すべてを吐露したというのが近いのではないだろうか。このように考えれば、経営理念の誕生も幸之助の哲学する姿勢がもたらしたものだと理解できる。
伝道師をつくる
所信を記録させ、またみずから筆をとるといった幸之助の“語ろう”とする努力は、経営理念の伝承という点で新しい現象を生んだ。幸之助の指導を長年にわたって受けてきた経営幹部たちが、それぞれ幸之助哲学の語り部になっていったことである。その代表格は、会長を務めた高橋荒太郎である。高橋は松下電器内でも「ミスター経営理念」と呼ばれるほど、幸之助の理念に即した経営を訴え続けた。幸之助が唯一“さん”づけで呼んでいたのは、それだけ幸之助と一心同体ともいえる信頼関係を結んでいたからであろう。
古参幹部たちは、それぞれが幸之助との対話や指導を受けたエピソードを誇りとして、後輩社員に語り継いだ。昭和53(1978)年から55(1980)年まで5冊にわたって、『PHPゼミナール特別講話集 松下相談役に学ぶもの』(PHP研究所編・非売品)が発行されている。
これらは彼ら経営幹部が、創業以来、戦前、戦中も含め、幸之助からどのような指導を受けたかという体験談、幸之助の人となりを示すエピソードの数々を語ったものである。研修における講話の形なので非常に説得力がある。
幸之助自身は昭和48(1973)年に松下電器会長職を退いて相談役となっており、経営の現場からはさらに遠ざかっている。しかし、こうした経営陣、OBの理念伝承への意識は相当高く、幸之助とのエピソードを語り合う回想録の存在は、経営理念の浸透徹底、社内風土の維持に対する問題意識の高さを示すものである。
こうした幸之助の“語ろう”とする活動は、経営理念継承という点では、経営幹部たちを次世代に理念を伝える貴重な語り部に育てあげた。人を介して語り継ぐことができる組織は、一般的な企業の理念継承にはたいへん有利だといえよう。
幸之助の没後、とかくトップ人事異動や組織改革が発せられるたびに幸之助哲学の維持がマスコミで問われたものであった。それは松下電器の理念に対する強い伝統が企業価値の根幹にあると社内外とも認めているからであろう。しかし、そうした理念の重みは、ほかならぬ幸之助自身の尋常ではない“語ろう”とする努力がつくった遺産だといえる。幸之助が松下電器社内において語り続けたからこそ、理念を重んじる経営は確立されたのであり、これからもパナソニックの伝統として継承されていくであろう。
さて、ここであらためて考えておきたいのは、幸之助にとって理念とは何かということである。経営理念とは、よい経営をするための基本の考え方にほかならないものだが、幸之助は理念とはそれぞれが確立するものだと考えており、その理念を確立するには、その人が 「みずからの人生観、社会観、世界観というものを常日ごろから涵養していくことがきわめて大切だ」 (『実践経営哲学』PHP文庫、21頁)と説いている。
幸之助は、何のための事業か、何のための仕事かということを考え続けた。その姿勢が経営理念に結びついた。しかし、経営理念と直接結びつかないことであっても、社員に語り続けるなかで、人生や人間、社会に対するみずからの思索を深めていったのではないか。そうした人生観や社会観は、社員にひたすらに“語ろう”と努力しているうちに、次第に築きあげられたのであり、さらにまた経営以外の分野についても蓄積されていったのではないだろうか。
思いの強さが根本
昨今、企業家がみずからの事業に見合った経営理念をつくるためのマニュアル本が販売されている。企業にふさわしい理念をかき集め、理念としての体裁を整えるのに便利なのは理解できる。しかし、それで本当に経営者の哲学に沿った経営理念が生まれるのであろうか。
幸之助は、事業において「経営理念を確立すること」を第一義とし、そしてその確立のためには経営者が人生観・社会観・世界観を涵養することが重要だと述べていた。その主張が、幸之助自身の経験に基づくものであることは見てきたとおりである。
厳密な意味で幸之助の思索の深さが天性のものだったからか、あるいは前半生におけるさまざまな苦労が育んだものかは、議論の余地があろう。ただ、事業に対する強い思いがあってこそ、みずからの経営理念に重みを与え、それがまた社員に伝えることに対する惜しみない努力につながっていったのだ。経営者が経営理念に対する思いを失っていては、伝えるのにどんな工夫をしても力のないものになる。まずはみずからの思いの強さを問いかけるべきではないだろうか。