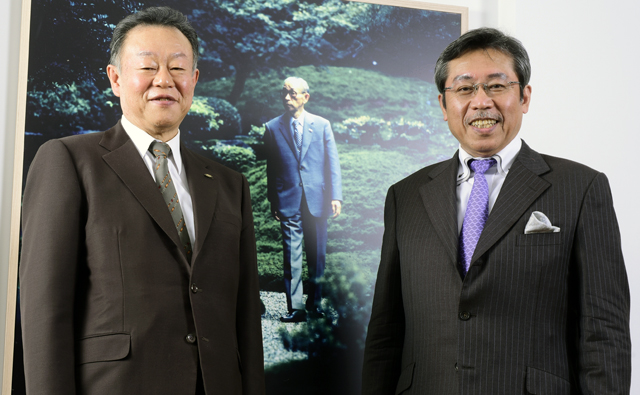『PHPビジネスレビュー松下幸之助塾』 2012年 9・10月号 Vol.7 より
創業者とは偉大である。まず何よりも会社に関わるすべての職能に通じているし、そもそも経営理念を確立したという点で偉大である。そして、創業者はただ理念をつくっただけでなく、経営理念を浸透させるということにおいて、だれよりも情熱を注ぎこむ努力の人であることが多い。ここでは、若き松下幸之助が創業期から取り組んだ、経営理念の浸透に対する努力のあとをふり返ってみたい。
松下幸之助にとっての理念
松下幸之助(以下、幸之助)が経営理念を模索し始めるのは、社員が100名を超えたころからであったという。比較的順調な経営を続けていたが、このころから経営上のさまざまな悩みに直面し始めた。
たとえば、同業他社との競争において、自分が勝利するということは、同業者の経営を圧迫することになり、それははたして許されるのかという道義的な悩みであるとか、代理店との結びつきが強固になって、代理店の中には自社の経営を松下電器に依存してくる会社が出てきたが、得意先の経営責任まで負わなければならないものなのかという疑問である。さらには決算において税務署との見解の相違があり、課税をいかに解釈するか葛藤したという経緯もあった。
こうした葛藤を経て幸之助は、「松下電器は人様の預り物である。忠実に経営し、その責任を果たさなければならない」(『私の行き方 考え方』PHP文庫、244頁)という覚悟が定まったという。
幸之助の経営理念がさまざまな形で定まるのは昭和4(1929)年からである。この年、経営の基本方針というべき「綱領」と仕事の心がまえを示す「信条」が確立され、昭和7(1932)年には松下電器の根本理念である、産業人の使命を闡明 <せんめい> する。昭和8(1933)年には、仕事の心がまえをさらに具体的に説いた「松下電器の遵奉すべき精神」、昭和10(1935)年には、社風づくりのための一環として制定した「松下電器基本内規」等を確立していく。
これら一連の経営理念は改訂されることはあったが、おおよそ40歳までに形成されている。
どのような手段を使ったか
経営理念は、トップマネジメントに関係する人だけが知っていればよいというものではなく、社員全員が価値観を共有して、初めてその効力が発揮される。具体的には倫理感が高まったり、戦略が定まったりする。だからこそ、理念を生み出した企業家は、みずからの理念をなんとか浸透させようとするのであろう。
では、先に述べたように日々の葛藤、気づきの中から理念を生み出した幸之助は、その後いかに組織内に理念の浸透を図ったのであろうか。
みずから語る
まず昭和16(1941)年の資料に『社主一日一話』というものがある。これは昭和8(1933)年5月から翌9(1934)年4月までの、幸之助が松下電器の朝会、もしくは午後の納会で話した訓話と、以降の断続的に行われた社員への訓話合計228回分の速記録である。日常的に見聞したことに材を得たごくありふれた所感の形をとっているが、どの話の結末でも社員の人生観や仕事観の向上を示唆しようとする。
この記録は、幸之助がとにかく社員に“語ろう”という姿勢を有していたことを顕著に示している。毎日、40歳に満たない青年経営者がそれなりの感懐を語るということは、話材を集めるだけでも相当の意識を持たなければ続かない。幸之助はこれを1年間やり通したのである。
しかもこの直話は、当初からそのまま速記が取られていたことに注意を払わなければならない。社史の整備のためや、現場で直接訓示を聴けなかった社員のために残したといわれるが、幸之助自身のためだったとも考えられている。というのは後年、幸之助は話術の達人として知られるようになったものの、元来口下手であったからだ。訓話のあと速記録を読み返したり、音声を聴き直したりして話術の修練に努めたといわれている。
また、戦後、昭和38(1963)年1月には、松下幸之助講演集第1集として『処世雑感』が、5月に第2集『経営雑感』、翌昭和39(1964)年2月に第3集『経営雑感(Ⅱ)』、同年5月には第4集『青雲雑話』と講演集が刊行されている。これら講演集の内容は、一部社内向けのものもあるが、多くは社外で求められた講演の記録である。この時期相次いで編まれたのは、幸之助が昭和36(1961)年に会長職に退き、講演がにわかに増えたからであろう。当時、高度成長期のリーディングカンパニーとして松下電器が評価されていたことから、立志伝中の人物として幸之助への講演依頼が増えていたようだ。