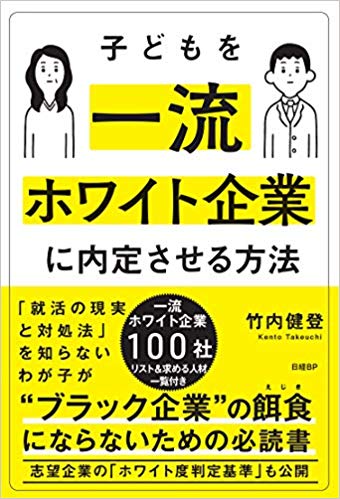一説には「7人に1人が就活うつになる」とまで言われているという、昨今の就職活動事情。その要因は、学生の多くが誰もが知る「ホワイト企業」を目指し人気が特定の企業に集中することにある。
こんな時代だからこそ、就活コンサルタントの竹内健登氏は、親のサポートが重要になると主張し、自らも就活指導のスクールを運営している。
ここでは、竹内氏の自著『子どもを一流ホワイト企業に内定させる方法』より、子どもに誤ったアドバイスをしてしまう要因となる、親と子の世代間ギャップと現在の就活の実情を語った一節を紹介する。
※本稿は竹内健登著『子どもを一流ホワイト企業に内定させる方法』(日経BP刊)より一部抜粋・編集したものです
「売り手市場」という神話が現実を隠す
あなたは、就活について今、どのようなイメージを持っていますか?
「今は、過去最高の有効求人倍率を更新して、"売り手市場"だから、楽勝とまではいかなくても、そこまで大変ではないはず」
メディアの情報を受けて、このように考える方は多いのではないでしょうか? 一方、就活生からはそういった楽観的な声は、まったくといっていいほど聞こえてきません。
実際、「7人に1人が就活うつ」になるほど、苦しい状況に置かれています。
この親子間における認識のギャップは、2019年2月に当スクールで実施したアンケートでも明らかになっています。
「就活中に親子間で感じたギャップ」の1位が「就活で内定を取ることの厳しさについて、(親が)理解してくれない」。当スクールに通う学生の実に35%が、このように感じていたのです。
さらに、その親子間のギャップを感じた理由を尋ねたところ、以下のような意見が集まりました。
「親は、大学名とGPA(学業成績)、TOEICのスコアだけで内定が取れると楽観視している」(早稲田大学生)
「父が高学歴であり、バブル期に就職したこともあって就活に苦労した経験がないため、今の就活を少し軽視していたように感じた」(法政大学生)
「世間は就職がしやすいと言うが、それは全会社に当てはまることではないと親が理解していない」(名城大学生)
「どれだけ就活が大変なのか、親はまったく理解していない。そのため、就活以外の活動(バイト、サークル、家事など)を減らすと、『お前はサボっている』と悪口を言われる。バブル時代と一緒にしないでほしい」(名古屋大学生)
このアンケートには、ここで紹介した以外にも「親が、今の就職活動の実情を知らない」
「大変さを理解してくれない」などの意見が目立ちました。実際、親御さんの時代と今の学生さんとでは、就職活動の様子は一変しています。端的に言うと、学歴や志望業界にかかわらず、競争が激化しているのです。
その背景には、次の3つの要因が挙げられます。