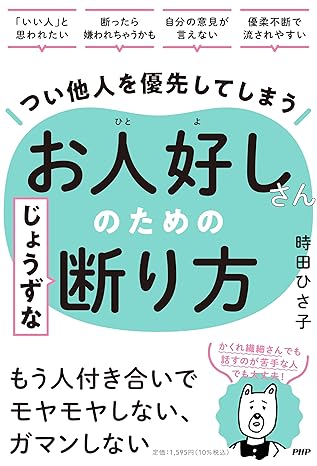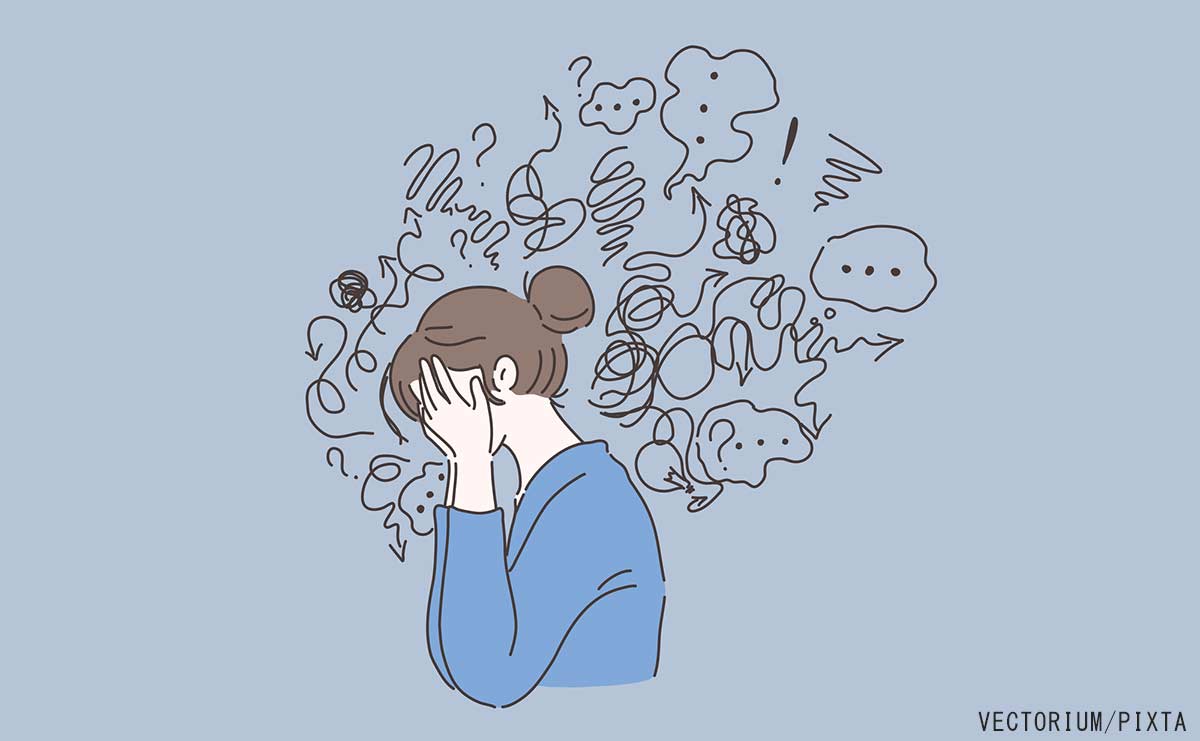本当は嫌なのに、頼まれたら断れない。上手な断り方がわからずに困ってしまう。お人好しな性格の人は「断ること」が苦手な傾向にあります。
先日『つい他人を優先してしまう お人好しさんのためのじょうずな断り方』を上梓した、HSS型HSP専門心理カウンセラーの時田ひさ子さんに「断れるようになることのメリット」や、お人好しさんでもできる「上手な断り方」を教えていただきました。
どうして断れないのか
――まず最初に、新刊『お人好しさんのためのじょうずな断り方』のテーマでもある「なぜ断るのは難しいのか」について、教えていただけますか?
【時田】人が断ることに困難さを感じるのは、相手をがっかりさせたくない、傷つけたくないという気持ちがあるからです。また、「断ったら次から誘われなくなるのではないか」「このチャンスを逃してはいけないのではないか」といった心理も働きます。
さらに、相手が年上であったり、仕事上の上司やお客様などの立場にある場合は、より断りにくくなることが多いです。
また、親しくない相手の場合、断った際の反応が読めず不安に感じることもあります。そのため、断れない人は「相手に嫌な思いをさせないこと」を優先し、自分が我慢するという悪循環に陥っているのです。
――相手の反応を考えすぎてしまうのですね。
【時田】そうですね。相手の気分を害することを恐れて、自分の気持ちを後回しにしてしまうのです。その結果、必要のないことまで引き受けてしまい、自分の時間や労力を浪費してしまいます。
本書では、そうした悪循環を断ち切る方法についても書いています。無理に引き受け続けると、「なぜ自分ばかり」といった不満が募り、人間関係が悪化することもあります。しかし、適切に断ることで、相手との関係を維持しつつ、自分の負担を減らすことができるのです。
――その「断れないループ」を断ち切ることで、具体的にはどのような変化があるのでしょうか?
【時田】メリットはいろいろあります。まず、断れることによって、やらなくても良い、負担に感じていたことから解放されます。「断れる」という自信がつくことで、自己肯定感にも良い影響を与えると思います。
また、いつでも断れるからこそ、何かの集まりに「ちょっと顔をだしてみようかな」と気軽に参加できるようになるかもしれません。もしその環境が合わなかったら、次回は行かないという判断ができるようになるのです。
さらに、優しさにつけ込まれることを防ぐこともできます。断ることに苦手意識のある方は、お人好しさんが多いと思うんです。自分にとって負担となることを頼まれた際に、やんわりと断れることで、自分の心を守ることができます。
人生にも大きく影響する?
――断れるようになると、ひょっとして人生が変わったりなんてことも...?
【時田】長期的にみれば、断れることによって人生は大きく変わると思います。私自身も以前は、頼まれたらつい引き受けてしまっていましたし、無駄なお金も結構払っていました。例えば、営業を受けると断れなくて買ってしまったり、洋服屋さんに入るのも苦手だったんですよね。
――洋服屋さんで接客を受けると、断りづらくてつい買ってしまうこと、私もよくあります。
【時田】勧められると「乗ってあげなきゃいけないんじゃないか」と思ってしまい、断れなくなってしまいますよね。その結果、買わなくてもいいものを買ってしまうのです。
でもいざ、お店から出た瞬間に後悔することも多いのではないでしょうか。家に帰って試着してみたら違和感があったり、思っていたのと違ったり。でも、試着の段階で「断ってもいい」と思えていれば、その違和感や、マイナスポイントに気づきやすくなるんです。
試着する時点で「買う前提」になってしまうと、マイナスポイントを探そうとしなくなります。でも、「断ることもできる」と思って試着すれば、例えば「チャックの上がり方が微妙」とか「色が思ったのと違う」といった点に気づきやすくなります。
そして、後になって「断れなかった自分」に腹が立つこともなくなります。断れるようになれば、無駄な買い物をせずに済み、自己嫌悪に陥ることもなくなります。
――断れないことが知らず知らずのうちに負担になっているかもしれませんね。
【時田】「断らなきゃ」と思いながらも言えないと、頭の中で葛藤が生まれ、自分を責めてしまうこともあります。でも、断ることが習慣化されれば、そのストレスから解放されるんです。
断り上手なのに人気者の共通点
――「きちんと断れるのに人気がある人」もいると思うのですが、何か共通点はあるのでしょうか?
【時田】確かに"断れるのに人気がある"人には共通点があります。先日たまたま見たYouTubeの動画で、ある成功した経営者の方が話していたことが印象的でした。その方は「優れた経営者は、非常にジェントル(穏やかで丁寧)である」と語っていました。
彼らは相手に配慮しながら、しかしきちんと断るべき場面では断ることができる。つまり、ただ柔らかく対応するだけでなく、必要な場面で毅然とした態度を取れるからこそ経営者として成功しているように思います。
――断っても相手を嫌な気持ちにさせない工夫が必要ということでしょうか。
【時田】人気のある人は総じて物腰が柔らかいです。相手がどう感じるかを考えつつ、しっかりと断ることができる。本にも書きましたが、その"しっかりとした断り"は、何気ないやり取りの中に自然に紛れ込ませることがポイントです。
逆に、嫌われる断り方をする人の特徴もあります。それは、断る際に突き放すような言い方をすることです。冷たく突き放すと、相手に不快な印象を与えます。また、第一声で「いやー」などと否定の言葉を発することも好ましくないでしょう。
――なるほど。では、具体的にどのように断れると良いでしょうか。
【時田】大きく分けて三つのポイントがあります。
一つ目は、"肯定から入る"こと。何かを頼まれたときに、いきなり否定から入るのではなく、まずは相手の依頼に共感を示すことが大切です。例えば、「なるほど、良いアイデアですね。ただ、今回は対応が難しそうです」というように、最初に肯定的な言葉を入れると、相手の受け止め方が変わります。
二つ目は、"自分の事情を話す"(事実を伝える)こと。何かの誘いに対して、無理な理由を率直に伝えましょう。「その日は予定がある」「今回は○○のような都合があり」と簡潔に説明します。
三つめは、"代替案を提示する"こと。「別の機会にぜひ」「他の方法でお手伝いできるかもしれません」といった代案を示します。また、その際に"クッション言葉を使う"ことも意識してみましょう。例えば「申し訳ありませんが」「恐れ入りますが」「可能であれば」といったフレーズを挟むことで、断りのニュアンスが和らぎます。
断るときに意識すべきポイント
――いざ断ろうとすると言葉が出なかったり、メールであれば文面を考えているうちに時間が経ってしまうこともあるのではないでしょうか。そんな時、最低限意識すべきポイントはありますか?
【時田】私がやっていておすすめなのは、丁寧な断り言葉の一覧表を作ることです。例えば、「申し訳ありませんが~」「せっかくですが~」といったフレーズを用意しておくと、断り方に迷うことが減ります。
断る際のステップは基本的に変わりません。まず、相手の話を肯定し、一言添える。そして、「その日はあいにく~で」と理由を述べ、「またの機会に」とやんわりと提案することが大切です。
相手との関係性によっても伝え方は変わります。例えば、時間変更をお願いする場合、あまり親しくない間柄であれば、いきなり「14時半に変えてください」ではなく、「時間の変更は可能でしょうか?」と一旦確認するなど、相手への配慮が見えると良いでしょう。
――先ほどの買い物の事例でも使えそうですね。
【時田】そうですね。店員さんに勧められたら「素敵ですね」と肯定しつつ、「丈が少し長いかも」などと事実を伝え、買わない場合は「申し訳ないのですが、また今度」などと優しく断ります。この流れを意識すると、お互いに気持ちよくお買い物ができるのではないでしょうか。
(取材・編集=PHPオンライン編集部 片平奈々子)