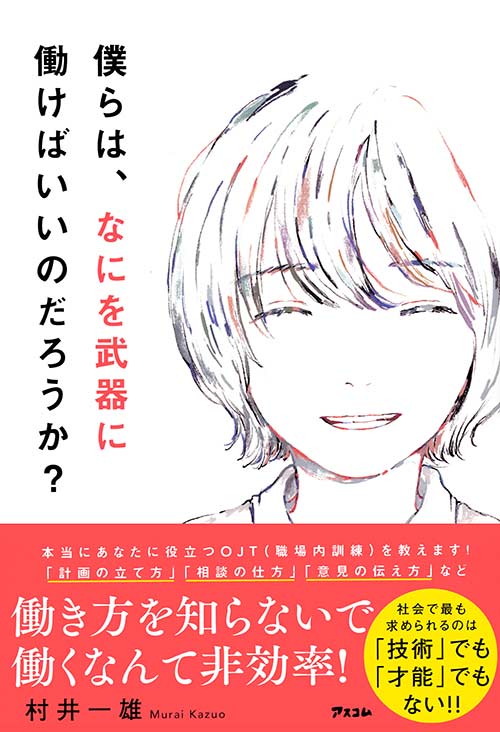「パワハラ扱いを恐れて指摘できない」マネジメントに悩む上司に必要な一つの視点
2025年06月05日 公開

「部下の指導に時間を取られ、なかなか自分の仕事が進まない」「パワハラと言われるのが怖くて思うように部下の指導ができない」など、部下の教育に悩む上司は多いのではないでしょうか?
マネジメントをしていく上での、部下との関わり方のコツについて、株式会社中之島設計代表取締役の村井一雄氏に話を聞きました。
※本稿は、村井一雄著『僕らは、なにを武器に働けばいいのだろうか?』(アスコム)より、内容を一部抜粋・編集したものです。
作業のやり方を伝える前に部下に教えるべきこと
例えば入社して○カ月は△△を覚えてといった、会社員としてのスキルアップの道筋などは、会社ごとで決められていることが多いでしょう。
しかし、ただ単純にタスクを渡すだけでは、単なる作業を覚えるだけになってしまいます。
仕事に慣れるという意味ではいいと思うのですが、それよりもまずは、会社員として、どのように働いていけばいいのか。そこを共有し、踏まえた上で作業してもらうことで、仕事への理解が深まります。
一人前の「プロ」と認められている人がどういう力を持っているのかを明確にすることで、具体的な目標が見えてきますし、意識しておくことで、働き方も変わってくるはずです。
部下と共有している基準があれば、部下がミスを犯したとしても、ダメな理由もよりはっきりして指導もしやすいのではないでしょうか。
もう1つ、どれくらいの期間で、どういう状態になってほしいのかを示してあげることも大切です。新卒は当然ですし、中途で入った人も、その会社でやっていけるかどうかということには、誰しもが不安を持っています。
先の見えない道を歩むのはとても不安です。
その不安に押し潰されて、途中で挫折してしまい、会社を辞めてしまう人も少なくありません。
できるだけ明確に、あなたがどういう道をこれから歩んでいくのか。そして、その先にはどういう「あなた」が待っているのか。仕事ができるようになって得られる楽しさも含めて伝えてあげてください。
そこでつづられた未来が、仕事に行き詰まったと感じたときの支えになってくれるに違いありません。
そしてなにより、あなたが仕事を楽しそうにこなす姿を見せてあげたり、話してあげたりすることです。
実際に目に映る光景や体験談以上に、説得力のあるものはないでしょう。
自分もこうなるために頑張るんだという気持ちが醸成されることで、日々の仕事へ打ち込む活力になるでしょう。
マネジメントは一人で抱え込まなくていい
多くの会社で新人が入ると、教育係という係に誰かしらが任命されて、その新人のマネジメントをすることになるでしょう。
直属の部下ができたことで、少し自分も会社の中で偉くなったように感じて、気合が入る人もいることでしょう。
ですが、人を育てるのは、大変です。
あまりにも部下への指導ばかりに目がいくと、自分に負担ばかりがかかってしまいます。
まず考えたいのが、自分の仕事の効率化です。
時間がかかっているところをもっと短時間にすませるコツはないか、上司や同僚にアドバイスを求めることにも時間を使ってください。
また、切羽詰まっているときなどは、ここからここは自分の仕事の時間に使うということを決めておくのも1つの手です。
人間は、同時並行でいろいろとこなせるほど、器用にはできていません。
部下に指導して、次に自分の仕事をしてといったように交互にやっていると、視野が狭くなり、非常に効率が悪くなります。
もし忙しすぎて質問などに答えられない日は、ほかの人に頼めばいいのです。
本人に許可をとった上で、「今日は、なにかわからないことがあったら〇〇さんに相談してくれる?」と頼めばいいだけです。
直属の部下という言葉に惑わされないでください。
会社全員で育てていけばいいのですから、なにからなにまで、あなたの時間すべてを捨てなくてもいいのです。
もし部下が言うことをきかずに扱いに困っているなら、状況を話した上で、ほかの人から部下を諭してもらうのもいいでしょう。
同じようなことをほかの人から言われれば「あの人だけの意見じゃないんだな」と部下も納得しやすくなることもあるかもしれません。
どうか「自分1人で面倒を見なくちゃ」という考えは捨ててください。
もう1つは、部下の作業スピードを把握し、終わりそうなタイミングで次の指示内容をまとめておくことです。
部下の作業スピードを把握していないと、自分が思っているより早く終わったときに、与えられる仕事がないので、部下を手持ちぶさたにさせてしまうことになります。
逆に、部下が思っているより遅い場合、次の準備をいつしようとか、ほかにもいろいろとやってほしいのにとモヤモヤします。
急に作業が速くなることはありませんし、成長速度は人それぞれ。速くなるようなアドバイスは必要ですが、自分は新人のときもっと速かったとか、他の子はもっと速いとかで、イライラするのは厳禁です。
部下のスピードを理解し、それぞれの速度で、ノンストップで仕事できるように調整することがマネジメントのコツだといえるでしょう。
パワハラと言われにくい部下との接し方
パワハラという言葉が世に広まって以来、部下や後輩に注意ができない、しにくいという人もいます。
結局は人の受け答え方なので、一概にこれが正しいというものはないのですが、ひとまず気をつけるべきなのは、部下に注意を促すときは、感情をのっけないことです。
感情がのっかってしまうと、語気が強くなったり、言葉づかいが荒くなったりしてしまいます。
一度感情を無にして、冷静に、今の事実のみを語ってみてください。
例えば、部下の仕事が遅々として進んでいないとき、「今までなにやっていたの?」とちょっと声を荒らげたくなるのを我慢して、「これだと、計画から○日遅れていて、納期に間に合いそうにありません」と事実を伝えるのです。
もう1つは、「2対1の法則」を意識することです。
あなたがしゃべるのを2、相手がしゃべるのを1にする。事実を述べて、質問で2、相手が答えるが1です。
一方的にしゃべっていくと、有無を言わさない感じがして、相手が圧力を感じやすくなってしまいます。
相手にもしゃべらせてあげることで、感じる圧力は、少し弱まるものです。
そして、最後には必ず解決策やアドバイスを提示することが肝心です。自分たちだけで、具体的な解決策やアイデアが出ない場合は、「上司に相談してみよう」というのも、立派な解決策の1つです。
解決策やアドバイスを最後に付け加えることで、叱責ではなく、助言へと昇華されるのです。
部下の「大丈夫です」は、大抵大丈夫じゃない
「困ったことがあったら相談してね」と部下に言っても、なかなか相談にこない人がいます。
あなたにも、「相談したいけど、上司は忙しそうで話しかけづらい」と思った経験はないでしょうか
だからこそ、最初のうちは、上司から「状況どう?」「順調に進んでいる?」と声がけすることが必要なのです。
それを繰り返し、関係が構築されるのと比例するように、いずれは部下から相談にくる可能性が高まってきます。
こちらから問いかけたときに具体的な悩みが出てくればいいのですが、困るのが、「大丈夫です」という答え。
もし、「大丈夫です」とだけ答えられたなら、必ず今の状況とこれからやることも聞いてあげてください。
そこまで聞いて問題なければ、本当に大丈夫です。
なにが言いたいかというと、「大丈夫です」という言葉を聞いて、それで安心して部下の席を離れないのが大切だということです。
「大丈夫です」の言い方がどこか暗くて迷っている感じなら大丈夫ではないことに気がつきやすいです
ですが、なかには、その場を取り繕うために、不安を押し殺して、元気に「大丈夫です」と言う人がいます。
さらには、今の自分の状況がいいのか悪いのかが判断つかない、もしくはなにを相談していいかがわからずにそう答える人もいるでしょう。「大丈夫」は、疑ってかかってください。
また、部下が困っていないか、目配りをすることも上司としては大切です。特に部下の挨拶の声には、気をつけてください。
いつもより声が小さかったり、言葉に覇気がなかったりすると、なにか困っていることがある可能性があります。
職場でのスイッチが入っていない状態なので、本当の自分の気持ちが出やすいのが挨拶ではないかと考えます。
挨拶が気になったなら、「元気ないね。なにか困っていない?」と上司のほうから声をかけてあげるのがいいでしょう。