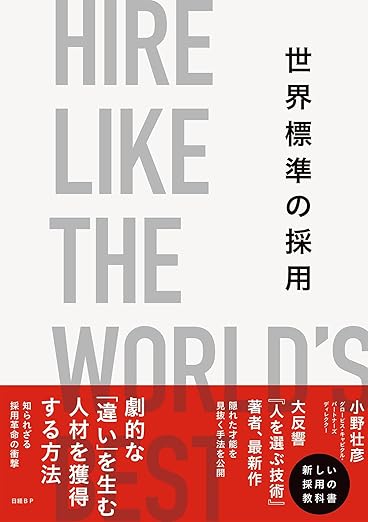2000年中ごろから、この20年ほどの間で、世界の採用手法は劇的な変化をとげました。その要因は、リンクトインやビズリーチ等による新しいサービスの発展、そして巨大企業グーグルが全世界で実践した革命的な人材採用にあるといわれています。
その大きな特徴は、採用エージェントに頼らないダイレクトリクルーティング、そして、より良い人材を獲得するために経営資源を惜しみなく投入する仕組みにあります。
本稿では、そのような世界標準の採用を導入するにあたり、ポイントとなる社内にTA(Talent Acquisition 才能ある人材を獲得しにいく)チームをおくことの意味について、グロービス・キャピタル・パートナーズ ディレクターの小野壮彦氏に解説して頂く。
※本稿は、小野壮彦著『世界標準の採用』(日経BP)を一部抜粋・編集したものです。
インハウス化の魅力
リンクトインやビズリーチがもたらしたダイレクトリクルーティングの革新性は、採用候補者を集めるソーシング業務を企業が自社内に取り込めるようになった点にあります。
それ以前、人材を求める企業は、ソーシングを外部の採用エージェンシーに大きく依存していました。なぜなら、市場に出ている候補者情報を網羅的にカバーするデータベースを持つのは、一部の採用エージェンシーだけだったからです。
ところが今では、リンクトインやビズリーチのツールがあれば、採用エージェンシーに頼らなくても、同じくらい充実したデータベースに自力でアクセスできるようになりました。つまり、採用活動の「インハウス化」が現実のものとなったのです。
では、そもそも、なぜソーシングをインハウス化する必要があるのでしょうか。それにはどのようなメリットがあるのか、まず概論として整理してみましょう。
ダイレクトリクルーティングによるソーシングのインハウス化が企業にもたらす利点は、大きく以下の5つに集約されます。
1.コスト効率化
まず注目すべきは、コスト効率の改善です。外部の採用エージェンシーを利用する場合、日本では一般的に、採用が決定した候補者の年俸に対して30~40%、時には50%もの手数料が発生しています。これは企業にとって大きな負担です。
一方で、インハウス化されたダイレクトリクルーティングを活用すれば、1人当たりの採用コストを大幅に削減することが可能です。
たとえば、英国では、外部の採用エージェンシーを利用した場合の採用コストが候補者の給与の15~30%程度であるのに対し、ダイレクトリクルーティングの場合、1~5%程度に抑えられるとされています。これは、特に成長を続ける企業や、採用ボリュームが多い企業にとって大きなメリットとなります。
2.広範なタレントプールへのアクセス
採用候補者の情報を蓄積するデータベースは「タレントプール」と呼ばれ、採用活動において極めて重要な役割を担います。外部の採用エージェンシーを利用する際には、それぞれのエージェンシーが持つタレントプールにアクセスできることが大きな魅力となりますが、一方で、特定のエージェンシーのネットワークに依存し、情報が制約されるというデメリットもあります。
これに対し、ダイレクトリクルーティングはそのような制約を受けません。TAチームが活用できる採用候補者の情報は、リンクトインやビズリーチなど採用プラットフォームにあるタレントプールにとどまりません。様々なソーシャルメディアや従業員からの紹介(リファラル)、業界特化型のネットワークなど、幅広いチャネルを活用し、採用候補者の情報を独自に集めることができます。このアプローチにより、トップタレントを探索し、特定し、引き寄せる活動の自由度が格段に高まります。
さらに、これらの活動を通じて、事前にアセスメント(評価)を行った候補者のデータベース、つまり自社独自のタレントプールを社内で構築できれば、重要なポジションを迅速かつ効果的に充足する準備が整います。
3.企業ブランドの強化
インハウスでダイレクトリクルーティングを担うTAチームのメンバーは、単なる採用担当者にとどまりません。彼らは、自社を代表する「ブランドアンバサダー」としての役割を担います。
自社を深く理解した社内人材が、まるで「ふるさと大使」や「おらが町の代表」のように、候補者との接点で自社の文化や価値観を体現します。これにより、スキルや経験の適合性だけでなく、文化や価値観の共有なども含めた多面的な観点から、最適な人材を引き寄せることが可能となるのです。
このプロセスを通じて、TAチームの活動は、ポジションを充足するだけの採用の枠を超え、採用市場における企業の存在感を高め、強固なエンプロイヤーブランドを形成するものとして機能しはじめます。
4.より大きな裁量と柔軟性
インハウスのTAチームを構築することで、企業は採用プロセス全体において、より大きな裁量と柔軟性を手に入れることができます。特に、時間軸をコントロールできることは大きなメリットを生みます。
採用エージェントを経由した採用では、往々にして、選考の進捗を急かされるものですが、インハウスの採用ならば、じっくりと選考を進めることが可能となります。優秀な人材に対して、相手が納得いくまで何カ月も相互理解の時間を取ることもできますし、逆に、内定を出すタイミングを思い切って早くすることもできます。
時間軸のコントロールは、候補者とのリレーションを育てるための選択肢を増やします。この柔軟性が、迅速でありながら質の高い採用を可能にし、ミスマッチのリスクを低減することにもつながります。
5.長期的な戦略的利益
インハウスのTAチームへの投資は、短期的な採用ニーズを満たすだけにとどまりません。長期的な戦略的利益をもたらす大きな布石となります。
インハウスであることによって、経営陣や様々な事業部門との密なコミュニケーションが可能となります。こうした経験を積んだTAチームのメンバーはやがて、自社の戦略的目標を深く理解し、それを達成するために必要な人材の特性を明確に見極められるようになります。この結果、採用が企業戦略とより高い整合性を持つようになり、効果的かつ持続可能な人材獲得活動が実現できます。つまり、企業戦略に合致した人材の質と量において他社と差別化ができるようになるのです。
このように、TAチームへの投資には、アウトソースしていた業務をただ外から中に置き換える、単純なコスト削減以上のメリットがあります。採用は、ポジションを充足するだけの活動ではなく、長期的な成長基盤を築く経営戦略の一環として捉えるべきだ、という主張もご理解いただけたのではないでしょうか。
デメリット: 試練の時期
ダイレクトリクルーティングを担う社内チームを立ち上げた初期には、期待したメリットが一時的にデメリットとして顕在化する「試練の時期」があります。
デメリットに感じられてしまうことの一つが、「コスト」です。外部エージェンシーに頼らなくていいから、コストが下がると思いきや、そうならないという話です。
なぜなら、日本では、ダイレクトリクルーティングに精通し、TA業務に慣れた人材の数が限られているところに、その多くが外資系企業出身であるため、新たに採用する際、報酬が相対的に高くなりがちです。最初にチームを組成するプロセスではどうしても試行錯誤が必要になるのもコストアップの要因となります。これらは初期投資として受け入れざるをえない現実です。
もう一つの課題は、ダイレクトリクルーティングが企業ブランドに与える影響です。良い方向に働けば、「エンプロイヤーブランドの強化」につながる半面、育成途上においてはマイナス面も発生しかねません。経験が十分でないTAチームのリクルーター(TAリクルーター)が、候補者やエージェントとのコミュニケーションで失敗し、結果として会社のブランドイメージを損なうケースもあります。新人のバーテンダーのミスでお店の評判を落とすようなものかもしれません。
しかし、これらのデメリットは、初期段階のつまずきに過ぎません。長い目で見れば一時的なことで、むしろ成長のための布石と捉えたいものです。オペレーションを磨き上げるには、どうしたって時間がかかります。だからこそ、先に挙げたメリットを手に入れるため、当初は少しの苦労を受け入れるべきだと思います。時がたてば、TAリクルーターたちも熟練し、チーム全体が力強く成長していくでしょう。