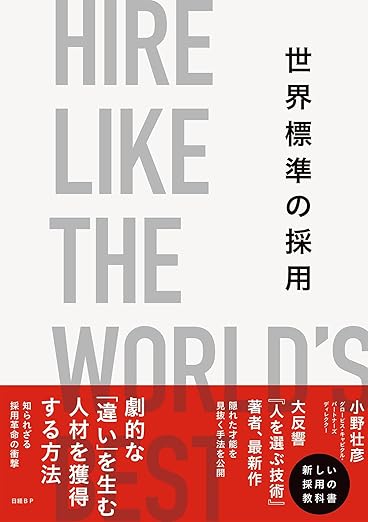2000年中ごろから、この20年ほどの間で、世界の採用手法は劇的な変化をとげました。その要因は、リンクトインやビズリーチ等による新しいサービスの発展、そして巨大企業グーグルが全世界で実践した革命的な人材採用にあるといわれています。
その大きな特徴は、採用エージェントに頼らないダイレクトリクルーティング、そして、より良い人材を獲得するために経営資源を惜しみなく投入する仕組みにあります。
本稿では、そのような世界標準の採用を導入するにあたり、対象者の人間性を見極めるポイントについて、グロービス・キャピタル・パートナーズ ディレクターの小野壮彦氏に解説して頂く。
※本稿は、小野壮彦著『世界標準の採用』(日経BP)を一部抜粋・編集したものです。
人間性が出る場面:(1)利がないとき
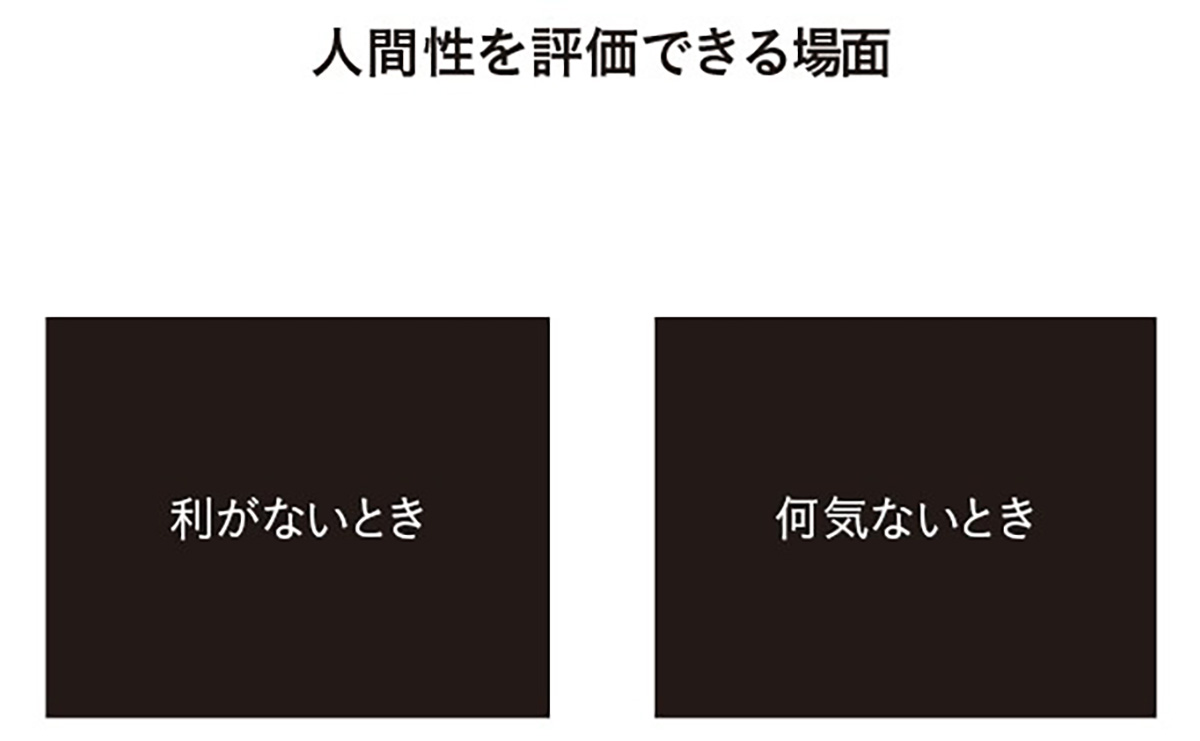
自分に直接の利益がない場面でその人がどのような行動を取るかは、その人の本質を知る上で極めて重要です。
特にビジネスの世界では、「良い人」と見られることが明確なメリットを生む状況に置かれれば、多くの人がそのように振る舞います。しかし、利益が絡まない、あるいは利害が隠された状況では、その人の本来の性質が浮き彫りになりやすくなります。
表では笑顔を見せ、裏では不誠実な行動を取ることもできます。つまり、良い顔をすることに利がある場面では良い顔をしながらも、そうでないときは、相手を平気で出し抜くような行動を取ることもできるのです。
しかし、お分かりのようにこのような「裏と表のある行動」は、ビジネスの世界においても、信頼関係の構築を阻む原因となりえます。
これに対して、「利がないとき」でも誠実に行動できる人は、「インテグリティ(Integrity)」を備えていると評価できます。これは日本語に訳すことが難しい言葉ですが、ここでは「道徳的な一貫性」と捉えてもいいでしょう。
表の顔と裏の顔が、道徳性という観点において一致している。これは、単に善良であること以上に重要な資質であり、組織のリーダーや信頼の置けるチームメンバーとして欠かせない要素です。
両者の行動の違いは、その人の内面にある価値観や倫理観を映し出します。
私は時に、採用の面接でよくストレートにこう質問します。「あなたが職場で、得をしないと分かっていても、誰かのために何かをしたときのエピソードを教えてください」と。
この質問の意図をお伝えすると、実は、相手がどのように答えるか、その内容そのものの是非を、判断したいわけではありません。
まずもって、この質問は優秀なビジネスパーソンにとって、意外と答えることが難しい質問です。
フリーズして、答えに窮する候補者は実感として多いです。
しかし、何らかの話術でうまく乗り切ろうとする人や、話をずらそうとする。つまり、自己防衛反応のようなものが見えたとき。それは、私が見立てるところ、損得勘定が強すぎてインテグリティにやや欠ける人である可能性が高いです。「得をしないときに何かをする」という、問いの設定そのものが、自分の価値観と衝突するので、心の中で価値観がクラッシュしている様が見受けられたりします。
反対に、少し考え込んでから、「そうですね、職場では確かに損得勘定が強くなってしまっているかもしれません」と反省したり、「それであらためて思ったのですが...」などと自己開陳に発展したりする方は、インテグリティの強い、良い人間性を持っていることが多いように思います。
もちろん、これが絶対的判別方法というわけではありません。状況に合わせて応用が必要となりますので、あくまで一例に過ぎません。ただ、こうした質問の工夫も含めて試行錯誤することが、絶対に妥協できない「候補者の人間性」を見抜くための参考になるのではないかと考え、ご紹介した次第です。
人間性が出る場面:(2)何気ないとき
もう一つ、その人の人間性が表れる瞬間というものがあります。それは何かというと「何気ないとき」です。たとえば、コンビニで会計する、駅で電車に乗るといった日常的な場面での小さな行動です。店員への接し方や乗車待ちの列に並ぶときの振る舞いは、その人がどれだけ他者を尊重しているかを示す指標となりえます。
会食の場をセットし、「素の姿」を観察することは、古典的ですが今も効果的だと感じます。なぜでしょうか。
そもそも面接という場は、「非日常」そのものです。リアルな面接であれば、見知らぬ相手と閉鎖された空間で向き合い、「最善の自分」を見せるために必死になる、緊張感の高い場です。
一方で、ランチやディナーをともにするのは、そもそも「食べる」という行為に日常性がありますし、レストランは人が出入りするオープンな空間です。面接室と違ってリラックスするためにつくられた空間ですから自然と素の姿が表れやすくなるため、人間性が垣間見えやすいセッティングだといえます。
もう少し踏み込むと、会食はマルチタスクを強いる場です。食べ物を口に運び、咀嚼しながら、相手の話を聞き、それに答え、相手に気を遣う。この一連のアクションで脳はフル回転しています。
マルチタスクは脳のリソースを分散させ、注意力を低下させることが知られています。
マルチタスクを試みると、「ストレスホルモン」とも呼ばれるコルチゾールが分泌され、情報処理能力が低下するそうです 。つまり、会食中の候補者は、脳をマルチタスクで働かせることで脳の処理能力が低下しています。その結果、「よく見せよう」とする演技への集中力が削がれ、本来の人間性が浮き彫りになる可能性が高まるのです。
言葉を変えれば、会食中は、自己コントロールが少し甘くなるということです。会食中に選ぶ話題や、食べるときの所作、空いたグラスや皿の扱い、店員に対する態度などの「何気ない」所作に注目することで、有益なデータを集めることができるでしょう。
なお、最後に少し脱線しますが、お酒については、注意が必要なので記しておきたいと思います。アルコールも、相手のガードを下げさせるために効果があると思うかもしれませんが、オファー面談(内定を出すと決めた後での面談)など候補者のエンゲージが目的の場面であればまだしも、「ジャッジ(裁定」の判断材料となる面接においては注意が必要です。
まず、お酒が入ったときに言動が変わることはよくあります。しかし、それがその人の「素の姿」だといえるかどうか。それも仕事における「素の姿」として見ていいのか。それはあくまで、酔ったらどうなりがちかというデータでしかなく、酔っていない仕事中の人間性を測るためのデータとしては使えないはずです。
また、コンプライアンスの観点からも、面接のプロセスの中でお酒を飲むことには慎重であるべきです。軽く乾杯する程度なら問題ないかもしれませんが、それ以上の飲酒は避けるべきでしょう。
さらに、お酒が入ることで面接官自身の判断力が鈍り、適切な評価ができなくなるリスクもきちんと直視すべきポイントです。気分がよくなった状態で候補者の評価を下すのはリスクが高い行為です。
酔っ払いはたいがい、自分は酔っていないと主張するものですから。