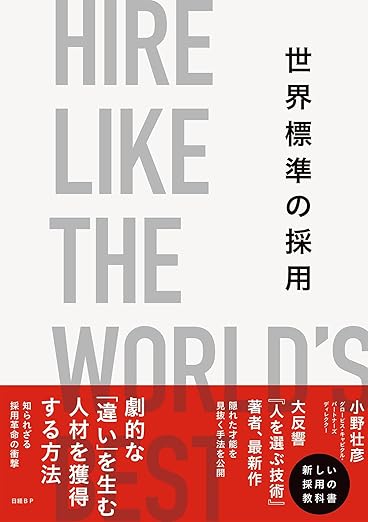2000年中ごろから、この20年ほどの間で、世界の採用手法は劇的な変化をとげました。その要因は、リンクトインやビズリーチ等による新しいサービスの発展、そして巨大企業グーグルが全世界で実践した革命的な人材採用にあるといわれています。
その大きな特徴は、採用エージェントに頼らないダイレクトリクルーティング、そして、より良い人材を獲得するために経営資源を惜しみなく投入する仕組みにあります。
本稿では、そのような世界標準の採用を導入するにあたり、即戦力採用のリスクについて、グロービス・キャピタル・パートナーズ ディレクターの小野壮彦氏に解説して頂く。
※本稿は、小野壮彦著『世界標準の採用』(日経BP)を一部抜粋・編集したものです。
即戦力採用の罠
「即戦力ならビズリーチ」─ あの日本のダイレクトリクルーティングを代表するプラットフォームのキャッチフレーズに象徴されるように、経験者採用において「即戦力」という言葉は非常に好まれます。企業が「即戦力人材」を求める背景には、採用に伴うリスクを最小限に抑え、速やかに成果を出してほしいという切実な期待があります。
しかし、採用の現場、とりわけジャッジの局面において、「即戦力」という概念の存在が、面倒な問題を生むこともありえるということを、ご存じでしょうか。たとえば、AさんとBさん、2人の候補者が最終的な選択肢として残ったシチュエーションを想定しましょう。
Aさんは、同じ業界の自社より大手の企業で、今回、募集するポジションと、ほぼ同じ職務を経験してきた方です。業界経験も職務経験もぴったり。まさに「即戦力」といえる人材で、食事に例えるならば、ランチにパッと高級なお弁当を買うようなものです。料理をする時間は必要なく、すぐにでも成果を上げてくれそうだと期待できます。
一方のBさんは、違う業界で、求めるポジションとぴったりとはいえませんが近しい業務を経験してきた方です。「即戦力」度はAさんに劣ります。しかし、リーダー人材としてのポテンシャルがあり、見送るには惜しい存在だったとします。こちらは、新鮮な食材を買って調理するようなイメージでしょう。少し手間はかかるかもしれませんが、うまく料理すれば、隠れたポテンシャルを引き出し、素晴らしい成果を生み出せる可能性があります。
さて、Aさん、Bさん、果たしてどちらを採用するべきでしょうか。
多くの企業は、何だかんだリスクが低く、即戦力で期待ができるように見える、Aさんを採用したいと思ってしまうものです。
しかし、Aさんのような候補者に「採用!」のジャッジを最終的に下す際には、いくつかの疑問点を解消する必要があります。
まず第1に、なぜAさんは自社よりも規模が小さい、ある意味、"格下"の企業を受けに来たのか?
第2に、なぜAさんが、「同じ業界で、同じ職務」を希望しているのか? です。
採用する側から見たとき、同業の、しかも自社よりも格上の大手で「ぴったり経験」を持つAさんが応募してくれた。という、その背景には、何かが隠れている可能性があるかも、と検証するべきではないでしょうか。
私が見てきた中でも、実に多くの企業がAさんのような「即戦力風」の候補者に対して「採用!」とジャッジを下し、オファーを出してきました。業界も職務もぴったりの経験を持つ人が見つかったことで興奮し、期待が一気に膨らんでしまうのは無理もないことです。
しかし、このパターンでの採用は、結果が芳しくないケースがあるということもまた事実です。いつの時代でも、おいしい話には裏があることは多いのが現実だというわけです。
一体、その「裏」には何がありうるのでしょうか。
Aさんについて、解消すべき疑問点を先ほど2つ挙げました。
第1に挙げた"格下"問題から、検討しましょう。安心感があるはずの同業大手からわざわざ転職する候補者には、現在の勤務先でのキャリアが行き詰まり、何か居心地の悪い状況に直面している可能性があります。
第2に挙げた問題は、見方によっては、より深刻です。
ここで考えていただきたいのは、本当に優秀な人が転職を考えたとき、果たして同じ業界で同じ職務のポジションを選ぶだろうか? です。
成長意欲のある人材は、常に新たな挑戦を求めます。そうした人が転職する際、同業他社で同じ仕事を繰り返すことを選ぶでしょうか。本当に優秀であれば、より大きなチャンスや新しい挑戦に向かい、成長の可能性を求めるでしょう。
それなのに、あえて業界も職務も変わらないポストに応募したAさんは、もしかしたら、向上心が欠如しているのかもしれません。今までの経験に安住し、楽をしたいと考えている可能性もあります。そう考えると、Aさんの仕事に対する意欲や今後の成長の余地、ポテンシャルに疑問符がついてしまいます。
この問題の本質は何かというと、実に多くの方が即戦力という概念を、狭く解釈してしまっているということなのです。
「優秀=即戦力」
「即戦力=ぴったりの経験」
という図式を頭の中から取り除くべきだと思います。
むしろ、「即戦力=当面の仕事はやってくれそう。でもなんでうちにきてくれるのかな?」程度の期待値へと、抑えることが賢明でしょう。
「もう、今までの経験を使って食べていければいいや」という体の、成長意欲の低い、ローカロリーな人生を志向しはじめた人材を新たに抱え込むことのリスクが、どれほどのものかを冷静に見極める必要があります。目の前の短期的な成果だけにとらわれず、長期的な視野で考えることが大切だということです。
企業というのは、いつだって即戦力を求めるものです。「経験ぴったりの人」に惹かれるのは自然な感情でしょう。しかし、その背後に落とし穴が潜んでいるという可能性を理解しておくべきです。
現場には、「即戦力でないと認められない」という「見えない圧力」が渦巻いていることもあるかもしれません。しかし、その圧力に屈してはいけません。
あまりに「ぴったりの経験」を持つ候補者を目の前にしたときこそ、一度立ち止まり、冷静にジャッジすることが必要なのです。