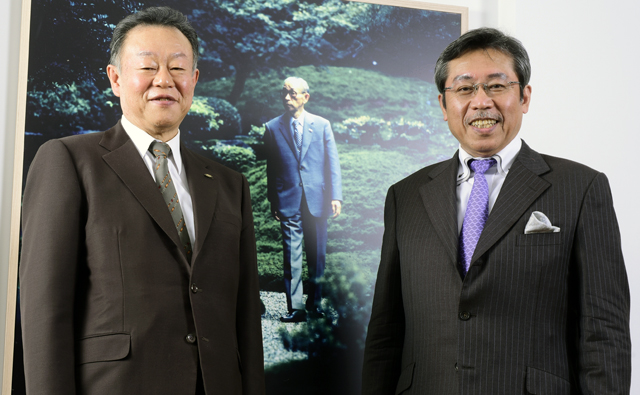苦境を乗り越え、革新的技術を~小飼雅道・マツダ社長兼CEO
2016年06月27日 公開 2024年12月16日 更新

生み出した「ONE MAZDA」の精神
「マツダは生き残れるのか」。数年前、そんなニュースが流れたことがあった。リーマンショック、円高と日本経済を揺るがす出来事が起こる中、広島を本拠とする業界4位の自動車メーカーのマツダは、売上高を大きく落とし、巨額の赤字企業に転落した。だが2013年、奇跡的なV字回復を果たし、2014年から3年連続で過去最高の営業利益を出した。なぜマツダは蘇ることができたのか。そして苦難の時期、人や組織はどう動いたのか。小飼雅道社長に「復活の舞台裏」をうかがった。
小飼雅道(マツダ社長兼CEO)
こがい・まさみち。1954年長野県茅野市生まれ。1977年東北大学工学部卒業後、東洋工業(現マツダ)に入社。1998年車両技術部長、2003年技術本部副本部長、2004年執行役員 防府工場長、2006年執行役員 オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd社長、2008年常務執行役員、2010年専務執行役員、取締役専務執行役員を経て、2013年6月から現職。
取材・文:高野朋美
写真撮影:梅村孝弘
強みに一点集中する
一般に、車のエンジンの熱効率は30パーセントが限界だといわれている。つまり、燃料の70パーセントは無駄になっているということだ。ここに着目したのがマツダの技術者。エンジンの高圧縮化(ディーゼルは低圧縮化)に取り組み、14.0という「世界一の圧縮比」を成し遂げた。誰もが不可能だと思っていたエンジンの高効率化を叶えたのだ。
この技術は、マツダでは「ボウリングの一番ピン」と呼ばれている。一番ピンを倒せば後ろのピンが次々と倒れるように、圧縮比の技術が、排ガスのクリーン化、エンジンの軽量化、高出力、静音、コストの抑制といった問題解決を一気に実現したからだ。
だが、たくさんの選択肢からこの方向性が選ばれたわけではない。「これしかなかった」のだ。マツダがスカイアクティブ・テクノロジーの開発に取り組んだ時、すでにハイブリッド車もEVも他社が先行していた。今さら開発に着手しても追いつけない。加えてリーマンショックによる業績不振。投入できる資金には限りがある。手の中にあるもので、世界一を目指すにはどうすればいいか。そう模索する中、様々な方向性を消していった後に残ったのが、「強みである内燃機関の技術を徹底的に進化させること」だった。
「強みを放っておいて、弱みを克服することなんてできません。『自分たちの強みはこれなんだ』と思うからこそ、社員たちは逆風にもめげず、開発に情熱を燃やせるのです」
開発担当者の全国行脚で「Btoファン」を実践
マツダはバブル前、5チャンネル体制で多車種を揃え、全方位の販売戦略をとったことがある。この戦略は結果的に失敗に終わった。そして、自分たちのブランドが何なのか一瞬見えなくなったと、小飼社長は思い返す。
「マツダの車を買ってくださるお客様は、運転する楽しみに濃い熱を持った方。世界で見た割合では、2パーセントほどにすぎません。でも、この方々に『最近のマツダ車、つまらないね』と言われたら終わりです。絶妙な運動性能やハンドリングを楽しんでくださるファンを絶対に裏切ってはいけない。バブル崩壊によってブランドの再構築を余儀なくされた時、私たちはそのことを思い出しました」。
誰にでも受け入れられる車をつくろうという発想はなくなった。目指すべきは、走る楽しみを知る顧客に愛される車。それを体現したのが、2002年に発表された「アテンザ」だった。それが、マツダ復活のスタート地点となったと小飼社長は言う。
以来、マツダは顧客と徹底的に向き合う姿勢を一貫して崩していない。その証が、開発担当者の全国行脚だ。マツダの開発主査とチーフデザイナーは、車が発売されると同時に設計室からいなくなる。海外を含めた各地の販売拠点に飛び、顧客の生の声を聞き、カージャーナリストたちの指摘に耳を傾けるためだ。「全国行脚が一通り終わるまで、次の開発車種は決めません」と小飼社長。顧客と開発者を直接つなげることで、BtoCならぬBtoファン の構図をつくり出しているのだ。開発、生産、販売に加え、ファンまでも一気通貫した車づくりといえよう。
※本記事はマネジメント誌『衆知』2016年7・8月号、特集「世界で戦える人材の育て方」より、その一部を抜粋して掲載したものです。