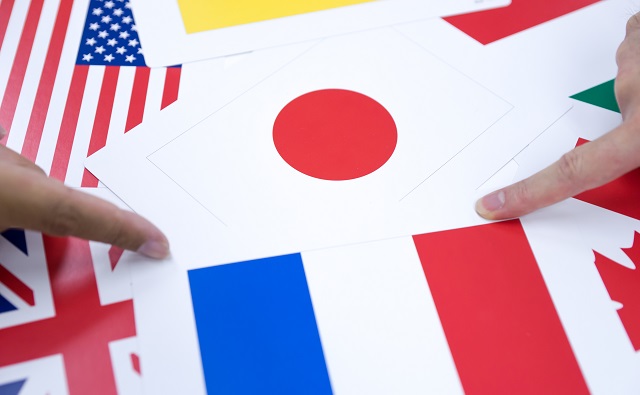1930年代への逆戻り? 自国第一主義の妖怪たちによる世界経済の「大激転」を阻止せよ
2017年06月08日 公開 2024年12月16日 更新

「僕富論」対「君富論」
 激転――著者の浜矩子氏が世界を見渡し頭に浮かんだその言葉は、辞書にはない。既存の転換という言葉にはない過激さや暴力性を孕む、目まぐるしい変化。今起きているのは、そんな変化だ。各地で踊り始めた自国第一主義の妖怪たちが世界を席巻すれば、その先には1930年代のような世界が待っているかもしれない。
激転――著者の浜矩子氏が世界を見渡し頭に浮かんだその言葉は、辞書にはない。既存の転換という言葉にはない過激さや暴力性を孕む、目まぐるしい変化。今起きているのは、そんな変化だ。各地で踊り始めた自国第一主義の妖怪たちが世界を席巻すれば、その先には1930年代のような世界が待っているかもしれない。
米国のドナルド・トランプを筆頭に、ナイジェル・ファラージュ(イギリス「英国独立党」前党首)、マリーヌ・ルペン(フランス「国民戦線」党首)、フラウケ・ペトリー(ドイツ「ドイツのための選択肢」党首)など、欧州もまた自国第一主義の激転妖怪たちが跋扈している。その様相は、「妖怪万華鏡だと」著者は指摘する。
著者は、グローバル時代は「僕富論(ぼくふろん)」対「君富論(きみふろん)」の綱引きの時代だという。いうまでもなく、アダム・スミスの「国富論」をもじったものだ。「僕富論」を言いかえれば、「自分(僕)さえ良ければ」。「君富論」を言いかえれば、「あなた(君)さえ良ければ」である。国境を越えて経済活動が広がるグローバル時代は、誰もが「君富論」に徹しなければ存続不能だ。誰もが「僕富論」を前面に出してしまえば、グローバル時代は暴力的な終焉を迎えるほかはない。それが、今日的現実だ。
にもかかわらず、かの妖怪たちは自国第一主義の「僕富論」を唱える。人類が決然と背を向けたはずの世界。2度と再び踏み込まないことを決意した道。国々の我欲がぶつかりあった1930年代への逆戻り。「僕富論」の妖怪たちがその世界に我々を導こうとしているいま、著者は、本書で「激転」阻止を強く訴える。
暗黒のるつぼに向かう「大激転」を阻むため、われわれはどのような理想を掲げてすすんでいけばよいのか。以下に本書より、抜粋編集してご紹介する。
君富論は存外に現実的だ
まさしく、諸悪の根源は僕富論にあり。改めてつくづくそう思い知らされる。だからこそ、そこに激転妖怪たちが引き寄せられていくわけだ。激転妖怪たちに断じて惑わされてはならない我々は、彼らが引き寄せられるものから最も遠いところに身をおくことが必要だ。そして、激転妖怪たちは僕富論亡者だ。だから、我々は、いかに難しかろうと君富論の領域にしっかり陣取らなければならない。そういうことになる。
どうすれば、それが出来るのか。君富論は、聞こえは実に麗しい。だが、とてつもなく理想論であって、とてつもなく非現実的だ。そのように思われる方も多いだろう。そう感じられるのも、ごもっともだ。だが、この点については、2ついえることがあると思う。
第1に、グローバル時代において、君富論は存外に現実的だ。第2に、いかなる時代においても理想は理想だ。
まず1点目からいこう。グローバル時代は誰も一人では生きて行けない時代だ。ということは、誰もが他者のことを気づかいながらでなければ、やっていけないということだ。メイド・バイ・ジャパニーズ・カンパニーのモノがメイド・イン・ジャパンで無くなれば無くなるほど、日本は日本のことばかり考えているわけにはいかなくなる。
日本が提供する高性能部品や素材やノウハウなくしては、世界の多くの企業が完成品の仕上げにたどりつけない。こんな状況の中では、自分さえ良ければ主義は自殺行為につながりかねない。ここに、「情けは人のためならず」型の君富論が広がる可能性が芽生える。このタイプの君富論は、今一つ純度が低い。見返りを期待した君富論だ。
突き詰めて行けば、自分のための君富論なので、僕富論色がそこに混じり込んでしまう。
そこは少々引っ掛かる。だが、それでも、純正僕富論よりははるかにマシだ。少々不純な君富論が、やがて本物の君富論に昇華して行く可能性に期待してもいいだろう。
グローバル時代はパックス誰でもない時代だ。「パックス・誰かさん」がその他大勢の面倒をみてくれる時代ではない。そうなれば、お互いに面倒を見合うしかない。誰かに最終決定をしてもらうのを待っているわけにはいかない。みんなで真剣に方策を考えなければいけない。最高責任者の最終決定に物事を委ねてしまうわけにはいかない。「やっぱり最後は社長に決めてもらわないと」とか、「どうせ結局あの人の一声で決まるんだもんな」などといって、その他大勢は、無責任を決め込んだり白けたり達観している場合ではないのである。
次のページ
リーマンショック直後の時期、各国首脳は君富論モードに