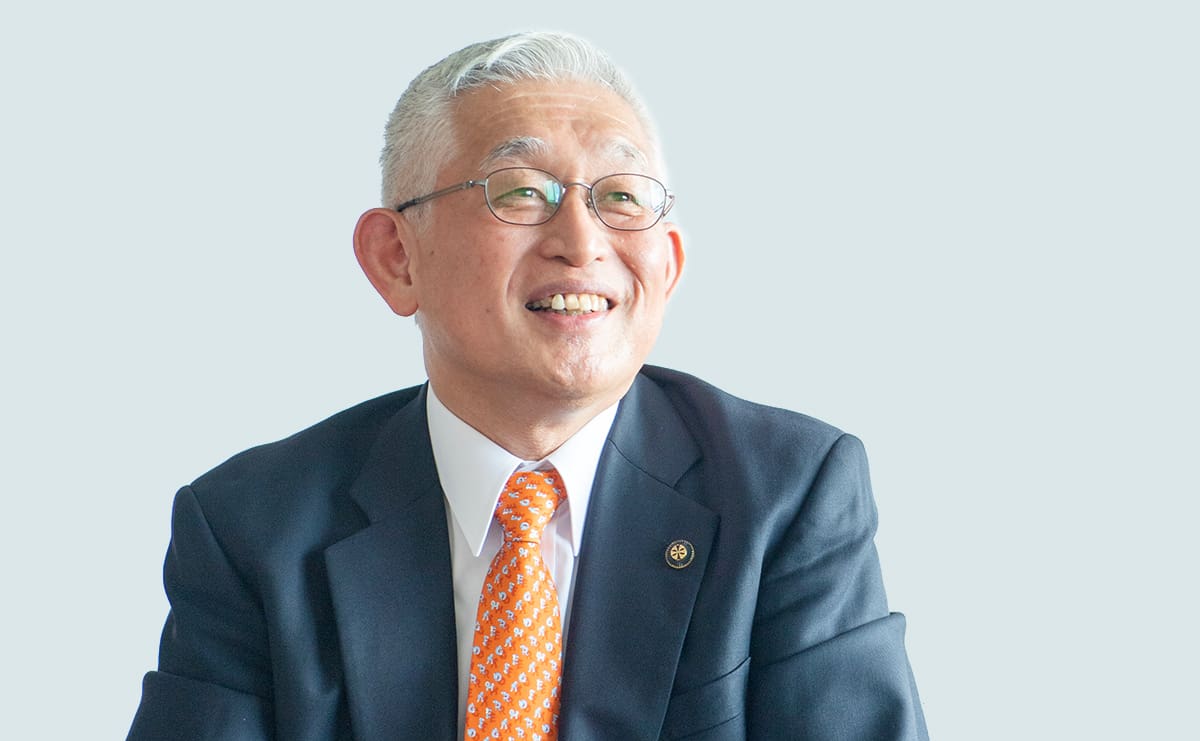被災地に「紙の家」を提供...坂茂さんが考える、建築家としての役目
2024年02月07日 公開 2024年12月16日 更新

↑1月の能登半島地震の被災地でも、避難所の体育館に仮設パーティションと段ボールベッドを設営した。(C)VAN(NPO法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク)
安価で、すぐにつくれて、強度や耐久性も十分な「紙の家」が世界を変えようとしています。これまで難民や、被災者にシェルターを提供してきた建築家・坂茂さんのお話しを紹介します。(取材・文:辻由美子、写真:関暁)
※本稿は、月刊誌『PHP』2022年12月号より、内容を一部抜粋・編集したものです。
幼少期から憧れていた「大工さん」
私が建築家になった原点は、大工さんでしょうか。うちはしょっちゅう増改築をしている家だったので、大工さんがいるのが当たり前の光景でした。小学生のころは大工さんが木を切るところや家具をつくるところを、飽きずにずっと眺めていました。
将来の夢は「大工さん」。弟の夢は「大統領」だったので、両親から「もっと大きな夢を持ちなさい」と言われたものです。
父は会社員、母は服飾デザイナーでした。家を改築していたのは、母の仕事の関係です。お針子さんが何人かいたのですが、今みたいにワンルームマンションがない時代。部屋を増築して、お針子さんの寮として使っていたのです。
ラグビー断念後は建築家一筋
子ども時代はラグビーに夢中でした。小中高とラグビーを続け、中学ではオール東京にも選ばれるほど。そのころの夢は「ラグビーをやりながら、建築家になる! 」。両立できたらカッコよかったでしょうね(笑)。練習が終わってクタクタのまま、夜は美術大学の建築学科を受験するための予備校に通っていました。
高二のときラグビーの全国大会に出場しますが、一回戦で負けてしまいました。全国レベルとの差を見せつけられ、ラグビーは断念。以後は建築家一筋です。
最初は日本の大学に入学するつもりでしたが、建築雑誌で見たジョン・ヘイダックの作品に衝撃を受け、この人のもとで勉強したいと留学を決めました。ヘイダック先生がいるニューヨークのクーパー・ユニオンという大学への入学を志望しましたが、当時はインターネットもなく、日本ではいっさい情報が取れませんでした。
渡米してみたら、クーパーは編入以外、外国人の入学を認めておらず、やむなくロサンゼルスの南カリフォルニア建築大学(サイアーク)に入学し、クーパーに二年次から編入します。
自由闊達なサイアークと違って、クーパーは歴史と伝統を重んじる大学でした。外国人には精神的にも肉体的にもきつかった。とくに指導教授だったピーター・アイゼンマンとは考えが合わなくて、卒業制作が不合格になってしまいました。
もう一度制作をやり直し、何とか半年遅れでクーパーを卒業。厳しい環境下で自分のやりたいことをやりぬくタフさはアメリカで身についたと思います。
そのままアメリカの大学院に進むつもりでいたところ、母から「アトリエを建て直したいので、設計をしてほしい」と頼まれました。実際に建物を建てたことがない私にはまたとないチャンスです。
さらにいくつかの展覧会のプロデュースを頼まれたこともあり、なし崩し的に日本での仕事が増えていきました。気づいたらそのまま日本でキャリアをスタートさせていたわけです。
それから10年間は依頼される仕事をこなすのが精一杯の毎日でした。でも30代後半になって、ふと自分の仕事はこれでいいのかと疑問を抱くようになりました。
専門職である医師や弁護士は知識を生かして、社会の役に立っています。一方、同じ専門家である建築家は社会の役に立っているのだろうか。
考えてみれば、建築家の仕事はある程度お金のある富裕層や特権階級が依頼主になります。彼らが人生で一番いい状態にあるときに、自らの財力、権力を見せるために立派な建築を建てる。昔のお城や教会がいい例です。
私たちの仕事は金持ちのためのもので、社会の役に全然立っていないじゃないか、と思ってしまったのです。
震災で焼け野原の神戸へ駆けつける
 ↑金沢市内の体育館でスタッフが「紙の間仕切りシステム」を組み立てる
↑金沢市内の体育館でスタッフが「紙の間仕切りシステム」を組み立てる
もやもやしていたある日のこと、週刊誌を開いたら、ルワンダの難民キャンプの写真
が目に飛び込んできました。200万人もの難民が雨季の寒い季節に、毛布一枚にくるまって震えていた。
彼らに雨風を防ぐシェルターを提供することこそ、私たち建築家の役目ではないかと、即座に思いました。頭に浮かんだのは、再生紙を使った紙の家のシェルターです。
当時、私は構造設計の第一人者である松井源吾氏の指導を受けながら、筒状にした紙管(しかん)を使った紙管建築法を開発。国の認定も得ていました。紙なら安価で、すぐにつくれますし、強度や耐久性も十分です。
さっそく国連難民高等弁務官(UNHCR)の日本の事務所に「シェルターをつくらせてほしい」と申し出たのですが、なかなか動いてくれません。スイスの本部に手紙を書いても、なしのつぶて。
これはもう自分で行くしかないと思い、ジュネーブの本部にアポなしで乗り込みました。すごい行動力だと驚かれましたが、私にとっては建築家が社会に役立つまたとないチャンス。逃すわけにはいかないという一心でした。
ジュネーブを訪ねたとき、運良くUNHCRのドイツ人のシェルター担当の建築家ウォルフガング・ノイマン氏にお会いできました。
難民キャンプでは、難民たちがシェルターをつくるために、周辺の木を伐採してしまい、深刻な環境問題を引き起こしていたため、私の紙管は木に代わる材料として注目され、紙の緊急用シェルターの開発がスタートしました。
その翌年、阪神・淡路大震災が起きました。多くの建物が倒壊し、たくさんの人命が奪われてしまった。建物にかかわる建築家として、強い責任を感じずにはいられませんでした。何か役に立てないだろうかと思っていたら、ベトナム難民たちが集まっている教会(たかとり教会)があると新聞記事で知りました。
日本人でも大変なのに、彼らはもっと大変だろうと、すぐに神戸に向かいました。関空まで飛行機で飛び、そこから神戸の港までフェリーに乗り、さらにバスを乗り継いで現地に入りました。
あたりは一面の焼け野原。まだ煙がくすぶっている状態です。茫然と歩いていたら、焼け野原の一角でたき火を囲んで、ミサを行なっている一団がいます。探していた元難民と教会の人たちでした。
教会は燃えてしまっていたので、神父さんに紙を使った仮設の教会の建設を提案しました。突然の申し出に向こうは警戒するばかり。信頼を得るために、毎週、日曜日のミサに参加し、公園のブルーシートのテントに住むベトナム難民の人々のために紙管の仮設住宅「紙のログハウス」を建設しました。
その後、ボランティアや建設費用も私が用意するとの約束で、紙管でつくったコミュニティホール「紙の教会」の建設が実現しました。このホールは教会が正式に再建されるまでの10年間、町のシンボルとしてさまざまな用途に使われたあと、台湾の被災地に移築され、今も集会場として活躍しています。
その後も、新潟の中越地震、東日本大震災、熊本地震など災害が起こるたびに駆けつけて、建築家としてできる支援をしています。
紙の建築には可能性がある
紙でつくる建築について、世間では大きな誤解があるようです。「強度は大丈夫なんですか」「水は大丈夫ですか」「仮設ですよね」などとよく聞かれます。
まず材質の点ですが、材質の強度と建築の強度とは一致しません。硬いコンクリートの建物でも地震で倒壊する一方、木造建築でも倒壊しないものがたくさんあります。
またコンクリートが木や紙より長くもつというのも誤解です。1000年以上前の平安時代の紙の巻物でも、ちゃんと残っていますし、世界最古の木造建築である法隆寺は築1300年以上です。一方、コンクリートの建物はどんどん建て替えられてしまう。
たとえば赤坂にあった丹下健三氏設計の有名な赤坂プリンスホテル新館も、30年を待たずに取り壊されてしまいました。日比谷の帝国ホテルも建て替えられます。
コンクリートの建物でも商業目的の建築は短期間で建て替えられる。つまりコンクリートこそ仮設であって、何百年ももつ建物ではないのです。
その点、木材からつくられる紙の建築は木と同じようにさまざまな可能性があるのではないかと思います。これからも社会貢献を意識しながら紙の建築を追求していくつもりです。

![PHP2022年12月号[「捨てる」と人生が好転する!]](/userfiles/images/book2/B0BJ4YJHM1.jpg)