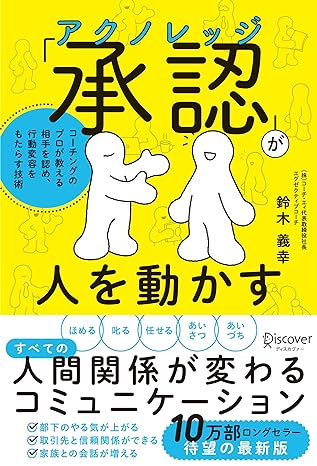「反論してくる若手」に高圧的に接しても、上司の権威は取り戻せない
2024年06月20日 公開 2024年12月16日 更新

部下や取引先生徒、家族など、「人を動かすにはどうすればいいのか」とお悩みの方は多いでしょう。人が目的地にたどりつくためには「エネルギー」が供給され続ける必要があり、コーチングではそのエネルギー供給のことを「アクノレッジメント(承認)」と言います。
では、若い部下や学生たちを動かすアクノレッジには、どのようなポイントがあるのでしょうか。
※本稿は『「承認 (アクノレッジ) 」が人を動かす コーチングのプロが教える 相手を認め、行動変容をもたらす技術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)を一部抜粋・編集したものです。
権威と呼ばれた存在が、軒並み失墜している
以前、関東地方のある私立高校の先生全員に対してコーチングの研修を行ったことがあります。このとき、研修に先立って、生徒10人と先生10人に個別にインタビューを行いました。生徒は先生のことをどんなふうに思っているのか、反対に先生は生徒のことをどんなふうに思っているのか、それぞれの立場から話を聞きました。
20人の話からすべてが推測できるわけではありませんが、少なくともそこから次のような現場の風景が浮かびあがってきました。
①生徒の多くは、昔のように先生の話に、とりあえず表向きだけでも素直に従うということをしない。
②そのため、何とか言うことを聞かせようと、より高圧的に出て生徒を震えあがらせている先生がいる。
③その一方で、とにかく生徒に「やさしく」接することで状況を改善しようと試みるものの、生徒をまったくコントロールできずに無力感に陥っている先生がいる。
④このどちらかの極に多くの先生が偏っていて、状況に応じて生徒と効果的なコミュニケーションを交わせる人が少ない。
今、日本という社会の中でかつて権威と呼ばれた存在が、軒並み失墜してしまっています。昔ならば、先生から何かを言われれば、生徒は「先生」の言葉として受け止め、それなりの敬意を払い応じたものです。
しかし、今日、多くの生徒は先生から発せられる情報を簡単に権威付けたりしません。ですから、かつての自分の言葉の重みを同じように再現したいと望む先生は、より高みから物を言い、何とか表向きだけでも自分のプライドを守ろうとします。
一方、これは若い先生に多いようですが、生徒を理解しようとカウンセラー的なスタンスに立ち、とにかく傾聴に努めるのです。しかし生徒はたがが外れたかのように自由にふるまい、先生の言うことを聞きません。先生はどうしたら良いのかわからずに途方に暮れてしまいます。
もちろんすべての学校でそうだと言っているわけではありませんが、私が研修をさせていただいたいくつかの学校では、少なくともそうした現状があるようです。
ていねいに理由を紐解く必要性
これとほぼ同じことが多くの企業の現場でも起きています。
30年ほど前までは上司の言葉は尊敬を払うべき対象として機能していました。それに背くことは会社に背くことであり、終身雇用、年功序列制度の中で競争のトラックから外れることを意味していました。
しかし今の若い人にとっては、上司の言葉はそこまでの重みを持っていません。自分の意にそぐわないことであれば、いとも簡単に反対意見を唱えます。そこで上司は「鬼」か「仏」かという議論が沸き起こるわけです。
つまり、言うことを聞かない社員には徹底的に厳しく、「鬼」となって臨むべきだ。いや、そうではない。叱るのではなく、「仏」のような心を持ってとにかく相手の意見を尊重すべきだ、と。
ところがそうシンプルに割り切ってうまくいくのかというと、そんなことはないものです。「鬼」になれば、それなら他に行くよと、部下は会社を離れてしまうし、「仏」になればなったで、部下は社会人としての常識を逸脱したような行動を取ってしまいます。一体どっちなんだと管理職は混迷を深めてしまうわけです。
では、どうしたら良いのでしょうか。もちろん、若い人も人間である以上、基本的には私たちと同じ「原理」で生きていると思います。
周囲から存在が認められなければ、内側はざわつくでしょうし、そのざわつきを解消してくれる人のほうに顔が向くのは間違いありません。単にほめるというだけではなく、日々の関わりの中で、どれだけ相手にマッチングした積極的なアクノレッジができるかは、やはり大事でしょう。
そして、若い人をアクノレッジする際に、中でも特に大事なのが「理由」という情報を伝えてあげることです。
昔であれば、上司がいえば理由なく部下が従っていたような事柄に対しても、きちんと説明を加える必要があります。オフィスであいさつするのはなぜ大事なのか。清潔感のある髪型で出勤することがなぜ大事なのか。机を整理するのはなぜ大事なのか。上司とアフター5に語らいあうことがなぜ大事なのか。一つひとつに説明を加えます。
ポジションパワーを使って「やれ!」ではなく、相手のためにわざわざ時間を使って、ていねいに理由を紐解いてあげるのです。「やれ!」には個の尊重がありませんが、「理由の説明」にはそれがあります。だからアクノレッジメントとして機能します。
慶應大学ラグビー部の上田元監督にしても、早稲田大学ラグビー部の清宮元監督にしても、最近の若い人相手に効果的な指導ができている人は、きちんと説明をしています。この練習はこのためにあって、このルールはこのためにあるということを説明するために決して時間を惜しまないのです。
学校も、もし一つひとつの決めごとに対して先生が労を惜しまず説明をしていれば、もう少し状況は変わるのかもしれません。