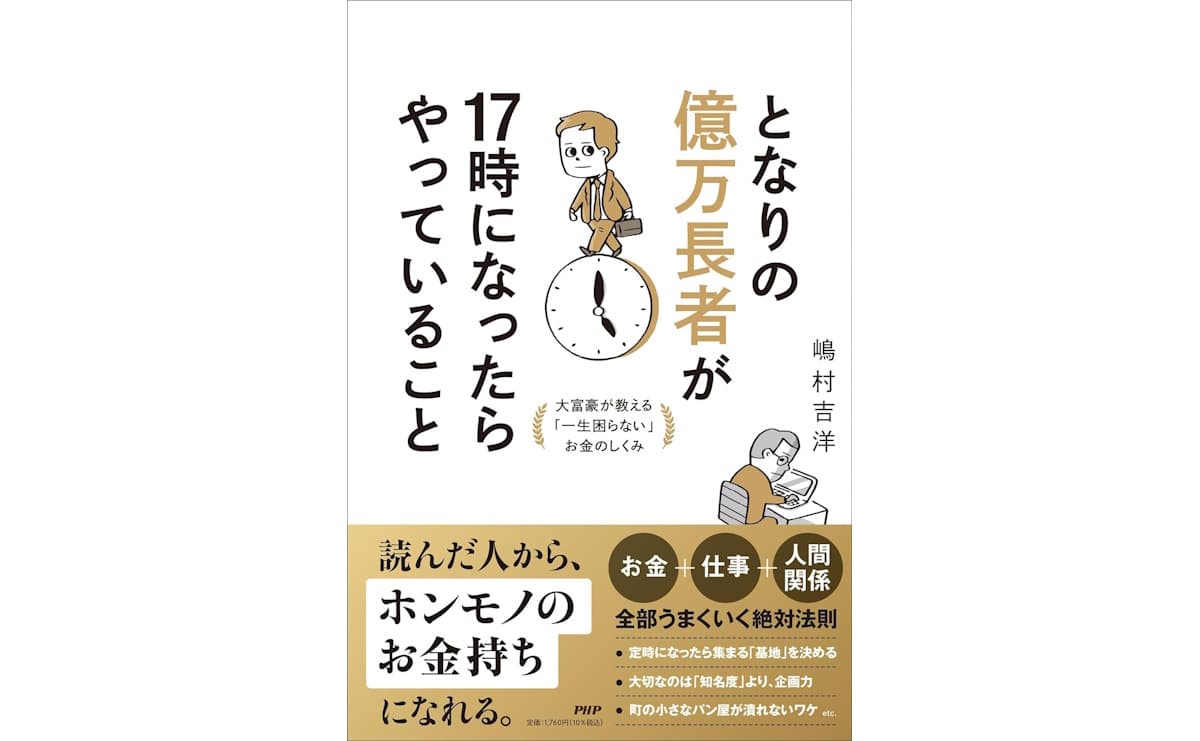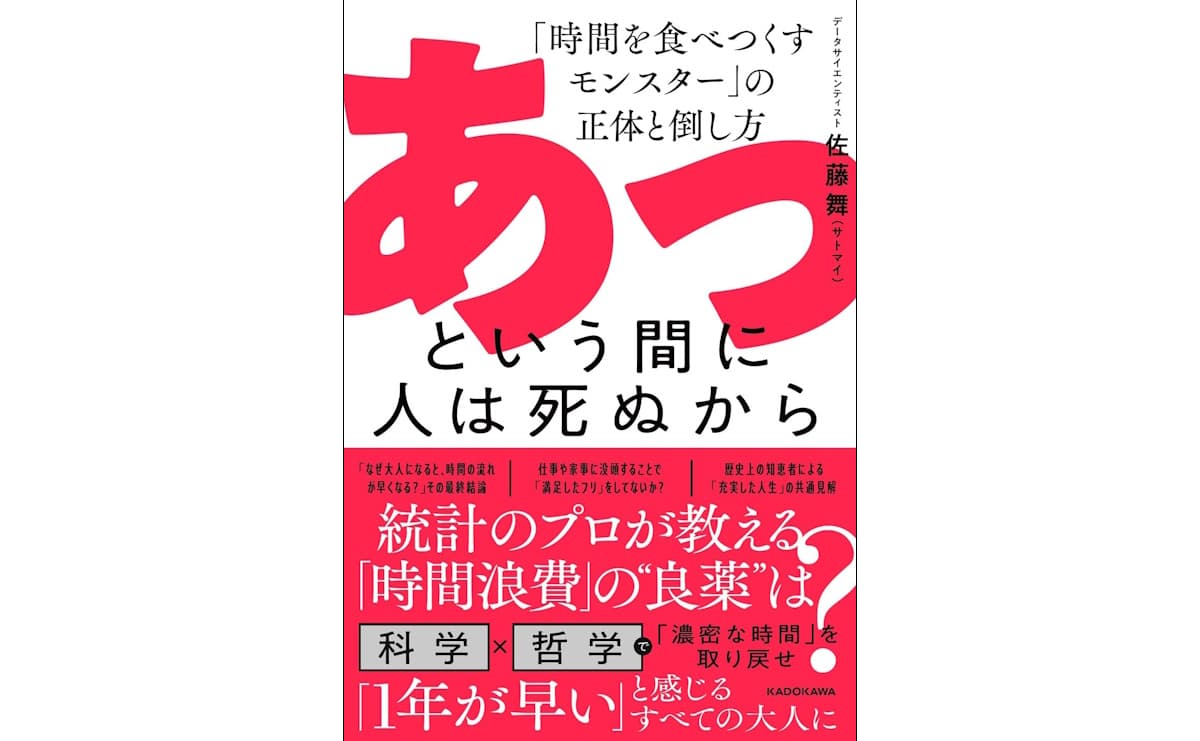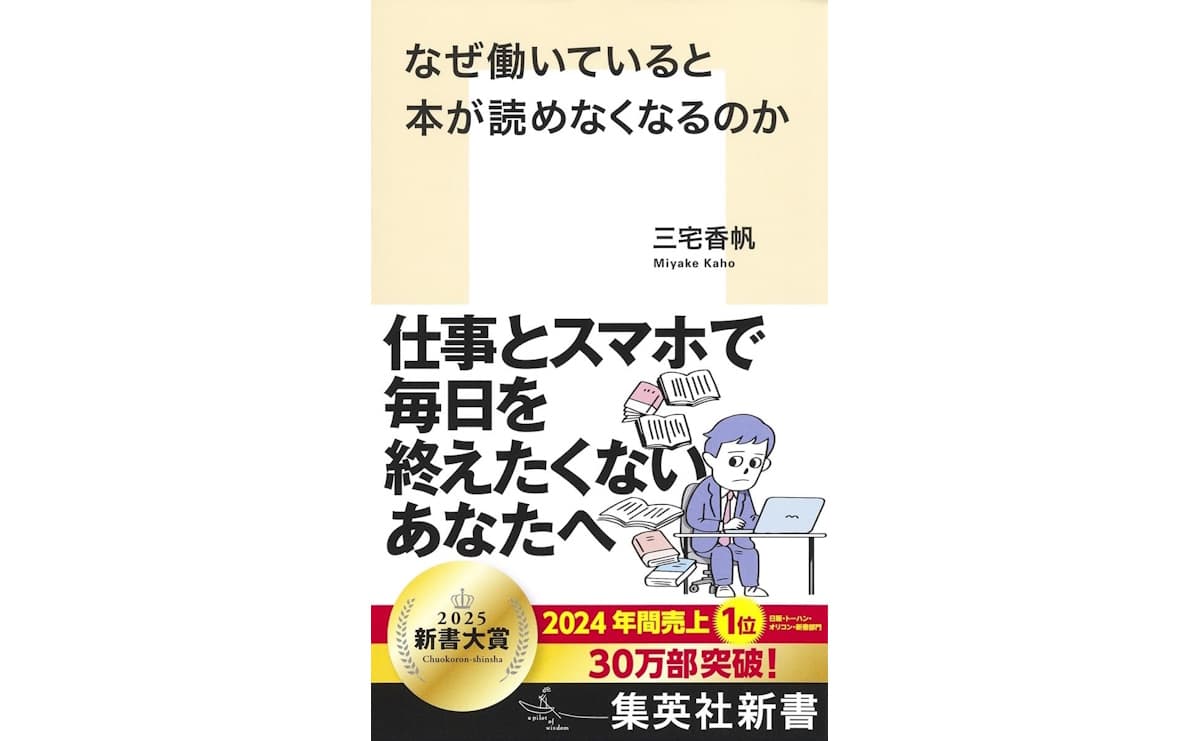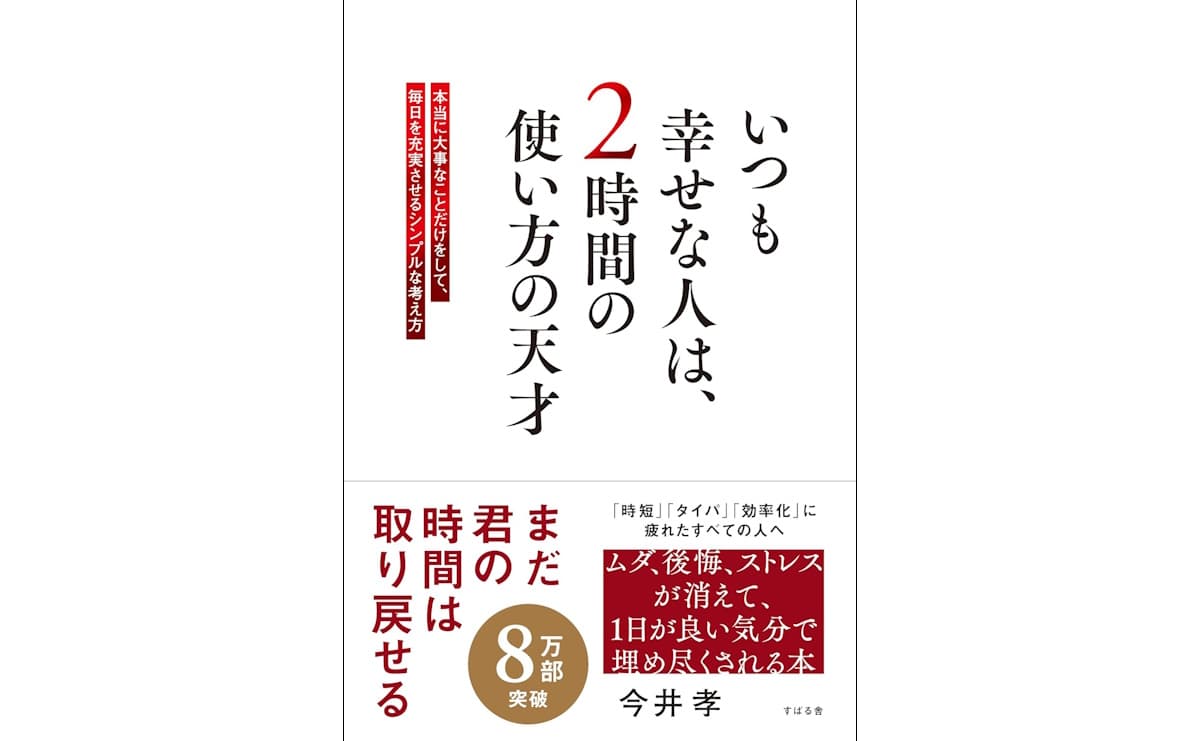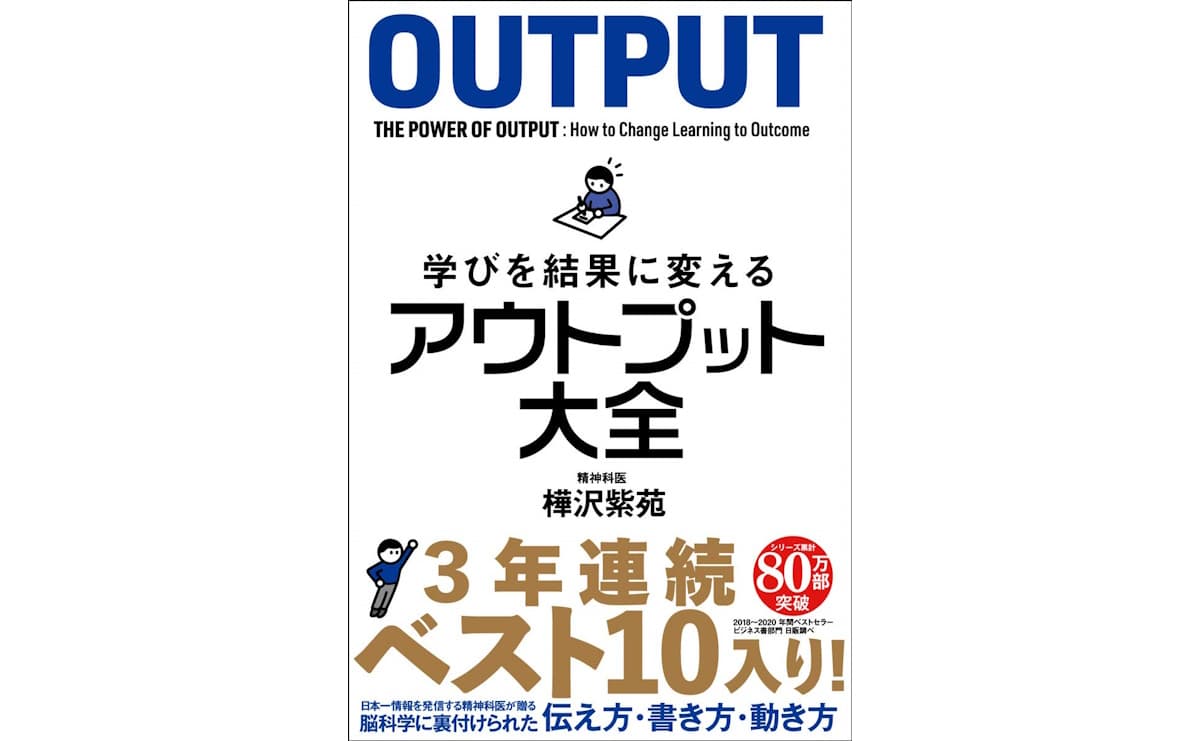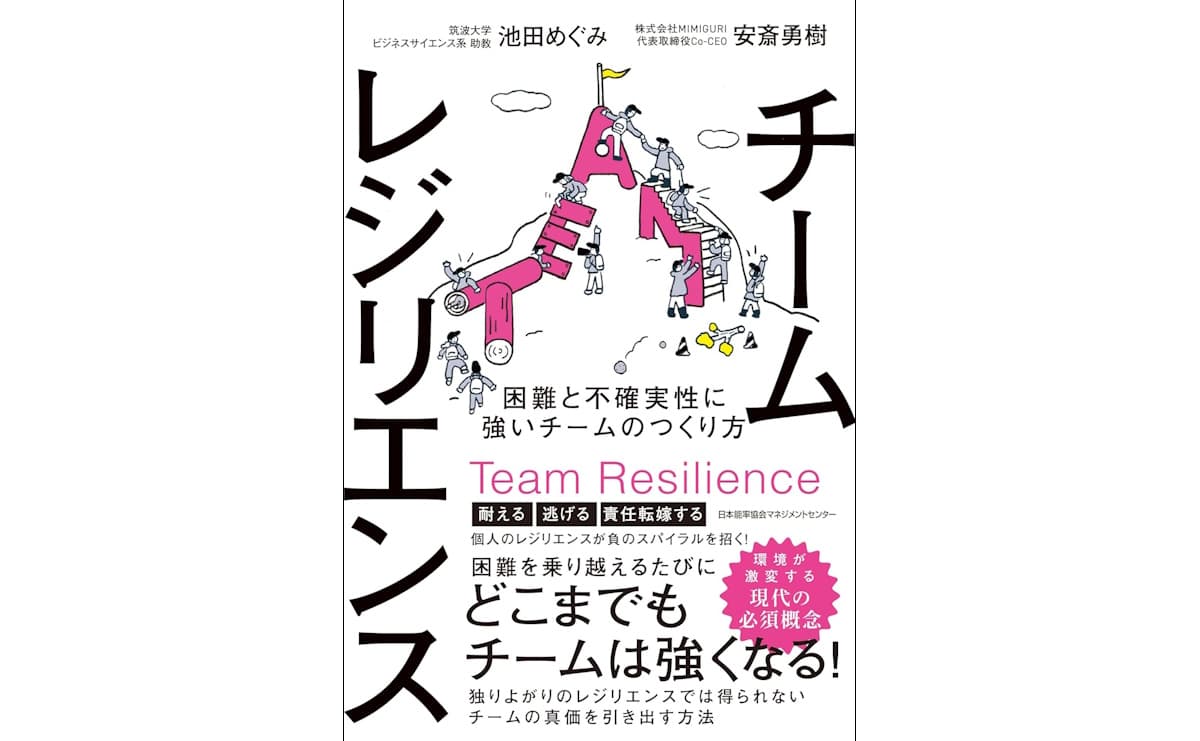どのように長いキャリアを生き抜くか? 「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」受賞作に表れた時代性
2025年02月13日 公開 2025年02月13日 更新

本の要約サービス「flier」とグロービズ経営大学院は、「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」の受賞作品を発表しました。本グランプリは、一般投票により決定するビジネス書の年間アワードで、今年で10回目を迎えます。エントリーされた152冊の書籍の中から選ばれた作品と受賞者の言葉、フライヤーCEOの大賀康史氏による受賞作品の総括をご紹介します。
「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」受賞作品
【総合グランプリ/マネジメント部門賞】
『部下をもったらいちばん最初に読む本』(橋本拓也/アチーブメント出版)
あなたのマネジメントがうまくいかないのは、無免許運転をしているせい――。 部下をもってマネジメントを任されるようになり、プレイヤーからマネジャーになり、その仕事の変化に悩む人たちの声をよく耳にしますが、本書がその解決策として提案するのは、「マネジメントは技術。学べば誰もが習得できるもの」ということ。 そのノウハウ「リードマネジメントのすべて」が詰まった本書は、2万人の研修実績を誇るトップコンサルタントである著者がたどり着いた、心理学をベースにした新しいマネジメントの手法をまとめた一冊。全マネジャーの必読書が登場です。

『部下をもったらいちばん最初に読む本』橋本拓也氏の受賞コメント
――本書では、リードマネジメントという言葉が繰り返し使われていました。この言葉の意味について教えてください。
【橋本】リードマネジメントは、通常マーケティングで使われている言葉です。マネジメントとは部下を管理監督する仕事と言われますが、リードマネジメントとは、管理監督するのではなく、本来メンバーの持つ力を引き出し、導くマネジメントです。
――「世の中のほとんどのプレーイングマネジャーは無免許運転状態」と本書では書かれていました。
【橋本】無免許運転の代表格が私自身です。28歳で初めて部下を持って以降、半年で必ず部下が離職するか、体調不良になるか、成果が出なくて異動していくということを4年間にわたって経験しました。面と向かって「橋本さんのことが嫌いです」と言われたこともあります。
無免許運転だった私が一番初めにしたことは、部下に対する捉え方を変えていったことです。「部下は無能で、自分より能力が低い」と捉えがちですが、「部下は私が持っていない力をもっている有能な才能の塊」だと思うことで、すぐにアドバイスせずに、部下の意見を最後まで聞くことができるようになりました。部下に対する捉え方を変えることがまずスタート地点なのかなと思います。
【イノベーション部門賞】
『イシュ―から始めよ [改訂版]』(安宅和人/英治出版)
2010年の『イシューからはじめよ』(旧版)発売以来、知的生産のバイブルとしてビジネスパーソンを中心に研究者や大学生などから幅広く支持されてきました。14年間一貫して売れ続けて累計58万部に到達(紙と電子版、旧版と改訂版を合算)。ビジネススキルの本として異例のロングセラー、ベストセラーとなっています。
そしてこのたび、「課題解決の2つの型」「なぜ今『イシューからはじめよ』なのか」など、読者の実践のヒントとなる内容を追加した『イシューからはじめよ[改訂版]』を発行いたします。

『イシュ―より始めよ』安宅和人氏の受賞コメント
――本書は知的生産性の本質に届いた本なのではないかと思います。どのような思いで書かれたのでしょうか?
【安宅】この本の最大のテーマは、日本に蔓延る「根性論の打破」です。「頑張れば報われる」といった根性論のせいで、この国は滅びたと僕は思っています。「正しく物を考える」ことをやらないと、いくらロジカルシンキングなどやろうと意味がない。そういった手法論よりも解くべきことに集中して考えましょうというメッセージを込めました。日本の根本的なメンタリティーにくさびを打つのが目的です。14年前に書きましたが、問題はまだ続いていますよね。
――生成AIの時代に突入しています。解くべきイシュ―を見出す重要性が高まると考えられますが、本書がどう活かされるのを期待されますか?
【安宅】このままいくと、人間はプロンプティングしかやることがなくなる可能性があります。何をやりたい、成したいと考えることしか我々のやることはなくなっていく。つまり「イシュ―から始めること」しかやることがないんです。
未来に変化がある、意義があることを我々は考えるべき所に来ています。実は生成AIは問いを立てるのは得意なので、もっと上位概念的に「何がしたい」「何に答えを出したい」という意思の部分が一番重要で、「人こそイシュー」だと思います。意思のない人にイシュ―はない。そこにしか人間の価値はないんじゃないでしょうか。
――多方面でご活躍の安宅さんですが、今後はどのような活動に注力される予定ですか?
【安宅】このままいくと未来には都市しかなくなってしまうと考えていまして、友人たちと行っている「風の谷をつくる運動」に人生の残りを捧げるつもりです。また、「根性論の打破」は一生のテーマです。
【経済・マネー部門賞】
『となりの億万長者が17時になったらやっていること』(嶋村吉洋/PHP研究所)
10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーとしての顔を持つ嶋村吉洋氏がお金持ちになるための法則を明かします。なぜ、お金持ちは自分から挨拶を欠かさないのか? トイレ掃除を徹底するのはなぜか? 1,500名を超える成功者と仕事をしてきてわかった「幸せな億万長者が大切にしていること」を45のエッセンスに分けて解説します。 会社に頼れない時代に、普通の会社員が「17時」から、社会資本、人的資本、金融資本の3つを同時に確立するための戦略書。

『となりの億万長者が17時になったらやっていること』担当編集者・大隅元氏の受賞コメント
――本書を企画されたきっかけについて教えていただけますでしょうか?
【大隅】ここ何年かマネー本といいますと、投資の本、お金を儲けるための本などたくさん出ていました。ただ一攫千金を手にした人たちは本当に幸せなのかなという疑問がありまして、「本当に幸せな億万長者」とはどういう人なんだろう、という疑問に対するアンサーを読者の方にお伝えしたいと思い、この本を企画しました。
――『となりの億万長者が17時になったらやっていること』というタイトルは非常に印象的です。嶋村さんと大隅さんの間でどのようにこのタイトルは決まったのでしょうか?
【大隅】幸せな成功者とは何かを嶋村さんに聞いたら、まず「定時にあがれる人」ということでした。「人生を切り開く力を身につけるためには、仲間と一緒に切磋琢磨する時間が必要で、その時間は17時以降」というお話から、このタイトルに決まりました。
――本書では「仲間の重要性」「具体的アプローチ」が描かれていました。編集される際にどのようなことを大切にされましたか?
【大隅】再現性という部分を念頭に置いていて、嶋村さんだけでなく複数のお金持ち・成功者の方に取材しました。基本的な挨拶や約束の時間前に到着する、など当たり前のことですが、皆さん本当に同じことをされていましたので、そういった共通点を示すことを重視しました。
【自己啓発部門賞】
『あっという間に人は死ぬから』(佐藤舞(サトマイ) /KADOKAWA)
あなたの時間は限られています。今、この瞬間をどう生きますか? 著者は統計のプロで、今もっとも注目を浴びるデータサイエンティスト。古今東西の知恵とエビデンスに基づいた「人生における有意義な時間の使い方」、その具体的な指針を展開します。「それって、あなたの感想ですよね」とは、死んでも言わせません。自己啓発の「常識」を、統計で叩き潰しまくった末に見えた「希望」とは? 自己啓発はコレで終わり。最後の「自己啓発書」ができました!

『あっという間に人は死ぬから』佐藤舞(サトマイ)氏の受賞コメント
――YouTubeなど多方面でご活躍されているサトマイさんですが、この本にはどんな声が届いてますか?
読者の方から聞く声で一番多いのが「この本を読んで会社を辞めました」というものです。それでいいかな?と思いながらも、人の人生に影響を与えたという点では良かったかなと思っています。
――本書では「死・孤独・責任」など避けられない闇と向き合うのは難しいと書かれていました。ご自身はどう向き合っていらっしゃいますか?
人は普段、「死・孤独・責任」といった重圧から逃げるようにして行動していますが、「ずっと逃げるだけで人生をおわっていいのか?」という問いをこの本の中でなげかけています。自分の本心に従って人生を歩んでいくために、本心や価値観を改めて問うようなコーチングブック的なものになっています。
私自身も4年間会社に勤めて、その後ニートを1年間していましたが、その時から、毎週1回「自分はどう生きていきたいの?」という問いを5年間継続して自分に問い続け、なんとか生きてこられたという経験があります。その時に、自分に対してどういう問いを投げかけていたのかということを、本書の中でワークブックとして用意していますので、読者の方にも追体験していただきたいと思います。
――最後に、読者の方にメッセージをいただけますでしょうか。
私自身はこれまで「人に価値提供しなければいけない」「人の役に立たなければ」という強迫観念があり、燃え尽き症候群を繰り返す癖がありました。しかしこの本を書くことで、交感神経が優位な状態よりは、副交感神経が優位な状態で集中できると持続可能な集中ができ、人生に対して没頭できる感覚が得られると実感できました。
この本を読みながら、交感神経が優位な生活だけではなく、集中しながらも副交感神経が優位になる時はどんな時かを探していただけると充実した時間の使い方ができるんじゃないかなと思います。
【リベラルアーツ部門賞】
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(三宅香帆/集英社)
「大人になってから、読書を楽しめなくなった」「仕事に追われて、趣味が楽しめない」「疲れていると、スマホを見て時間をつぶしてしまう」...そのような悩みを抱えている人は少なくないのではないか。「仕事と趣味が両立できない」という苦しみは、いかにして生まれたのか。自らも兼業での執筆活動をおこなってきた著者が、労働と読書の歴史をひもとき、日本人の「仕事と読書」のあり方の変遷を辿る。そこから明らかになる、日本の労働の問題点とは? すべての本好き・趣味人に向けた渾身の作。

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』担当編集者・吉田隆之介氏の受賞コメント
――本書の誕生のきっかけについて教えていただけますか?
私が担当した書籍『ファスト教養』の著者レジ―さんと三宅さんが対談している時に、まさに「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」というフレーズが出て、反響がありました。そこで、労働の話を書かなければいけないんだという気づきを得たことが、本書の誕生につながりました。
――本書では、本に対する愛情が描かれているように思いました。編集で大切にされたことは何でしょうか?
新書というジャンルは50~60代がターゲットと言われていますが、実は本をたくさん読んでいるのは働き盛りのビジネスパーソンだと感じています。そこで、普段はビジネス書を読んでいる方に向けて、本書ではまた違った世界を見せられるんじゃないかということを意識して三宅さんは執筆されていました。どのようにすれば、ビジネスパーソンの方に届く言葉、見せ方ができるかという所を意識して編集を行いました。
【ビジネス実務部門賞】
『いつも幸せな人は、2時間の使い方の天才』(今井孝/すばる舎)
充実したいい1日を過ごすことは、とても簡単です。なぜなら、「いい1日だった」と感じるために、24時間すべてが素敵である必要はないからです。「友だちと飲みに行った2時間がとても楽しかった」「今日観た2時間の映画が最高に刺激的だった」じつは充実した「いい1日」とはこのように、たった2時間あれば得られるものなのです。人生の幸福度を上げるために「生産性を上げる」という方向を目指すのではなく、「大切な2時間にだけコミットする」という、新しい切り口の「時間×幸せ」の1冊が誕生。

『いつも幸せな人は、2時間の使い方の天才』今井孝氏の受賞コメント
――出版後の反響はどんなものがございましたか?
【今井】「本を読んですぐに幸せになれた」という声が多いです。高校生から80代の方まで、幅広い世代の方から声が届いたので嬉しかったです。
――今井さんにとって、本書はどのようなものになりますか?
【今井】いままでの本は、クライアントさんやビジネスの話を題材にしていましたが、今回はほとんど僕の話なんです。これまで自分がやってきたことを全部思い出し、自分自身がエビデンスになって、幸せに楽しく生きるにはどうすればいいかということを書きました。
――「お金がないと何もできないという思い込み」はよくあるものかと思います。お金を使わずに幸せになるとはどのようなことでしょうか?
【今井】よく、お金持ちになったら〇〇をやりたいと言う人がいます。この前、ちょっと高いランチを食べに行ってSNSに写真をあげたら「成功したらそんなランチを食べたいです!」とコメントがきました。でも、5000円のランチだったら、ちょっと奮発すれば行こうと思えば行けると思うんです。「成功したら~」と思いがちですが、値段をみて無理じゃなかったらやったらいいんだと思いますよ。
<特別賞>
【10年を彩るビジネス書】
『学びを結果に変えるアウトプット大全』(樺沢紫苑/サンクチュアリ出版)
説明・アイデア・雑談・交渉など...すべての能力が最大化する。日本一情報を発信する精神科医が贈る、脳科学に裏付けられた、伝え方、書き方、動き方。「メルマガ、毎日発行13年」「Facebook、毎日更新8年」「YouTube、毎日更新5年」「毎日3時間以上の執筆11年」「年2~3冊の出版、10年連続」「新作セミナー、毎月2回以上9年連続」...日本一アウトプットしている医師である、ベストセラー作家・樺沢紫苑が圧倒的に結果が変わる「アウトプット術」を大公開。

『学びを結果に変えるアウトプット大全』樺沢紫苑氏の受賞コメント
――『アウトプット大全』は発行部数が75万部を突破するなど、誰もが知る本かと思います。樺沢さんにとって本書はどのような存在でしょうか?
【樺沢】居酒屋にいるサラリーマンの会話で「お前、アウトプット足りないよ!」なんて言葉を聞くとニヤっとしています。というのも、『アウトプット大全』を出す以前は、日常的にアウトプットという言葉は全く登場しなかったんです。日本中に、アウトプットという言葉が広まったのは嬉しいことです。
――「インプット対アウトプットの黄金比は3:7」という言葉も有名になりました。樺沢さんは、アウトプットとして、日頃どんなことをされているのでしょうか?
【樺沢】20年間メルマガを毎日発行、10年間YouTubeを毎日更新しています。これを続けることで本を書くネタが出来るので、年5冊の本の出版を3年連続で行うことができました。アウトプットは呼吸のようなものですね。
――これからは、どのような活動に注力されていかれますか?
【樺沢】3月に『子どもアウトプット図鑑』という小学生版の本がでるんです。これからは外国人が職場に入ってきますから、日本人はアウトプット負けしてしまいます。そこで、子どものうちからアウトプットが普通にできるようになってほしいと思います。子どもたちのアウトプット力を伸ばしていきたいです。
<特別賞>
【グロービス経営大学院賞】
『チームレジリエンス』(池田めぐみ,安斎勇樹/日本能率協会マネジメントセンター)
国内外の50本を超える研究論文を下敷きに、ベストセラー『問いのデザイン』の著者と新進気鋭の研究者がタッグを組んで、チームレジリエンスの概要と実践可能な高め方を3ステップで解説する。
①困難に対処し、②そこから学び、③被害を最小化する
シンプルなステップだからこそはまりやすい罠とそこに陥らない施策を紹介していく。組織の危機を救い、困難を成長の機会に変える。変化に強いしなやかなチームは何物にも代えがたい価値がある。

『チームレジリエンス』池田めぐみ氏の受賞コメント
――まさにレジリエンスが重要な時代だと思います。本書の執筆の背景について教えていただけますか?
【池田】この本は、私の友人で、チームのリーダーを任され始めた新米マネージャーが重たい問題を抱えて困っていたので、そんな人に向けて書きました。
――レジリエンスという言葉はまだまだ知らない方がいらっしゃるんじゃないかと思います。レジリエンスという言葉に込めた本質とは何でしょうか?
【池田】レジリエンスというのは、困難に押しつぶされそうなとき、パフォーマンスが下がった時に、そこから回復するために必要な力のことを指します。しかし、レジリエンスというと、困難に遭遇した時に、どう乗り越えるのかということに注力しがちですが、実際は乗り越えた後にしっかり振り返って、教訓を得て、それを乗り越えられるチームを作っていくのが大切だと思っています。
フライヤーCEO・大賀康史による「ビジネス書グランプリ2025」総括

2024年は見通しにくい1年でした。能登半島地震などの災害から始まり、ウクライナやハマス周辺の紛争、パリ五輪などのメダルラッシュ、衆議院選挙、トランプ大統領の再選など、価値観と感情が揺さぶられる出来事がありました。世界ではポリティカルコレクトネスの揺り戻しの動きが各国で見られ、ますます個人の生き方の複雑性が増しています。
経済面ではインフレ傾向が定着し、堅調な企業業績や1月から始まったNISAの新制度などの影響もあって、日経平均は全般として好調に推移しました。貯蓄から投資の流れが定着し始めた1年と言えるでしょう。テクノロジー面ではChatGPTが象徴するAIが急速に進化していて、2025年はAIエージェント元年とも呼ばれ、いよいよ人を超える知性を持つAIの足音が聞こえてくるようです。
私たちを取り巻く環境の変化がめまぐるしい中で、今のビジネスパーソンはどのように長いキャリアを生き抜くのかというテーマに向き合わざるを得なくなっています。このような背景から今回のビジネス書グランプリのキーワードは「自分らしく選び、自分らしく生きる」としました。
キャリアを真剣に生き、組織が抱える課題を解消していく流れと並行して、個人としての幸福をキャリア以外に求める流れもあります。過去は、キャリアの成功と個人の幸せの2つが同時に達成されやすいものだったように思いますが、現代はそれぞれに個別に向き合う必要があります。
変化し続ける世の中で、ありのままでいたいと思っても、ありのままでは自分の理想に近づけないものでもあります。今回の受賞作は、キャリアや人生に主体的に前向きに向き合うものばかりでした。時代をとらえ、素晴らしい本を作られる出版業界の方々に、改めて感謝申し上げます。
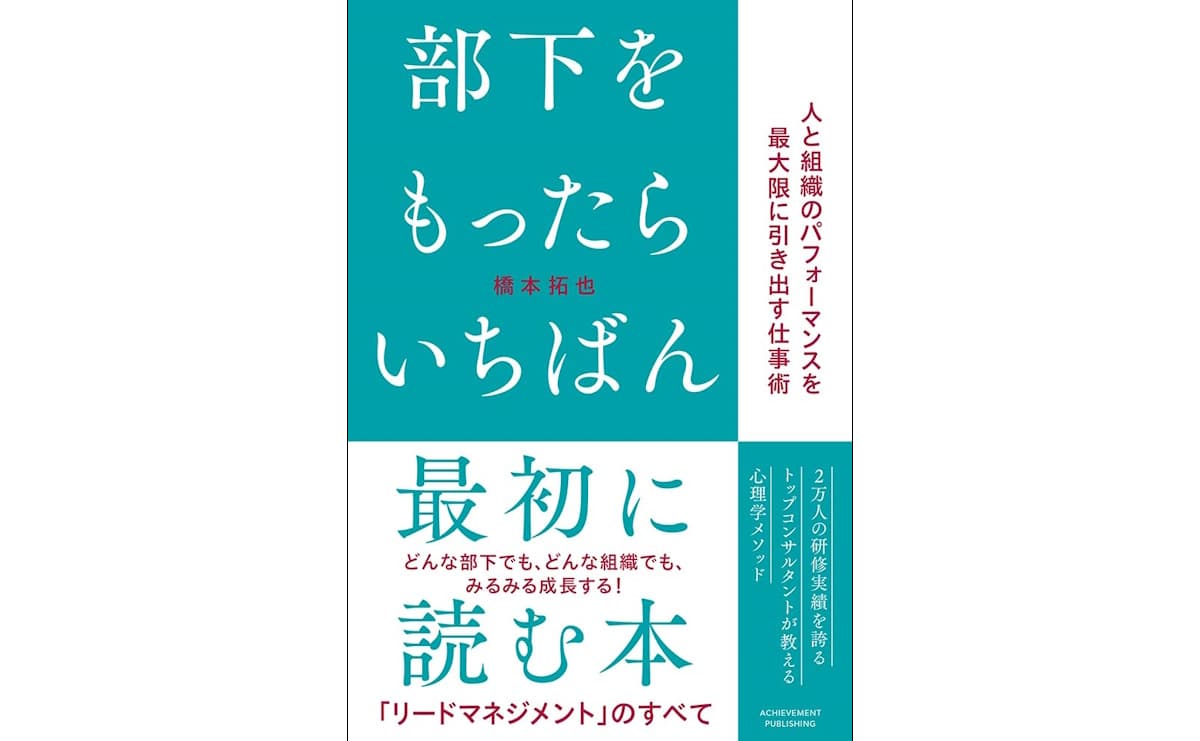
![イシューからはじめよ[改訂版]](/userfiles/images/2025/2025A/250213flier02.jpg)