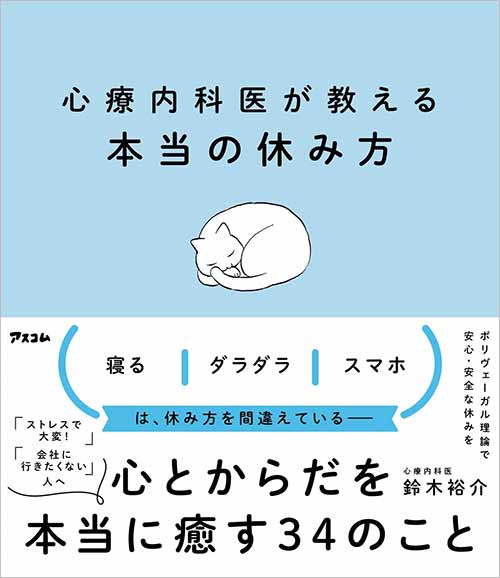心療内科医・鈴木裕介氏が、アスコム主催のメディア向け勉強会にて「冬季うつとメンタルケア」について語った。冬の間は気分が落ち込みやすくなる人も多いが、適切な対策を取ることで冬季うつを防ぐことができるという。本記事では、1月中旬に行われたイベントの内容をレポートする。
冬季うつとは?
鈴木氏は、季節性うつ(季節性感情障害:SAD)について、「日照時間の短縮によってセロトニンの分泌が減少し、気分の落ち込みを引き起こす疾患」と説明する。一般的なうつ病と異なり、過食や過眠が特徴的であり、朝起きるのが辛くなったり、食欲が増して体重が増加しやすくなる傾向があるという。
日照時間の重要性と対策
「人間は動物の習性として日照時間で季節を感知している」と鈴木氏は述べる。冬季うつの患者はこの感覚が特に敏感に残っている可能性があるため、光を積極的に浴びることが症状の改善につながるという。
特に朝の光を浴びることが重要だ。これにより体内時計がリセットされ、自然な生活リズムを取り戻しやすくなる。曇りの日でも3万ルクスほどの光があり、外に出ることで十分な光を取り込むことができる。最近では光照射器も市販されており、5,000円ほどで購入可能なものもある。こうしたアイテムを活用するのも有効な方法の一つだ。
メンタルヘルスと食事の関係
「メンタルが不調になると高脂肪食に偏りがちになる」と鈴木氏は指摘する。これは、脳が一時的にエネルギーを求めるためだ。しかし、セロトニンの分泌を促すためには、タンパク質をしっかり摂取することが重要である。
セロトニンの材料となるトリプトファンは、卵、ナッツ、大豆、バナナなどに多く含まれる。また、糖質を摂ることで一時的にセロトニンの分泌を増やすことができるが、過剰摂取すると血糖値の乱高下を引き起こし、かえってストレスを増幅させるリスクがあるという。
さらに、料理をすること自体がメンタルヘルスに良い影響を与える。鈴木氏によれば、料理はポジティブな感情を生み、創造性を高め、達成感を得ることでセルフケアとしても機能する。難しい料理である必要はなく、簡単なもので十分効果があるという。
温度変化はメンタルヘルスにどう影響を与える?
鈴木氏は、「寒暖差は体だけでなくメンタルにも影響を与える」と説明する。特に気温の変化が大きく、短時間で変動するほど体への負担が大きくなる。
寒さによって筋肉がこわばると、胸式呼吸がしにくくなり、眠気やぼんやりした感覚を引き起こす。また、精神的ストレスが腰痛の原因にもなり得る。特にデスクワークの人は上半身のストレッチを行い、筋肉の緊張をほぐすことが大切だという。
対策として、入浴やストレッチを取り入れることが推奨される。お風呂に浸かることで体が温まり、副交感神経が優位になりリラックスしやすくなる。温かい服装を心がけることも寒さによるストレスを軽減するのに役立つ。
休むためのプロセス
「休息をとるには適切なプロセスが必要」と鈴木氏は強調する。そのプロセスは次の3つのステップに分けられる。
①休む必要があると気づく
②「休みます」と宣言する
③適切な療養行動をとる
特に日本人には「過剰適応」が多いと指摘する。これは、社会的な要求に応えて行動はできているが、内面的には満たされていない状態を指すという。
「休むことは、意味のある行動と意味のない行動のバランスが重要」と鈴木氏は語る。そのため、仕事をしていないからといって、必ずしも休めているわけではないという。
鈴木氏によるメンタル3モード
鈴木氏はメンタルの状態を3つのモードに分類している。
炎のモード(アッパー系):血圧が上昇、切羽詰まっている
リラックスモード:穏やかで余裕がある、ゆっくりした呼吸ができる
氷のモード(ダウナー系):無気力、感情を感じにくい、エネルギーを消費しない
「重要なのは、いま自分がどのモードにいるか認識すること」と鈴木氏は説明する。冬季うつは氷のモードに分類されることが多いため、前述したような光療法や適切な食事を摂ることがメンタルの回復につながるという。
まとめ
冬季うつを防ぐためには、朝の光を浴びることや、バランスの取れた食事を心がけることが重要である。また、寒暖差による影響を抑えるためにストレッチや入浴を取り入れることも効果的だ。さらに、適切に休むためのプロセスを意識し、自分のメンタル状態を把握しながら調整していくことが大切である。
鈴木氏の著書『心療内科医が教える本当の休み方』には、さらに詳しく「本当に心と体を回復させる」休み方が書かれているという。同書も参考にしながら、日々の生活の中でできることから実践してみてほしい。
(取材・執筆:PHPオンライン編集部 片平奈々子)