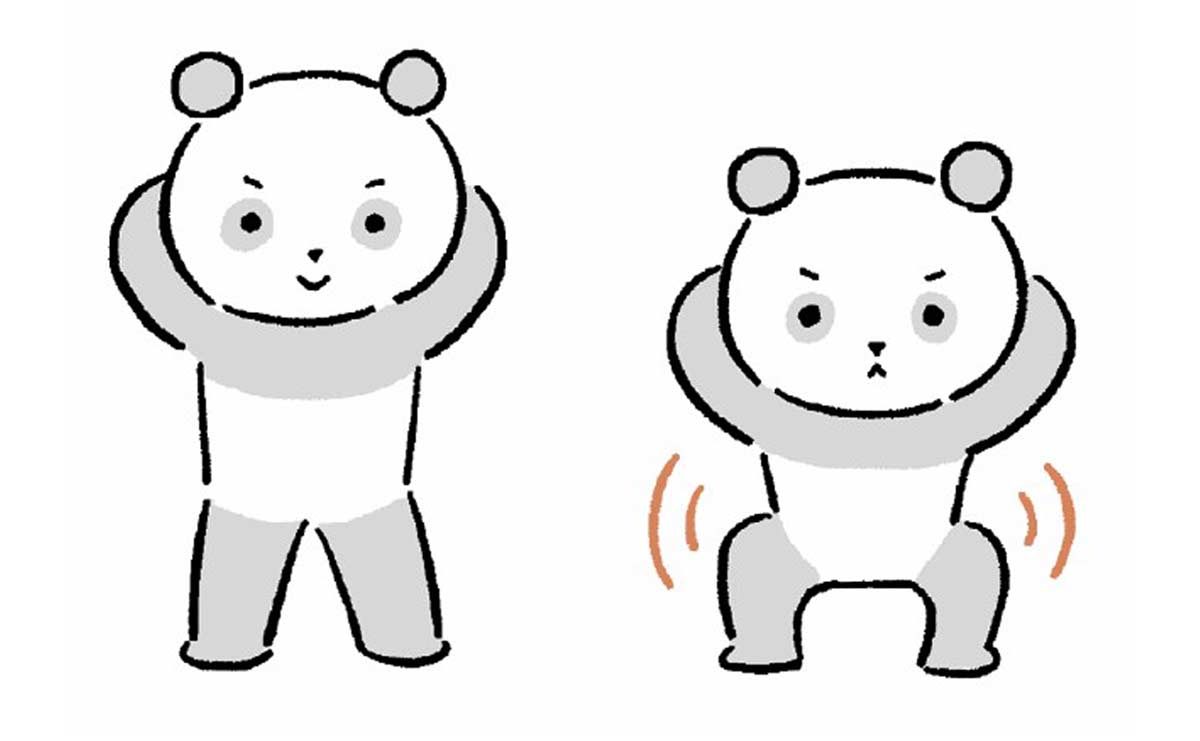要領のいい人と悪い人は、いったい何が違うのでしょうか?その違いを作業療法士の菅原洋平さんが「脳の使い方」から紐解きます。
※本稿は、『PHPスペシャル』2025年7月号より、内容を抜粋・編集したものです
「トップダウン注意」と「ボトムアップ注意」
あなたは、やるべきことがあるのに、つい他のことに気を取られて時間を費やしてしまい、後悔したことはありませんか?
私たちの脳が向ける注意には、自らの意思で注意を向ける「トップダウン注意」と、目の前の刺激に反射的に注意を向ける「ボトムアップ注意」の2つがあります。たとえば、「この本を読むぞ!」と思って本を手に取るのがトップダウン注意、何気なく目に止まった本を手に取るのがボトムアップ注意だと言うとわかりやすいかもしません。
もちろんどちらも大事なのですが、日々の生活の中では、ボトムアップ注意のほうに翻弄されるあまり、トップダウン注意を忘れてしまうということが起こりがちです。なぜなら、ボトムアップ注意というのは外敵から身を守るための本能的な注意なので、重要度が低いものでも優先的に対応すべきだと脳が勘違いしてしまうからです。
そうやって1日中ボトムアップ注意に振り回されていると、こなしたタスクの数は多くても、本来やるべきことが進んでおらず肝心のゴールにたどり着けない、ということが起こります。この状態は「要領がいい」とは言えませんよね。
つまり、「より多くのタスクをこなせること」は、必ずしも「要領がいい」というわけではないのです。
大事なのは脳のマネジメント力
「要領がいい」とは、「設定したゴールに最短距離で向かえること」です。
もちろん設定したゴールに最短距離で向かえるかどうかは、やるべきことをやれたかどうかにかかっているわけですが、それを左右するのは、「やる気」や「意志の強さ」などではありません。脳を上手にマネジメントして、望んだ行動ができるように仕向けられるかどうかです。
脳をうまく使い、思い通りの1日を過ごすことができるようになると、自分自身の満足度も高くなります。それこそが、真に「要領がいい」ということなのです。
〈1〉余計な刺激が入らない環境を作る
やるべきことがあるのに、ついスマホに手が伸びてしまうというのも、ボトムアップ注意に惑わされている典型的なパターンです。そもそも脳は、快感を得られる報酬系の刺激のほうに敏感に反応するようにできているので、スマホが目の前にあるのに使うのを我慢する、というのは土台無理な話です。
だからこそおすすめしたいのは、仕事や作業に集中したいときは、そのような刺激、とりわけ報酬系の刺激がない環境を用意しておくこと。スマホはもちろん、おやつなどもロッカーの中に入れておき、作業をする場所から遠ざけるのが一番です。
〈2〉15分に1度、「消化作業」の時間を取る
休憩を一切取らずに同じ作業を続けていると、脳は勝手に情報の「消化モード」に入り、別のことを考え始めたり、前にしたことが頭から消えたりしてしまいます。この状態を「マインドワンダリング」と言います。そうなると「心ここにあらず」のまま作業を進めることになるので、これほど無駄なことはありません。
マインドワンダリングは16分に1回起こると言われているため、15分ごとに作業に区切りをつけ、情報を消化するタイミングを意図的に持つようにすれば、それを防ぐことができます。具体的には10秒程度、パソコン画面から目を逸らしたり、目を閉じたり、まばたきを繰り返したりすれば充分です。
〈3〉1つの場所で1つの作業を行なう
脳は、過去の記憶に基づいて「どのくらいの代謝率(血圧や心拍数)で臨むか」という見通しを常に立てています。会社や仕事部屋のデスクにつくと、パッと仕事モードに切り替わるのは、その記憶が「空間情報」とセットになっているからです。
ところが、同じ場所でさまざまな作業をするのが当たり前になってしまうと、脳がうまく準備できず、なかなか集中できなかったり、急に代謝を調整したせいでどっと疲れてしまったり、ということが起こります。
「勉強する机では他のことをしない」など、1つの場所で1つの作業を行なうことを心がければ、脳が予測を立てやすくなるので、速やかに集中できるうえに、疲れも感じにくくなるでしょう。
〈4〉体の記憶をうまく使う
脳が持つ記憶には、筋肉が動く感覚や、触覚なども含まれます。それらの記憶を呼び起こすような工夫をすれば、脳はどう代謝を調整するかの見通しを立てやすくなり、無理に「やる気」を起こそうとしなくても、スムーズに作業に移ることができます。
たとえば、汚れた鍋を洗うのが面倒だと思うときは、とにかくその鍋を両手で触ってみてください。洗うときのジェスチャーをするだけでもかまいません。そうすると、その感覚を元に脳が勝手に準備を進めてくれます。ここまで来ると、それに抗うほうがストレスなので、洗うという作業に移りやすくなるのです。
〈5〉思い込みを手放す
過去の記憶を基に先の見通しを立てるのは、効率的にエネルギーを使うための脳の優れた仕組みです。ただ、脳に余計な負荷をかけないというメリットがある一方で、馴染みのある方法や考えに引っ張られてしまい、別の視点が持ちにくくなるというデメリットがあります。
「構え効果」と呼ばれるこの弱点を克服するのに有効なのが、先ほど情報を消化するのにおすすめした方法、「目を閉じること」や「まばたき」です。それらをすることによって構え効果から解放された脳は、情報を冷静に整理できるようになります。新たな視点も生まれやすくなり、目的を達成するために一番適した方法を見つけられるでしょう。
【「ToDoリスト」ならラクに動ける!】
実行へとつなげる「ToDoリスト」を作るコツは、具体的なフレーズで詳細に書くことです。たとえば単に「片づけ」と書くよりも、「机の上の資料をファイリングして棚にしまう」と書いたほうが、脳がその先の展開をラクに予測できるので、行動に移しやすくなります。
ただし、「ToDoリスト」が常に見える状態にあると、それは余計な情報(ボトムアップ注意)となってしまいます。次の作業が気になって集中できなくなる可能性があるので、リストを見てやることを決めたら、そのたびに見えない場所にしまいましょう。
アイデアがひらめく3つの方法
思い込みから抜け出す方法は、他にもあります。副交感神経の一種である「迷走神経」が刺激されると、固執した考えから離れることができ、ひらめきが起こりやすくなります。迷走神経を意図的に刺激する3つの方法を紹介するので、試してみてください。
〈1〉10秒呼吸法
ゆっくり10秒カウントしながら1から3までで息を吸い、4で止めて、5から10で吐き切ります。これを6回繰り返してください。
〈2〉手足を温める
洗面器などにお湯を入れて、手や足を温めましょう。脳の血流量が増えるので、脳機能の低下を防ぐ効果も期待できます。
〈3〉ホットアイマスク
タオルを濡らして軽く絞り、電子レンジで温めます(500Wなら1分くらい)。やけどしない程度に冷ましたら、目元に当てましょう。
作業効率を上げる24時間の過ごし方
脳に備わっている「生体リズム」をうまく活かせば、よりラクに、そして効率的にパフォーマンスを発揮することができます。生体リズムは「起床時間」を起点にスタートします。そのため、人によって「午前」「午後」「夕方」「夜」にあたる時間帯が変わるので注意してください。
\目覚めたらまず、光を浴びよう!/
脳に光が届くと、脳内物質のメラトニンの分泌がストップし、それによって健康的な1日のリズムが作られます。これが真の「起床」となるので、目覚めたらまず窓際に行くなどして、光を浴びるようにしましょう。
【午前】起床から6時間後まで...頭を使う知的作業を行なうとGOOD
朝イチにパッと思い浮かんだことは、脳が重要だと判断したことなので、それに基づき行動を起こすようにしてみましょう。外からの刺激には距離を置くほうがいいので、SNSやメールのチェックは、後回しにしてください。
午前中は頭がよく働くので、新しい企画を考えたり、クリエイティブな作業をしたりするのにピッタリです。ただし、総じて男性ホルモンが優位になり、共感力より戦闘力が高まるタイミングでもあるので、誰かに新たな提案などをしても、受け入れてもらえる可能性は低めです。この時間帯は、自分本位で進められる作業に徹しましょう。意見を戦わせることが目的なら、会議を入れてもOKです。
【午後】起床から7~9時間後...頭より、手を動かす作業がおすすめ
ひたすら手を動かすような単純作業がはかどる時間帯です。午前中のうちに大まかに仕事の方針を決めておくと、スムーズかつスピーディーに作業が進むでしょう。
また、メールなどへの対応も、この時間に行なうのが脳の使い方としては理想的です。テンションが高まり、相手も自分もノリがよくなるので、企画提案や意見を伝えるのにもいい時間。ただし、調子に乗るぶん失言もしやすいので、その点は気をつけてください。
また、ネガティブなことを伝えるのも、午後がおすすめです。相手のことを受け入れやすくなるこの時間なら、角も立ちにくく、比較的スムーズに受け入れてもらえるでしょう。
【夕方】起床から10~11時間後...パワー全開で何でもできる無敵の時間帯
午後に引き続き身体能力が発揮されますが、知的作業にも向いています。計算力や決断力が高くなることも研究で明らかになっているので、やり残した作業を一気に片づけてしまいましょう。
また、本来したい作業以外の雑務をできるだけ午後の時間帯に済ませておくのも、この時間の集中力を活かすコツです。困難な作業にもそれなりに対応できるので、この時間帯に少し踏ん張って、翌日の見通しが立つところまで作業を終えておきましょう。
理想的なのは、翌日やろうとしている作業に少しだけ手をつけておくこと。そうやって脳に作業の「下見」をさせておくと、翌日の取り掛かりがスムーズになります。
【夜】起床から12時間後~次の起床まで...新奇情報は入れず、決断は翌日に
基本的にパフォーマンスが低下するので、単純作業だけにとどめるのがベターです。避けたいのは新奇情報に晒されること。
もともと脳には、「自分に必要のない情報をマスキングする(覆い隠す)」機能が備わっているのですが、1日働いて疲弊しているため、夜の脳はその機能をうまく働かせられません。そのせいで、すべての情報が自分に関係があると思い込みやすくなり、情報の選別ができず、ただ疲弊するだけになってしまいます。
でも、馴染みのあることや知っていることの延長であれば、うまく結びつけられるので、これまでに学んだことがある分野の勉強をするのには、向いている時間です。

![PHPスペシャル 2025年7月号[毎日が変わる時間の使い方]](/userfiles/images/book2/B0F9GT5JH1.jpg)