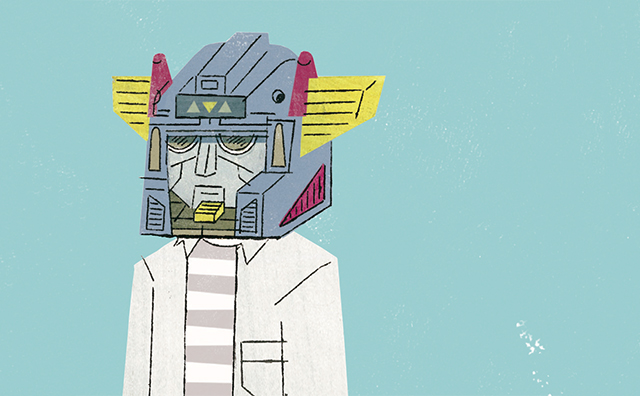企業内の世代間格差は「問題」ではない
2011年03月22日 公開 2024年12月16日 更新

※本稿は、『Voice』2011年4月号[『若者厚遇』で世代間格差を破壊せよ](PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです。
"成果主義"の強化が生んだ世代間格差
私は2003年後半から年およそ100人ペースで、大企業の20代、30代社員を一貫して取材し続け、自身の経営するニュースサイトで記事を発表しつつ、7冊の単行本にも分析結果を収録している。
この7年間ウォッチしていて、若手社員の働く環境には、ある明確な変化がみられ、確実に世代間格差を広げた。それは、成果主義の人事処遇が強化され、ほぼ定着に至ったことである。
戦後の年功序列型の給与制度は、1990年代半ばから形式的に人事査定による評価で差がつくようになってはいたが、ソニーが2004年4月から係長以下の一般社員約12,000人に「グレード制」を導入、キヤノンが2005年に「役割給」を導入して職務給(=人ではなく役割やポストに給与が紐づく)に20代の段階から近づけるなど、各社で急激に年功序列色が薄まった。
もちろん業種次第で強弱があり、規制産業(電力、ガス、マスコミ)は旧態依然として変化がない一方で、国際的な競争が激しい電機とエレクトロニクス・メーカーでは変化のスピードが最も速かった。代表格は、海外販売比率が7割を超えているソニーである。グレード制導入とともに、家族手当や住宅手当も全廃され、上の世代が享受してきた手厚い福利厚生も消えた。
昨年、同社の中堅社員に話を聞くと、すでに待遇面については諦めたふうだった。「いまのまま、給料は上がらないだろうと思っています。課長になれなければ、サラリーが毎年1,000~2,000円ずつしか上がらない。40代のバブル期入社世代でさえ課長になれていない人が多いので、30代のわれわれがそれを飛び越えて課長になるのは、かなり難しいんです」。数年前に組んだマンションのローン返済もあり、不安そうだった。
会社の成長が鈍化、および低下するなかで、年功序列でみなの給与を上げ続けたら、固定費増で赤字体質になってしまう。よって、総人件費の抑制が必要で、削減インパクトが大きいのは頭数が多いバブル期入社組だから、彼らの給与が高くなる40歳までにルールを変えてしまえ、というのが会社側の狙いだった。だから、バブルピークの1990年入社組が30代後半を迎えた2004年前後に、"成果主義"への変更が相次いだのである。
要は、人件費が削減できればよいので、人事制度改定ではなく「運用」で対処している会社も多い。
流通大手のイオンは、昇格試験の合格率を恣意的に下げることで調整している。「2010年度の『M2』への昇格試験は、なんと合格率2%だったというんです」(同社30代社員)。
イオンの社員(総合職)はJ(ジュニア)とM(ミドル)の二階層に分かれ、それぞれが三段階あり、毎年1回、5~9月に実施される昇格試験に基づいて、J1→J2→J3→M1→M2→M3と昇格する。M2に昇格できないと年収は600万円程度から上がらない。つまり、この水準で定年まで頭打ち、という社員が増えそうなのだ。
キヤノンも、役割給の導入に加え、昇格試験の絶対的な難易度が上がったとの声が多い。「年々、狭き門になっていて、昇格試験の会場に行くと、ものすごい人数で驚いた。隣のおっちゃんをみていると『この歳まで受からなかったらどうしよう。自分は一生、いまのポジションかもしれない』と思いました」(30代社員)。
「リストラはしない」と明言してきたキヤノンだけに、その代償として、総人件費の高騰を抑えるために、若手から昇格者を絞らざるをえない事情がある。前出の同社30代社員がいう。
「若い人ほど昇格が厳しくなっているんです。若い主任はスゴい人ばかりですが、年配者の主任にはバラツキがある。つまり、いまの基準なら主任になれないはずの人も、ひと昔前まではなれていて、一度なった人は、よほどのことがないかぎり降格はされない。一方、いまの若い人のなかには、一生、主任になれない人もいます」
ルールは変わったが、中高年が獲得済みの既得権(すでに年功序列で高水準に上がり切った給与)は守られるため、中高年が退職するまでの期間は、若い人ほど割を食うわけである。
悠々と余生に入った団塊の世代
一方、大企業では、この成果主義導入と軌を一にして、希望退職募集による50代のリストラが行なわれた。一時期(2003年11月)、ソニーの希望退職募集の応募資格年齢が30歳まで引き下げられたことが話題となったが、ソニーに限らず、松下電器産業(現・パナソニック)でも日立製作所でも、部下のいない50代の担当部長クラスを中心に、多額の割増退職金が支払われ、半強制的に"勇退"となる例が相次いだ。
「自分が所属する部は150人くらいでしたが、約20人が早期退職制度で辞めていきました」(ソニー中堅技術者)。この制度により、2004年3月期だけで約5,000人が退職している。応募条件として、最大で基本給60カ月分もの手厚い加算金が提供されたという。基本給にして、なんと5年分である。
資生堂も、2004年末に50代社員を対象に、1,000人を目安に早期退職を募集したところ、1,364人が応募するという異例の定員オーバーになった。当時、50代は約2,600人いたため、半数超が応募したことになる。なぜかというと、通常の退職金に加えて特別加算金が一人当たり平均で3,000万円も積まれたからだった(同社は、特別加算金として300億円を計上した)。多くの人は、これでローンの支払いも終えられる、と考えたに違いない。
資生堂のように3,000万円も余計にもらったり、ソニーのように年功序列で50代まで給与が上がり、かつ上がり切った基本給ベースで最大5年分も上積みされ、悠々と余生に入ったのが、大企業勤務の「団塊の世代」であった。
三井物産の希望退職は1999~2003年に、秘密裏に行なわれた。勤続15年以上、45歳以上の総合職が対象で、前年度年収の6割が10年間支給され、退職金も定年まで働いたとみなして支給するという、超・好条件の早期退職支援制度だった。
「残り期間6割保証という、とんでもなくオイシイ制度。オニのように幸せな人生ですよ。バブル時代に40代を過ごし、みんな年収1,600万円とかもらってね……」(同社の中堅社員)
若手・中堅社員は、こうした「羨望の目」以外では、同情の念も抱いている。「たしかに手厚いとは思う。でも会社から、そこまでして辞めてほしい、といわれるのも悲しいものがありますよね……」(前出のソニー中堅技術者)。
そして若い人ほど、もはや過去の話になっている。資生堂の30歳前後の社員はいう。「次はバブル期入社組を徐々に辞めさせていくでしょう。同期がわれわれの2倍に当たる100人以上もいて溜まっているため、自分の世代は3、4人に一人しか課長以上に昇格できないといわれているんです」。
すでに逃げ切った年配者たちよりも、むしろ、より身近なバブル期入社組を「目の上のたんこぶ」として気にしているのが、いまの30代なのだ。
20代~30代前半くらいまでの世代は、入社時点から、すでに成果主義が導入されていた戦後初の世代である。「団塊の世代」のリストラもすでに入社時には終わっていた。いまでは、自分の処遇に直結するバブル期入社組の扱いに関心は移っている。そして20代社員に聞くと、昔話にすぎず、特段の感想を聞くこともない。
ただ実際には、JALの倒産で表面化したように、多くの大企業では「団塊の世代」が退職後も手厚い企業年金を受け取り続け、その一方で現役社員はその“仕送り”を続けるために働き、自分がもらう時点ではJALのように会社が存続しているかすら危うい実態がある。これは、国の年金や保険とまったく同じ、ねずみ講(賦課方式)の構図である。
![Voice 2011年4月号[『若者厚遇』で世代間格差を破壊せよ]](/userfiles/images/book2/img_disp_pub(4).jpg)