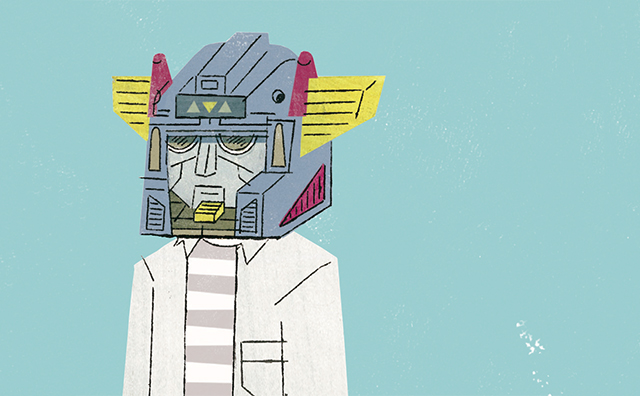企業内の世代間格差は「問題」ではない
2011年03月22日 公開 2024年12月16日 更新

「後ろから刺してやろう、とは思わない」
このように、大企業内における「団塊の世代」(現在、60代前半中心)以上と、「ポストバブル期入社世代」(現在、20代~30代)の世代間格差は、間違いなく存在する。かつては年功序列的に上がると考えられた給与が、いまの30代以下の中堅社員では「幻」と化し、20代の若手社員は入社時から成果主義なので「そんな世界はない」と最初から諦念をもって働いている。はたして、この格差は問題というべきなのか。
リアルに上下世代をみている前出の三井物産社員(30代後半)は、こう分析する。「いまの50代以上が恵まれているのは確か。でも、だからといって後ろから刺してやろう、とは思わない。団塊の世代は、戦後の何もない状態からスタートして、いわば先行投資をした。苦労して投資に成功し、会社も国も経済成長したのだから、そのリターンを得るのは当然。そして、GDP(国内総生産)の成長が止まった現在、30代以下が同様の果実を得られないのも、当然なんです」。
たしかに、団塊の世代といまの若者世代では、「苦労の度合い」が違う。団塊の世代は貧しい時代からスタートし、子供のころに海外を旅するチャンスなどなく、寿司を食べるチャンスもなかった。いまの若者がどちらも簡単にできるのは、団塊の世代の苦労があってこそ、だ。
団塊の世代は猪突猛進に働いた。パナソニックで週休2日制が実現したのは1965年のことで、それまでは週休1日が当然だった。いまの若者世代は、コンプライアンス強化の名のもと、労働基準監督署の監視も厳しくなり、サービス残業が劇的に減っている。
2004年、ビックカメラで未払い残業代が問題となり、社長を含む役員ら8人が労働基準法違反容疑で東京地検に書類送検され、2005年3月、未払いだった賃金約30億円を従業員らに支払った。この事件に、昨今の動きは象徴されている。じつは、労働環境がまともになったために、取材していても面白い話を聞く機会が減っているのが私の実感だ。これは好ましいことである。
かつての成長を支えてきた三井物産の50代社員の多くは、内部統制やコンプライアンス系の部署に異動し、高賃金を得ながら定年を待っているという。それも、若いころの苦労に対する報いと考えれば、容認できないことはない。
前出の中堅社員がいう。「昔は、落ちていくチャンスもなかったが、突き抜けるチャンスもなかった。みなが普通にサラリーマンになった。いまはグローバル化、IT化で、(非正規社員に)落ちるのも、(起業して海外事業で)突き抜けるのも自由。グローバル時代なのだから、学生時代に海外に出ないのなら、落ちていくリスクは高まる。地球儀をみればわかるようなもんでしょう」。
若干、厳しいとは思うが、これが現実である。団塊の世代は、焼け野原の状態から勤勉に働き、世界史に残る、戦後の奇跡的な高度成長を牽引した。「奇跡」は何度も起きないものだ。「奇跡」と比べて貧しいとか苦しいとかいうのは、明らかに比べる対象が間違っている。つまり、企業内の世代間格差は、解消すべき「問題」というほどのものではない、というべきだろう。
「世代内」格差をグローバルでみよ
では、いまの若者世代は、何と比べるべきなのか。それは当然、同じグローバル労働市場で、最大規模の人口を誇る中国やインドの労働者にならざるをえない。そしてそれが、若い世代が仕事上の苦境から脱出する唯一の方法でもある。
一例として、私が2月下旬まで4週間滞在していたインドで取材した会社の話をしよう。インドは近い将来、中国を抜いて世界最大の人口を擁する国となる見込みで、好むと好まざるとにかかわらず、グローバル化によってインド人がわれわれと同じ労働市場に参入してくるわけだ。
私が訪れたのは、日本の財閥系商社が51%の株をもつ中堅企業で、約130人の社員がいる。業務内容は、携帯電話の情報サービス(ショートメッセージ等)の提供だ。日本人が一人派遣されているだけで、残りは全員がインド人という会社である。
社員は全員大卒で、現地語に加え、英語を話す。大卒新人は、まず「トレイニー」として月給1万ルピー(2万円弱)で採用される。成果が上がれば毎年、倍々で上がっていくが、全体で毎年およそ半数の社員が、自分から辞めるか解雇される。平均在籍年数は1.5年くらいだという。
給与の上昇率がゼロだと、「そろそろリストラ」の合図。そして、ある日突然、自分の席の隣に、自分と同じポジションの人がやってきて、自分が呼び出され、解雇通告を受ける。インドの法制度では、基本給の2カ月分を払い、2週間前に通告すれば解雇が可能なのだという。
社長の年俸は約2,500万円、その下の幹部7、8人が、600万~1,000万円。これらは毎年、約2割ずつ上がり、ハングリーな彼らは、上げなければ転職してしまう。年1回の給与交渉は、経営側にとっても最大のイベントだ。給与水準の相場は現在、都市部では日本の5分の1くらいの感覚であるが、13億人のインド人が、どんどん日本との距離を縮めている。
こうした1年勝負の"超成果主義"のなかで鍛えられた強烈な向上心をもつインド人と、年功序列のぬるま湯に浸かってきた日本人とが、同じ労働市場で働かざるをえない時代が、近づいているのだ。
その会社で2年間、採用責任者をしていた日本人によると、「感覚的に、日本人一人の人件費で、新興国では優秀なピカピカの外国人を3人雇える。だから、外国人にキチキチのノルマを課して死ぬほど働かせたほうが、業績は上がる。ユニクロやパナソニックが外国人を増やすのは、人件費を下げる点でも正しい流れだと思う」。
日本人の雇用は、新興国との競争のなかで、国際的に侵食されていくと考えるのが普通だ。上の世代と比べて少し待遇が悪いとか、貧しいとか苦しいとか、瑣末なことを考えている場合ではない。親世代がつくった仕組みにタダ乗りしようと考えるのではなく、自分らで新たな秩序を切り開くことを考えるほうが正しい。チュニジアでもエジプトでもリビアでも、若者を中心に、いままさにそういう動きが起きている。
![Voice 2011年4月号[『若者厚遇』で世代間格差を破壊せよ]](/userfiles/images/book2/img_disp_pub(4).jpg)