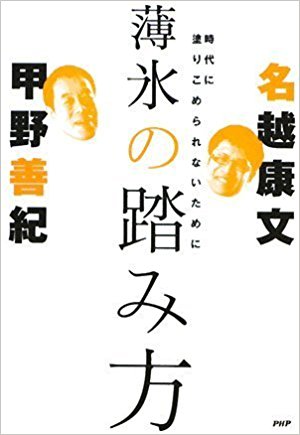広角的な視点をもたらした哲学書や現象学、言語学
当時、精神科医として医療を行っていた私は、同じ家族でも一人ひとりの現実の認識が違うということを痛感していました。
世界とは、人とはどういうものかという世界(他人)認識、自分はどんな人間かという自己概念、自分はどんな人間になりたいかという自己理想──クライアントさん(患者さん)たちは、この3つのうちのどれか(あるいはすべて)が深く傷ついていて、非建設的になっていることが多いのです。
いろいろなクライアントさんを診ているうちに、私が現実だと思っているものが本当に現実なのか心配になってきました。人間は病のあるなしにかかわらず、世界の見え方に大きな隔たりがあるのではないか、という不安です。
現象学は、自分の先入観なしに世界はどこまで見ることができるのかということを思い悩む(研究する)学問です。
また、私たちは主に言葉で世界を知る・知らされるわけですが、言語の構造などから世界を見ていくのが言語学です。ある意味、切り取ってきた映像も言葉といえるかもしれません。
それでフッサールの現象学の本を読みましたが、1行もわかりません。次に哲学者・竹田青嗣(せいじ)さんの現象学の解説本を読んだら、「なるほど現象学とはこういうものか」とわかりかけてきました。
そうして、現象学について書かれた本を何冊か読みます。その次の言語学では丸山圭三郎氏の本を片っ端から読んで、次に廣松渉氏や、正確にいうと哲学というより思想という範疇かもしれませんが、吉本隆明氏の本などをウンウン言いながら読んでみました。
そんなときの私の読書タイムは夜中の12時から3時くらいまでの2〜3時間で、これが30代からの日課でした。
今は、何が本当のことかがわからない時代と言われています。自分を見失いがちなそんな時代には、見る目を養っていかなければなりません。
私は30代の頃にウンウンうなりながらでも哲学書や現象学、言語学の本を読んでいてよかったと思います。自分が見るものを相対化できる力が養えたからです。
文学や哲学の本によって、以前よりは広角的な視点で世界を見ることができるようになったと思います。
昔から受け継がれる文学作品を読む
ドストエフスキー以外にも、文学はいろいろと読んできました。多くは、「いまどきの文学」ではなく、室生犀星(むろうさいせい)や、古くは鴨長明、泉鏡花や永井荷風、折口信夫のような昔の作家・学者です。青空文庫(著作権がなくなった小説などが読めるインターネットサービス)などで作品をダウンロードし、気ままに少しずつ読んでいます。
中でも私が好きなのは、太宰治と川端康成です。書店でも著作が手に入る有名な作家です。なぜこの2人なのか。それは、この2人はすごく文章がうまい上に、短編が多いからです。
はじめから上中下もあるような大長編はハードルが高い。ですから、短編を文庫本のなかの一話分(数ページの作品もあります)でいいので読んでみる。
何回か読むと「うまい人の書く文章はこんなにすごい!」ということがわかってきます。川端康成を3、4編も読むと、「はー、文豪と呼ばれる人の文はやっぱりうまい」と感嘆させられることしきりです。
特に古典の文章は声に出して音読するといいのですが、黙読しているだけでも、日本人のリズム・五七調で気持ちがいいですし、内容も今の論理の訴え方、理屈とはちょっと違うので新鮮です。一説によると、今は三段論法ですが、昔の日本は五段論法だったそうです。
また、旧仮名遣いの文などは2ページ読んだら疲れてしまいますが、一方で普段とは違う脳の部位がほぐされるように感じます。
文学の翻訳書も、誤訳があったり言葉遣いが古いとはいえ、たとえば森鷗外が明治時代に訳したゲーテの『ファウスト』は、現代の訳よりもずっと格調高い文章に感じたりします。内容は難しくてわからなくても、スッと入れるのです。
「現代訳のほうが読みやすくて内容も理解しやすいのはありがたいけれど、心に響くのは案外、森鷗外の『ファウスト』だ」という、面白いことにも気がつきます。
ドストエフスキーの訳も、時代が分かれるほどあるようですが、古いほうの訳がかえって心に迫ってくることもあります。言葉遣いや言い回しはわかりにくいかもしれませんが、心にフィットする感覚です。