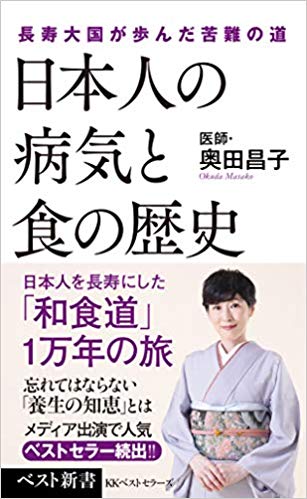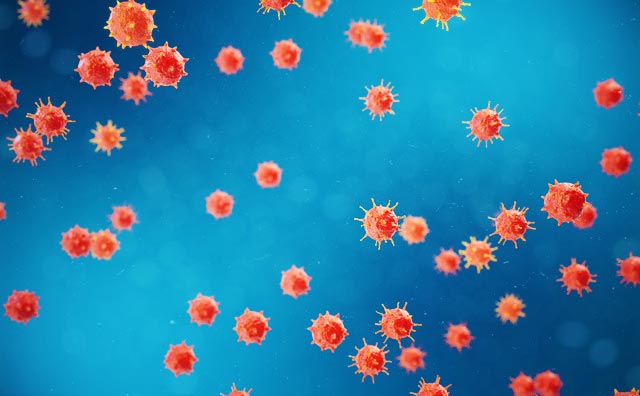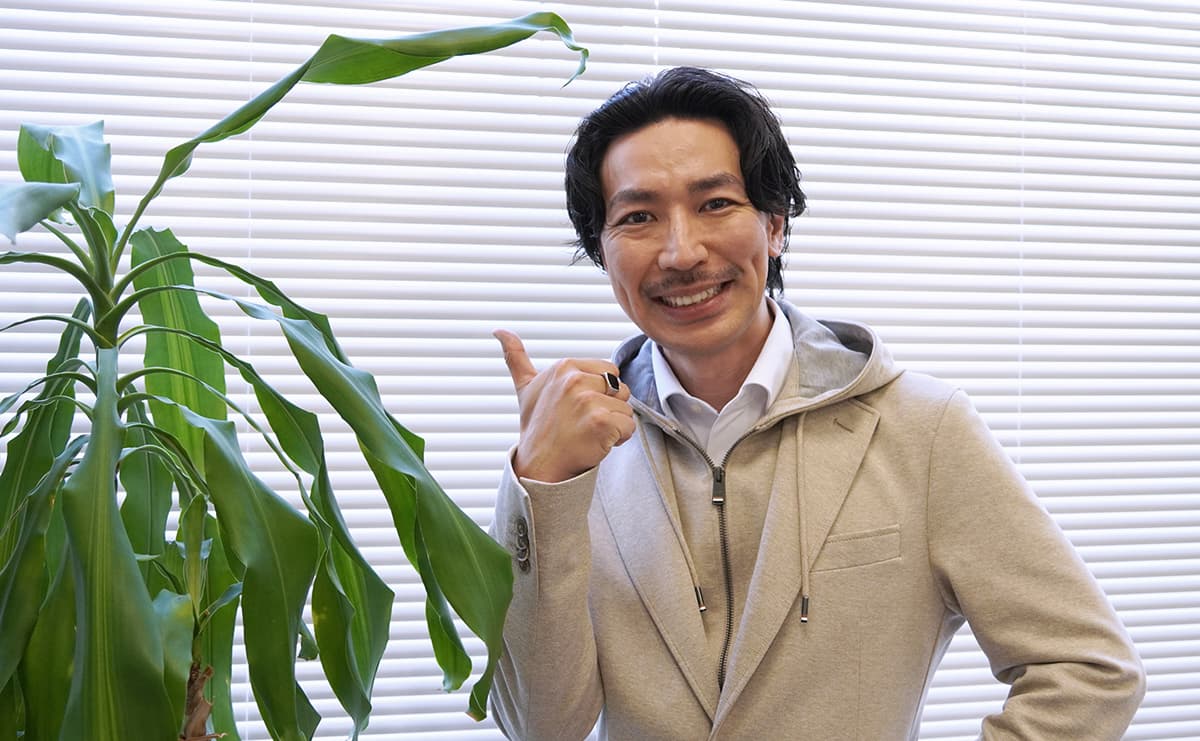奈良時代のパンデミック…「大陸からの感染症」に次々と倒れた藤原氏一族
2020年03月17日 公開 2024年12月16日 更新
次々と感染症に倒れた藤原氏
海外との交流が盛んになるにつれ、大陸の唐や新羅への遣唐使、遣新羅使(けんしらぎし)の一行が疫病を持ち帰ることが増えました。
奈良時代を中心とする100年間に疫病は約40回発生したとされ、735年に始まった天然痘の流行も、大陸からの人の移動にともなうものと考えられています。
このときは、中臣鎌足あらため藤原鎌足の子、藤原不比等と、その4人の息子が相次いで天然痘で死亡しました。
感染の拡大を食い止めようと、数百人規模の僧が宮中で読経し、ときの聖武天皇は大赦を行い、全国に国分寺、国分尼寺を設立し、さらには東大寺に大仏を建立するなど思いつく限りの手を打ちました。
それまで豪族が私的に信仰していた仏教は、奈良時代には国家仏教へと変化して、国が寺を建立し、天皇が国家の鎮護を願うようになっていた
のです。
全国で猛威をふるう天然痘だけでなく、限られた地域で発生する疫病もあり、湿地ではマラリア感染が頻繁に起こりました。マラリアは、奈良時代には瘧(おこり)と呼ばれ、大宝律令は重要な病気の一つに瘧をあげています。
マラリアというと熱帯の病気と思われがちですが、マラリア原虫に感染した蚊が湿地で繁殖するため、水田が広がる日本では昭和時代の終戦後までありふれた病気でした。
国内で最後までマラリア感染が残っていたのは、水路が発達した琵琶湖のほとりだったようです。
さらに、らい病、現代でいうハンセン病、フィラリア原虫による寄生虫症、結核、赤痢、腸チフス、急性胃腸炎などの感染症、脳卒中、脚気(かっけ)なども日常的に発生しました。
加持祈祷だけでなく、医療知識の集積始まった
これらの病気が相手では呪術も読経も効くはずがありません。とはいえ、当時も加持祈祷だけに頼っていたわけではなく、735年に始まった天然痘の大流行の際には、朝廷は医術にもとづく通達も出しています。
おなかと腰を温め、生ものを避けて粥や重湯を食べ、海藻ないし塩を口に含ませよ、などの指示が記されていました。
体を温かくして消化によいものを食べるのは体力をつけてウイルスを撃退するため、海藻や塩を口に含ませるのは、発熱が続いて汗を大量にかき、脱水になるのを防ぐためと考えられます。
どれも回復を促す効果が期待でき、取りうるなかでは最善の対処法といえそうです。
薬草を使った薬酒も作られるようになっていましたし、日本各地の物産、草木、伝説などを記載した風土記の編纂も進められ、病気の治療法と、各地に自生する薬草が数多く収録されました。
呪術医や僧の力にすがる一方で、その力が万能ではないことを痛感していたのでしょう。
756年に崩御した聖武天皇の遺物をおさめた東大寺の正倉院には、大陸や、遠くはインド原産の薬が約60種類伝えられており、一部は鑑真和上が持参したものではないかといわれています。
鑑真は聖武天皇の招きで苦難の末に来日し、仏教だけでなく医術、薬学を広めました。おそらくは、全国から選び抜かれた秀才たちが、病に打ち勝つ手がかりを求めて、鑑真が伝える最新の知識を熱心に学んだと思われます。