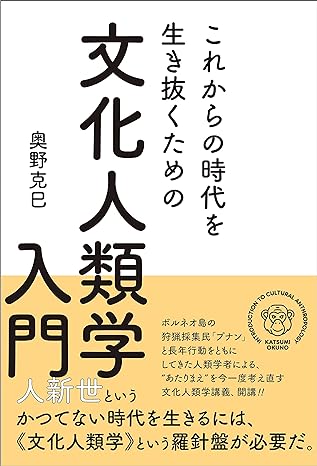Trans-womanであり性社会文化史研究者の三橋順子さんが明治大学文学部で12年にわたって担当する「ジェンダー論」講義は、毎年300人以上の学生が受講する人気授業になっています。その講義録をもとにした『これからの時代を生き抜くためのジェンダー&セクシュアリティ論入門』が刊行されました。
それを記念して、同じ「これからの時代を生き抜くための"入門"」シリーズの前巻である『これからの時代を生き抜くための文化人類学入門』著者の文化人類学者の奥野克巳さんとの対談がジュンク堂書店池袋本店にて行われました。
ジェンダー&セクシュアリティ論と文化人類学はどのように響き合うのか。今回は、その内容の一部抜粋してご紹介します。
前編となる今回は、カラダを通して学んでいくジェンダー論、お二人が海外に行って学んだこと、そして性別二元論ではない多元論の社会について話は広がっていきます。(構成:斎藤岬)
トランスジェンダーとしての経験がベースになっている
【奥野】この本は三橋さんが大学で教えられている大人気授業をまとめられたものだとうかがっています。本書を読んで私が感じたのは、ひとつには、三橋さんご自身のトランスウーマンとしてのご経験が、身体動作も含めてすごくベースになっている点です。
その意味において、「ジェンダー&セクシュアリティ論」というタイトルではありますが、いわゆる学問の中のジェンダーあるいはセクシュアリティ論とは一線を画するものになっているのではないでしょうか。
それからもうひとつは、医学や生理学の観点からのご説明がものすごく詳細だったことです。本書の中で、ご実家がお医者さんで子どもの頃からトイレに医学書などがあったと書いておられましたね。
それゆえにジェンダーあるいはセクシュアリティにアプローチされる際に社会現象として捉えるだけでなく、医学あるいは生理学の観点から人体の構造そのものを十分に踏まえられた上で全体の見通しを示されているところがとても印象に残りました。
そして3つ目は、最後の章ですね。この「これからの時代を生き抜く」シリーズは私の『これからの時代を生き抜くための文化人類学入門』を含めて今3冊出ていますが、どれも最後の章では自分自身の経験を語る形になっているんですね。
三橋さんはそこで「あまりそういうことは語りたくないんだけれど」と言いながらも非常に饒舌に語っておられる。
【三橋】(笑)
【奥野】そこが良かったです。最初に言ったような、ご自身の経験からジェンダー&セクシュアリティ論という学問領域にどうアプローチされているのかが最後の章で見えてきたと思いました。
ジェンダー論の教科書には身体のことが書かれていない
【三橋】ありがとうございます。私がジェンダー&セクシュアリティ論を大学で講義することになった経緯は「はじめに」に書いたんですが(※)、本当に不思議な成り行きで、日本のジェンダー論の中で私は全くの異端なんです。
そもそも私の世代ではそういった講座が大学になかった。私自身、もともと専攻していたのは日本古代史です。
だから講師の依頼があったときにも「ちゃんと勉強したことはないので、自分がトランスウーマンとして生きてきた経験を踏まえて、その視点からジェンダーやセクシュアリティをどう捉えるかという話でよろしければ」ということで引き受けました。
現在でも日本の大学ではジェンダー論はあってもセクシュアリティ論の講座はまだまだ少ないです。ジェンダー論の先生もジェンダーについては熱心に語って、セクシュアリティについては一切語らない先生が多い。
それに、学生からしてみるとやっぱり正統的なジェンダー論の講義は今ひとつつまらないんですね。こんなことを言うと叱られますけど(笑)。それでジェンダー論が嫌いになってしまったら逆効果ですから、せめて少しは面白がってくれるような話をしようというのはひとつの動機になっています。
2つ目の医学的な知識については、たまたま医者の家に生まれたものですから、トイレに日本医師会雑誌が積んであって、カラーページには症例写真や手術の写真が載っていました。
一般の人が見たらちょっとグロテスクなものだと思います。私の世代で男の子だと医者の家に生まれたら後を継ぐものだという固定観念の中で育って、自分でも「医者になるのは仕方ないかな」と思っていたんですが、あるとき父から「開業医にはなるな。本当は自分もなりたくなかったんだ」と言われたんですね。
だったら好きな歴史をやろうと思って高校3年生で文系に変わって、そこで医学とは縁が切れたと思っていました。
その後、日本では1990年代後半に性同一性障害という概念が入ってきて急速に広まります。それが自分自身がトランスジェンダーとして社会的に発言をし始めた時期と偶然重なったんですね。当事者として自分は何なのかという語りをする上で性同一性障害の知識が必要になって、勉強をし始めました。
それで1999年にGID(性同一性障害)研究会[現・GID学会]が初めて開かれたときに、交流があった先生に「三橋さん、コンパ要員としておいでよ」と呼ばれたんです。お酌をするのは仕事でやっていたからできるけど、どうせなら学会も聞こうと思って参加するようになりました。
その中であるとき、お医者さん以外の一般の人と自分では、人間の体の仕組みに対する基礎知識が全然違うことに気がつきました。研究会では血だらけの手術症例画像がスライドで出てくるわけです。
手術のとき、設計図のように体に線を引いて、その線にそってメスが入っていくと血が出てきて......という手順があったときに、何をしようとしているのか大体わかってしまう。それは子どもの頃に読んでいた医学会雑誌の影響なんですね。
講師を引き受けた後で先行するジェンダー論の講義のいろんな教科書を読んでみたら、身体のことがほとんど出てこないんです。これはとてもショックでした。私のジェンダー&セクシュアリティ論は身体の知識の上に成り立っています。ですから、奥野さんにその点を読み取っていただけたのはとても嬉しいです。
※2010年夏、都留文科大学にて後期のジェンダー論を担当予定だった先生が出講できなくなったことから、大学側が三橋さんに登壇を急遽依頼。そこで半年間の講義を受け持った。2011年、明治大学からも「ジェンダー論」講義のオファーが届き、現在に至っている。
【奥野】幼いときに医学関係のものを読んでいたところにまた戻ってきたんですね。
【三橋】そうです。私、本当は血を見るのが苦手で、長時間見ていると貧血を起こすんですよ。それもあって医者にならなかったのに、なんでまたこんなものを見せられてるんだろうと思いながらも、そこから逃げはしませんでした。
バングラデシュで仏僧になった理由
【奥野】なるほど。考えてみれば、私もそういうことはあります。小学校のときにピアノをやっていて、ピアノを習うのはどうでもよかったのですが、待合室に紀行写真集が置いてあったんです。
世界中のいろんな場所、たとえばラクダを引いているキャラバンの写真を見て「大きくなったらそんなところに行ってみたいな」と強く思っていました。そして結局、今やっているのは海外での人類学のフィールドワークです。その前には世界のいろんなところを放浪もしました。
【三橋】奥野さんの『これからの時代を生き抜くための文化人類学入門』を読んで、バングラデシュでお坊さんになられた話がすごく衝撃的でした。私より少し下の、まさに奥野さんくらいの世代は、青年時代に世界を放浪することが一種の流行りだったからそれ自体には驚かないんですが、「そこまで!?」と思いました。
【奥野】その前はタイにいて、日本から50万円くらい持っていったんですが、バンコクで遊びまくってお金がなくなったんです。それでバングラデシュでは仏教寺院に無料で泊めてもらっていたんですが、急性腸炎を起こして病院に担ぎ込まれました。
ところが点滴に不純物が入っていて、病状がさらに悪化したんです。結局JICAのお医者さんが来て治療してくださって命を取り留めました。
それで寺院に戻ったら「九死に一生を得たわけだし、せっかくだからお坊さんをやってみないか」と言われたんですね。大乗仏教の日本とは違って、上座部仏教は一生のうち1週間でもお坊さんになれば徳を積むことができるんです。
それで出家して1カ月半くらい修行して、托鉢をして回りながらいろいろ仏教経典を読んだことでその後仏教にも関心を持つようになりました。
【三橋】それでいうと、私が大学院生の頃、NHKで『シルクロード』(1980年)が放送された直後の時期に、自分のいた大学がシルクロードの学術調査団を組んだんです。
そう言いつつも実質はかなり観光的だったんですが、このときにチームの末席として参加しました。まだ個人や団体旅行ではシルクロード(西域)に入れない頃だったので、日本人としてはかなり早いうちにトルファンや敦煌(とんこう)に入っているんですよ。
その後、仏教とはまったく縁がないつもりだったんですが、バンコクで国際学会が開かれたときに、現地のサポート団体の代表がテレビなどで仏教を語る仕事をしている方で、お話をする機会がありました。それがきっかけで仏教とジェンダーの問題をあらためて考えるようになりました。
だから、自分から目的や連関性を持って学んだわけじゃないけれど、人生の中でたまたま勉強したり見聞したりする機会があったものが、60歳になる頃にやっとつながってきた結果がこの本なのかなと思っています。
性別二元論ではなく、多元論の世界
【奥野】これまでやってきたことの集大成、あるいは統合したような形でつくられているんですね。
【三橋】そうですね。自分としては終活の一環というイメージだったんですが、書いているとやっぱりまた別の疑問が浮かんで考え始めるんですよね。今回の本では載せられなかったんですが、世界のサードジェンダーについてもそのひとつです。
以前に出した『歴史の中の多様な「性」』(岩波書店)でアジアの性別越境文化について書いていて、中でも「インド『ヒジュラ』に学ぶサード・ジェンダー」という章は私なりの世界サードジェンダー巡りでした。
「男女」の二元論ではなく、3つ目4つ目の性、そういうジェンダーの区分がある社会が存在しますよね。奥野さんの『これからの時代を生き抜くための文化人類学入門』では5つの性がある事例が書かれていました。
私のサードジェンダー知識の原点になっているのは、40年以上ヒジュラを撮り続けている写真家の石川武志さんから聞いたお話や見せていただいた写真なんです。
その中で聞いた「ヒジュラは『お前は男か、女か』と聞かれると『私はヒジュラだ』と答える」という話が強く記憶に残っています。実際、アジア・太平洋のトランス当事者を集めた国際学会で、ヒジュラの「グル」(リーダー)にお会いしたこともあります。
同じく国際学会で、南太平洋のトンガ王国のファカレイティと呼ばれるサードジェンダーの方とお話をしたこともあります。近代化される以前のトンガでは、王様の右側には"政(まつりごと)"を行う大臣たちが座り、左側に"祭(まつりごと)"を司るファカレイティたちが座っていたそうです。
そういうふうに社会的役割を担っていたけれど、キリスト教徒が来て、ファカレイティはそうした場所から追い出されてしまった、と。ちょっと類型化されている部分もあるかと思いますが、その話はとても印象的でした。
欧米人や現代の日本人は男・女という二元論的な枠組みの概念を持っているけれど、実は三元論あるいは多元論的なアイデンティティを持つ人がいる社会が、南アジアや東南アジア、太平洋はインドネシアからポリネシアまで相当あちこちにあるわけです。
それに、アラスカからカナダ、アメリカ西部、中米メキシコ、南アメリカまでtwo-spirits(※)と呼ばれる人々の文化もあります。
どうやって拡がっていったのか証明はできないけれど、人類の拡散の過程、歴史のかなり早い段階からそうした文化が各地に伝わっていった。多元的なジェンダーを認める文化がかなり古くて普遍的なものであることは間違いないのではないかと考えています。
※アメリカ大陸の先住民コミュニティの中に古くから存在した性別越境者を指す。two-spiritsは男女両方の精神を持つという意。
【奥野】そうですね。ジェンダーに関する議論に文化人類学が資するとすれば、それは「性別は2つだけではない」ということが以前からいろんなところから報告されてきたということだと思います。
【三橋】ただ、そういう研究はあるし本も出ているけれど、文化人類学に限らず学問領域ではやはり二元論がどうしても強いですよね。私は自分のことをトランスジェンダーと言っていますが、ヒジュラが「私はヒジュラだ」と言うのと同じように、本音をいえばサードジェンダーでいいんじゃないかと考えています。
一方で、現代のインドでもヒジュラ・アイデンティティをトランスジェンダー・アイデンティティに読み替えるような社会的圧力があるそうです。
さきほど話に出たヒジュラのグルの方は私と同世代くらいで完全にヒジュラ・アイデンティティでしたが、10歳くらい下の人は「自分自身は、ヒジュラ・アイデンティティとトランスジェンダー・アイデンティティとでかなり揺れている」と言っていました。
この会話は10年近く前のことですが、日本でも私より上くらいの世代は「男か女か」と言われたら「私はニューハーフ」と答えていました。
「それでなんの問題もないでしょ」と開き直っていたわけですが、それをLGBT概念で読み替えるのはかなり厄介で難しいことであり、同時に「本当に読み替えていいのだろうか」という疑問が今もあります。
※後編に続く。
【三橋順子(みつはし・じゅんこ)】
1955年、埼玉県生まれ、Trans-woman。性社会文化史研究者。明治大学文学部非常勤講師。専門はジェンダー&セクシュアリティの歴史研究、とりわけ、性別越境、買売春(「赤線」)など。著書に『女装と日本人』(講談社現代新書)、『新宿「性なる街」の歴史地理』(朝日選書)、『歴史の中の多様な「性」―日本とアジア 変幻するセクシュアリティ』(岩波書店)がある。
【奥野克巳(おくの・かつみ)】
1962年、滋賀県生まれ。文化人類学者。立教大学異文化コミュニケーション学部教授。大学在学中から世界中を旅し商社勤務を経て、大学院で文化人類学を専攻。2006年からボルネオ島の狩猟民プナンのもとで定期的にフィールドワークを続けている。著作に『はじめての人類学』(講談社現代新書)、『これからの時代を生き抜くための文化人類学入門』(辰巳出版)などがある。