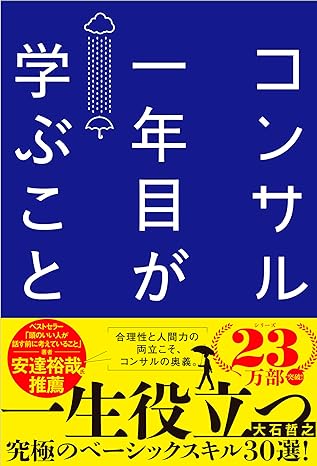無駄な労力をかけずに「上司の期待値を超える」仕事術
2024年05月28日 公開 2024年12月16日 更新

新入社員として仕事をするにあたり、重要になってくるのは「上司からの信頼を得ること」。上司から信頼されれば、次々にチャンスを与えられて成長の機会が増えていきます。そのためには、どのようなマインドが必要なのでしょうか?
※本稿は『コンサル一年目が学ぶこと』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)を一部抜粋・編集したものです。
上司の期待を超え続けていくには...
「ビジネスというのは、突き詰めると、相手の期待を、常に超え続けていくことにほかならない。顧客や消費者の期待を超え続けていくこと。上司の期待を超え続けていくこと」
このうち、若い人、特に一年目にとっては、最後の「上司の期待を超え続けていくこと」が重要になってくるかもしれません。言われたことを言われたように100%できて当然(それすらできない人が現実にはほとんどなのですが)。そこを少しでも超えていくように日々努力することで、ビジネスパーソンとしての成長は驚くほど早まります。
そこで、上司の期待を超え続けるための、仕事の基本中の基本について、お話ししましょう。
報連相の基本は、上司からの仕事の指示の内容を明確に把握すること
多くの会社で、新人が最初に言われることのひとつに、「報連相」というのがあると思います。「報告・連絡・相談」の略です。この報連相については、賛否両論があります。「報連相はビジネスの基本であり、しっかり行うべき」と考える人もいれば、「報連相を行ってもビジネスの成果にはつながらない」としてとりやめている会社もあります。
わたしの考えでは、単なる情報共有のためだけの報連相は無駄です。なんでも報連相したところで、上司も煩わしいだけです。
報連相の本当の目的は、上司と部下が仕事の目的と内容について、「共通の理解を得る」ことです。そこで、ここでは、報連相の背景となるそもそもの基本として、仕事を受けるとき、いったい何を上司に確認すればいいのかのポイントについて挙げておきます。部下が上司から仕事を受けるときに確認すべきポイントは、次の4つです。
①その仕事の背景や目的
②具体的な仕事の成果イメージ
③クオリティ
④優先順位・緊急度
この4点をしっかり確認すれば、上司の期待値を把握したことになり、どのようにすれば上司の期待に沿う仕事ができるかが明確になります。順に説明していきましょう。
その仕事の背景と目的を確認する
まず、その仕事にある背景や目的について、あらためて確認します。たとえ単発の仕事の依頼であっても、きちんと確認してください。上司のなかには、面倒なのでいちいち言葉にするのを避ける人もいるかもしれませんが、確認しておいたほうが、あとあとズレがなくなります。
たとえば調べものの依頼の場合、調べたけれどずばり見つけたいものが見当たらない場合も想定されます。そんなときも、もしも目的や背景を事前に聞いていれば、その目的を満たすような別の調査結果や事例を提示できるかもしれません。
期待される成果物のイメージを明確にする
多くの仕事の指示は曖昧です。だからこそ、上司が求めているものが何なのか、成果物のイメージレベルまできっちり聞き出しておくことができれば、それだけで仕事は成功に近づきます。
たとえば、「A社の新サービスだけれども、まずはざっくり調べておいて」といった指示があったとしましょう。かなり曖昧な指示です。これに対して、「はい、ざっくりやっておきます」と答えるのは最悪です。
「ざっくり」のレベル感が合わなかったら、おそらく、あとで怒られるうえに、作業に後戻りも発生してしまいます。かといって、「ざっくりってなんですか? もっと指示を明確にしてもらわないとできません」というのも、これもまた最悪です。単なる受け身で、問題解決の力がない人だと思われてしまうでしょう。
相手の指示の曖昧な部分を補い、こういうことではないかという自分なりの仮説を立ててコミュニケーションをとる、これが正解です。
たとえば、「ざっくりというのは、わたしなりに、①おもなターゲット、②サービスの特徴と競合との差別化要因、③価格体系、④提供体制、その4つくらいだと思っていますが、それぞれ資料1枚、合計5枚ぐらいでまとめればいいでしょうか」といった具合です。
それぞれ資料「1枚」、表紙も含めて、計「5枚」のように、数字で示すことも重要です。成果がイメージできるよいコミュニケーションとなります。
相手が求めるクオリティ(期待値)を、質問によって推し量る
「クオリティ」は、期待値にもっとも関係してくる部分です。相手は、どのくらいのクオリティのものを求めているのか? 先ほどのコミュニケーションでは、それぞれの点について、資料1枚と言っています。資料1枚というのは、本当にざっくりとした概要を伝えるといったレベルです。
ここで上司が、「いや、それぞれ3、4枚にはなるんじゃないか」と答えたとしたら、ざっくりと言いながらも、それなりに細部までしっかり調べてくることを期待していることがわかります。
項目数を尋ねてみるのもいいでしょう。4つでいいのか、それとも10項目にわたって、詳細に調べるのか。それによって、相手が求めるレベルがわかります。
さらに、資料の作成目的によっても、レベル感は推し量られます。顧客に提出する資料などに盛り込むような正確さが要求されるものなのか、それとも社内会議のための資料なのか、はたまた、上司の頭の中に参考としてインプットするためのものなのか。それぞれで達成すべきクオリティのレベルは違います。
スピード感についても、時間をかけても100%正確につくるべきものなのか、それとも、明日の会議で使うから期限のほうが大事なのか、そこからも期待されるレベル感がわかります。
3日の100点を求めているのか、3時間の60点を求めているのか。事前にしっかり確認しなければ、上司の期待を満たすことはできません。そうして期待値を把握したうえで、その期待以上の成果物をもっていくのです。期限を優先している場合は、当然何があっても、時間厳守です。
優先順位と緊急度を把握する
いま、最後にお話ししたスピード感、すなわち、優先順位、緊急度を把握することは、相手の期待に沿うという意味で、とても大事なことです。たとえば、緊急度が高く、絶対に明日までにほしい資料があったとします。そういう場合は、間に合うことがもっとも大事なことです。その場合、締め切りをすぎて100%の完成度の資料をもっていっても、なんの役にも立ちません。
いつまでに必要なのか。1日か、3日か、1週間か。それとも、手が空いたらできればやってほしいくらいなのか。また、その締め切りは絶対なのか、もし締め切りを過ぎたら用をなさなくなるものなのか。それとも締め切りは、あくまで完了してほしい目安を意味しているのか。
さらには、別に命じられている仕事や自分のルーティンの仕事がある場合、どちらを優先させるべきかを確認することも重要でしょう。特に、命令系統が複数にまたがっていて、別の人からも緊急の要件を依頼されている場合など、自分では判断できませんから、上司同士で話し合ってもらう必要が出てきます。そういう場合の優先度は、新人の場合、自分で判断しないことが重要です。
指示を出す側、受ける側双方が、共通認識をもち、期待値を明確にする
以上の4つの項目を確認し、曖昧な部分があれば、お互いに明確にし、共通の認識をもつこと。これが、期待値を把握するということであり、別の言い方をすれば期待値を「マネジメントする」ということです。
これは、部下の側だけではなく、仕事を依頼する上司の側から見ても重要です。部下が時間をかけて仕事をした結果、役に立たないものをもってくる、そんなリスクを避けるためにも、この4項目をふまえた明快な指示を出してください。
新人のときから上司との間でこれができるように経験を積んでいけば、社外の人を相手にしたときも、同じようにできるようになります。ただし、クライアントは、上司とは違って、いちいち明確には言ってくれない、もしくはそもそも明確になっていないこともあります。こちらからコミュニケーションをリードして、確認をとる必要があります。
この「期待値のマネジメント」は、コンサルタントや営業職だけに求められる能力のように聞こえるかもしれませんが、技術サービス、カスタマーサービスといった直接顧客と接する仕事はもちろんのこと、総務・経理・秘書・アシスタントなど、社内向けの部署に勤めるすべての人にとって重要な基本です。
すべての仕事には、なんらかの相手が存在します。その相手の期待値を把握して、それに常に応えて、ときに上回るようにしていくこと。これによって、あなたの評価は着実に高まります。そして、期待値が把握できれば、無駄な労力をかけずに相手が満足する仕事ができるようになりますので、結果的に仕事の効率も上がっていきます。