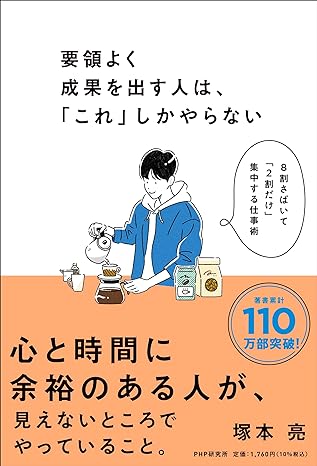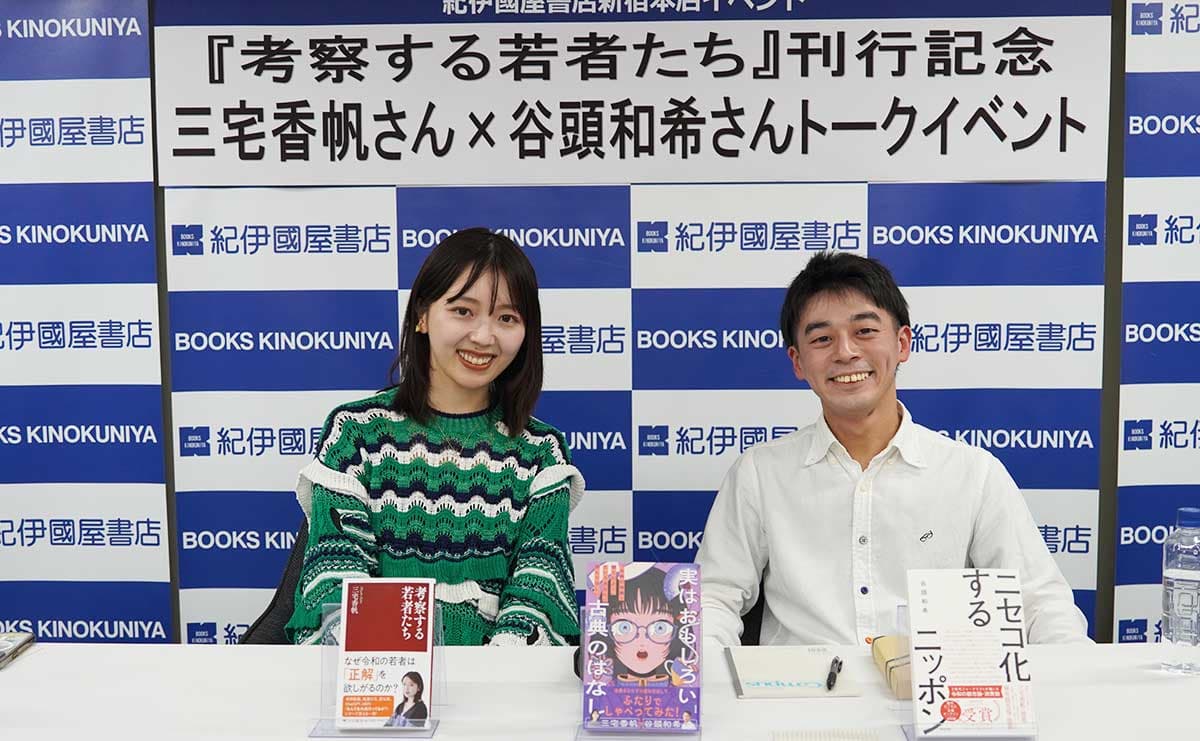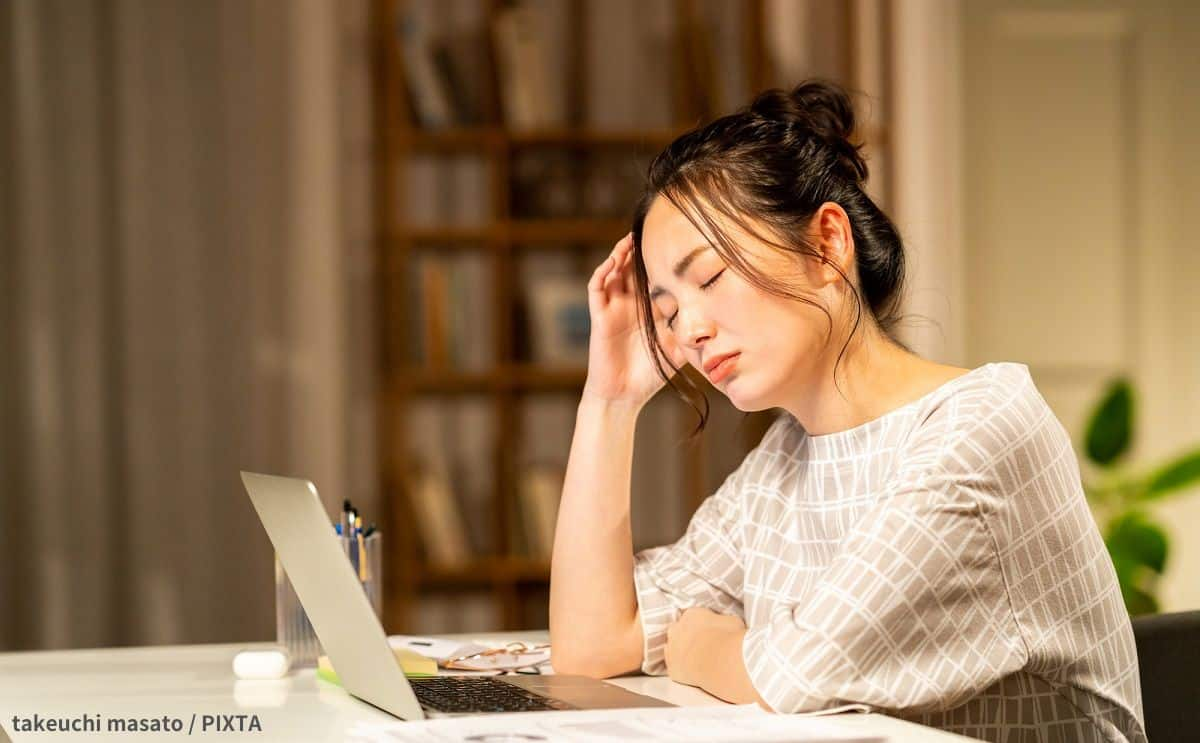「ミスを繰り返す人」と「一度で学習する人」の違いを生む1つの習慣
2024年06月13日 公開 2024年12月16日 更新

次こそはミスなく終わらせよう、と思っても過ちを繰り返してしまう...。その原因はどこにあるのでしょうか? 要領のいい人が失敗を繰り返さないわけを、 塚本亮さんが解説します。
※本稿は塚本亮著『要領よく成果を出す人は、「これ」しかやらない(PHP研究所)より、一部を抜粋編集したものです。
要領のいい人は、なぜ同じ過ちを繰り返さないのか?
ミスや失敗は、誰もが通る道です。ただしそこで、要領のいい人は、同じ過ちを繰り返しません。過ちを繰り返す人と一度で学習する人は、いったい何が違うのでしょうか?
・「経験学習モデル」の4ステップ
「経験学習モデル」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。このモデルは、心理学者デイビッド・コルブによって提唱され、彼の「経験学習の理論」(1984年)で詳述されました。
経験学習モデルは、学習のプロセスが実際の経験を通じて行われるという考え方に基づいています。現代のように環境の変化が激しい時代では、日々の経験から学び、それを自分の知識やスキルとして統合することが重要です。経験学習サイクルは、経験したことをノウハウに変え、成長していくために欠かせないプロセスと言えるでしょう。
このサイクルを理解し、実践することで、絶えず変化する環境のなかでも適応し、成長を続けることが可能になります。経験学習モデルは、具体的な経験から学び、成長するプロセスを示します。
このモデルでは以下の4つのステップが重要です。
①経験:実際の経験を行う
②内省:行動の振り返りとフィードバック。経験を内省し、分析するプロセスです。これはビジネスにおける「振り返り」とも呼ばれ、「リフレクション」としての重要な要素を持ちます。ここで重要なのは、経験から学び取ろうという意欲です。
③教訓:経験を多面的に捉え、教訓にする。振り返りを通じて、「これは成功した(または失敗した)。次はこうするべき」という仮説を立てます。このステップでコツやノウハウとしての教訓が生まれます。
④実践:行動を修正し、挑戦する。教訓を実際の職場で実践し、新たな経験を得るプロセスです。これにより、次の経験学習サイクルに進むための基盤が形成されます。
要領のいい人は、経験をした直後に振り返りを行うことで、その経験から学ぶことができます。このアプローチは、新鮮な記憶を活用し、具体的で有意義な教訓を引き出すのに効果的です。
彼・彼女らは経験した出来事に対して深く考え、自分の行動や結果に対して責任を持ちます。このプロセスを通じて、彼らは繰り返し同じミスを避け、継続的な改善と成長を遂げることができます。
・学んだことは「すぐ」復習しよう
忘却曲線について、多くの人がその存在を知っていることでしょう。忘却曲線は、ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスによって提唱されたもので、時間の経過とともに学習した情報がどのように忘れられていくかを表す曲線です。
エビングハウスの研究によれば、情報を学んだ直後は記憶が鮮明ですが、時間が経過するにつれて忘れやすくなります。特に学んでから20分後には約42%の情報が忘れられ、24時間後には約70%が忘れ去られるとされています。
ただし、これはあくまで平均的な傾向であり、個人差や内容などによって忘れる速度は異なります。したがって、時間が経過すればするほど忘れるのは自然なことなので、なるべく早期に振り返りを行わないと振り返りの効果が薄くなると言えます。
多くの人は、経験から直ちに学ぶことを怠ります。行動の結果をしっかりと振り返ることなく、次のタスクに移行してしまうのです。これにより、彼らは同じ過ちを繰り返す傾向にあり、成長の機会を逃してしまいます。彼らは経験から学ぶことがないため、根本的な問題の解決に至らず、同じ問題に何度も直面することになります。
要領のいい人と要領の悪い人の大きな違いは、振り返りと学びのプロセスにおいて顕著に表れます。経験をただ経験として受け止めるのではなく、それを自己成長の機会として活かすかどうかが、成果につながる鍵となるのです。
ニーズとズレないための「聞く力」
いくら一生懸命に仕事をしたところで、顧客や取引先、上司の求めているアウトプットとずれていれば、成果にはつながりにくいでしょう。思い込みで仕事を進めると、労力の割にリターンが小さくなってしまいます─。
・すべては「聞く」ことから始まる
ピーター・ドラッカーは『創造する経営者』(ダイヤモンド社)のなかで、次のように述べています。顧客と市場を知っているのはただ一人、顧客本人である。これは、相手が何を求めているのかは、相手自身しか知らない、ということを示しています。
たまに、打ち合わせなどで自分の話ばかりに集中している人がいます。こうした人は、相手が何を求めているのかを聞き出すチャンスを逃してしまいます。その結果、自分なりの解釈で仕事に取り組み、がむしゃらにがんばっても、成果につながらないことが多いでしょう。
成果が出ないのは、努力が足りないからではなく、相手のことを理解できていないために、努力の方向性が間違っていたことが原因です。
要領よく仕事をするには、相手の要望や意向を正確に理解することが欠かせません。要領のいい人は、総じて聞き上手です。相手の話をしっかりと聞き、的確な質問を通じて相手の課題を見つけ出します。これにより、適切な解決策を提供することが可能になるのです。
私自身、以前は聞くことの重要性を理解していませんでした。話し方や伝え方に関する本をたくさん読んでいましたが、それだけでは十分ではありませんでした。なぜならば、それらはすべて「一方通行のコミュニケーション」だからです。
昨今は、「伝え方」にばかりフォーカスされがちですが、コミュニケーションはむしろ、「聞く」ほうが大切なのではないでしょうか。相手の話を「聞く」から始め、それから「話す」。そうすれば、相手が求めている内容とずれずに済むでしょう。これは、私が話し方教室に通った際に、気づいた学びです。
・本当の「聞き上手」とは何か?
そもそも、「聞き上手」とは、いったいどんなことを意味するのでしょうか。それは、相手の意図を理解し、ニーズを把握することです。そのうえで、相手の抱える問題に対して解決策を伝えることができれば、言うことはありません。
ただし、聞くことは簡単なようでいて、案外難しいものです。自分が何かを伝えようとしている際に、相手の話を途中で遮さえぎったことなどはありませんか?
これでは、相手が不快になるだけでなく、意見を伝える機会を失ってしまいます。相手の本当の意図や気持ちを理解することは、ますます難しくなるでしょう。
また、一方的な営業トークも、聞く側にとっては疲れるものです。それだけでなく、営業を受ける側は、「本当に、私たちに必要な商品を紹介してくれるのかな?」と不安になるでしょう。
では、どうすれば聞き上手になることができるのでしょうか。
基本的なことですが、相手から求められるまで、基本的には「自分の話をしない」ことです。もちろん、自分から胸きよう襟きんを開くことで、相手との距離を詰めることも大切ですが、緊張して余計なことを言ったり、つい自分のほうが話しすぎることはあるものです。
目的は、相手のニーズを把握することなのですから、まずは相手に「この人は話をちゃんと聞いてくれる」と感じさせることが大切です。そうすることで、相手は心を開き、より深い話をしてくれるようになります。
相手が話しているときは、共感する姿勢を示してください。相手の目を見て相づちを打ち、会話にリズムをつけることで、相手が話しやすい雰囲気をつくるよう心がけてください。そうすると、より相手はあなたに心を開きやすくなります。人は自分の話に関心を持ってくれたり、共感してくれる人に心地よさを感じます。
相手が話し終わったら、「ありがとうございます。お話、よくわかりました」などと、相手が伝えようとしている内容をきちんと理解したという意志を示しましょう。そのうえで、より深く理解をするために、「なぜ、〇〇されているのですか?」「なかでも一番改善したいポイントはどこでしょうか?」といった質問を投げかけることで、相手のニーズをより深掘りできます。
もし、相手の伝えたいことがよくわからないようであれば、「〇〇ということでしょうか?」というふうに、あなたなりに相手の話を要約してみてください。理解の通りであれば、問題ありませんし、仮に違っていたとしても、相手は訂正してくれます。
よく、「自分の解釈が間違っていて、相手から話が通じない人だと思われたらどうしよう」と考えて確認を怠る人がいますが、むしろ、ここでわかったフリをして確認しないことのほうが問題です。
後日、相手と擦り合わせをするほうが、余計な手間となるので、要領のいい人は、必ずその場で確認します。ともあれ、聞き方を磨くことで、良好な関係を築くことが容易になり、小さな疑問や質問もしやすくなります。相手も遠慮なく要望を伝えやすくなるため、有益な関係が形成されます。