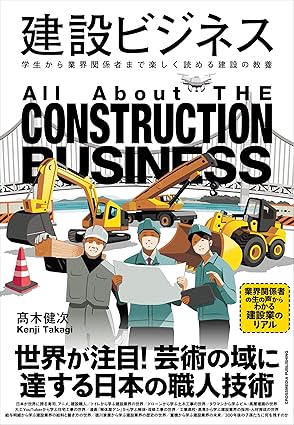もともと少ない大工がさらに減っている...目前に迫る「家を直せない未来」
2025年02月21日 公開

近年問題視されている「大工不足」。それに伴って、「経営の安定を図るために住宅以外の仕事を請ける」大工工務店が全国的に増加しているという。クラフトバンク総研所長の髙木健次氏の書籍『建設ビジネス』より、記事前半は大工不足について、後半は建設業関係者や業界へ就職を考える人などのSNSとの向き合い方について考える。
※本稿は、髙木健次著『建設ビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)を一部抜粋・編集したものです。
もともと少ない大工がさらに減っている
昨今、「大工不足」がメディアで取り上げられることが増えました。クラフトバンクのもとにも「大工が探せない」という問い合わせは多いです。
建設投資で最も多いのは土木を中心とした公共工事、次いで、倉庫・ビルなどの非住宅工事です。住宅工事の投資額は建設投資全体の3番目です。
当然、担い手である大工の数も多くありません。国勢調査で建設業就業者の構成を見ても、最も多いのは土木工事の技能者で、次いで電気工事、大工は3番目です。しかも、直近10年で最も数が減っているのが大工と左官です。「もともと少ない大工がさらに減っている」のです。
大工・左官は電気や土木などの他工種と比べ、一人親方や家族経営の小さな会社が多く、発注者に対する価格交渉力が他工種より弱いです。そのため、他工種よりも利益を確保しにくく、数を減らしているのです。
野村総研の予測では、人口減少に伴い、新設住宅着工戸数は減っていきますが、それ以上に大工の減少するスピードの方が速い、とされています。かつ、ただでさえ少ない大工が住宅の仕事を請けなくなっています。
「経営と社員の待遇を安定させるために住宅以外の仕事を請ける」大工工務店が全国的に増加しています。工務店からするとインバウンド需要を見越した店舗やホテルのリノベーションなどを手掛けた方が経営は安定するのです。
また、工務店は人口が減る町よりも、半導体工場の新設などが盛り上がる町の工事を優先するので、大工不足は過疎地から進みます。
工務店の経営の視点に立つと、公共工事や非住宅工事はお金の出し手が国、自治体、企業なので、資材価格や人件費が上がる中、相対的に価格転嫁の交渉をしやすい相手です。
他方、戸建て住宅はお金の出し手が個人です。「資材価格や人件費も上がっているので、住宅価格を上げます。たくさんローンを組んでください」と個人客に提案することは困難です。実質賃金がなかなか上がらない中、工務店は個人客を相手にしにくいのです。
そのため、私は「これから新築戸建注文住宅は富裕層のぜいたく品になり、中古物件の活用がポイントになる」と予測しています。
また、災害後の住宅復旧は地方中心に遅れるリスクがあり、広域で大工を確保していく体制と、大工不足に適応したテクノロジーが求められます。国が大工や大工育成機関を保護する取り組みも必要と私は考えます。
未だに電話帳が現役の業界
電話帳を令和の今、上場企業が使っている、と聞くと驚かれることでしょう。
「新規エリアに支店を出店した。その際に発注先の大工を探したが、探す手段がなく、電話帳で一件ずつ電話をかけるしかなかった」
上場ハウスメーカーの方の話です。ハウスメーカーで大工を直接雇用していない場合、発注先の企業(一次請け)を探すことになります。建設業界、特に中小企業の場合、ホームページを持たない会社も多いため、発注先を探す手段は未だに「人の紹介」(ツテ)が中心です。
ハウスメーカーがツテのない地域に出店した場合、大工などの発注先を探す手段は少なく、最悪の場合は「電話帳」になります。
しかも大工が住宅の仕事を断るケースも増えているため、電話しても仕事を断られ、結局、工事を断念する、そんな事態が起こるのです。私が勤務するクラフトバンク株式会社のマッチング事業は、この業界課題を解決するために行っています。
「建設業界はやめておけ」というSNSの声と向き合う
SNS上では建設業の魅力を発信するインフルエンサーと、「元施工管理だが長時間残業で心を病んだ。建設業界はやめておけ」という声が混在しています。私もYouTuberとコラボして情報発信する立場なので、私なりのSNSとの向き合い方をまとめます。
① SNSは「ネガティブ」から拡散する
「倒産増」などのネガティブなタイトルの動画の方が再生数は伸びます。意外と「人材採用」「成功事例」の動画は再生数が伸びません。そのため実態以上に悲観的なイメージが拡散します。特に社会人経験のない学生は、強くその影響を受けます。
また、私のようにデータや法令、取材に基づいて「理屈と事実で」説明する動画よりも、「自分はこれだけ苦しんだ」などの個人的エピソードの動画の方が共感を集めやすく、拡散します。人間は「繰り返し見聞きした情報を(本当かどうか別にして)真実と思い込んでしまう」傾向があると心理学の研究でわかっています。SNSで繰り返される言葉が認知をゆがめてしまうのです。
② 業界構造を正確に理解する
「残業が多いから建設業界はやめておけ」と発信されている方の内容をよく見ると、残業時間の長い施工管理の問題を指摘しています。「職人さんは(施工管理の自分を)心配してくれたので、悪いイメージはない」という発言もあります。施工管理と職人の役割、働き方、また職種(電気、解体など)や現場(住宅、非住宅など)の違いが一般視聴者にはわかりにくいため、混乱を招いています。
③業界よりも会社と経営者を見る
統計を見ると建設会社の業績は今、二極化しています。地方でも対前年比1.5倍で売上が伸びるなど、大きく成長する会社もあります。そういう会社は大抵、経営者が優秀で情熱と信念を持っています。他方で「法律を守らないことが競争力」などと発言するコンプライアンス意識皆無の経営者もいます。
また、大手ゼネコン各社では経営層の意識はかなり変わったものの、現場所長の対応には個人差があると言われています。そのため、かかわった会社、現場の「ガチャ」によって業界に対する印象が大きく変わるのです。「はずれ」を引かないための知識を身に付けましょう。
もちろん、長時間残業やセクハラ、パワハラで苦しんでいる方がいるのは事実なので、建設業界はその被害者がネット上で声を上げていることに向き合わなくてはなりません。「1人の経験」が拡散され、「アンチ」を生む怖さを認識しましょう。
【髙木健次(たかぎ・けんじ)】
クラフトバンク総研所長/認定事業再生士(CTP)。1985年生まれ。京都大学在学中に塗装業の家業の倒産を経験。その後、事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。その後、内装工事会社に端を発するスタートアップであるクラフトバンク株式会社に入社。2019年、建設会社の経営者向けに経営に役立つデータ、事例などを発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、業界団体等での講演、建設会社のコンサルティングなどに従事。
【クラフトバンク総研】https://corp.craft-bank.com/cb-souken
【X】https://x.com/TKG_CraftBank