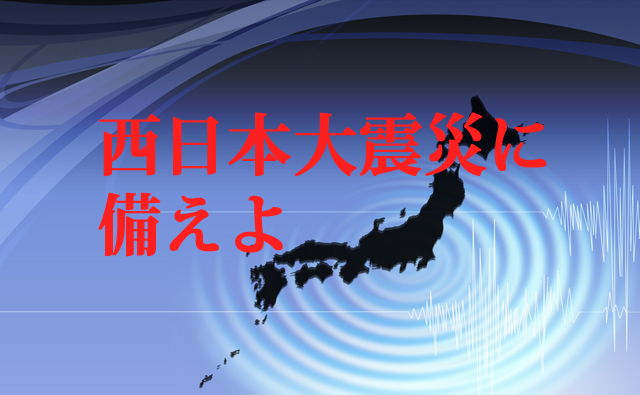死の淵を見た男 - 吉田所長が語る福島原発事故の真実
2012年11月27日 公開 2024年12月16日 更新

2011年3月11日、福島第一原発事故。暴走する原子炉を前にして、人は何を思い、どう行動したのか…。
本書は、吉田昌郎(福島第一原子力発電所所長:事故当時、以下同じ)へのロングインタビューを中心に、菅直人(総理大臣)、班目春樹(原子力安全委員会委員長)をはじめとした東電関係者、自衛隊、地元の人間など、90名以上の証言をもとに記した、渾身のノンフィクション。驚愕の真実が、今、明かされる!
吉田昌郎と福島第一原発の五〇〇日』
私には、東日本を襲った大地震と津波によって起きた福島第一原発事故で、どうしても知りたいことがあった。
福島県に、いや東北地方全体に、未曾有の悲劇をもたらしたこの事故の影響は、震災から1年半が経過した現在でもつづいている。この状態がいつ終息を迎えるのか、予測もつかない。
人々は不安と怒りの中にいる。故郷を離れて“疎開”を余儀なくされ、あるいは仮設住宅や借り上げアパートに住まざるを得ない人々の苦しみは、通りいっぺんの表現で表わすことはできない。すべての思いを呑み込んで故郷を捨てた人も少なくない。
事故を起こした東京電力は震災から1年3か月後、実質、国有化された。もはや、一民間企業として被害を受けた人々への膨大な補償をまかなうことは不可能だった。日本を代表する最大の電力会社は消え、新しい会社となったのである。
しかし、この一連の流れの中で、私は、「あること」がどうしても知りたかった。
それは、考えられうる最悪の事態の中で、現場がどう動き、何を感じ、とう闘ったのかという人としての「姿」である。
全電源喪失、注水不能、放射線量増加、そして水素爆発……あの時、刻々と伝えられた情報は、あまりに絶望的なものだった。冷却機能を失い、原子炉がまさに暴れ狂おうとする中、これに対処するために多くの人間が現場に踏みとどまった。
そこには、消防ポンプによる水の注入をおこない、そして、放射能汚染された原子炉建屋に何度も突入し、“手動”で弁を開けようとした人たちがいた。
伝えられる数少ない断片的な情報でも、現場で最後まで奮闘した人たちかいたことが、私たち国民にはわかった。電気が落ちた暗闇の中で闘う人間の姿は、私たちの想像を超えるものだった。東電の社員、協力企業の人々、さらには命を賭けてやって来た自衛隊員 …… 多くの人間が、放射能汚染の真っ只中で踏ん張ったことを、私たちはおぼろげながら知っていた。
しかし、その「現場」の真実は、なかなか明らかにならなかった。民間、東電、国会、政府 …… さまざまな事故調査委貝会の報告書が出そろっても、現場で闘った人間の実態は、わからなかった。
私は、事故直後から東電本体はもちろん、関係各機関や地元にもアプローチをつづけ、なんとかその実態に迫ろうとした。だが、厚い壁に何度も跳ね返された。
断続的に取材をつつける私の前に、漠然とではあったが、次第にその姿が輪郭を表わし始めたのは、年が明けて2012年になってからてある。
それは、当初予感した通り、やはり想像を絶するものだった。
極限の場面では、人間は、強さと弱さを両方、曝け出す。日頃は目立たない人が土壇場で驚くような力を発揮したり、逆に普段は立派なことを口にする人間が、いざという時に情けない姿を露呈したりする。
ぎりぎりの場面では、人間とは、もともと持ったその人の“素の姿”が剥き出しになるものである。
時間が経過するにつれ、私の前にだんだんその現場の真実の一部が垣間見えるようになっていった。福島第一原発所長として、最前線で指揮を執った吉田昌郎 〈まさお〉 氏に私がやっと会うことができたのは、事故から1年3か月が経過した時だった。
「もう駄目かと何度も思いました。私たちの置かれた状況は、飛行機のコックピットで、計器もすべて見えなくなり、油圧も何もかも失った中で機体を着陸させようとしているようなものでした。現場で命を賭けて頑張った部下たちに、ただ頭が下がります」
吉田氏は、私にそう語った。癌に倒れ、手術を経た吉田氏は、げっそりと痩せ、事故当時の姿とはすっかり面変わりしていた。
病いを押して都合2回、4時間半にわたって私のインタビユーに応えてくれた吉田氏は、2012年7月26日、3回目の取材の前に、凄まじいストレスや闘病生活でぼろぼろになっていた脳の血管から出血を起こし、ふたたび入院と手術を余儀なくされた。
吉田氏をはじめ、私は多くの現場の人間にインタビューを繰り返した。証言してくれた東電や協力企業、あるいは、自衛隊、政治家、科学者、地元の人々など、関係者の数は、いつの間にか90名を超えていた。
あの事故の時、福島第一原発の1号機から6号機までの原子炉建屋に隣接した中央制御室には、それぞれの当直長と運転員たちがいた。
放射線を測定する線量計が高い数値を検知し、無機質で、甲高い警告音が響く中、それでも彼らは突入を繰り返した。電気が失われた現場では、あらゆる手段が“人力”に頼るほかなかったからである。
生と死をかけたこの闘いに身を投じたのは、多くが地元・福島に生まれ育った人たちだったことを私は知った。恐ろしいほどの危機的状況に息を呑みながら、私は、漆黒の闇の中、闘いつづける人たちの姿を想像した。
あの福島第一原発は、太平洋戦争末期、陸軍の航空訓練基地だった「磐城陸軍飛行場」の跡地に立った発電所である。
震災が起こった2011年3月11日、私は特攻や玉砕という悲劇の中で、若者が次々と命を落とす姿を証言で描いたノンフィクション作品『太平洋戦争 最後の証言』(小学館)の第一部「零戦・特攻編」を執筆中だった。
大量の戦争資料に囲まれていた私は、そのため、福島第一原発がどういう地に立った発電所であるか、偶然、知っていた。
明日の見えない太平洋戦争末期、飛行技術の習得や特攻訓練の厳しい現場となった跡地に立つ原子力発電所で起こった悲劇 ―― 絶望と暗闇の中で原子炉建屋のすぐ隣の中央制御室にとどまった男たちの姿を想像した時、私は「運命」という言葉を思い浮かべた。
戦時中と変わらぬ、いや、ある意味では、それ以上の過酷な状況下で、退くことを拒否した男たちの闘いはいつ果てるともなくつづいた。自らの命が危うい中、なぜ彼らは踏みとどまり、そして、暗闇に向かって何度も突入しえたのか。
彼らは、死の淵に立っていた。
それは、自らの「死の淵」であったと同時に、国家と郷里福島の「死の淵」でもあった。そんな事態に直面した時、人は何を思い、どう行動するのか。
力及ばず大きな放射能被害が生じた。しかし土壇場で、原子炉格納容器爆発による放射能飛散という最悪の事態は回避された。
本書は、原発の是非を問うものではない。あえて原発に賛成か、反対か、といった肯非論には踏み込まない。なぜなら、原発に「賛成」か「反対」か、というイデオロギーからの視点では、彼らが死を賭して闘った「人として」の意味が、逆に見えにくくなるからである。
私はあの時、ただ何が起き、現場が何を思い、どう闘ったか、その事実だけを描きたいと思う。原発に反対の人にも、逆に賛成の人にも、あの巨大震災と大津波の中で、「何があったのか」を是非、知っていただきたいと思う。
本記事は門田隆将著『死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発の五〇〇日』まえがきより、抜粋編集したものです。