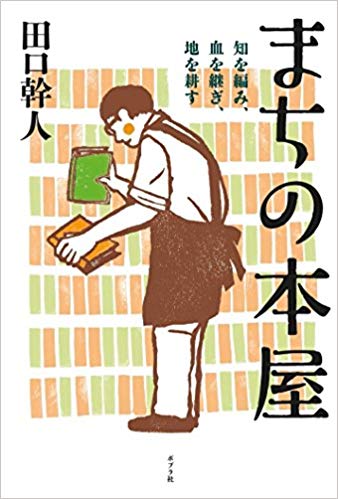本が売れない時代の「まちの本屋」の生き残り方
2018年08月31日 公開 2024年12月16日 更新

<<ネット書店の台頭、市場の縮小、「書店空白地域」の急増──。この時代における、リアルな本屋の存在価値とは?「まちの本屋」の活路はどこにあるのか? 全国から熱視線を集める盛岡の書店が実践していることとは。>>
同じ本でも、土地によって売り方は変わってくる
本を置けば売れた時代がありました。工夫をすることで、さらに売り上げを伸ばすことができました。
現在は、手をかけても、成果を得られるまでに要する時間と労力が、売り上げと釣り合わないところまできています。
まさに冬の時代と言えるかもしれません。要因は一つではなく、いろいろな要素が複雑に入り乱れ、簡単に解きほぐすことはできません。
業界全体で取り組まなければいけない問題。それぞれの地域で取り組まなければいけない問題。会社単位で取り組まなければいけない問題。そして、書店員一人一人が取り組まなければいけない問題。
冬の時代の向こうに、また春がやってくることを信じている人たちが結集して、一度それぞれの利害を離れ、真摯に議論するべき時期なのかもしれないと感じています。
今は、かつてなかったほどに、本というものの存在が問われている時代なのかもしれません。
「本の未来」と「本屋の未来」は違います。本の持つ可能性に、本屋がどのように寄り添い続けることができるのか。試行錯誤する中で、本屋の枠を超え、全国的にさまざまな試みが立ち上がっています。
その土地ごとの「本屋大賞」が生まれ、盛り上がりを見せています。また、「文芸書」を対象に行われてきた本屋大賞を、より生活に密着した「料理本」を対象に行うといった企画も生まれました。最近では「ノンフィクション本大賞」も新設されました。
しかし肝心なのは、受賞した本を、自店のものとしてから売ることです。それができないと、「売りたい本」ではなくて「売らされている本」になってしまうから。
「まちの本屋」の本質は、地域に根を張る覚悟
さらに、新しい本の在り方に寄り添うように、新しい業態の本屋が登場しています。規模もコンセプトもまったく異なるさまざまな本屋に挑む人たちが増えたことが、長く続いている冬の時代の中で、雪解けの後に一斉に芽吹く新芽を思わせてくれます。
本屋は、ある時期から大型化が進み、中・小書店はどんどん閉店・廃業していきました。では失われていった本屋の数だけ、延べ床面積が減っているかというと、そんなことはありません。
むしろ、増えていると思います。本の持つ多様性は、本屋を大型化するだけでは担保しきれないということではないでしょうか。大型化の後には、必ず細分化されてゆく。僕はそう考えています。
本屋は、新規参入するには障壁が大きいと言われています。その障壁を取り除き、新しい本との出会いを模索する動きが加速してゆくことが必要なのかもしれません。
しつこいようですが、それが成立するには、しっかりとした総合書店に地域に根を張ってもらう必要があります。
その中核となる本屋は、地元資本でも、チェーンの本屋でもいいのです。ただ、その地で本屋という商売を続けてゆくという覚悟のある本屋が担っていったらいいのだと思います。
その覚悟を持ち、地域と向き合い、根づいている本屋すべてを、「まちの本屋」と呼びたい。僕はそう思います。
本屋にとって、まちの存在は必要不可欠です。逆に、まちにとって本屋が必要不可欠なのだという理由を、店づくりの根底に持ち、そこに存在し続けることが、「まちの本屋」の本質でしょう。
どんなお客さまとこれから一緒に生きていきたいか
まちの本屋を成功させるノウハウは、もしかしたらさまざまにあるのかもしれません。
しかし、最も大事なことは、自分たちがどんな本屋にしたいのか、どういう店を最終的につくりたいのか、どんなお客さまとこれから一緒に生きていきたいかを考える、ということに尽きると思っています。
これをスタッフと、店と、会社とで、みんなが共有し、そこに向かっていくことができたら、この業界はまだまだやれるのではないか、と思っています。どうしてそう思うのかといえば、今は多様な選択肢の中から好みや利便性によって選ばれる時代だからです。
僕はお客さまによく、自分のお気に入りの本屋をつくるといいよ、という話をします。そういうお店が一軒あれば、読書はますます面白くなるから。
その意味でも、いろんな本屋に行ってみてください、と伝えています。たとえば、僕たちの店だけに来ていると、見えてこないことがあります。他の店にも行くことで、本屋というのは一緒じゃないということがわかってもらえるのです。
きっかけは何でもいいのです。立地でもいい。一番近いところ、車を止めやすいところ、駅から行くのに便利なところ……。
探す意識を持ってもらうと、違いがちょっとずつ見えてきます。だからこそ、本屋の側も意識しないといけません。その店だから売れる一冊は何なのかを。それが、その店の個性にもつながります。
挨拶ついでに配達もすれば「安否確認」もする
売れている本を置くことは、もちろん大切です。しかし、それだけではない何かを、お客さまに伝えられているか。それを自問自答することもまた、同じように大切です。
これは、店頭の話だけに留まりません。お客さまから、適当に五〇〇〇円分買っておいて、一万円分買っておいて、と頼まれるような信頼関係が生まれたら、挨拶ついでに本を届けてもいいと思うのです。
そして、お客さまといろんな話をする。仕事の愚痴を聞いてみたり、出身の話を聞いたり、親戚の話を聞いたりする。そうすると、ふたたび店頭でお会いしたとき、関係はまったく違うものになります。
長話をする必要はありません。おなじみとして挨拶を交わすだけで、居心地が良くなります。
僕たちの店には、そういうお客さまがたくさんいらっしゃいます。
年配のお客さまも多いので、来店していただくことを言葉は悪いですが「安否確認」と呼んでいたりします。たまに顔出してくれないとこっちも心配だから、何でもいいから報告しに来てよ、新聞の死亡欄を確認しちゃうぞ、なんて軽口も飛ばしながら。
こうした関係になるまでには何年もかかります。でも、一度いい関係ができると、本当に楽しいのです。お客さまも楽しいと思います。もっともっと本屋に来てほしい。
そこにさわや書店があるから、今日も行こう。そういうお店をつくっていきたいと思います。
※本記事は、田口幹人著『まちの本屋』(ポプラ社)より、一部を抜粋編集したものです。