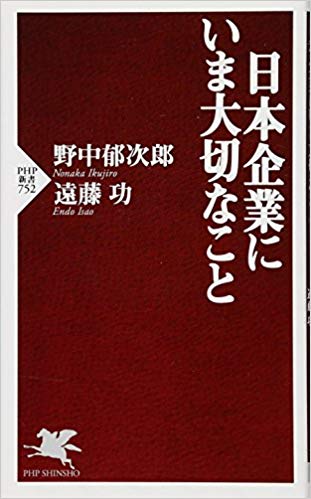グローバル企業にあって、日本企業から消えた「社員間の共感」
2018年09月21日 公開 2024年12月16日 更新
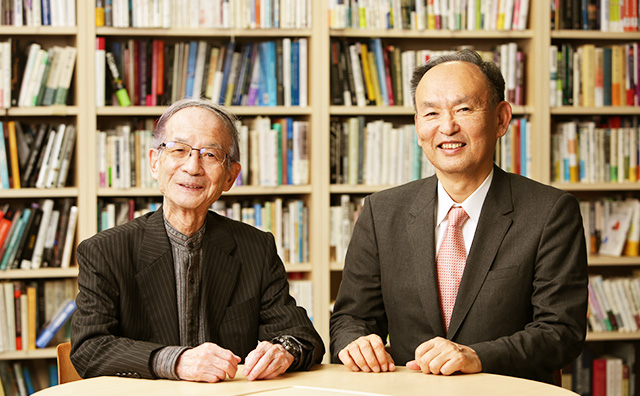
<<キリンビール内でも売上が最下位クラスだったダメ支店「高知支店」の売上を劇的に回復させ、その改革手法を他支店、本社でも成功させることで、同社のシェア1位奪還に導いた田村潤氏。
経営学者・野中郁次郎氏との対談を通して、本来の日本企業の強みであり、むしろ今やグローバル企業でこそ実現されている「人と人同士の共感」の重要性に迫る。>>
(本稿はPHP研究所刊『負けグセ社員たちを「戦う集団」に変えるたった1つの方法』に収録された「対談野中郁次郎氏 × 田村潤」より一部抜粋・編集したものです)
アジャイル開発の手法として、アメリカ企業が採用した日本企業のScrum(スクラム)
(野中)本来、日本企業の強みは、チーム一体で現場に飛び出し、そこで得た現場の経験知(暗黙知)を概念化して共有することでした。暗黙知から形式知への変換をスパイラルアップして絶えずイノベーションを起こしてきたのです。
ところが、現在は多くの日本企業が過剰計画、過剰分析、過剰法令順守に縛られて、知識創造のスパイラルがうまく循環していない。これではイノベーションが起こりにくい、といわざるをえない
(田村)いまの日本企業は、細分化された部門を横断するようなプロジェクトも圧倒的に少なくなっています。
(野中)わたしは1986年、ハーバード大学経営大学院の竹内弘高教授とともに当時、高い生産力を誇っていた日本の製品開発のプロセスについて研究し、『ハーバードビジネスレビュー』に論文「The New New Product Development Game」を発表しました。
その論文を読んだジェフ・サザーランド博士(現・Scrum inc.CEO)たちが1990年代半ば、事業部門と技術部門のメンバーがチーム一体となってプロダクトを開発する「Scrum(スクラム)」を提唱しました。
これは、課題が生じたら要件定義、設計、開発、テストなどの各部門が横断的にチームを組み、共同で解決に取り組むという工程方法です。スクラムは、アジャイルソフトウェア開発の手法として一気に世界中に広まりました。
(田村)アメリカのソフトウェア業界がスクラムを必要とした背景には、何があったのでしょうか。
(野中)当時、コンピュータのプログラム開発はウォーターフォール型と呼ばれ、要件定義、設計、開発、テストというシステム開発の工程をバトンリレー方式で行なっていました。
ところが、開発段階でニーズの変化や技術の進歩に左右されてしまい、完成品のクオリティが安定しない。プログラマーの疲労も蓄積するばかりで、分業制をやめて、当時、日本の生産現場で行なわれていたスクラムを取り入れたのです。その結果、製品のクオリティが飛躍的に高まり、顧客にも喜ばれるようになったのです。
(田村)スクラムのように、複数の部門にまたがる開発手法を実践する場合、中核を担うプロジェクトリーダーの役割がポイントですね。
(野中)そのとおりです。たとえばプロジェクトリーダーは毎朝15分、メンバーを集めてミーティングを行なう。いかなる条件下でもメンバー同士が顔を合わせることが大事であり、海外にいるメンバーにもスカイプなどインターネット通話を介して情報共有を必ず行ないます。
たんに予定や作業進行などの情報を確認し合うのではなく、表情やしぐさから相手が何を考えているかを感じ合うためです。場合によっては顧客まで巻き込み、互いに試行錯誤しながらスピーディに機動的にソフトウェアを開発します。
この共感をベースにしたスクラムが、いまアメリカのプログラム開発の分野で日常的に実行されています。デジタル時代の「共感」のあり方は、残念ながら日本よりシリコンバレーのほうが進んでいる、といわざるをえません。
次のページ
AIと人間 将来どちらが他人の共感を勝ち取ることができるのか?