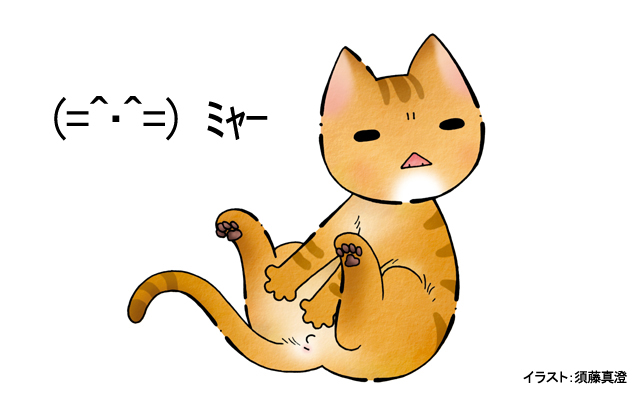猫がそこにいてくれる。ただそれだけの何でもないしあわせが、コロナ禍で人と会う機会が減ったことなどを機に再認識されている。だが、猫と暮らすには、最後まで寄り添う覚悟も必要だ。猫との出会いには猫の数だけストーリーがあり、猫と交わす約束もそれぞれである。
出会った日、こころ寄りそわせた日、別れの日……、交わした約束を猫はきっと忘れない。実際に交わされた「約束」の選りすぐりのエピソードをご紹介していこう。最終回は、絵描きのいっとくさんが、21年間いっしょに過ごした愛猫との別れの時に、交わした約束。「きっとまた会おうね」
※本稿は、佐竹茉莉子・著『猫との約束』(辰巳出版)より、内容を一部抜粋・編集したものです。
残りの時間はあとわずか
23歳を超えた、いっとくさんの愛猫「ねぎ」には、衰えが増してきた。
12月に入ると、食欲がパタッとなくなり、シリンジで流動食を飲ませはしたが、嫌がるのでもう無理強いはやめた。共に過ごす時間はもう残りわずかだと、わかっていた。ねぎは、旅立つ準備を始めていた。
英語教師のいっとくさんは、造形や絵画などジャンルにとらわれない創作作家でもある。クリスマスの朝、職場に向かう前に、すっかり軽くなったねぎを胸に抱き、こう言い聞かせた。
「ねえ、ねぎ。一人でいるあいだに死んではいけないよ」
若いときと変わらぬシャインマスカット色の美しい目が、いっとくさんを見つめ返した。
大みそかの夜は、ホットカーペットに横たわるねぎの傍らに座って、 つもる話をした。あのときは楽しかったねえ。あのときも楽しかったねえ。あれこれと思い出された。
ねぎが彼氏に選んだ雄猫たちのこと。夜の公園でベンチに並んで月を見上げたこと。 おにぎりを分け合ったこと。一緒に散歩していたら近所の女の子に笑われたこと……。
「21年間、おもしろかったねえ」と言うと、ここしばらく鳴いたことのなかったねぎが「にゃあ」と鳴く。「ねぎもおもしろかった?」と聞くと、また「にゃあ」と鳴いた。
おかしくなって、「おまえ、ほんとは人間の言葉がわかるんだろう?」と尋ねても、返事はない。ねぎは、ちょっとバツが悪そうだった。
温厚ないっとくさんと、好き嫌いのはっきりしたねぎは、この上ない相棒だった。
庭を横切った器量よし
ねぎは、21年前の春に、つと庭を横切った猫だった。ノラなのか半ノラなのか、 「お、美人」と目で追うほどの器量よしだった。
11月の寒い夕べ。いっとさんが夕食の用意をしていたら、あの猫が外からのぞいている。戸を開けて「おまえも一緒に鍋でも食うか」と言うと、スッと入ってきた。鶏肉をやると、前脚で転がして冷ましてから食べた。
食後、畳の上でゴロンとしていたいっとくさんの胸に、猫は乗っかってきて香箱を組んだ。もうずっと前からこの家にいたみたいに。
猫は、朝になると出ていったが、夜にはやってきて、そのうち、出ていかなくなった。
少年時代、捨て猫を拾っては親に叱られ、飼うことが叶わなかった猫との初めての暮らし。猫がのぞいたときに、箸でつまんでいたのが葱だったので、「ねぎ」と名づけた。獣医さんに診せると、2歳前くらいで「手術済み」とのこと。地域のボランティアに手術してもらったノラの1匹のようだった。
ねぎはいかにも自由な猫だったので、「そのうちいなくなるのかな」という思いもあったが、すんなり家猫になった。
いっとくさんは、ねぎのペースに合わせて暮らし始めた。朝は、きっちり5時50分に起こされる。ねぎはノラだったくせに、大きなものは食いちぎれず、皿からはみ出たものは絶対に食べない。旬の魚を夕食用に買うことが多くなり、ねぎ用には塩分を加えず、小さく切って焼いてやった。
ご飯をあげても、好きなブラッシングをしてやっても、鳴きやまないときがあった。そんなときは抱っこして、玉置浩二の「メロディー」でも歌ってやると、幼子のように眠った。そんな話を聞いた友人たちは、ねぎを「ねぎ様」と呼んだ。