
沈黙は、誰でも気詰まりするものです。避けようとするあまり、余計なことまで話し続けてしまうということはありませんか? しかしフリーアナウンサーの田中知子さんは、かつて怖かった沈黙が、考え方を変えることで怖くなくなり、むしろゆったりと受け止められるようになったと言います。
寡黙な相撲取りへのインタビューなど実例も交えて、沈黙に怯えなくて済む考え方を紹介します。4月から新年度、新しいスタートにこんなコミュニケーションの心得を加えてみては?
※本稿は『口下手さんでも大丈夫 本音を引き出す聞き方』(かんき出版)より一部を抜粋編集したものです。
沈黙を恐れずに「待つ」と相手が信頼する
「沈黙」という言葉からどんなことを想像しますか? よいイメージ? それとも悪いイメージ? どちらかというと後者のイメージではないでしょうか。
今まで会話していたのに、プツッと途切れてしまうとどうしたらいいか焦ってしまうことありますよね。間が怖くて話し続けてしまう。私もよくありました。間ができると思わず埋めようとしていたことが。
特に初対面の相手との沈黙ほど怖いものはありません。
ラジオでのインタビューはコロナ禍が始まってからの3年間はすべて電話でした。
顔を見ずに電話だけで話す20分間――。表情が見えない分、お互いの声がぶつかることもありますし、少し間ができると「どっちが話す?」みたいな空気になります。
私はそういうとき、基本的に相手が話し出すのを「待つ」ようにしています。相手からより深い話や情報を引き出したいときには「沈黙」がとても大事な時間になるからです。
インタビューしていると、質問に対してゲストの方が「う~ん」と考え込んで沈黙になることがあります。私の場合、口の重い力士や一般の方を取材する機会が多いこともあって、頻繁に「沈黙」に直面します。そんなときこそ「待つ」。
その沈黙は相手が質問をよく考えて一番いい答えを探している、いわば「シンキングタイム」。その時間を「それってこういうことですよね?」とまとめようとしない。相手のじゃまをせず「待っていますから大丈夫です」という思いで待ちます。
そうした姿勢は、「この人は真剣に私の話を聞いてくれている」「私の話をちゃんと受け止めようとしてくれている」という信頼にもつながっていくのです。
私が聞くときに心がけているのは、相手と私の間に「安心した空間をつくること」「温かいドームをつくること」です。「安心して自分らしさを出してほしい」、最終的な会話の舵取りはしますが、話すペースは相手に合わせています。
頭の回転が早く、早口な方はテンポよく、ゆったりかまえて話す方はこちらもゆったりと。そのおかげで、ラジオでインタビューさせていただいた方からこんなうれしい感想をいただきました。
「緊張していたところ、田中アナウンサーから「人を安心させる力」を体感。初対面で安心して身をゆだねられると感じさせてくださる方がおられたことで、必要以上に緊張することなく、生放送を終えさせてもらいました。こちらが伝えたいことをしっかりとキャッチされるという想いが、安心感につながったように思います。」
相手がその人らしく話せること。そしてその人の魅力を引き出して広げること、深めることが聞き手の役割です。
営業のクロージングタイムでも「沈黙は金」
実は私が「沈黙を待つことの大事さ」に気づけたのは、アナウンサーになる前、リクルート求人広告の営業をしていたころのこと。
売れっ子の男性営業マンがいました。声も体も小さくて、「あれAさんいたの?」というくらいの存在感。物静かでしゃべるのは一言二言。そんなAさんですがいつも営業成績はトップでした。
「Aさんはしゃべらないから売れるんだよ」
と別の先輩が言っていて、「しゃべらない営業が売れる」という理由を当時はよくわかりませんでした。それがわかってきたのは営業3年目、やっと売れてきたころです。
一番営業として緊張するのは、お客様が求人広告をやろうと決断するタイミング、つまりお客様へのクロージングタイム。特に金額を決めるときが一番ナーバスになるところです。「本当にこれでいいかな」と迷われるお客様もいらっしゃいました。そういうとき、沈黙が訪れることが多いのです。
「広告費で100万円。これで大丈夫かなぁ......」と相手が迷って考え込む。そのときに「早く売りたい」「結論を聞きたい」とこちらの欲がでてしまうと
「費用対効果を考えたら絶対にお得です」
「今やりましょう」
と、最後の一押しといわんばかりに口を出してしまう。すると「押し売られ感」が生まれてしまい、「やっぱりもう一度検討する」と考え直されるケースにもなってしまいます。
私はお客様から「次のひと言」が出てくるまで、ずっと黙って待つようにしていました。結論を早く聞きたいけど沈黙に気詰まりしてもガマン。その沈黙がしばらく続いてもガマン。お客様から質問されたときには答えますが、そのあとはまた黙る――。
結果的にはそのほうが契約が成立する確率は圧倒的に高かったのです。沈黙を待つほど、黙れば黙るほどに受注できるようになったのです。
相手からより深い話やいい決断を引き出すためにも、「沈黙を待つ」勇気と心の余裕を持つことを学びました。
沈黙は怖いものではありません。悪いイメージもありません。こちらが怖いと感じるほど、相手はそう感じていないことも多いのです。
間を楽しんで、相手を信頼してみてください。沈黙をガマンできたら自分を褒めてくださいね。
沈黙の間は、相手を観察する
「待つ」がよい効果を生むのは大相撲の取材現場でも活きました。
沈黙といえば力士も寡黙なイメージがありませんか?
これは営業時代に身につけた「待つ」ことで、よいコミュニケーションになった大相撲取材の経験談です。デビューからわずか5場所で関脇昇進というスピード出世で世間を驚かせた元関脇・逸ノ城関。取材した時期は2017年、大阪場所前に朝稽古取材に行ったときのこと。
逸ノ城関は、当時、身長190センチ超、体重220キロ。幕内力士のなかで最重量のモンスター級の大きさ(褒め言葉です!)。私は身長156センチなので圧倒的で、存在感があります。決してニコニコと愛敬を振りまくタイプではありません。大相撲中継で見る関取の返答は一言二言。しゃべらない力士の代表格と言ってもいいでしょう。あまり多くを語らないので何を考えているのかわかりにくく、話を引き出すのが難しい……と感じました。
「逸ノ城関、春場所を間近に控えて調子はどうですか?」
「......まぁいい感じです」
「2場所連続の金星、どんなお気持ちですか?」
「......とれてよかったです」
「質問、聞こえなかったかな?」と思ってしまうくらい、ゆっくりとした間があって、ようやくボソッとひと言答えてくれる。
取材する側としては「もう少し話してほしい」「深い話を聞きたい」と、じれったく感じることもありました。いつもの自分だと「何とかしゃべってもらおう」とあの手この手で必死にアプローチしたものです。特にテレビでは相手に言葉で言ってもらわないとわからないため、「ちゃんと話してもらおう」と思っていました。
――いや待てよ、こんなときこそ営業時代の「待つ」の出番。
よくよく観察してみると、なんだかしゃべらない姿も可愛らしいではありませんか。なんだかモフモフしていて「ぬ~ぼ~」っぽい。子どものころ、森永製菓が発売したお菓子のマスコットキャラクター「ぬ~ぼ~」の「大きくて、のんびり、ゆったり」というイメージが、逸ノ城関とダブって見えたのです。あの黄色いキャラクターです。バリバリしゃべっているイメージはありません。
そう見えてきたら、なんだか彼の寡黙さも、ゆっくりした話し方も、独特の存在感も、すべてが可愛らしい、愛おしいという気持ちになってきたのです。
私にとっての逸ノ城関は「愛すべきぬ~ぼ~」。その「ぬ~ぼ~」が今、私の質問に答えようと一生懸命に考えてくれている――。そんなふうに考えたら、「もっと話して」という自己都合の焦りは消えました。そして、彼が話し始めるのを笑顔でじっくり待つことが取材の楽しみになったのです。
沈黙もコミュニケーションと考える
相手に話をさせようではなく、相手を観察して、まず相手のよさを味わう。
そして、相手のよさに気づく。何も話さないたたずまいは、土俵の上での激しさはなく、なんとも穏やかで優しい雰囲気でした。言葉は少なくともひと言ひと言が誠実に伝わってきました。
話してくれない相手にもどかしく思うのはこちらの一方的な気持ちです。沈黙もコミュニケーション。待つ時間は相手を信頼している証。しゃべらない相手と話すときは相手のペースに合わせて、まずは相手の様子を観察しましょう。言葉にならない雰囲気もしっかり味わって感じて、どっしり受け止める横綱相撲でいきましょう。
【田中知子(たなかともこ)】
フリーアナウンサー。大相撲愛好家。コミュニケーション講師。株式会社ちゃんこえ代表取締役。通称「たなとも」。リクルート求人広告代理店営業から31歳でNHKキャスターに転身。NHK大相撲取材から学んだ独自メソッド「金星コミュニケーション」を講演しながら、「人と話すって楽しい!」「勇気を出して挑戦すると道が開ける!」を伝えることをミッションとして全国を飛び回っている。
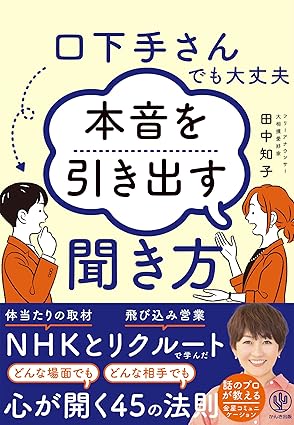
.jpg)














