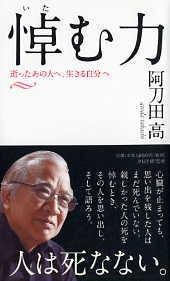[悼む力] 心臓が止まっても、人はまだ死なない。
2013年06月13日 公開 2024年12月16日 更新
![[悼む力] 心臓が止まっても、人はまだ死なない。](/userfiles/images/a_image4/atouda_150.jpg)
《『悼む力 逝ったあの人へ、生きる自分へ』より》
マン・イズ・モータル
マン・イズ・モータル。人間はかならず死ぬ。人間にとって、死ほど重大なテーマはほかに見当たらないのではあるまいか。
なのに “太陽と死は直視するのがむつかしい” なんて……まことしやかな言葉があったりする。太陽のほうは直視できないが、おおよそどんなものか見当がつく。その点、死のほうは、見当のつくところも少しあるけれど、やっぱりよくわからない。
まったくの話、死については古来いろいろなことが語られ、思案されているけれど、決定的に不足しているのは、死者の側からの視点を欠いていることだ。会議場に集まってみんなで議論しようにも、満たされているのは生きている人の席ばかりだ。もしここに半数でも、3分の1でも死者が参加していたなら議論も議決も相当に異なっているだろう。今も述べた通り、死者の考えはまったくわからないけれど、わからないなりにそんな気がしてならない。
イタリアのダンテ(1265~1321)は死後の世界を〈神曲〉に書いた。天下の名著と評されている力作だ。それまでの知識の詩的な集約であり、その後の(少なくとも欧米的な)思索や表現にさまざまな影響を与えているが、どう考えてもこれは生きている側の、きわめてキリスト教的な考えを反映していて、
- ちょっとちがうんじゃないのかなあ -
すなおには首肯できないところも多い。
地獄のどん底に、一番の罪人として3人があって苛まれ、1人はキリストを裏切ったとされるユダ、これは、まあ、理解できるけれど、紛うことないキリスト教的判断だし、残る2人がシーザー暗殺の首謀者、ブルータスとカシウスとなると、
- それってイタリアの歴史じゃないの -
と鼻白む。さらに天国に入れば、これは往時の三位一体の理屈を反映して、やっぱり生きている側の視点に溢れている。
話は飛ぶが、1992年に作られたアレクサソドルーソクーロフ監督の手による映画〈ストーン/クリミアの亡霊〉で、チェーホフの亡霊がヤルタの町に現われ、これはかなりの現実感があった。死者の世界は、ぼんやりとした、弱々しいイメージで、ぜんぜん楽しそうではない。チェーホフも冴えない。
- そうかもしれない -
現実感はあったが、これとても生きている側の想像にしかすぎない。
市井では、もっぱら幽霊のたぐいが死者の世界をかいま見せてくれるが、
「この世に恨みがあるんでしょうね、幽霊になって出てくるところを見ると」
「恨み? 恨みを抱いて死ぬ人なんか山ほどいるよ」
「うん」
「そのわりには幽霊の数が少ないと思わないかね」
確かに。あの世に行って、そこから恨みを晴らすために幽霊になってこの世に現われるためには、
- よほどむつかしい資格試験があるのかなあ -
馬鹿らしいことを考えないでもない。
思案を正常に戻して……死んだら、人はすべて塵芥になる、まったくの無、なにもない。これが一番科学らしい見解のような気もするが、少し寂しい。とても寂しい。あまりにもなさけない。
そこで……1つの哲学があって……哲学と言うよりとても現世的な考えがあって、
「死んだ人は、だれかがその人を思い出している限り生きているんだ」
私はこれをとても気に入っている。
死という、まったく測り知れない重大事に対して現実に対処できるせめてもの理屈はこれしかないのではあるまいか。同じ考えを持つ人はけっして少なくない。少し吟味してみると、この考えに基づく風俗や生活習慣は、私たち生きている側の社会でよく見られることでもある。まったくもって一方的な視点なのだが、生きている側は慰められる。自分の死についても、これを思うとなにかホッとするものを感じたりする。
親しかった人の死……。いつまでも、いつまでもその人を思い出す。すると生きていたときと同じように身近にその人のイメージを抱くことができる。それは、多かれ少なかれその人が生きていたときと似ているではないか。その人が生きているときも、長く会えなければあれこれ想像して存在を確認しているのだ。だから、死んだあともこれこそがその人を“生きていること”とする唯一の方法なのだ。
自分が死んだあと、親しい人たちが、こぞって、あるいは1人でも2人でも、
- 私を思い出してくれればいいな -
命のはかなさに立ち向かえるかもしれない。死の恐怖に少しは抵抗できるかもしれない。
私儀、いつのまにかずいぶん長く生きてしまった。80歳も近い。この先も年々歳々年齢が増えていくのだろう。そのせいもあってか優れた同業者との訣別にも繁く接した。若い作家の死にも遭遇した。いくつかの追悼文を綴り、いくつかの思い出を記した。そのこころは、
- しばらく生き続けてください -
何人かが、何十人かが、何百人かが、そう思い続けるならば、その人は生きている、と苦しいけれど言えなくもない。
作家について言えば……この仕事はもともと読者に多彩なイメージを与え、それによってみずからの存在を示す立場である。当人がいなくなってもイメージを与え続けることができれば、生きていたときと……似ている。しかも、作品が残るからそれをやりやすい。有利な立場と言えなくもない。
さらに言えば、作家はその生き方自体が小説の気配を帯びている。追憶はその作品を解く鍵ともなる。私はだから訃報に接しては、しばしばその人柄を偲び、生涯に思いを馳せ、その作品を考えた。
たったいま作家について“有利な立場”と記したが、それは作家の仕事が一つの典型として“イメージを見せやすい” からであり、作家以外の人の死についても、それを広げて考えればきっと同じことが言えるだろう。同じことを考えて、それぞれ意味がありうるだろう。
あなたの親しい人の死……。いつまでも思い出し、その存在を感じ続けよう。生涯を少しずつでもたどってみよう。あの世でどう生きているかはわからないけれど、そうすればこの世で少しだけその人は生きるのだ。死者を生かす方法はほかにない。これに尽きる。
この思案をさらに深めて、
- ああ、そうなのか -
小説の誕生はそこにあったのではなかろうか。私はそう考えている。いつとは言えない遠い日のこと、だれかが死ぬ。悲しい。辛い。生き返ってほしい。
そのためにその人を思い出す。その人を考える。エピソードが語られ、ストーリーとなる。これが小説の原点となった。原点の一つとなった。物語の発生において亡びたものへの哀悼が関わっていたことは疑いない。
マン・イズ・モータル、この英語を習ったのは中学生のときだったと思うが、そしてこれを習った理由は“人間一般を言うときにはマンに定冠詞も不定冠詞もつけない”というひどく散文的な用例としてであったが、その中身のほうも私の心に残った。近親者の死に接しては、
- やっぱりそうなのか -
と思った。頭の片隅に……ほとんどこぼれ落ちそうになっても、ずっとこの思案があって、文章を書くようになっても、これが時折モチーフとなって脳裏にちらつき、作品に映った。私は“マン・イズ・モータル”という言葉に他人より多く取りつかれた作家だろう。そんな気がする。
阿刀田 高
(あとうだ・たかし)
作家
1935(昭和10)年、東京生まれ。早稲田大学文学部卒。国立国会図書館に司書として勤務しながら執筆活動を続け、78年『冷蔵庫より愛をこめて』でデビュー。79年「来訪者」で日本推理作家協会賞、短編集『ナポレオン狂』で直木賞、95年『新トロイア物語』で吉川英治文学賞を受賞。2003年に紫綬褒章、09年に旭日中綬章を受勲。
日本ペンクラブ15代会長、直木賞選考委員。12年より山梨県立図書館館長に就任。
他に『闇彦』『源氏物語を知っていますか』(以上、新潮社)、『影まつり』(集英社文庫)、『松本清張を推理する』(朝日新書)など著書多数。
<書籍紹介>
人はいつかは死ぬものである。大切な人を失い、多くの人を見送ってきた作家が見つけた悼む意味とは。80歳を迎える小説家の死生観。