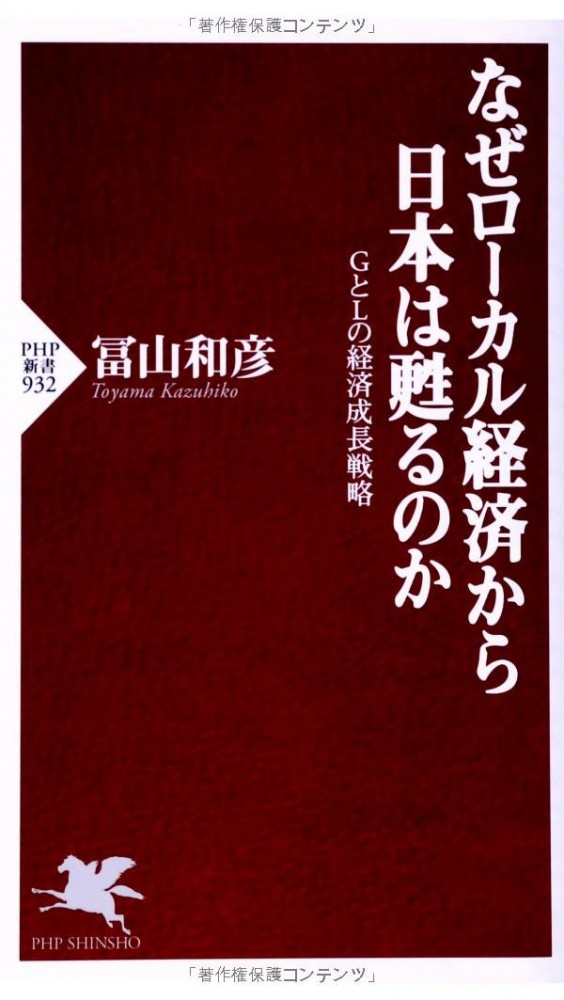冨山和彦「なぜローカル経済から日本は甦るのか」
2014年07月31日 公開 2024年12月16日 更新
 この人類史上初の少子高齢化起因による人手不足は、地方経済から始まった。中央より地方のほうが生産労働人口の減少が先に起こっているからだ。冒頭のいくつかの企業の事例は、それがついに中央でも起こり姶めたということである。アベノミクスの効果が出始めたことで、景気が回復したからではない。
この人類史上初の少子高齢化起因による人手不足は、地方経済から始まった。中央より地方のほうが生産労働人口の減少が先に起こっているからだ。冒頭のいくつかの企業の事例は、それがついに中央でも起こり姶めたということである。アベノミクスの効果が出始めたことで、景気が回復したからではない。
この現象を、いまだに多くの人は一過性だと捉えている。2020年の東京オリンピックが決まったことによる建設市場の活況もあり、たしかに建設業に関しては数年単位の一通性の現象と言えるかもしれない。だが、これから先の日本の人口動態を考えると、どう考えても構造的な問題ということがわかる。
1947年から1949年に生まれた「団塊の世代」が、2012年から65歳以上の高齢者になり始めた。2013年10月の人口推計では、高齢者の比率が初めて25パーセントを超えた。
彼らが平均寿命を迎えるまでのおよそ20年間は、高齢者層の数が圧倒的に多くなる。団塊の世代以後の数は急激に少なくなっているとともに少子化が深刻化しているので、人手不足に関しては最も逼迫が大きい時期を迎える。
ただ、この20年間を過ぎて団塊の世代が寿命を迎えると、高齢者の絶対数も減少に転じる。それでも、真に有効な少子化対策が実施されない限り子どもの数は増えないと予測されるので、生産年齢人口が増加に転じることは考えられない。
結局、人手不足の構図は解消しないのである。深刻な人手不足の状態がこれから20年は続くという事実は、決して一過性とは言えない。加えてその先も好転が予測できないのであれば、構造的な問題として対処していかないとこの状況はしのげない。
現在の日本の経済政策、産業政策、労働政策は、基本的に人が余っている前提で構築されている。常に失業圧力がかかっていて、どのようにして雇用を支えるかというのが問題とされている。
そうなると、たとえば雇用の受け皿になっている中小企業はできるだけ守らなければならない、非正規労働者は可能な限り日本型正規雇用に引き戻さなければならないという結論になる。
そこに、議論と実態のズレが生じている。現実には、政策を考えるときの大前提が変わってしまったのだ。そこからすべての議論を起こしていかなければ、適切な解にたどり着くことはできない。
アベノミクスによる景気回復で、大手製造業を中心に業績が好調だ。その事実を根拠に、グローバル企業が高度経済成長期からバブル時代のように加工貿易モデルで再び世界を席巻し、それが日本の経済成長を牽引するかのような幻想のなかで議論が進んでいる。
しかし、繰り返すが日本のGDPと雇用のおよそ7割を占めるのは、製造業ではなくサービス産業だ。しかも、サービス産業の大半は、世界で勝負するようなグローバル企業ではなく、国内各地域内の小さなマーケットで勝負するローカル企業が大半だ。
本編でまた詳しくふれるが、サービス産業の多くは、経済構造的にローカル企業がローカルに活動する構造から、あまり大きくは変化しない。だとすれば、これからの日本の経済成長は、ローカル経済圏のサービス産業の労働生産性とその相関変数である賃金が大きく左右すると考えていい。
もちろん、世界で勝負できる製造業やIT産業のグローバル企業にはがんばってもらえばいい。日本のような少資源国、かつ財政が危機的な状況にある国においては、グローバル企業群が世界のトップレベルの競争力を獲得し、その「稼ぐ力」で、貿易収支であれ所得収支であれ、我が国の国際経常収支に貢献してくれることは極めて重要だ。
それはローカル経済圏の持続性にとっても重要である。しかし、それだけでは必要十分条件にならない。世界で勝負できるわずかな数のグローバル企業がどれほどがんばっても、残り大半のローカル企業が足を引っ張っていてはどうにもならない。
しかも、本編でも詳しくふれるが、経済のグローバル化が進展すると、ローカル経済圏で活動する非製造業への依存率が高まるのは、先進国共通の現象である。だから世界で勝負するグローバル企業と日本国内で勝負するローカル企業の割合が大逆転するようなことも、構造的には絶対に起こり得ない。
いずれにせよ、今、日本の社会と経済に起こりつつある巨大なパラダイムシフトは、グローバルな経済圏とローカルな経済圏の違いを際立たせているのである。
政府は、2014年6月を目途に閣議決定を目指す「経済財政運営と改革の基本方針(通称、骨太の方針)」の検討に入っている。これからの日本経済の成長を考えるうえで、こうした前提条件のなかでどのようなことに取り組んでいけばいいのだろうか。
本書では、グローバル(G)の世界とローカル(L)の世界それぞれの分野において、私なりに考えられる処方箋を提示したいと考えている。違うものは違う。しかもGとL、2つの経済圏の直接的な連関性も希薄になっている。
だとすれば、それぞれの実態、特性をしっかり把握して、それぞれの問題に真正面から対峙しようという、ある意味、当たり前の思考姿勢である。
本書を通じて、読者諸氏には、日本の現状がどうなっているかを正確に認識していただきたいと思う。そのうえで、私の提示する処方箋をもとに、これからの日本と日本企業、および日本人が歩むべき道に思いを馳せていただければ幸いである。