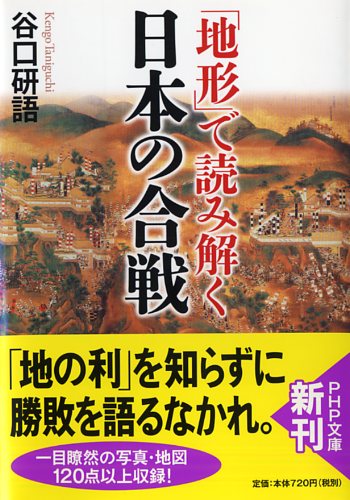地の利は西軍にあった!? 地形で読み解く「関ケ原合戦」
2014年09月13日 公開 2024年12月16日 更新

尾張平野を一望できる要害の小牧山をいち早く押さえて、天下取りへの野望を燃やす3倍の秀吉軍と互角以上に戦った徳川家康――。だが、その家康もかつて上洛を目指す武田信玄には、三方ケ原の台地を巧みに利用され、無様に敗走させられた“苦い経験”をもっていた。
谷口研語氏が「地の利」を活かして作戦を練り上げた“戦巧者たち”の駆け引きと、関ヶ原の合戦の勝敗の舞台裏を「地形」「地名」から読み解いていく。
※本稿は、谷口研語著『「地形」で読み解く日本の合戦』(PHP文庫)より一部抜粋・編集したものです。
天下分け目の関ケ原――大垣城の「攻城戦」をさけた家康
歴史に名を残すような大きな合戦は、大軍と大軍との衝突ということになるから、それなりのひろい場所を必要とする。原名で呼ばれる合戦が多いのは、そのような事情による。原名で呼ばれる、歴史に名高い合戦ということだと、まずあげるべきは関ヶ原の戦いだろう。
慶長5年(1600)に戦われた関ヶ原合戦は、「天下分け目の関ヶ原」といわれるように、戦国の世を最終的にしめくくる戦いだった。すでに豊臣政権は全国統一をなしとげていた。
したがって、その後継をめぐるこの合戦は、全国的なひろがりをもっており、付随する戦いが各地でおこなわれているが、一般に関ヶ原合戦と呼ばれるように、本戦は美濃(岐阜県)の西部、現在の岐阜県関ヶ原町域でおこなわれた。
豊臣秀吉亡きあと、豊臣政権の実権をにぎった徳川家康は、慶長5年、五大老筆頭の名目で、上杉景勝に上洛をうながしたが、拒否されたため、秀頼の名代という立場で、豊臣系大名をもふくめた会津(福島県)遠征軍をおこした。その裏には、石田三成を挑発しようとの目論見もあったものだろう。
案の定、家康の留守を好機ととらえた三成らは、五大老の1人毛利輝元をかついで挙兵した。
7月17日には、長束・増田・前田三奉行連署の家康弾劾状、いわゆる「内府違いの条々」をはっして、諸大名の糾合をはかり、つづいて山城(京都府)伏見城、丹後(同府)田辺城、近江(滋賀県)大津城など、家康方の諸城を攻撃。伏見城落城後、三成は美濃へくだって、8月11日、大垣城に入城した。
美濃大垣城は、濃尾平野の西部にあって、木曽三川(濃尾三川、木曽・長良・揖斐の三川)の西側に位置する交通・軍事上の要衝であり、秀吉と柴田勝家の賤ヶ岳合戦のさいにも登場する。秀吉は大垣城を「大事のかなめ之城」(一柳文書)と認識していたが、その大事の要の城を、まず西軍がおさえた。
いっぽう、遠征途上で刻々と西軍の情報をえていた家康は、下野(栃木県)小山で、いわゆる小山会議をひらくと、諸将に上方の異変をつげ、去就は各自の自由意志にまかせた。この会議では、武断派の豊臣系諸将が三成打倒を主張、その結果、遠征軍のほぼ全軍が反転して美濃へとむかった。
こうして、8月末には、東西両軍あわせて約20万の軍勢が西美濃に集結し、西軍の総司令部となった大垣城を中心に、西軍諸隊はその西方から南方にかけて、東軍諸隊は北方から東方にかけて野陣をはった。東西両軍の集結をまって、東軍の主将徳川家康が西美濃に到着する。
「慶長年中卜斎記」によれば、9月13日に岐阜へはいった家康は、14日の夜明け、長良の渡しで長良川を渡り、岐阜より西美濃に進出した。長良の渡しとは、岐阜城の麓、現在、有名な長良川の鵜飼いがおこなわれるあたりで、家康は、西軍主力が籠城する大垣城をさけて、大きく北方を迂回したものらしい。
関ケ原は「不破関」にちなむ――古代律令制の軍事施設
西軍主力は9月14日深夜に大垣城を出て関ヶ原へ移動し、東軍もそのあとをおって関ヶ原へ進出、翌日の決戦となる。関ヶ原とは古代の関所「不破関」にちなむ地名である。
古代律令制度では、都から放射状に、東海道・東山道・北陸道・山陰道・山陽道・南海道・西海道という7つの官道がもうけられた。このうち東国へむかう官道は東海道・東山道・北陸道の3道だったが、この3道それぞれに東国と畿内を画する関がもうけられていた。
東海道筋では伊勢(三重県)と近江との境におかれた鈴鹿関、北陸道筋では越前(福井県)と近江との境におかれた愛発〈あらら〉関、そして東山道筋では近江と美濃との境におかれた不破関である。
これが「律令三関」と呼ばれるもので、この3関の東側がひろい意味での関東であり、事実、奈良時代には、そう称されていた。
3関のうち、美濃不破関以外はその故地が確定されていないが、不破関は都から近江をとおってきた東山道が、近江・美濃境の狭隘部を美濃へ出た位置にあり、鈴鹿関も東海道が近江あるいは伊賀(三重県)から鈴鹿山脈を越えた伊勢側の山麓に推定されている。
おそらく愛発関も、北陸道が近江から山越えで越前にはいった越前側にあったのだろう。この、いわゆる律令三関は、関といっても江戸時代の関所のような警察施設ではなく、軍事施設だった。
不破関の発掘調査によれば、不破関の平面プランは、東西約460メートル・南北約436メートルの台形状をなし、総面積約12万3500平方メートル(約3万7400坪)、藤古川の崖で西側を区切り、南・北・東の三方に土塁をめぐらせた要塞だった。
そして、その中央を東西に東山道がはしり、東山道に面して北側に、築地塀でかこまれた、ほぼ100メートル四方の政庁跡が確認されている。
こうした大規模な要塞化がいつごろなされたのかは、よくわかっていない。ただ、『日本書紀』によると、672年の壬申の乱にあたって、大海人皇子方は「鈴鹿関」や「不破道」をかためており、すでにそのころ、三関あるいはその前身をなす施設がおかれていたものと推定される。
この不破関があった地として、関ヶ原という地名は生じたものである。関ヶ原という地名は、すでに南北朝時代からみえており、北畠親房の『神皇正統記』では、平治の乱(1159)のさい、美濃までのがれた源頼朝が捕らえられたのは、「関ヶ原」であったとしている。
ちなみに、三重県に関町(亀山市)があるが、これも律令三関の1つ鈴鹿関に由来するものだ。
次のページ
西軍主力の陣取り――近江への「間道」をおさえた石田三成