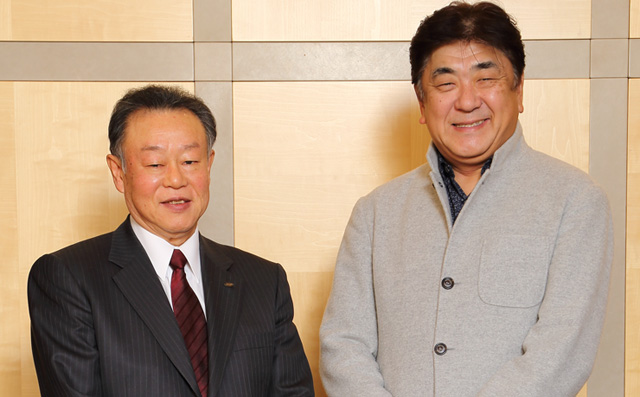佐渡裕 「1万人の第九」にかける思い
2014年11月06日 公開 2024年12月16日 更新
PHP新書『棒を振る人生』より

1人ひとりが主人公になってほしい
1999年から僕が総監督に就いた〈サントリー「1万人の第九」〉は、一般公募で集まったアマチュアの合唱団員1万人が毎年12月、大阪城ホールで「第九」を演奏する。関西らしいこの壮大なコンサートは、毎日放送の企画・制作、山本直純指揮で1983年から続いていた。
この「1万人の第九」というプロジェクトには膨大な時間と労力を要する。
通常オーケストラの定期演奏会のパターンというのは、3日間練習して、1回か2回の演奏会を開く。しかし、「1万人の第九」の本番はたった1回のためだけに合唱の新人は8月から12回、経験者にも最低6回のレッスンを義務付けている。そのうえで僕自身が千人ずつの合唱を1時間半かけて合計10回練習する。オーケストラの練習も3、4日間やる。
それだけ時間と労力を費やしながら、長年続けている最も大きな理由は、この「1万人の第九」が、ベートーヴェンの作品の核心に触れるきっかけになったからだった。
ベートーヴェンは、ヨーロッパで生まれ発展したクラシック音楽のいわば象徴的存在である。ヨーロッパ生まれでありながら、その音楽の感動は地球の裏側に生きるわれわれも含めてみんなのものであることを、僕は証明したかった。
1万人の中には楽譜を読めない人もいる。いやむしろ、小学生から90歳を超える参加者の大半は、ふだんオタマジャクシには縁のない人たちだ。しかし、音楽をやるのに楽譜が読めるかどうかは関係がない。「1万人の第九」で大事になるのは、まず演奏会に臨む姿勢である。
最初はみんな「私1人くらい歌わなくても大丈夫だろう」という気持ちで参加する。しかし、それでは苦労して1万人でやる意味がない。1万人が冷めて歌っている光景ほど、ぞっとするものはない。だから僕は練習のたびに
「ガラガラ声もキンキン声も全部受け入れるから、1人ひとりが主人公になってほしい」
と訴えてきた。
「1人ひとりの名前を持った音をつくりたい。山田さんなら山田さん、鈴木さんなら鈴木さんの声がほしい」と。
しかし、問われているのは僕自身でもあった。
1万人に自分の思いを伝えるためには、自分の中に強固な核を持っていなければならない。夢中で音楽と向き合っているか。理想の音をつくろうとしているか。その確信とともに、自分の思いを伝える飾りのない言葉、シンプルな表現が必要になる。なにしろ会場では、一番遠くで80メートルも離れた合唱団員に僕の気を届けなければならないのだから。
厳しい現場であることが、実際にやってみてわかった。僕が気を発すれば発するほど、その気が1万人に吸い取られていく。でも新しい気がどんどん湧いてくる。そしてまた僕が気を投げかけると、1万人からグワッと気が返ってくる。それを受け止めるのがまた大変だ。
初めての演奏会が終わった後、僕はぶっ倒れた。体重が7キロ減っていた。心身ともに限界だった。
1万通りの人生を響かせる
1回だけと思って引き受けた仕事だった。お祭り騒ぎだと思っていたイベントが、扉を開けるとまったく違っていた。やってみると何とも言いようのない、温かなものが胸の奥まで広がったのだ。
「歓喜の歌」はシンプルなメロディーでできていると書いたが、「第九」の4楽章全曲を歌うとなると、かなりの難曲である。しかもドイツ語という言葉の壁がある。
この舞台に立つためには、その年の夏から、たとえば仕事の合間を縫って、たとえば受験勉強の中を、あるいは親の介護をしながら、欠かさず練習に出て、この大変な曲に立ち向かわなければならない。
1万人それぞれが自分なりに、この1年間を懸命に過ごしたに違いない。そうしてなんとか大学に合格できたとか、無事健康に過ごせたとか、あるいは恋人ができたとか、年齢も職業も経験もバラバラな1万人が、自分自身が実感できるよろこびを思いながら「歓喜の歌」を歌いあげる。文字通りひとつになって、「フロイデ」という言葉を口にする。
1万人がただ集まって歌う場ではなく、1人ひとりが自分の人生をひっさげて、1度きりの本番に臨んでいる。亡くした奥さんの遺影を持って舞台に立つ男性もいれば、臨月のおなかを抱えて歌う若い母親もいた。孫と参加するおじいちゃん、おばあちゃんの笑顔もあった。
そんな普通の人たちがそれぞれの人生を背負いながら集まって、ともに心を震わせながら、とても創造的な音楽を生み出した。その達成感を胸にそれぞれが生活する場に戻り、明日からの日常をまた誇らしく生きていく―─。
世の中には暗いニュースが日々溢れているが、「人間、捨てたもんじゃない」と心から思えた。
1万人それぞれに違う人生を響かせてつくる音楽だ。だから合唱に参加する1万人は、本当はタキシードとドレス姿ではなく、それぞれ自分が誇りに思う格好で歌ってほしい。消防士は消防士の格好で、看護師は看護師の格好で、エプロン姿や学生服もいいと僕は思っている。人が本当に誇らしく思える姿は人によってまちまちであることが、ひと目でわかるだろう。
「歓喜の歌」には行進曲が登場するが、フランス革命における民衆のパワーを信じていたベートーヴェンが思い描いていたのは、軍隊のように一糸乱れぬ行進ではなく、足並みがそろわなくても、1人ひとりが自分の力で力強く歩く姿だったに違いない。
「1万人の第九」では僕の発案で、男声合唱の行進曲の部分を特別なやり方で毎年練習するのが恒例となっている。リハーサル会場でたまたま隣り合わせた人同士が肩を組み、僕もその列に加わって皆で身体を揺らし、掛け声をかけるようにこの部分を歌いあげるのだ。7歳の男の子も、70歳のおじいちゃんもみんなが同級生のようになって、自由に、誇らしげに見える。こんな姿をベートーヴェンはきっと夢見ていたに違いない。