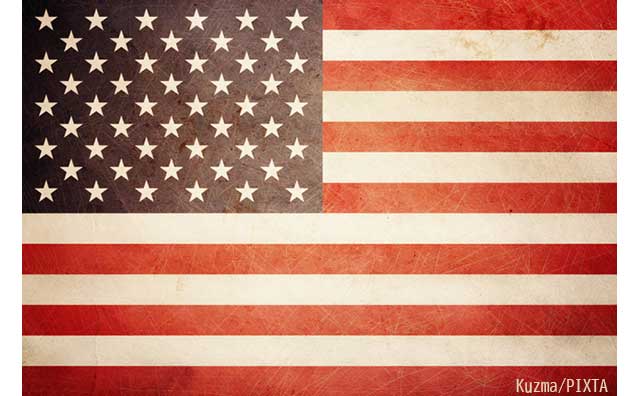アメリカはイスラム国に勝てない
2015年01月26日 公開 2024年12月16日 更新

《PHP新書『アメリカはイスラム国に勝てない』より》
イスラム世界の「パンドラの箱」を開けた米国
2014年秋、イラク・シリアを中心に活動範囲を広げる「イスラム国」が、米国人や英国人のジャーナリストを殺害する映像を公開するなど、国際社会を震撼させるようになった。それには、「イスラム国」を空爆する米国に対し、その停止を要求する“メッセージ”を送るとともに、“斬首”というショッキングな方法で自らの主張を世界に訴える目的があった。神の創造物である人間を殺害するのは、イスラムという宗教からは正当性を得られないが、「イスラム国」の行動は、イスラム本来の教義に背いてまでも強硬にとられている。
「イスラム国」は「イラクのアルカイダ(統一と聖戦機構)」から出発したものの、その大きな違いは、「アルカイダ」は米国や米国人に対する単発的なテロしか行わないのに対して、「イスラム国」は実際に、西はシリアの古都アレッポから東はイラクのティクリートまで統治を行なっている点だ。「イスラム国」は「カリフ(スンニ派における預言者ムハンマドの正統な後継者)」による統治を行い、イスラム法(シャリーア)を法基盤とする国家、イスラム国家の樹立を宣言し、その領土の維持や拡大を図っている。
それは、1990年代にアフガニスタンの「タリバン」が、国土の90%を支配して厳格なイスラム支配をしていたことと似ていて、実際の国家づくりをめざしている。「イスラム国」のメンバーたちのほとんどはスンニ派ムスリム(イスラム教徒)だが、その支配地にはマイノリティ(少数民族)を含むようになった。
「イスラム国」はマイノリティを弾圧したり、公開処刑したり、さらには少年兵がメンバーであったりするなど、人権侵害で人権団体から評判が悪い。しかも、公開処刑の様子をソーシャルネットで国際社会に配信するなど、故意に目立つショッキングな方法、“処刑”を行なっている。
2014年6月の「イスラム国」によるイラク北部の都市モスルへの進撃は電撃的で、サダム・フセイン政権崩壊後は政治・社会的安定を見せてきた「クルド自治区」まで、軍事的にうかがう様子であった。
これに衝撃を受けた米国は、「イスラム国」の急速な台頭の背景を検討した結果、米国が支えてきたイラクのヌーリー・アル・マリキ(マリキー)政権の腐敗ぶり、無能ぶりを認識することとなった。そして、マリキ首相に辞任を求めて“挙国一致内閣”をつくり、マリキ政権に対する反発が強かったスンニ派の人物を国防相に据えるなど、にわかに各宗派に対する権力の分配を考えるようになった。
2014年9月、マリキに代わって首相になったのはハイダル・アル・アバディで、これは米国からも、また米国と敵対するイラクの隣国・イランからも支持される人事であった。アバディは「ダワ(イスラムへの呼びかけ)党」に属し、フセイン政権時代はイランに亡命歴をもつ人物だが、米国はずっと警戒してきたイランと親しい人物を、マリキの次の首班に据えざるをえなかったのである。
「イスラム国」は2014年夏、シリアでも勢力を拡大し、反アサド政府軍が支配していたシリアの古都アレッポを中心にする地域を手に入れるようになったが、それは反政府軍にとっては、政府軍との戦闘能力を低下させるものであったことは疑いがない。米国CIA(中央情報局)の見積もりでは、「イスラム国」の戦闘員の数は3万人、そのうちの半数が外国人で、2千人が外国のパスポートをもっているということである。
「イスラム国」の最高指導者アブー・バクル・バグダーディは、2003年に米軍がイラクに侵攻すると、米軍との戦闘に身を投じていった人物で、現在の幹部たちとは、彼が拘束されていた米軍の収容所でネットワークを築いた。そのなかには、フセイン政権時代の軍人たちも数多くいた。外国人のなかには、ヨルダン人、チュニジア人、サウジアラビア人、チェチェン人などが含まれている。
トルコのエルドアン政権は、外国籍の武装勢力がシリア領内に入ることを黙認してきた。それはエルドアン政権が、2010年に入り「アラブの春」が訪れると、アサド政権が崩壊することを考えるようになったからだ。シリアで「イスラム国」のメンバーとして戦っていた日本人の元自衛官は、トルコ経由でシリアを出入りしたし、私戦準備罪容疑で逮捕された日本人の北大生も、トルコからシリアに入国することを計画していた。
トルコやサウジアラビアのような米国の同盟国の思惑もまた、米国に対して牙を剥く「イスラム国」の台頭につながった。実際、トルコのエルドアン大統領の風刺画には、シリアに武装集団を送り込む一方で、シリアのクルド人難民の入国を拒む大統領の姿が描かれている。
米国内のネオコン(新保守主義者)は、オバマ政権の「イスラム国」への対応が手ぬるいと批判し、2011年末に米軍がイラクから撤退したことが誤りであったと指摘するが、そもそも「イスラム国」は、サダム・フセイン政権の崩壊がなければ、その誕生も活動の展開もなかった。フセインの独裁体制は、よくも悪くもイラクに政治的安定をもたらしていたのである。
イスラム法は、殺人に対して現世と来世における罰を規定する。殺人を改俊しない場合は、来世において殺人者は永久に火獄に住むことになる[『クルアーン(コーラン)』第四章九十三節]。現世においては、意図的殺人に対しては同書の報復刑(死刑)が科せられることになっている(『岩波イスラーム辞典』)。
こうしたイスラム法の規定を考えると、「イスラム国」の暴力の抑制や停止については、イスラムの聖職者の影響力の発揮など、イスラム世界内部の役割も大いに求められるものであるが、2013年10月に国連の潘基文事務総長は、国連と「イスラム協力機構(The Organization of Islamic Cooperation: 57カ国のイスラム諸国が正式加盟/旧・イスラム諸国会議機構)」との連帯を強く呼びかけた。潘事務総長は、過激主義が成長する背景を分析することの重要性と、宗教間の対話が強く求められていることを述べた。イスラム世界安定のために、その自助努力を他の国際社会が促し、後押しすることが、現在、最も必要とされている。
2014年9月3日、米国のオバマ大統領は「イスラム国」を根絶するという決意を述べたが、軍事的行動で過激派や武装集団の活動を“根絶”することは不可能で、暴力のいっそうの増殖をもたらすことは、2001年に始まった「対テロ戦争」が証明している。米国やその同盟国が過去の教訓に学ぶべきであるということは、いうまでもないだろう。
「イスラム国」のような過激な集団の成長を封じるためには、欧米社会におけるムスリムの若年層の疎外感や格差の是正に加え、イスラエルによるパレスチナの占領や入植地の拡大、ならびにパレスチナ・アラブ人への人権抑圧をやめさせるとともに、そのイスラエルを米国が偏って支持することや、イスラム世界に欧米諸国が軍事的に介入することを、抑制・停止する必要がある。国際社会にはまず、それらを自覚することが強く求められている。
イギリスもイラクの「イスラム国」への空爆に参加しているが、国内には「イスラム国」に心情的に共鳴するムスリムの若年層もいて、長期的に見れば、「イスラム国」への攻撃は国内のムスリムたちの急進化をもたらしかねない、というジレンマもある。
2014年6月に大統領選の決選投票があったアフガニスタンでは、選挙への不正な操作が指摘され、次期大統領もなかなか決まらず、米国がタリバン政権を打倒したのちの国づくりがまったく順調でないことを示した。またタリバンのなかにも、「イスラム国」との協調を訴える勢力も現われはじめた。米国の「対テロ戦争」はイスラム世界の「パンドラの箱」を開けてしまった感があるが、米国にはその蓋を閉じるための有効な方策がまったくない状態だ。
武装集団「イスラム国」の急速な台頭で、イラク・シリア情勢がいっそう混迷するようになった。「イスラム国」はイラクの少数宗派やシリアのクルド人などに対する抑圧を強め、その結果、大量の難民が発生するようになり、その対応を迫られるトルコなどの周辺諸国は警戒を強めている。また米国のオバマ政権も、イラクとシリアの「イスラム国」に空爆を行うようになったが、その“根絶”のための作戦にはまるで出口が見えず、米国がイラクやシリアで空爆を行なっても、「イスラム国」には弱体化の兆しが見られない。
本書は、米国はなぜ 「イスラム国」に勝てないのか、「イスラム国」が台頭した背景やその活動の現況、米国の中東イスラム世界政策失敗の要因を明らかにするとともに、米国の中東における同盟国であるイスラエルが、いかに米国のイメージをイスラム世界の若者たちのあいだで曇らせているか、などの問題にも触れつつ、いよいよ混迷を深める中東情勢を、米国と「イスラム国」が対時する構図のなかで捉えるものである。
<著者紹介>
宮田律(みやた・おさむ)
現代イスラム研究センター理事長
1955年、山梨県生まれ。慶應義塾大学文学部史学科東洋史専攻卒。1983年、同大大学院文学研究科史学専攻修了後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院修士課程修了。1987年、静岡県立大学に勤務し、中東アフリカ論や国際政治学を担当。2012年3月、現代イスラム研究センターを創設した。著書に『現代イスラムの潮流』(集英社新書)『イスラムの人はなぜ日本を尊敬するのか』(新潮新書)『イスラムの潮流と日本』(イースト新書)などがある。