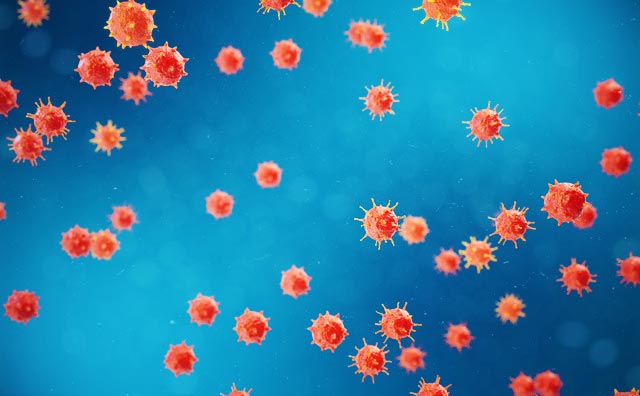中国人はつらいよ―伝統からその実像を知る
2015年03月09日 公開 2024年12月16日 更新
《PHP新書『中国人はつらいよ-その悲惨と悦楽』より》

元気な中国人
中国文学の研究にたずさわり、長年にわたってしばしば中国にも行き、多くの中国の友人たちとつきあってきた。総じていえることは、中国の人々は元気である。パワーがあるといってもいいし、しぶといといってもいいかもしれない。少なくとも決してひ弱ではない。そして、時に文句をいいつつも、日々を前向きに、楽しそうに生きている。これまで暗い印象の中国人を見たことはあまりない。実は、みなかなり厳しい状況のなかで生きているように思われるにもかかわらずである。
ことを作家に限っても、日本の近代文学の作家たちには、北村透谷あたりを先頭に、芥川龍之介、太宰治、川端康成と、自殺した作家たちが目白押しである。ところが、中国の作家を見ると、暗殺されたり虐殺されたりといった作家は少なくないものの、自ら命を絶った作家は数えるほどしかいない。『駱駝祥子』や『四世同堂』などの小説で知られる老舎は文化大革命のさなか、みずから命を絶ったとされているが、一方で暗殺説もある。多くの知識人にとって、反右派闘争から文化大革命の時代、当時として最高のインテリたちが、あるいは労働改造と称して工場や農村に送られ、慣れない肉体労働を強いられ、あるいは監獄に送られるなど、どれだけ過酷な生活を強いられたか、想像にあまりある。しかし、それでも彼らの多くがこの時代を、絶望してみずから命を絶つこともなく生きのびたのである。
中国の人々は、なにゆえにかくも強靭であり、前向きなのであろうか。文化大革命などの時代は、ある意味例外的な時代であったといえるかもしれない。だが、中国で実際に暮らしてみると、ごく日常的にもなかなかしんどい世界かもしれないのである。
筆者がはじめて中国を訪れたのは、大学生時代の1979年。その当時は、1972年の日中国交回復後の日中蜜月時代ともいえ、友好ムードのまっただなかであった。この時代、まだ個人旅行は認められず、大学の中国文学の研究室で組織した団体に参加しての中国行きであった。夕暮れにはじめて到着した北京空港では、タラップを降り、歩いて空港ビルへ。入国審査場の明かりが裸電球1つであったのが、妙に印象的であった。このときには、北京、天津などいくつかの都市を巡って、最後は上海から帰国したが、いまから思えば中国のいいところしか見えないしかけになっていたとみえ、印象はとてもよかった。逆にいえば、表面しか見せてもらっていなかったということか。
その後、大学院時代の1984年、上海の復旦大学に留学し、1年間を実際に中国で暮らすことになった。1984年といえば、もちろんまだ友好ムードの時代ではあったが、今回はいかんせん、お仕着せの団体旅行とはちがい、何といっても自分で生活しなければならない。復旦大学は上海の東北郊にあるが、そこから市の中心に出ようとすると、相当長い時間、殺人的なまでにぎゅうぎゅう詰めになったバスに揺られて行かなければならない。町で何かしら買おうと思って、何々はあるか、と聞けば、木で鼻をくくったような「没有(メイヨウ:ない)」の返事。たまたま買いたいものがあって、買おうということになれば、なにやら紙切れを渡され、あっちへいって金を払ってこい、となる。代金を払えば、釣り銭をぽいと投げてよこされる。支払い済みのはんこを押してもらった紙を持って行き、ようやく物が手に入る。これなどは、社会主義ゆえと考えられないこともないが、紙を持ってあっちへ行き、こっちへ行くというのは、むかしの役所でも同じことが行われていたようでもある。
旅行に出ようなどと思えば、それまた一苦労。切符1枚を買うために、切符売り場の窓口の前に大行列。そしてそこには必ず割り込もうとする手合いがあり、窓口は大混乱になる。一事が万事。この国で暮らすのはなかなかたいへんだと思ったものである。列車に乗るときも、降りる人が降りてから乗ればいいものを、みんなが降りる前に乗り込もうとするから、いつまで経っても乗れないし、降りられない。人のことになんかかまっちゃいられない、オレがオレが。これもまた、元気な中国人と、どこかでつながっているのかもしれない。
中国における生活のしんどさ、そして前向きで明るい彼ら、そうした状況やメンタリティーは、いったいどこに源流があるのであろうか。
筆者の専門は、明清時代を中心とする中国の文学である。この時代の文学作品を見ていると、現代に通じる問題の源流を見ることもできるようである。本書においては、主として明清の資料を材料に、こうした驚きのもとをさぐってみたい。
中国人の遊びの哲学─悲観から楽観へ
「暗い中国人」「くよくよと悩む中国人」はあまりいない。中国人はつらいことがあっても物事を楽観視しようとする。有名な蘇軾「前赤壁の賦」も、実は悲観にあらざる楽観を述べている。
何ぞ燭を秉りて遊ばざる
さてここまで、中国で生活するのはたいへんだ、そして中国の文学は、不平不満から生まれている、といった悲観的なことばかりを述べてきた。それはまちがいではない。しかし、先にも述べたように、実際に中国に行って中国人の生活ぶりを見てみると、みんな妙に元気があって、何より人生、生活そのものを楽しんでいるようにも見える。この両面性はいったい何であろうか。今度は、その生活の楽しみの方に目を向けてみよう。文学についても、遊びを語る文学がないわけではない。
遊びといってもさまざまな背景がある。まずはこのような作品を見てみよう。漢代の「古詩十九首」の1つである。
生年百に満たず
常に千歳の憂いを懐〈いだ〉く
昼の短くして夜の長きに苦しむ
何ぞ燭を秉〈と〉りて遊ばざる
楽しみを為すには当〈まさ〉に時に及ぶべし
何ぞ能く来茲〈らいし〉を待たん
愚者は費〈あたい〉を愛惜して
俱〈とも〉に塵世の嗤いと為な る
仙人王子喬
以て期を等しくすべきこと難し
中国では人生百年という。人生百年とはずいぶん長いようであるが、人の寿命はどんなに努力したところで3桁の数字にはならないとの意味で、結局、人生は短いことをいう。そんな短い人生なのに、人は毎日まるで千年分もの心配事を抱いて暮らしている。しかも1日の時間のうち、活動できる昼の時間は短く、何もできない夜の時間ばかりが長い。そういうわけだから、楽しむべき時には、その時を逃さないように、夜も灯りをつけて遊べばよいではないか。
2000年も前の話である。当時の人々はだいたい夜明けとともに起き、日没とともに床に入った。したがって遊び、この場合は宴会といっても、ふつうはお日様のあるうちのこと。夜になってまで酒を飲んでいるのは、ずいぶんぜいたくでもあり、だらしない話なのであった。
さて、楽しめる時には徹底的に楽しもう。夜に酒を飲んだっていいではないか。楽しめる時間を無駄にしてはいけない。こういった考えは、一見楽天的な考え方のように見える。しかし、その背景にあるのが実は「何ぞ能く来茲を待たん」、つまり来年の楽しみを待つことはできない。それは1つには人生が短く、明日にも死んでしまうかもしれないからであり、1つには未来にあるより大きな楽しみのために、現在の楽しみを我慢してもしかたないことがわかっているからである(未来のために貯金しておいたところで、何の意味もないではないか)。仙人の王子喬のように長生きできればよい。しかし、そのようなことは絶対に不可能だとわかっている。そこから、今を楽しめというこのテーマが生まれているのである。短い人生、しかも憂いの多い人生なのだから、楽しめる時には楽しまなければいけない。楽しみの背後に悲観的な人生観があるのである。
死をみつめながら
明末清初の人で、生活を楽しむための美学の教科書である『閑情偶寄〈かんじょうぐうき〉 』を書いた李漁(1611〜1680頃)も、『閑情偶寄』「頤養部〈いようぶ〉 」の序文で次のように述べている。『閑情偶寄』もまた本書でこれからしばしばのぞいてみたいと思う書物であるが、頤養部は、健康法を述べた一節である。
悲しいことだ。造物主は人を生み出したが、その時間は百歳に満たない。若死した人たちについてはいうまでもないが、長生きしたものについてみても、三万六千日すべてに歓楽を求めたとしても、無限の時間があるわけではなく、ついには終わりの日が来るのである。ましてやこの百年の中には無数の憂いや苦しみ、病気があり、名利にしばられ、風波に驚かされて、宴遊が拒まれている。たとえ百歳という虚名があったとしても、幸福な時間は一年二年分くらいしかないのである。ましてや、この百年の間に、毎日のように人々の死が告げ知らされてくる。自分より先に生まれたものが死に、自分より後に生まれたものも死に、自分と同い年のもの、互いに兄弟と称していたものが死んでゆく。ああ、死とは何者であろうか。不吉であり忌避されることであって、毎日死んでいない者をして目で驚かせ、耳で恐れさせることなのであろうか。そのような死を準備するとは、千古の不仁、造物者のそれよりひどいものはない。だが一説に、不仁とは仁の極致である。わたしがかならず死に、毎日人々の死を聞かされるのは、わたしを恐れさせるためである。わたしを恐れさせるのは、楽しめる時には楽しめということで、この輩を前車の教訓とすべきだからなのである。康対山(康海)は園亭を築いたが、その場所は北邙〈ほくぼう〉山麓(洛陽郊外の墓地として知られる)にあって、見えるのは墓ばかりであった。客がたずねた。「毎日こんな景色を見ていて楽しいのですか」。対山はいった。「毎日こういう景色を見ているからこそ、楽しまないわけにはいかないのだ」。この言葉は至言であって、わたしはこれを座右の銘にしている。ここに養生の法について論ずるが、行楽を先にする。人に行楽を勧めるのに、死によって恐れさせようとするのは、その意にならったのである。天地至仁の心を体しようとすれば、造物者の不仁の跡を踏まないわけにいかないのである。
人間いずれはまちがいなく死ぬのだから、楽しめる時には徹底的に楽しまなければならない。これもまた、悲観的といえば悲観的な楽しみの哲学である。
<著者紹介>
大木 康(おおき・やすし)東京大学東洋文化研究所教授
1959年横浜生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程(中国語中国文学専門課程)単位取得退学。博士(文学)。東京大学東洋文化研究所助手、広島大学文学部助教授、東京大学東洋文化研究所助教授を経て現職。2012年4月から14年7月まで、同東洋文化研究所所長。専門は中国明清時代文学。
著書に『不平の中国文学史』(筑摩書房)、翻訳書に『山の郵便配達』(集英社文庫)、『現代語訳 史記』(ちくま新書)など。
<書籍紹介>
 中国人はつらいよ――その悲惨と悦楽
中国人はつらいよ――その悲惨と悦楽
伝統から彼らの実像を知る
大木康著
本体価格780円
中国人は生きづらい。その反面、彼らは人生を愉しむ達人でもある――。中国人のタフさや洗練された享楽主義の根源を歴史的に辿る。