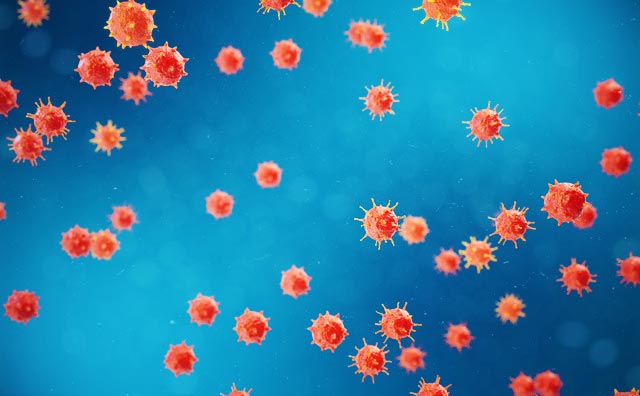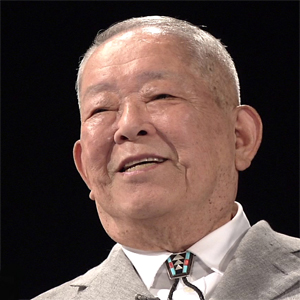ノバルティス事件・なぜ、臨床データの不正はおこなわれたのか
2015年10月08日 公開 2024年12月16日 更新
なぜ、やめられないのか?
研究費というのは魅惑的な力をもっている。その額(大きなケタの研究費)は魅力的な力の1つではあるが、すべてではない。
ノバルティス社の不正は、主として金儲けを主目的とする企業のなかの個人による暴走的行為であり、研究者の不正という概念から言えば、取るに足らない問題である。ただこの問題のなかに、「なぜ不正をするのか、やめられないのか」という問題に対する重要なヒントが隠されていると考えられる。
研究者らが不正行為をし、それがやめられない理由は、大きく分類して「研究費獲得」と「キャリアパス」の2種であろう。それらはさらにいくつかの小分類に分けられる。まずは研究費獲得から説明しよう。
俗に「研究費」と呼ばれるものには、公的な(税金を使う)ものと、私的な(民間による)ものとが存在する。わかりやすい例として、理研の小保方氏の研究費は公的、ノバルティス社が支出したのは私的である。
このうち、文科省による科学研究費(名目上は日本学術振興会からの補助金)は公的研究費の代表格であるが、ほかにもいくつか公的な研究費が存在する。まずは、公と私の2種があることを知っておいてもらいたい。
公的研究費の最大の問題点は――税金を使う以上、当然ではあるが――こまごまとした書類仕事がわずらわしいことである。会計規準は言うにおよばず、旅費規程、アルバイト代、会食の規準、許される費目とそうでないものなど、かなり細かく決められており、流動性(費目間の流用可能性)も低い。
通常は、研究費の管理専用に人員を張りつけないとこなしきれない。大学には間接経費として何パーセントかが収入として入るが、それを除く科学研究費はいちおう大学が管理するだけで、大学の収入とは見なされない。
もう1つの問題点として、科学研究費などの公的支出は、通常1年間、長くても2年までの研究計画が対象であることがあげられる。短期間ですむ研究もないわけではないが、遺伝情報や成長記録を長期的に観察するタイプの研究など、1年や2年の単位では十分でなく、少なくとも10年単位が望ましいものも少なくない。医療の副作用や臨床、現地調査が必要な発掘(考古学)調査なども、やたら長時間軸が求められる分野である。
前出の杉晴夫氏は、時間的に「追いつめられた(であろう)」大学研究者の立場を、以下のように説明する。
(1)幸運にも研究費の配分にあずかった研究者(特に、研究履歴の短い若い研究者)は、「成果をただちにあげねばならない」という重圧を感ずる。
(2)政府の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月末日に終わる。しかしすでに述べたように、実際の研究費が大学に交付され、研究が可能になるのは、6月である。つまりこの年度の最初の2か月は研究の空白期になる。
(3)研究者の研究成果の報告は、筆者の経験では研究費交付年度の11月ごろである。つまり、研究者が研究成果をあげるための期間は半年に過ぎない。
(4)もし研究者が研究費交付の初年度内に学術誌に論文を発表し、研究能力の高さを示そうと思えば、研究期間はさらに短くなる。なぜなら論文を学術誌に投稿し受理され、実際に出版されるまでには、1か月単位で時間がかかるからである。
(杉晴夫『論文捏造はなぜ起きたのか?』〈光文社新書、2014年〉)
このプロセス1?4には続きがあり、それについてはあとでもう一度紹介することにするが、1年間の公的研究費で結果を出そうとする研究者のあわただしさがどんなものかがよくわかる記述である。
現在では2年間という縛りは緩和されつつあるものの、時間軸が比較的ゆるやかな民間の研究費が重宝されるのは自然なことなのである。民間資金の場合、研究期間は契約によるが、多くのケースで研究者の意向が尊重される。
科学研究費の書類上、多くの研究者が「もっともわずらわしい」と感じるのは、与えられた金額をその年度内に使い切らなければならない点である。たとえば、学会が4月に開かれるケースなら、3月までに振り込むのが普通だが、旅費などを前年度の費用に計上することは不可である。
これがアメリカのNSFだと、「研究費の20パーセントまでは次年度に繰り越し可能である」(『論文捏造はなぜ起きたのか?』)と、杉氏は述べている。単年度会計が基本で複式簿記すら存在が危うい国公立大学ならではの融通のなさであるが、これくらいの会計処理すらできないのだろうか。それとも、わざと使いにくいシステムにしているのであろうか。
1つの研究成果を出し、有名な学術誌に論文が掲載されることは、次の研究費――公であれ民であれ――の獲得を容易にする。ところが、もし、(失礼な言い方だが)二流の学術誌にしか掲載されないなら、次の研究費の獲得には暗雲が立ち込めることになるかもしれない。したがって、ほとんどの研究者にとって、まずは一流どころをめざすことになるわけであるが、よほどインパクトのある内容でなければ、一流どころには採用されないというジレンマがある。そこに不正の芽が存在するのである。
<著者紹介>
谷岡一郎(たにおか・いちろう)
1956年、大阪生まれ。1980 年に慶應義塾大学法学部を卒業後、1983 年南カリフォルニア大学行政管理学修士課程を修了。1989 年社会学部博士課程を修了(Ph.D.)。大阪商業大学教授を経て、1997 年大阪商業大学学長、2005 年学校法人谷岡学園理事長。専門は、犯罪学、ギャンブル社会学、社会調査論。
著書に『ギャンブルフィーヴァー』(中公新書)、『「社会調査」のウソ』(文春新書)、『ツキの法則』『ラスヴェガス物語』(以上、PHP 新書)などがある。