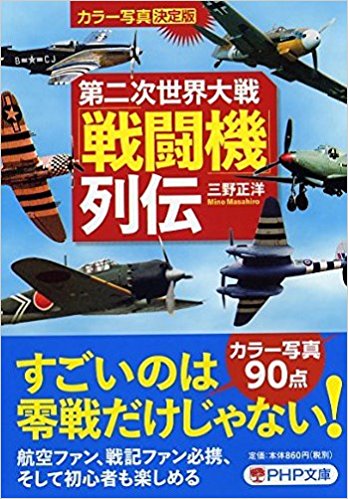零戦の栄光と挫折をもたらしたものとは何か?
ともあれ、本記事では、零戦について語りたい。
日本でもっとも広く国民に知られた兵器は、言うまでもなく戦艦大和、そして零式戦闘機、通称〝零戦〟である。紀元2600年、つまり昭和15年、1940年に制式化されたこの戦闘機は、当時にあって最新の技術が盛り込まれた日本の航空界の結晶とも言えるものであった。
これは単に設計という観点だけではなく、材料工学のうえからも注目に値する。ESDと呼ばれた高張力アルミの導入をはじめ、目に触れないところにも我が国の先端技術が取り入れられ、さらに強力な20mm機関砲、落下式の増加燃料タンクも実質的に世界で初めて装備されている。
開発の途中では2度の空中分解という事故も起こしているが、海軍は粘り強く本機を育てていった。
この点が同じエンジンを装備しながら、古い思想にとらわれすぎて、開発途上で1年半も放置されていた陸軍の一式戦隼と異なる。
零戦は39年4月に初飛行に成功、翌年の夏には中国大陸の戦場に登場するなど、着々と実績を挙げる。
中国空軍のソ連製戦闘機を相手に格の違いを見せつけ、勝利を重ねた。
この理由は、旋回性能、速度の優位に加えて、長距離飛行性能にあった。
言い換えれば滞空時間が長いということであり、操縦者は余裕をもって空中戦を戦うことができた。英独のバトル・オブ・ブリテンの空中戦では、メッサーシュミットの操縦士たちは、はじめから終わりまで燃料の消費を心配しながら戦わなければならなかった。
なにしろ零戦とメッサー109の航続力の違いは、3700キロと700キロなのである。この長大な航続力は、開戦初頭の航空戦でも大いに役立った。
さて戦争が始まって半年の間、零戦は太平洋狭しとばかり暴れ回る。北はアリューシャン、南はオーストラリアまでアメリカ陸海軍機、イギリス空軍機を相手に、勝利を重ねていった。

当時、この戦闘機の名は、アジア、太平洋のアメリカ、イギリス軍に畏怖をもって広がっていったのである。まさに零戦が光り輝いた時代であった。
これには多くの理由が考えられるが、具体的には俊敏な運動性、長距離飛行性能、操縦士の技量などである。
しかし一言にまとめれば、欧米諸国の「技術的に大きく遅れているはずのアジアの人々、または有色人種に、自分たちに対抗できる兵器、なかでも技術の頂点に位置する戦闘機など造れるはずはない」という思い込みにあったと思われる。
つい十数年前までは、教師として日本人に技術を教えていたのであるから。
さて42年6月のミッドウェー海戦の敗北にもかかわらず、南太平洋方面における零戦の活躍は続いていた。
しかし思いもかけない形で、暗い影が忍び寄っていた。それは8月から勃発したソロモン諸島ガダルカナルの戦いの状況であった。これは海軍の大基地ラバウルから1000キロも離れた島が、アメリカ軍による反撃の拠点になったことによる。
海軍の上層部は、「それが可能であるから」として、遠路はるばる零戦隊をこの島を巡る戦いに送り込む。これが海軍戦闘機隊の過大な負担となり、多くの零戦とその操縦士を失う原因となった。
1000キロといえば、東京から屋久島までの距離に相当する。ラバウルを離陸した零戦は1000キロの距離を3時間半かけて飛び、アメリカ機と空戦を行ない、その後同じ時間をかけて同じ距離を帰投しなければならない。
初期の段階では中継基地がないから、機体の損傷、パイロットの負傷となれば、必然的に未帰還となる。
一方、相手のグラマン戦闘機は、自軍の基地の上空で戦うので、あらゆる点で余裕がある。このことから、ガダルカナルを巡る戦闘は、零戦にとって圧倒的に不利となり多くの損害を出してしまった。
現代においては、大企業の優秀な社員が、その能力ゆえに過大なノルマを強いられ、精神的、肉体的に追い詰められていく状況とよく似ている。
零戦の優れた長距離飛行性能が、かえって負の結果を招いたのである。
さらに空中戦のさい、旋回戦闘では不利と悟ったアメリカ軍戦闘機が戦術を変更し、いわゆる〝ヒット・エンド・ラン〟、つまり一撃離脱を重視し始めると、零戦の優位は徐々に揺らいでいった。
それでも43年、44年前半の戦いでは、まだまだ零戦は活躍する。攻守が入れ替わったラバウル基地の攻防戦では、今度は日本側が基地上空で戦うことができ、侵攻してくるアメリカ軍機を迎撃、かなりの損害を強要している。
ただし44年の初夏に至ると、アメリカ海軍にはグラマンF4Fに代わり、新鋭F6Fヘルキャットが大量に投入される。エンジン出力は零戦の2倍という大型で強力な戦闘機である。
しかも日本側がまだ持っていない、高性能レーダーの管制に誘導されて戦うのである。これにより一時は太平洋の覇者の名をほしいままにした零式戦闘機は、完全に旧式化したのであった。武装と装甲を多少強化した後期型の零戦であっても、エンジン出力はそのままであるから、大幅な性能向上などあり得るはずはなかった。
あとはあらゆる面で圧倒されていくのみである。さらに熟練した操縦士と燃料の不足が輪をかけていった。それでも後継機であるはずの川西紫電が故障続出で使い物にならず、旧式化した零戦はあいかわらず先頭に立って戦わざるを得なかったのである。
44年の秋の終わりからは、250キロ爆弾を抱えた特攻機となり、次々と消耗していった。
先に述べたとおり、零戦の運命は大日本帝国のそれとまったく同じであったことになる。
さてもう一度、この戦闘機に関する技術論に戻ろう。
零戦は装甲が充分ではなく、被弾に弱いという点に関してはそのとおりであろう。しかし航空機の設計とは、結局のところ妥協の産物であると思う。航続力を増すため搭載燃料を増やせば、その分重量がかさみ、装甲がおろそかになる。このあたり、技術者は充分理解して、設計に取り組んでいるはずである。
またもう一つの問題点は、エンジンの出力が低いままであった。
最初のタイプでは940馬力、強化されてもわずかに1140馬力で、これでは続々と登場するアメリカの新しい戦闘機にとうてい太刀打ちできない。
早くから1500馬力の金星(発動機名)に換装すべきであった。これができなかった理由は、一般に言われているように機体の強度の不足ではなく、生みの親の三菱の技術者不足に起因している。
陸軍の三式戦飛燕は、発動機をハ140に換装して五式戦となり、これは極めて優秀な戦闘機と評価されている。このハ140は、金星と基本的に同じエンジンなのである。こう考えると、金星付きの零戦は、最終的には敗れる戦争であったとしても、最後まで第一線で、それも緒戦に近い形で活躍できたものと思われる。
もちろん海軍としても、当然この改造を考慮しなかったわけではなかったが、技術者不足により試作型の2機が誕生しただけで終戦を迎えてしまった。
それにしても日本人の技術の集大成であるこの戦闘機の飛行する姿は、兵器であることを忘れさせるほど美しい。このように感じるのは、日本人よりも欧米の人々であるように思える。
兵器、武器が生まれる段階で、“美”とはまったく無縁であるのは当然だが、そのもの自身また造り出した人々が意識していないだけに、ますます美しく見えるのである。これは多くの博物館で展示されている、日本刀にも通じるのではあるまいか。
たぶん、今後、幸運にも日本各地で零戦の飛ぶ姿が見られるようになると思われるのだが、ぜひ一度自分の目で確かめてほしい。
またアメリカでは、飛行可能な“ゼロ”が5機まで増え、大きなエアショーであれば、かならずフライトする旨を記しておく。
※本記事は、三野正洋著『第二次世界大戦「戦闘機」列伝』より、その一部を抜粋編集したものです。