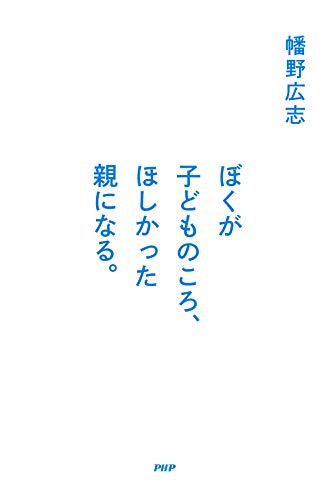父、35歳、末期がん。2歳の息子からの贈り物
2018年12月21日 公開 2024年12月16日 更新

<<末期ガン、余命3年の宣告を受けるも、精力的に発信を続ける写真家の幡野広志氏。幡野氏は言う。「34歳でガンになるとは考えていなかったけど、ガンになって本を出版することになるとは夢にも思わなかった」
そして、「一時期は自殺を考えるほどの苦しみがあったけど、僕は今、人生で一番穏やかで幸せな時間をすごしている」と続ける。
処女作の『ぼくが子どものころ、ほしかった親になる。』は、家族を持つひと、持たないひと、失ったひと、これから新しい家族を迎えるひと……SNS上には多くの感想が寄せられた。本書のメッセージでもある「幸せ」について、同書の一説から紹介する。>>
※本稿は幡野広志 著『ぼくが子どものころ、ほしかった親になる。』(PHP研究所)より一部を抜粋し、編集したものです
死ぬことを引き受けた、祖父についた嘘
僕がガンになって間もない冬、92歳になる妻の祖父が入院した。
おじいちゃんの生きがいはずっと畑仕事だったから、妻の妊娠も畑仕事の合間に告げた。ひ孫が生まれるという知らせに、おじいちゃんは本当に幸せそうだった。
息子が生まれるころには、おじいちゃんは畑仕事をやめていた。「その年で農作業なんてやめて。もう危ない」と家族に止められたからだ。
若々しいおじいちゃんは生きがいをなくしたことで、どんどん老いていった。そしてついに、入院してしまったのだ。おじいちゃんにとっては、畑の上で死ぬことが幸せだったのではないだろうか。
僕と妻が優と一緒にお見舞いに行くと、おじいちゃんは僕の顔を見るなり
「幡野さんは大丈夫か? 心配だ」と涙を流した。
おじいちゃんは何も知らされていなくても、死を覚悟しているのだろう。
死ぬことを引き受けた人間は、自分のことよりも残る人のことが心配になるものだ。
おじいちゃんはもう覚悟していると、僕にはよくわかる。
耳の遠いおじいちゃんに「僕もすぐ逝いくから、あの世で会おうね.」と大声で言ったら、看護師を含めた全員から、白い目で見られた。
僕はあの世なんて信じていないけど、少しでもおじいちゃんの不安が薄まればと思って言った嘘だった。
同じ嘘なら「安心して。僕のガンは治りそうだよ」と言えば良かった。
どちらにしても後悔が残りそうな嘘だし、遺族というのは後悔からは逃げられないのかもしれない。
次のページ
なにが「幸せ」か、どんな治療をするかは、患者に残された最後の権利