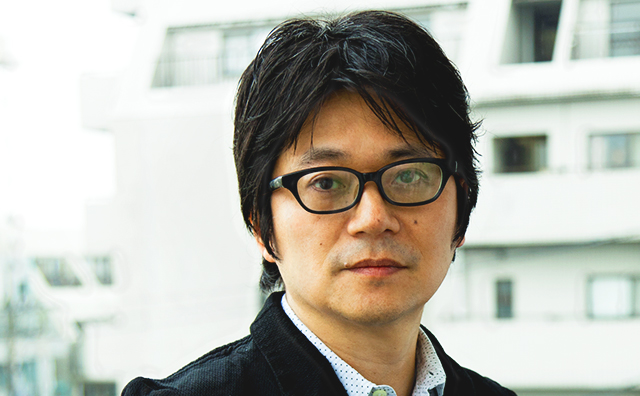小説家になった国家公務員 仕事を辞めて手に入れたもの
2019年03月11日 公開 2024年12月16日 更新

職業に拘りがなかった
僕に特徴的なことがあったとすれば、それはつまり、みんなが拘っていることに僕は拘らなかった、という点くらいだろう。
せっかく勤め上げて、業績も挙げて、周囲との関係も構築されてきたのに、僕はそういったものに拘る気持ちがなかった。周囲からの評価が、僕にはあまり影響しない、ということもあったと思う。
常々僕は考えて、いつも自分の好きな道を選ぶ。どうすれば、将来の自分が喜べるか、楽しめるか、と考えて判断をしている。人からどう見られるか、みんなはどうしているか、普通はこうする、これまではこうだった、というようなことに影響されない。
否、影響されないのではない。考えなければ、影響される。そういった既往の圧力に従わざるをえないだろう。現に、世間の人の多くは、周囲の空気を読んで、それに従っているように見える。
子供のときから天の邪鬼だったから、既成路線を外れるためには、自分の理屈を持つしかなかった。たとえ、それが屁理屈だといわれてもかまわない。自分を納得させることができれば、そちらの道を選ぶことができる。考えることで、空気に逆らうことができるのだ。
そういう意味では、僕は実に「拘り屋」だったのである。自分の理屈に拘った。僕にしてみれば、いろいろなものが既に決まっていて、自分が好きに選べない不自由さがあった。
世間というのは、なにもかも「こうしなさい」という「普通」が定められているように見えたのだ。その選択をすれば、みんなの仲間にはなれるけれど、自分らしさは薄れてしまう。なんとか、それに反発することで、自分に拘った、といえる。
それが、四十歳になって、座右の銘として、「なにものにも拘らない」という言葉を選んだのだから、これまた、自分の本来の性格に反発したともいえるのだ。拘り屋だったからこそ、拘らないようにしよう、と考えた。
ある意味では、歳を取って「丸くなった」とも取れるだろう。しかし、そうではない。
作家になったことで、僕はそれ以前に比べて自由になれた。研究者だった頃も、世間一般からすれば自由だったかもしれない。
でも、時間的にも経済的にも、それまでは拘束されていた。子供たちも小さかったし、僕の両親も存命だったから、そういった家族にも縛られていた。これは、今流行の「絆」かもしれない。絆とは、家畜を縛っておく綱のことである。
四十八歳のときに大学を辞めた。これは、作家として稼いだ金が、生涯生きていく充分な金額になったからだ。子供たちは成人して独立したし、また両親もその頃に二人とも他界した。
ほぼ同時に、作家の仕事も縮小して、半引退のような立場になった。