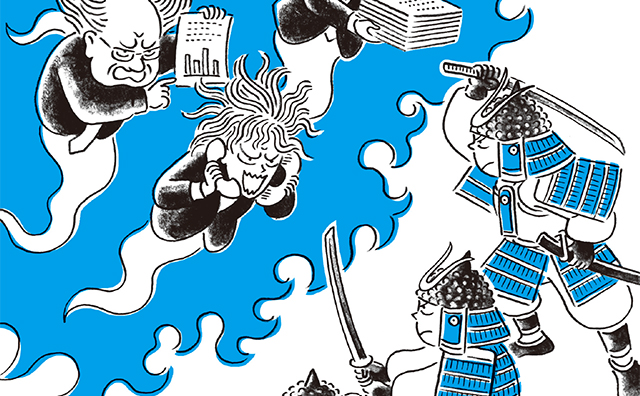なんとなく定例で開催。とりあえず部署の全員を招集。ほとんどの人が内心「本当はいらない」と思っているのに習慣化してしまった会議ほど、ムダなものはない。
世にはびこる目的不在の会議のムダを指摘するのは、日本マイクロソフト業務執行役員としてPowerPointやTeamsなどOfficeビジネスの責任者等を務めた経歴も持つ、株式会社クロスリバー代表取締役の越川慎司氏。
同氏はアンケートや作業記録の解析による「ムダの数値化」や、累計8000時間におよぶ会議の観察を通して、これまで623社の会議改革を支援してきた。
本稿では、越川氏の新著『超・会議術~テレワーク時代の新しい働き方』より、ムダな会議を減らす意外なポイント、「適切な参加人数の設定」や「参加者を招集するときの工夫」について触れた一節を紹介する。
「適切な参加人数」を考える4つの基準
会議で適切なアウトプットを効率的に得るためには、参加する人数が大きな要因となります。会議の適切な参加者数は、次の4つの基準によって見つけ出すことができます。
【1.参加者全員に意見を求めるか?】
人は集団で作業をする際に、関わる人数が多いほど1人当たりの生産性が低くなります。この現象を心理学者のビブ・ラタネは、「社会的手抜き」と名づけました。
例えば大勢で重いものを持つ時、人数が多いほど1人当たりが発揮する力は低くなります。これは、周りに人が増えれば増えるほど、自分の責任感が低下し、「がんばっても評価されない」「さぼってもわからないだろう」という心理状態になるからです。
参加者全員にアイデア出しを求めるブレインストーミングや、意思決定を目的とした社内会議の場合、1人当たりの生産性は大きな意味を持ちます。
そのため、「社会的手抜き」が発生する状況を避けなければいけません。弊社で19社385件の会議を調査した結果、参加者数を7名以下にすることで「社会的手抜き」を避けやすくなることが判明しました。
メール履歴とAIによる分析でも、参加者が7名以下の場合、会議中に他の仕事をしている可能性が67%下がることが判明しています。参加者全員の積極的な参加が必要なブレインストーミングやグループワークでは、7名以下のグループで作業をさせるのが効果的です。
オンライン会議でも、ブレイクアウトセッション機能を使って各グループで話し合う際には、7名以下のグループを作るようにしてください。
【2.すり合わせを要する会議であるか?】
社内の各組織は、機能やミッションごとに分かれており、だからこそ分業によってビジネスを回すことができます。その一方、組織ごとにミッションやリーダーが異なるため、意思決定には組織間の調整が必要になります。
会社の規模が大きくなればなるほど、そして意思決定プロセスが階層化すればするほど社内会議が増えるのは仕方がないとも言えます。しかし、こうした社内調整に膨大な時間を費やすのはナンセンスです。
そこで、社内の調整や交渉を目的とした会議は、9名以下でセットしてください。人数が多くなれば様々な意見や思惑が出る可能性が高まり、結論が出なくなります。交渉ごとは、相手の表情を見ながらの方が進めやすいものです。
オフィスの会議室であっても、オンライン会議であっても、参加者が9名以下であれば全員の表情が見えます。オンライン会議サービスで、初期設定でビデオの表示数が9になっているものが多いのも、そのためでしょう。
また「意思決定」の会議は、人数よりも、決定する人が本当に集まっているかどうかが重要です。本当に必要な、最少人数の意思決定者のみで「決定」会議を行ってください。
【3.多様な意見を求める会議であるか?】
「アイデア出し」会議では、出されるアイデアの量に加え、様々な種類の意見が出た方が、新結合(イノベーション)が起こりやすくなります。
参加者に意見を求める会議では、意見を出しやすい環境を用意しないといけません。例えば45分のアイデア出し会議に20名も出席していたら、全員が発言することは困難です。
また参加者数が10名を越えると、周りの空気を読むことが多くなり、発言がしにくくなることも調査でわかりました。
そこで、参加者全員でなくとも多様な意見を引き出すことを求める会議は、10名以下でセットしてください。過剰な気遣いをする同調圧力を感じにくく、1人当たりの発言時間も確保しやすくなります。
それでも、7名を超えると1つめの基準で挙げた「社会的手抜き」が発生する可能性がありますので、ファシリテーターが意見を出しやすい空気作りを行うことが必要になります。
【4.啓蒙を含んだ共有会議であるか?】
「情報共有」の会議は、集まることが目的となりがちです。ただし情報を共有するだけでなく、経営会議の雰囲気を臨場感を持たせて説明したり、組織のミッションやビジョンを力強く語って参加者の心に訴えるような場合もあります。
このように「伝えること」だけでなく「伝わること」を目指すには、時間を取って一堂に会した方が効果が出ます。
諸説ありますが、人は7割以上の情報を視覚から脳に入れ、また相手と目が合った状態で情報を伝達すると、そうでない状態よりも記憶力が約2倍に高まるといわれています。
この点を考慮すれば、伝達と啓蒙を目的とする定例会議などでは、発言者が参加者の顔を見える状態が望ましいでしょう。組織の大きさや会議室の広さにもよりますが、こういった「伝達・啓蒙」会議は20名以下でセットしてみてください。
社員数500名以上の企業11社で、「共有・啓蒙」会議は20名以下というルールを設定したところ、主催者および参加者の会議後の満足度は設定前よりともに15%ほど上がりました。
もちろん、すべての会議が、これらの基準でアウトプットが出るというわけではないでしょう。皆さんの会社ならではの「正しい参加人数」もあると思います。それでも、こうした基準があれば、実際に試してみて、効果を検証することができます。
以上の4つの基準を参考に参加人数を決めて、社内会議を2週間実施してみてください。効果が出たら継続しましょう。