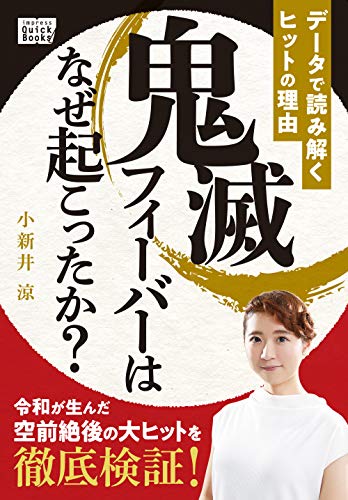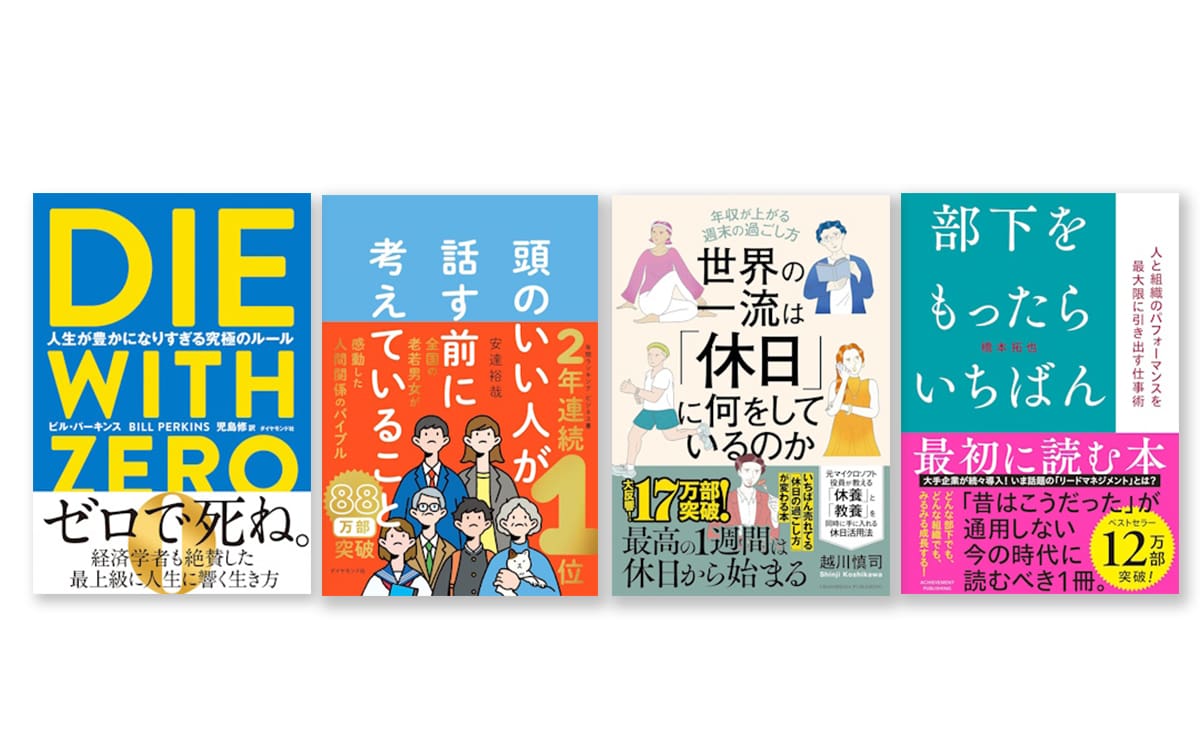“コロナ禍”も影響か…『鬼滅の刃』が「知らないとヤバイ」レベルにまで流行した要因
2021年01月14日 公開 2024年12月16日 更新

2019年から続く『鬼滅の刃』の大ブーム。2020年に公開の劇場版が歴代興行収入トップに上り、累計発行部数は1億2000万部超えと、“社会現象”と言われるまでとなった。
アニメコラムニストである小新井涼氏は、本作のブームはアニメの放送が要因となったと断言し、さらに漫画の連載終了や新型コロナ禍もヒットに拍車をかけたと分析している。
本稿では小新井氏の著書である『鬼滅フィーバーはなぜ起こったか? データで読み解くヒットの理由』から、“ヒットのきっかけ”を詳しく解説していく。
※本稿は、小新井涼 著『鬼滅フィーバーはなぜ起こったか? データで読み解くヒットの理由』(impress QuickBooks)より、内容を一部抜粋・編集したものです。
ブームが勢いづいたタイミング(1) アニメ放送後から年末にかけて
アニメ放送の中盤以降に火が付いた『鬼滅の刃』ブームですが、そのブームをさらに勢いづかせた最初のタイミングが、“アニメ放送終了後から2019年の年末”にかけての時期でした。
“アニメ化をきっかけに人気があがる”だけならば、それは漫画原作の作品においては極めて一般的な出来事です。
ところが『鬼滅の刃』は、アニメ放送終了以降3ヶ月のこのタイミングで、累計発行部数がアニメ放送中以上のとんでもない伸び(アニメ放送中:500→1200万部、放送終了後から年末:1200→2500万部)をみせたのです。
ブームの火付け役となったアニメが放送を終えたにもかかわらず、そこで生まれたブームをさらに勢いづかせることになったこのタイミングには、一体どのような出来事があったのでしょうか。
原作関連の話題にも火が付く
アニメの放送が終わった10月以降からは、それまでと比べて、特に原作関連のニュースが話題になることが増え始めました。
最初に注目を集めたのは、アニメ放送終了後すぐの10月4日に発売された原作第17巻と、小説版「片羽の蝶」に関する話題です。新刊発売に合わせて関連ワードがSNSで続々とトレンド入りをしたのですが、話題となった一因に“店頭で完売が相次ぎ、全国的な品薄状態となっていた”ことがありました。
これまでは発売日に問題なく購入できていたコミックスがなかなか買えないこの事態は、アニメ放送を経た本作の人気の高まりを、原作ファンが益々痛感した出来事でもあったと思います。
またこのころからは、毎週のジャンプ発売に合わせて「鬼滅本誌」というワードがトレンド入りする頻度も増えてきました。
これはそのときに掲載されていた原作の内容がクライマックスに向けた怒涛の展開であり、本誌派の人々が、まさに登場人物達の生死がかかった戦いに、毎週大いに盛り上がっていたためだと思います。
この時期、“基本的に最新刊のみを求める(既刊は既に持っているため)既存のファン”だけでなく、このタイミングで“既刊全巻を新たに購入するアニメ放送以降の新規ファン層が急増”し、年末にかけて様々なコミックス売上ランキングにおいて『鬼滅の刃』が上位独占するという異例の事態が増加していったのだと考えられます。