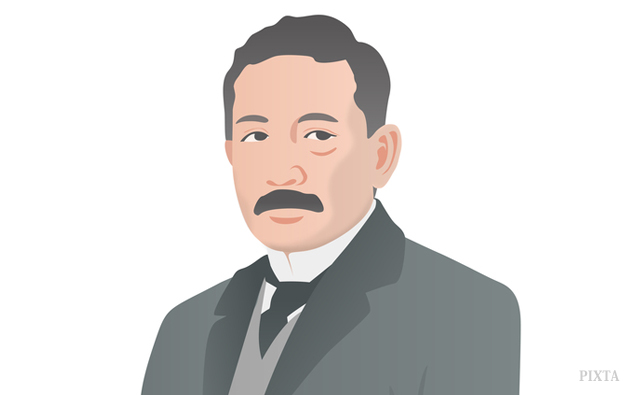漱石の文章は漢文や英文学の深い素養に支えられたものであるが、その文章力の才能を大きく開花させたのは、正岡子規の「写生文」の概念であった。漱石の「てんまる」(句読点)の使い方からその理由を考察してみる。
※本稿は、山口謠司[やまぐち・ようじ]著『てんまる 日本語に革命をもたらした句読点』(PHP新書)を一部抜粋・編集したものです。
正岡子規の写生文
子どもの頃から漢詩漢文が好きで二松學舍で漢文学を勉強した漱石ですが、正岡子規(1867〜1902)との出会いによって、大きな転換をします。
俳句ももちろんそうですが、子規の「写生文」という記述方法が、漱石の小説の文体に与えた影響は、大変大きかったのではないかと思われます。
明治36(1903)年5月、正岡子規の弟子・寒川鼠骨(そこつ)(1875~1954)が書いた『写生文』という本があります。
鼠骨は、結核で亡くなった子規の原稿や遺墨を守り、また子規の遺族の貧生活を支えた人として知られています。
こうした鼠骨の活動はもちろんとても大切なことですが、病気になった子規の代わりに「写生文」という文章の綴り方を教えた人として大きな役割を果たしています。
「写生」は、フランス語の「デッサン」を訳したものです。
もともとは、フランスに留学して洋画を学んで帰国した画家・中村不折(1866〜1943)が、友人の正岡子規に教えて作った言葉です。
中村不折は、正岡子規に対して、日本人は、浮世絵などで作られた「型」にはまったものばかりを描いているといいます。本当の絵は、下手でもなんでも、自分の目で見た通りに描くべきで、その訓練として、技術を習得するためのデッサンをしなければならないと。
正岡子規は、この不折の言葉を聞いて、伝統的な和歌や俳句も同じだ! と悟るのです。
こうして、子規は、我々が小学校の図画の時間に「写生」をするように、自分の目で見えるもの・感じるものを、自分の言葉で素直に書いていくことを漱石や弟子たちに教えるのです。
写生文の工夫
寒川鼠骨の『写生文』に掲載される「月待」という文章を1つ紹介しましょう。この文章を書いたのは、子規の弟子で俳人の坂本四方太(しほうだ)です。
----------------
廿六夜の十時頃、上野の山王台には、早や月待の人が三々五々集まって来た。
石段を登りつめて、左側の処に、茶屋が一二軒並んでいるが、其茶店の灯火や、樹の間の電燈などは、椎の茂に遮られて、我々が立っている柵のところまでは届かない。
----------------
なんと読みやすい文章でしょう!
ここで、比較のために、ほとんど同じ時代に書かれた中江兆民の『一年有半』の冒頭を引きたいと思います。
----------------
明治三十四年三月二十二日東京出発、翌二十三日大坂に着したり、二三友人停車場に来たり迎え、余が顔を熟視し大に驚きて、余が或は直に卒倒せざるやと迄に思いたると、旅館に着したる後に言えり、宜なり余は去年十一月より頻(しきり)に咳嗽を患い、当時咽喉専門の医の診断には、普通の咽頭加答児(カタル)なる旨に付き、爾来打棄(うちすて)置きたるに咽頭漸く疼痛を覚え、飲食共に半減せる中、夜汽車にて来りしか(が)故に、斯くは疲労を現したるなる可し、
----------------
漢文訓読体は、切迫する場面を描くのにとても効果がある文体ですが、やっぱり難しい文章です。
ところで、坂本四方太の文章には、「、」と「。」が使われるほか、
「ここからお上がんなさいますよ。」
「イエ、何時頃に出ますか。」
と、現代日本語の表記と同じく会話文は「 」が使ってあります。
漢文は、明治時代まで我が国で、物事の客観的な事実を叙述するのに不可欠の文体でした。しかし、誰もが簡単に、漢文での作文の技術を習得できるかというと、それは不可能です。
それに対して写生文は、もちろん文才の有無はあるでしょうが、いろんな工夫をすることによって、感じたことをそのまま、書き写すことが可能です。
子規は、「貫之(つらゆき)は下手な歌よみにて古今集は下らぬ集に有之候」と言ったことでも有名ですが、まさに、「型」を破って自由な文章の書き方を力にして、新しい時代を切り拓こうとしたのです。