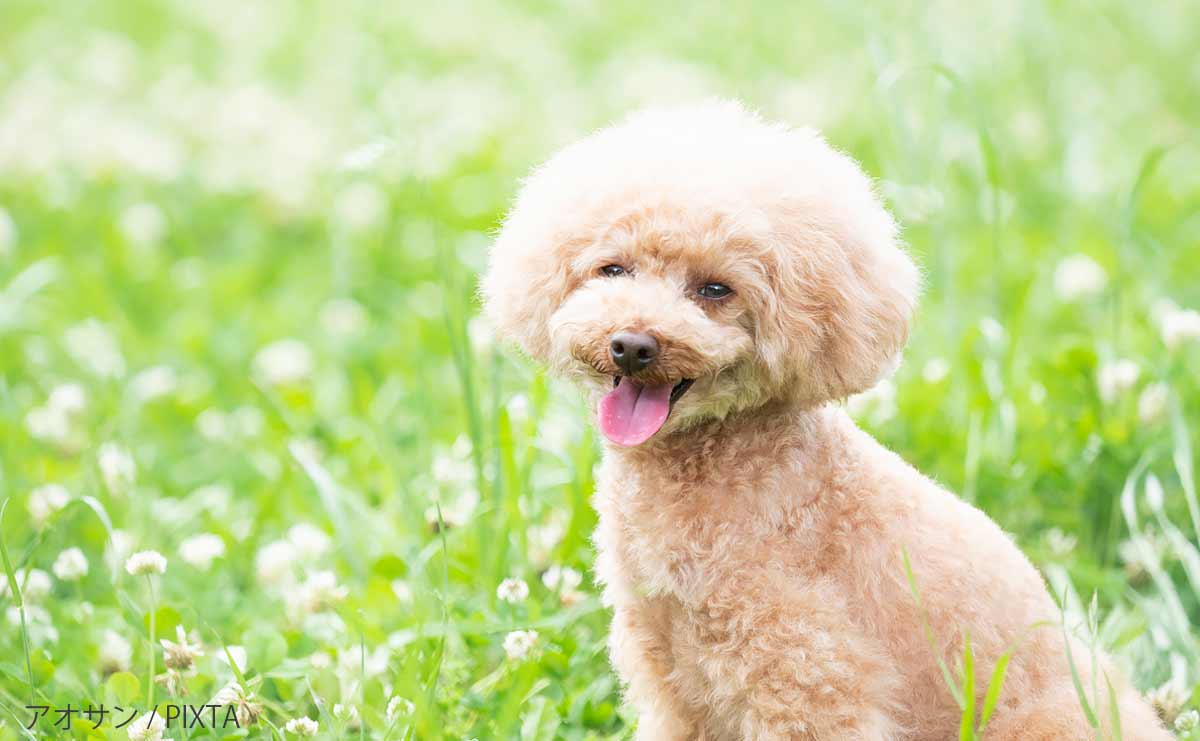Photo Crredits(c) Whitney Hassett
一生一緒にいたいと願っても、犬の寿命は人よりもはるかに短い。苦楽をともにした愛犬を失った辛さははかりしれない。自身を支えてくれた親友・デナリを失い大きな喪失感を味わうベンだが、あるとき運命的な出会いをする。虹の橋を渡った愛犬がもたらしてくれた新たな出会いは、ベンに生きる喜びを思い出させてくれる。
※本稿は、ベン・ムーン著『デナリ ともにガンと闘い、きみと生きた冒険の日々』(&books/辰巳出版)から一部抜粋・編集したものです。
新たな出会い
デナリがいない家は空っぽに感じられた。孤独のさびしさから、犬の友情が自分にとってどれほど必要なものか思い知らされた。デナリのように心のつながりを持てる犬が見つかるのだろうかと思いながら、気づけばネット上で里親を探している犬たちを見ていた。
ポートランドの大規模なアニマルシェルターにも行ったが、わけがわからなくなるばかりだった。真の仲間を探すというより、コンテストのようだ。可能性を感じる子犬がいても、ほんの数分しか触れあうことはできず、すぐにつぎの候補の時間になる。人気のある犬種はたいてい3人か4人くらいキャンセル待ちがいる。
ぼくのところに来るべき子犬なら、向こうからぼくを見つけるはずだと思って気長に構えることにした。
7月4日の独立記念日のあとの月曜に、ホイットニーが家に泊まりに来ることになっていた。デンヴァーを発つ早朝の便に乗るまえに、彼女は一行だけのテキストメッセージを送ってきた。
このかわいい子をチェックして(^_^)
あまり期待せず、ため息をつきながらリンク先をクリックした。最初の画像をダウンロードしたとき、心臓が破裂するかと思った。ノリというそのメスの子犬は、毛の模様が不思議なくらいデナリと似ていたからだ。
だが、いちばんどきっとしたのはその目だった。眼差しは柔らかいが、心は大人びていることが感じられる。まだつぎの犬を飼う準備はできていないのに、なぜかこの犬こそ、デナリを失ってからずっと感じている空しさを埋めてくれるにちがいないと確信していた。
ためらっていたら機会を逃してしまうので、トイレにすわって日課の洗腸をしながら、さっそくその子犬を預かっている〈マイウェイホーム・ドッグレスキュー〉という施設に長いメールを送った。
デナリとの関係や、ノリとも同じように冒険するつもりでいること。施設から車で2時間ほどのところに住んでいて、ガールフレンドを空港で出迎えたら、すぐにノリに会いにいきたいと書いた。
空港への2時間のドライブに出発して25分後、iPhoneの着信音が鳴って考えごとがとぎれた。ノリを預かっているシェリルからだった。彼女は興奮した声で、公開されたデナリの映画を観て、それがガンの闘病や回復期を乗りこえる力になったと話した。
空港でホイットニーを拾い、〈マイウェイホーム〉に直行した。挨拶すると、シェリルは家のなかにいるノリにおいでと呼びかけた。毛むくじゃらな子犬が扉の向こうから現れ、まっすぐホイットニーとぼくのところに来て、足元で興奮してはしゃぎまわった。
ノリは生後2か月ごろ、カリフォルニアのセントラル・バレーで母やきょうだいと一緒に見つかったそうだ。ひどい恥ずかしがりで、人におびえ、保護されてからもたいてい家具の後ろに隠れていたという。
だがそのときにはもう人なつこく成長していた。どんな性格なのか知りたくて芝のあるところに行くと、後ろから突進してきて、茂みのなかでぼくを追いかけまわした。ぼくが急に寝ころがると、ノリは立ち止まって、ぼくの頭の上に小さな身体を乗せて、もっと遊んでとせがんだ。この瞬間、ぼくたちのあいだに絆が生まれた。
わが家に来た最初の日、ノリを海岸に連れていった。デナリと最後の日々を過ごした場所だ。時は流れ、人生の季節はめぐっていく。
それからは、デナリ以外の犬をぼくの心に入れることに対するためらいが日ごとに解けていった。どんな犬もデナリとはちがう、とあきらめかけていたのだが、ノリがちょっとした変なしぐさをするたびに、犬がもたらしてくれる人生の喜びがよみがえった。
にぎやかな生活のはじまり
生後3か月のノリはずっと目が離せず、子犬を引き取ったときの忙しく眠れない日々が久しぶりにやってきた。ノリを迎えいれたことはどんな不便にも代えられない価値があった。
ぼくは海のそばでの暮らしがとても気に入っていた。どこへ出かけるのも、海岸を歩くのも、ノリが横ではしゃいでいるともっと豊かな時間になった。そのころちょうど、ぼくはこの本を書きはじめていた。ノリはいつも海岸に誘い出すことで、毎日キーボードを見つめては自分が信じられず不安でいっぱいだったぼくを救ってくれた。
一緒に暮らしはじめて数か月がたつと、デナリと同じ、ぼくの大好きな性質がノリにもあることがわかってきた。思慮深い瞳や毛色、額のしるしやアイラインだけでなく、ちょっとした癖もよく似ていた。
デナリは独立心があったけれど、いつも一緒にいたがり、愛情表現は激しかった。ノリも同じで、とても注意深く観察していて、自信に満ちていた。バランスが取れていて、それにメスらしい優しさもあった。
犬と人との穏やかな絆は時間の経過とともに築かれていくものだが、ぼくとノリの場合、それほど時間はかからなかった。40代に入って落ち着き、人にどう思われるかを気にしなくなったことも関係しているかもしれないが、それにしてもノリとはすぐに波長が合った。
ぼくはかつてデナリのことをときどき"ナリ"と呼んでいた。それもあって、ノリがますますデナリに近いように思える。
ノリは、気づかないうちにぼくがなくしていたものを思いださせてくれた。穏やかな気持ちを取りもどし、自分の気持ちに区切りをつけるためにも、犬と暮らすことは必要だった。
これでようやく完全な生活が戻ってきた。ぼくが自分のまわりを囲っていた壁は崩れた。デナリがいなくなって、忘れてしまっていた愛しかたを、ノリがまた教えてくれた。
キャンピングカーで暮らしていたころは、まだWi-Fiが普及していなかった。当時はネットワークが自由に使えて、パスワードを要求されることもなかったので、よく車を住宅地に停めて、いちばん強い信号を使わせてもらっていた。
デナリは晩年、何時間も電話をのぞきこんでいると、あきらめたような、がっかりした表情でぼくを見ていた。多くの時間をアウトドアで過ごしてきた、ぼくの冒険仲間はどこに行ってしまったんだ、と問いかけられているようだった。
ノリを迎えいれたころには、iPhoneは高性能のアプリが入った、情報処理機器の中心の座を奪っていた。多くの人はそれを手放せなくなった。ナイトシフトの機能によって夜間に浴びるブルーライトは軽減されたが、そのまえは昼と同じような光にずっとさらされていた。
ノリはぼくがiPhoneをいじっていることにデナリ以上に我慢できず、それをいつも遠慮なく主張する。ベッドにいるぼくの上に乗り、手から電話を奪って、頭をぼくの胸の上に置いて耳を撫でるように要求する。それに満足すると、今度はベッドから飛びおり、ドアまで何度も駈けていって、ビーチに行こうとせっつく。