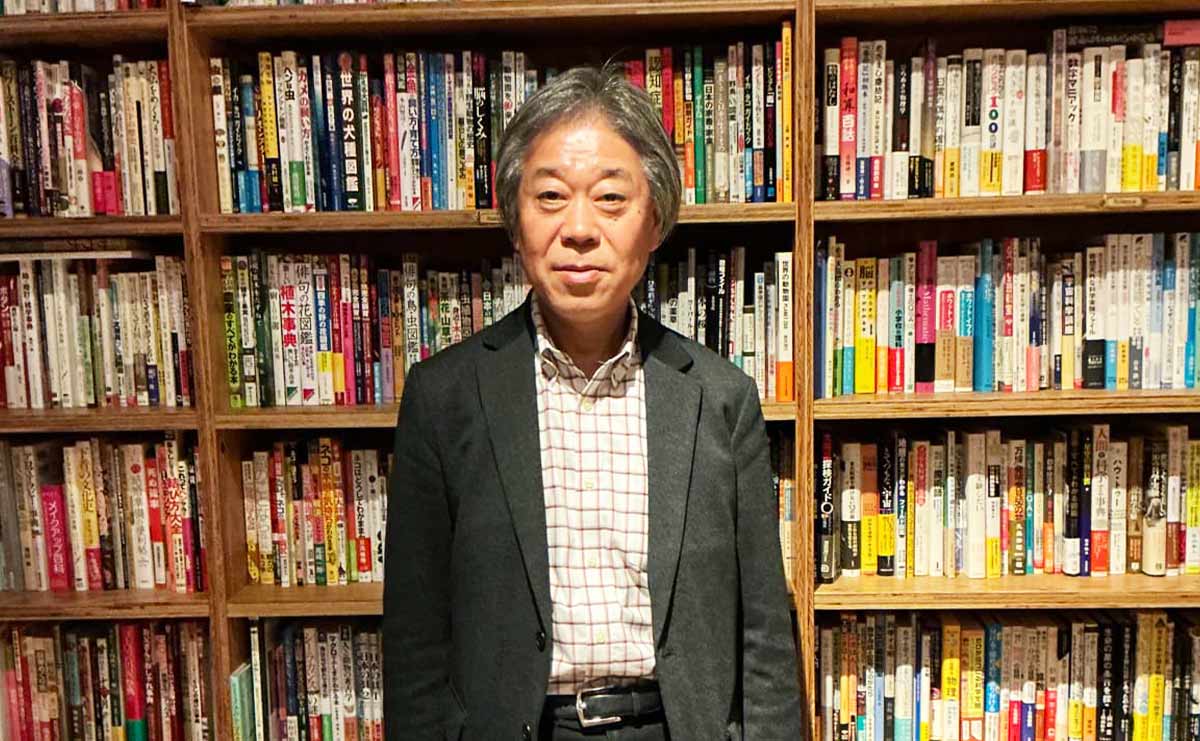
世の中にはたくさんの名言や迷言、奇跡のような出来事が存在します。でもそれだけではありません。誰かの何かきっかけになる言葉だったり行動は十人十色存在していて、それは飾らない何気ない言葉や行動だったりもします。誰がどんな言葉や出来事できっかけをもらったのか、些細なことから大きな出来事までさまざまな分野で活躍されている皆さんに伺いたいと考え、実際に伺ってきました。
第2回としてお話を伺ったのは、東京スリバチ学会会長として『ブラタモリ』にも多数出演されている皆川典久さんです。皆川さんは大手ゼネコン会社に勤められていて、さまざまな建築物の設計にも携わられています。
皆川さんといえば、やはり「街歩き」のイメージがあるのですが、最近知った興味深い皆川さんの能力があって、それはどんな場所にいても「北」がどっちにあるのか瞬時に判断できることなんです。かなり前に『探偵ナイトスクープ』でも取り上げられていた能力を皆川さんも持っていて衝撃を受けたのでした。
もうご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ある言葉から皆川さんの人生は変貌を遂げました。
青山通りから一本入れば情緒あふれる「すり鉢状の窪地」
皆川さんはそもそも街歩きをされていました。そしてあるとき「スリバチ」という名称を思いつき、それを街歩きで見つけたすり鉢状の窪地のことをそう命名しました。東京を歩いてみるとたくさんの坂や谷があり、地形マニアとしても知られるタモリさんはその中でも坂に着目して坂道学会と自称されています。皆川さんの場合は坂ではなく、凸凹地形に着目して、そこを「スリバチ」と名付けました。
その「スリバチ」について皆川さんは、例えば都心の青山通りから一本裏に入った黒鍬谷(薬研坂)のように、単純にくぼ地なだけではなくて、くぼ地の底には表通りとは一味違う下町風情の全く異なる街並みがすぐ側にあることが驚きだったんだそうです。
表通りとは隔絶された街が「スリバチ」の中にあったのは体験的に非常に面白く、それが直感的に「スリバチ」という言葉を思いつくきっかけになりました。そして皆川さんが「スリバチ」と名付けたことが、不思議な縁を手繰り寄せていくことになります。
スリバチの高低差を楽しんでいたら、気がつけばタモリさんがいた
スリバチ学会を2003年に数人に友人で立ち上げた皆川さんは、今では至るところで再開発されている東京の中で、そんな開発から取り残された街に面白さを見出して始めたのが東京スリバチ学会の初期の活動だったそうです。
東京都内を歩くと奥行きが200mや300mの小さなくぼ地がたくさんあります。そんな小さなくぼ地をなぞるような高低差を楽しむ活動が東京スリバチ学会の活動です。しかし、東京スリバチ学会が立ち上がった2003年といえば、まだSNSは影も形もないころでした。
最初に「スリバチ」という言葉に食いついたのは、現「東京スリバチ学会」副会長で慶應義塾大学教授の石川初さんでした。皆川さん曰く、『会長が思いついた一番のスリバチポエムは「スリバチ」という言葉だ』と石川さんからは言われたそうです。
当時、参加者をどう集めていたのか。皆川さんによるとブログで発信をされていたとのことです。単純に街歩きと書くと集まるかどうかわからない。でも「東京スリバチ学会の街歩き」として募集をかけると、その言葉の物珍しさも手伝って見ず知らずの方々が集まってきたそうです。
そしてその集まってきたなかに例えば出版関係のリサーチをされている方だったり、「タモリ倶楽部」のリサーチをやっているような、ネタ集めをやっている方々が紛れ込んでいたことが、後につながっていきます。
皆川さんがタモリさんと最初に出会った番組は「タモリ倶楽部」でした。ネタや情報を集めている人が「東京スリバチ学会」のブログを読んで皆川さんに声を掛けたことがきっかけでした。「東京スリバチ学会」のブログでは街歩きの募集の他に、その街歩きについてのレポート記事も定期的にアップしていました。街歩きの募集、街歩きのレポート記事のサイクルでコンテンツが増えれば増えるほど、徐々に参加者も増加していきました。
NHK「ブラタモリ」誕生の影にスリバチあり?
皆川さんは「ブラタモリ」には何度もゲストとして登場しています。皆川さんや「東京スリバチ学会」のことを「ブラタモリ」で初めて知った方も多いんじゃないでしょうか。
そんな「ブラタモリ」にはひとつ興味深いエピソードがあります。番組が始まる前に皆川さんにタモリさんと始める新番組に関しての相談があったそうです。そこで皆川さんがスタッフに話したのが「ブラタモリ」の元になるようなアイデアだったそうです。
もし皆川さんが「あ、スリバチ」と「東京スリバチ学会」なる団体・企画を立ち上げなければ、「ブラタモリ」は存在しなかったかも知れません。そう考えると「スリバチ」という言葉の発明は非常に大きな意味を持っていると言わざるを得ません。
















