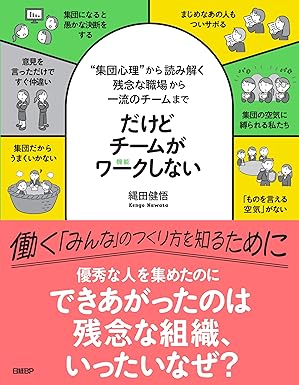アッシュの同調実験は、多数派の意見が個人の判断に与える影響を調べた実験です。被験者は、線の長さ比べという簡単な課題を与えられますが、実際には他の参加者はサクラであり、意図的に誤った回答をします。その結果、多くの被験者が明らかに誤った多数派の意見に同調してしまうことが示されました。なぜこのように人は同調してしまうのでしょうか。書籍『だけどチームがワークしない』より解説します。
※本稿は、縄田健悟著『だけどチームがワークしない』(日経BP)を一部抜粋・編集したものです。
どんなときに同調は強くなるのか
文化や年齢、性別などによる違いは見られるものの、同調の効果は繰り返し示されてきました。(※1)同調を強める要因を、いくつかご紹介しましょう。
●斉一性
同調の重要な要因は、集団全体がみんな同じ一枚岩であることです(※2) 。全員が一致して同じ意見を言っているときには、より同調が強まります。誰も反対していない場面で、自分1人だけが手をあげて違う意見を言うのは、難しいのです。
●集団サイズ
一般に集団が大きいほど、つまり人数が多いほど、同調はより起こりやすくなります(※3)。ただし、同調は3人の集団でも十分に生じることも示されています(※4) 。つまり、3人という小さい集団でも、集団というものができただけで十分に同調は起きるし、人数が大きいほど、さらにその影響は高まっていきます。
●集団からの受容
自分が集団から受け入れてもらうことが重要となる場面では、自分を集団に受け入れてもらおうとして、同調が強くなります。
たとえば、
・後からメンバーどうしで交流することが知らされるとき(※5)
・集団メンバーが自分と同じ心理学専攻の学生から成る身内だと知らされ、さらに彼らから見られているとき(※6)
といったときなどに、同調はより強くなります。
※1 Bond(2005);Bond & Smith(1996)
※2 Asch(1955)
※3 Mann(1977)
※4 Asch(1955)
※5 Lewis, Langan, & Hollander(1972)
※6 Abrams et al.(1990)
人はなぜ規範に同調するのか?
アッシュ型実験で見られる同調の主な原因は、集団に所属していたい、まわりの人から嫌われたくないと思うことです。人は、集団から爪弾きにされることなく、集団に受け入れられていたいと思います。そのため、自分1人だけ逸脱者にならないように、まわりの人に合わせる行動をとるのです。
アッシュの実験では、他の人の前で自分の回答を発表するという形でした。つまり、回答を他の人に聞かれている状況でした。
じつは、多数派の間違った回答は知らされるものの、自分の回答自体は誰にも見られず個人的に手元のボタンを押すだけという場面では、通常のアッシュ型の場面と比べて、同調が低いことが示されました(※7) 。逆に言うと、人は他人に見られているからこそ、間違った他者に同調をするとも言えるのです。
同じ実験で、全員正解すると演劇のペアチケットという報酬がもらえるという場面では、同調が高くなりました(※8)。これは、自分1人が違う回答をして報酬を失えば、まわりの人から拒絶されるかもしれないと思ったからだと解釈されます。
また、fMRIを用いて、同調場面での脳活動を調べた研究があります(※9) 。この実験では、2つの図形を回転させたときに、複数人で同じかどうかを回答する課題(メンタルローテーション課題)を順に回答してもらいます。
このときに、同調しなかった場合(つまり人と違う回答をしたとき)の脳活動を調べたところ、扁桃体という、感情と関連する深い脳部位の活動が強く見られていました。
言い換えると、集団に抗って1人だけ違うことを述べるのは心理的に苦痛を伴うということです。同調するのは人から悪く思われる不安を回避するためだと言えます。
少し補足します。
実は、同調には「規範的影響としての同調」と「情報的影響としての同調」の2種類があります。ここまで説明してきたのは前者のみです。「メンバーから嫌われたくないから」というのが規範的影響です。
もう1つの「情報的影響」とは「正確な情報を得て正しい判断を行いたい」ときに、同調して周りの人と同じ判断をすることです。これは特に、自分の判断や行動が正しいか確認ができない状況で起きやすいものです。ここでは情報的影響の詳細についてはこれ以上説明しませんが、こういった場合もあることにも留意してください。
※7 Deutsch & Gerard(1955)
※8 Deutsch & Gerard(1955)
※9 Berns et al.(2005)
規範は内面化する
集団規範というのは、もともとは自分の外にあるものです。特に集団に参加したばかりの最初の段階では、個人が元々持っている価値観と集団規範とが一致しないということはよくあります。そうであるがために、最初はまだ納得できずとも、「皆やってることだから」という理由でその集団規範に従うことが一般的です。
しかし、その集団での生活が続くうちに、その集団の価値観がだんだんと自分自身のものとして内面化していきます。つまり、もともと自分にはなかった集団の価値観やルールを自分自身のものとして取り込んでいくのです。これは、ことわざでいう「朱に交われば赤くなる」という現象です。
たとえば、ある会社の新入社員が「こんなに早く来て、みんなで掃除して、朝から1人一言あいさつするのか。面倒だなあ」と入社すぐには感じていたとします。
しかし、3年も経つと「早く来て、しっかり掃除するのはあたりまえ。そういう会社の決まり事はしっかりと守らないと。不満ばかり口にして、最近の若者はほんと甘っちょろい」などとしたり顔で我が社のあり方を後輩に語るようになったりするものです。
このような現象は、会社だけじゃなく、部活や趣味サークルでも見られるものです。集団の価値観を身につけ、所属集団の色に染まっていく過程それ自体は悪いことでもなく、組織の一員として成長してきた証でもあります。
日本人は本当に同調しやすいのか?
「日本人は同調しやすい」という印象を多くの方々が持っているかもしれません。しかし、研究の結果を踏まえると、そうとは限らないことが示されてきました。
海外と日本の文化間比較を行った心理学の研究では、賛否両論の結果が示されてきました。「日本人=同調しやすい」とは一概に結論づけるのは困難です。
たとえば、線の長さを答える形での同調を調べる実験では、日本とアメリカの同調率には差がないという結果が得られています。(※10)
一方で、規範からの逸脱を許さない度合い(タイトネス)を国際比較した調査では、日本は33カ国中8番目と高い順位だったりします(※11) 。日本の集団主義の特徴は、他者から嫌われるのを回避しようとする傾向だ(※12)という指摘もあり、これは規範を意識することにもつながっています。
このように規範や同調に関する比較文化研究のごく一例をあげましたが、研究ごとに主張が異なることも多いものです。これだけ意見が割れる議論ですので、本稿で深入りはしません。
むしろ大事なのは、規範への同調は、日本を含めて、世界中で普遍的な現象であるという点です。同調は、世界中いつでもどこでも生じるものだと理解することが重要です。
そもそも先に紹介したアッシュの同調実験も、もともとは個人主義社会だと言われるアメリカで行われたものです。これは、個人主義が強調されるアメリカでも、同調は頻繁に生じることを意味しています。
したがって、同調に関して「そりゃ日本人だからね」と言いながら、単純に日本人の「国民性」や「文化的特徴」だけで解釈してしまうのは、思考停止につながり、問題の本質を見過ごしてしまいます。
どこの国や文化においても、人間は規範に同調しやすいものだということを念頭において、組織づくりや社会づくりを考えていくことが重要です。
※10 Takano & Sogon(2008)
※11 Gelfand et al.(2011)
※12 Hashimoto & Yamagishi(2013)