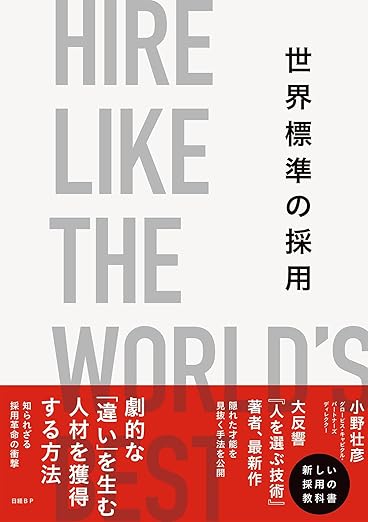2000年中ごろから、この20年ほどの間で、世界の採用手法は劇的な変化をとげました。その要因は、リンクトインやビズリーチ等による新しいサービスの発展、そして巨大企業グーグルが全世界で実践した革命的な人材採用にあるといわれています。
その大きな特徴は、採用エージェントに頼らないダイレクトリクルーティング、そして、より良い人材を獲得するために経営資源を惜しみなく投入する仕組みにあります。
本稿では、そのような世界標準の採用を導入するにあたり、ジョブ型人事の導入を第一ステップとした日本型人事制度の変革について、グロービス・キャピタル・パートナーズ ディレクターの小野壮彦氏に解説して頂く。
※本稿は、小野壮彦著『世界標準の採用』(日経BP)を一部抜粋・編集したものです。
ジョブ型人事制度と解雇規制緩和
日本という社会はこれまで幾度も逆境を乗り超え、再び立ち上がってきました。安宅和人氏の慧眼によれば、その成功の軌跡は次の4つの勝ち筋に集約されるといいます。
すなわち、
1.「すべてをご破算にして明るくやり直す」
2.「圧倒的なスピードで追いつき一気に変える」
3.「若い世代を信じ、託し、応援する」
4.「不揃いな木を組み、強固なものを作る」
というものです。
私の見るところ、現在、日本企業の採用力の低さは、もはや国難とも呼べる深刻なレベルに達しています。しかし、見方を変えれば、まさに1番目の「すべてをご破算にして明るくやり直す」のにふさわしい時期が到来しつつあり、そのためのエネルギーやマグマは十分に溜まってきているのではないでしょうか。
マグマが一気に噴き出すきっかけとなるのが、政府が進める「三位一体の労働市場改革」、なかでも「ジョブ型人事」の導入です。
一見、これは部分的な人事制度の改革に思えるかもしれません。しかし実際には、日本の雇用システム全体を変える可能性を秘めた第一歩なのです。
私は、この動きを、連続ドラマの「第1話」として捉えています。
続く第2話の展開として予想されるのは、組織の「新陳代謝の促進」です。内閣官房が経済産業省、厚生労働省とまとめた「ジョブ型人事指針」(2024年)では、リコーの事例として「長期間同じポジションに滞留している社員全員に対しては、適所適材が実現できているかの確認」を毎年実施する、という取り組みが紹介されています。ここでの表現は「確認する」にとどめてありますが、果たして確認だけで終わらせてよいのでしょうか。
この先、どの企業においても確実に取り組むべきことは、高いポジションに長期間いながら、成果を上げず、不当な報酬を得ている「滞留人材」の適切な「排出」でしょう。ジョブ型人事制度に移行したのちは、メンバーシップ制度と違い、今の職務(ジョブ)で成果を上げられていない人に、別の職務を与える必要は、原則としてなくなるのではないでしょうか。
そして、続く第3話のシナリオは、「解雇規制の限定緩和」だと思われます。まさにこのドラマの肝は、解雇規制にあり、その変化は収入もポジションも高い層から、限定的な形で始まるのではないかと見ています。
解雇規制緩和は政治的にはタブーの類いに入るでしょう。しかし「本当の生産性向上は、そこから始まる」と、おそらく政府でも企業でも、中枢にいる方々はよく理解しておられます。その上で、慎重に各所の堀を埋めはじめているように見受けられます。
もし、これらのドラマが現実となった場合、それは採用の変革とどう結びつくのでしょうか。
ジョブ型人事導入の第1話は準備運動です。組織の新陳代謝の第2話が始まるとともに、採用革命は一気に動き出す可能性があります。スペースが空くことで、新たな人材、新しい風を積極的に取り入れる機会が生まれるのではないでしょうか。
このような断片的な変化の兆しを、利害関係と因果関係を意識しつつ読み解いてみると、
ジョブ型人事の導入が、すべての連鎖を引き起こすトリガーとなる─という大きな絵が、くっきりと浮かび上がってくるのです。
日本は、これらのステップを、この先、どれだけのスピードで踏んでいけるでしょうか。
「奇跡」と評される明治日本の工業化は、わずか30年ほどで一気に欧米列強と肩を並べるまでに至りました。インフラ整備を伴う工業化と比べれば、採用の変革など、はるかに短期間で進められるはずでしょう。
変革は中心部へ
静かに、しかし確実に、日本の大企業が変革の舵を切りはじめています。
具体例として、オムロンは2012年以降、職務の役割・責任に応じたジョブ型の評価・報酬制度を段階的に導入し、2015年以降、係長級以上の非管理職にも対象を広げていきました。これに伴って経験者採用の比率も高まっており、2022年度には約68%になっています。
リコーも2022年から国内グループ企業の管理職・非管理職に対し、ジョブ型人事を一斉に導入しました。その背景には、高すぎる管理職比率と年功的な登用による、若手のやる気減退という課題意識があったとのことです。
やっときたか。とも言えますが、「これ以上後れを取ってはならない」という大企業のアラート感は、かつてないほど高まっています。
痛みを伴う改革を推進している日本の大企業として、特に注目したいのがNECと富士通です。それぞれの取り組み内容には違いがありますが、共通しているのは、ソフトウエア開発に軸足を置く企業である点です。その背景には、グローバル企業との熾烈な競争が存在し、採用革命にキャッチアップしなければ市場での競争力を維持できないという、経営上の切迫した要請があるのでしょう。
NECでは、外資系企業でHRトップを歴任してきた佐藤千佳氏を2018年に迎え、人材組織開発部長に据えたことで、人事改革が本格化しました。その後、NECは幹部クラスの経験者採用を強力に推進し、外部人材の活用に積極的な姿勢を鮮明にしています。
一方、富士通では、2019年に就任した時田隆仁社長の下で、大胆な人事戦略が展開されています。特に注目すべきは、経営陣に外部人材を積極的に登用している点です。現在、執行役員副社長4人のうち3人が外資系企業で経営トップや執行役員を歴任してきた外部出身者であり、その中にはインド系のIT人材も含まれています。
さらに、富士通は2019年、AI(人工知能)やサイバーセキュリティ分野の人材に、役員クラス並みの年収3000万~4000万円を支払う方針を打ち出しました。そして2023年には事業部長クラスの月額賃金を最大29%引き上げ、年収2000万~3000万円に設定する方針を発表し、さらなる改革を進めています。
NECも新入社員や若手にも年収1000万円を支払う制度を導入し、人材獲得競争で攻めの姿勢を見せています。
このような施策は、両社が市場での人材確保の競争に本気で向き合っている証しであり、人材への投資がいかに経営戦略の中核であるかを物語っています。
続いて明確な変化が現れているのがパナソニックです。松下電器産業時代のパナソニックを飛び出し、日本ヒューレット・パッカード執行役員や日本マイクロソフト社長を歴任した樋口泰行氏をパナソニックコネクトの経営トップとして迎えた2017年以降、変革のスピードが一気に加速しています。
このパナソニックコネクトでは、グループの他社に先駆け、モダンな採用手法への転換が全社的に進められています。樋口氏の社長就任以降、マーケティングやCTO(最高技術責任者)といった重要ポジションにおいて、外資系企業などでキャリアを積んだ人材を次々に招聘し、役員に占める外部人材の割合を大胆に高めています。現場で採用に携わる知人からは「目を回しながら、ついていくのに必死です」との声も漏れ聞こえてくるほどです。
いずれも、巷では「JTC(ジャパニーズ・トラディショナル・カンパニー)」と呼ばれた企業です。それが、ここまで大きく変革の舵を切ったのです。外資系企業から始まり、ベンチャー企業へと広がってきた日本の採用革命の流れは、ついに中心部、日本の伝統的な大企業の心臓部まで到達したのです。そして、それはここからさらに加速していくことが予想されます。
もはや「中小企業だから」「地方だから」「老舗だから」といった言い訳は通用しません。
採用革命は一時的なトレンドではなく、マーケットメカニズムそのものなのです。好むと好まざるとにかかわらず、すべての企業を強烈に巻き込み、変化を促していきます。
だからこそ、今、自ら進んでこの波に乗るべきではないでしょうか。採用革命の波に乗り、世界標準の採用を実装する。その選択が、企業の未来を切り拓く鍵となるのです。